Scope3とは?最新情報と環境への影響と企業の取り組み

企業の温室効果ガス(GHG)排出管理において、Scope3は最も広範で影響力の大きいカテゴリーです。
自社の直接排出(Scope1)や購入エネルギーの使用(Scope2)を超え、原材料の調達から製造、輸送、消費、廃棄まで、サプライチェーン全体にわたる間接的な排出を含みます。
多くの企業では、GHG排出量の7割以上がScope3に該当し、この領域を正確に把握しなければ、本質的な削減は困難です。
日本国内でも、Scope3を重視する企業が徐々に増加しており、大企業だけでなく中小企業も算定に乗り出す例が見られるようになりました。
この背景には、グローバル市場での競争力を維持するための圧力や、カーボンニュートラルの推進、カーボンフットプリントの透明性を求める顧客からの期待があると考えられます。
Scope3の把握と削減は、単なる環境対応にとどまらず、ビジネスリスクの軽減や取引先・消費者との信頼構築のための重要な戦略的要素となりつつあります。
本記事では、Scope3の定義や国際基準に基づく算定方法、15のカテゴリーの詳細を解説し、企業が果たすべき責任と実際の削減事例を紹介します。
さらに、環境省のガイドラインやScope3対応ツールを活用した効果的なデータ管理手法を探り、今後の規制動向や市場競争力への影響も考察します。
企業の持続可能性と競争力を高めるための戦略的アプローチを、ぜひ本記事でご確認ください。


Scope3とは?環境への影響と企業の責任
Scope3の定義と重要性
Scope3は、企業活動に伴うバリューチェーン全体の間接排出(サプライヤーから顧客・廃棄まで)を対象とする温室効果ガス(GHG)の区分です。
自社の直接排出(Scope1)や購入電力などに伴う間接排出(Scope2)を超え、原材料の調達、生産、物流、使用、リユース・リサイクル、廃棄といった製品ライフサイクル全体をカバーします。


多くの企業では総排出量の大半がScope3に集中しやすく、ここを把握しない限り実効的な削減は設計できません。
投資家・顧客・規制当局は、サプライチェーン全体を含む包括的な排出管理を重視しており、対応が不十分だと信頼性や競争力の低下につながるリスクがあります。
▼おすすめのお役立ち資料

Scope3の算定と企業に求められる責任
なぜ算定が「経営課題」になるのか
温室効果ガスの算定は、気候変動対策の出発点であると同時に、事業戦略そのものです。
Scope1/2/3の国際枠組みに沿って排出を体系的に可視化すれば、影響の大きい工程や取引先を特定でき、現実的な削減計画に直結します。
特にScope3はサプライチェーン横断の取り組みが不可欠で、サプライヤー・顧客との連携や一次データ(実測・実態データ)の活用が成果を左右します。
透明性と説明責任
算定プロセスの透明性は、企業の信頼の土台です。精度の高いデータ収集・分析と、分かりやすい情報開示により、ステークホルダーに対して責任ある姿勢を示せます。
これが不十分だと「環境対応に消極的」という評価を招き、レピュテーションや資金調達にも影響します。
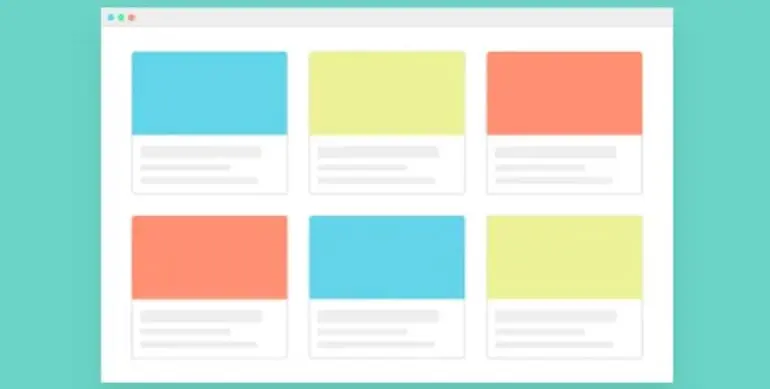
規制・基準への整合
EUのCSRD(企業サステナビリティ報告指令)やSBT(Science Based Targets)など、主要基準はScope1–3の包括的開示・削減を求めています。
適合は単なるコンプライアンスを超え、取引継続性や市場アクセスに関わる競争条件になりつつあります。


期待されるアクションの例
- 重要排出源の特定(カテゴリ別・工程別・取引先別)
- 削減目標の設定(短期と中長期)と進捗モニタリング
- 省エネ・再エネ導入、低炭素素材や設計変更、物流最適化
- サプライヤーとの協働(データ連携・改善支援・基準づけ)
- 第三者の検証を通じた開示の信頼性向上
算定で得た知見は、製品設計の刷新、コスト削減、リスク低減、新規事業の創出にも波及します。
Scope3を軸にした可視化と連携こそが、持続可能性と競争力を同時に引き上げる近道です。


▼出典:グリーンバリューチェーンプラットフォーム サプライチェーン排出量全般
Scope3の15カテゴリの詳細
カテゴリの一覧とその意義
ScopeX3の広範な枠組みは、15の具体的なカテゴリーに分かれており、それぞれが異なる排Scope3の各カテゴリを算出することで、企業は活動のあらゆる段階における環境負荷を包括的に把握し戦略的な削減策を講じるための基盤を得ることができます。
1. 購入した製品およびサービス
企業が調達する製品やサービスの生産過程で発生する排出を対象とします。
サプライヤーの排出量が含まれるため、サプライチェーン全体の持続可能性を向上させる鍵となります。
たとえば、低炭素素材の採用や持続可能な調達基準の導入が効果的な対策です。

2. 資本財
建物、機械、設備などの資本財を製造する過程で発生する排出を含みます。
特にインフラ投資が多い製造業や建設業では、これが重要な排出源となります。
耐久性や効率性の高い設備を選ぶことが削減に繋がります。

3. 燃料およびエネルギー関連活動(Scope 1・2に含まれない部分)
エネルギーの生産や輸送に伴う間接排出を対象とし、電力や燃料のサプライチェーンでの排出が含まれます。
再生可能エネルギーの利用が効果的な削減策です。

4. 輸送および配送(上流)
原材料や部品を調達する際の輸送活動に関連する排出を含みます。
輸送効率の向上や、低排出の物流手段への転換が推奨されます。
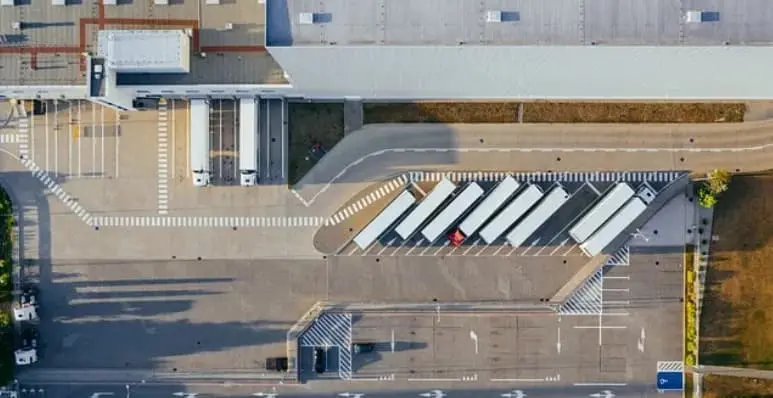
5. 廃棄物からの排出
製造工程や業務活動で発生する廃棄物の処理に関連する排出を対象とします。
廃棄物削減、リサイクル率の向上が重要な取り組みとなります。

6. 従業員の出張
従業員が出張で利用する交通手段に伴う排出を含みます。
オンライン会議の利用や公共交通機関の活用が削減策として挙げられます。

7. 従業員の通勤
従業員が通勤する際の排出を対象とし、通勤手段の選択(自動車、公共交通機関、自転車など)が影響します。
柔軟な勤務形態やシェアライドの導入が対策として有効です。

8. リース資産(上流)
企業が借りて使用する資産の使用に伴う排出を含みます。
省エネルギー型のリース資産を選択することが削減策となります。

9. 輸送および配送(下流)
製品を顧客や小売業者に届ける過程での輸送活動に伴う排出を対象とします。
効率的な配送ネットワークの構築が必要です。

10. 販売した製品の加工
企業が販売した中間製品を顧客が加工する際に発生する排出を含みます。
効率的な加工プロセスを促進する製品設計が求められます。
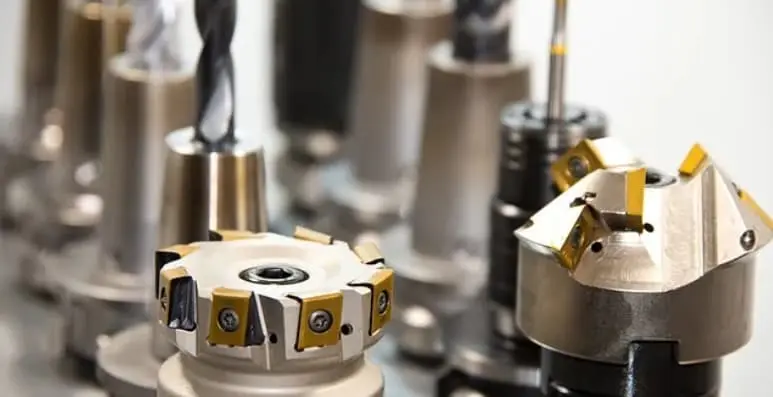
11. 販売した製品の使用
最終製品が使用される際に発生する排出を対象とします。
特に自動車や家電のようなエネルギー消費が大きい製品では、このカテゴリーの排出量が顕著です。
エネルギー効率の高い製品の開発が重要です。

12. 販売した製品の廃棄処理
使用後に廃棄される製品の処理過程で発生する排出を含みます。
リサイクル可能な素材の採用や廃棄物削減が推進されています。

13. リース資産(下流)
企業が顧客に貸し出す資産の使用に伴う排出を対象とします。
省エネルギー型のリース製品を提供することが鍵となります。

14. フランチャイズ
フランチャイズ店舗や事業における排出を対象とします。
フランチャイジーとの連携を強化し、持続可能な運営を支援することが必要です。

15. 投資
企業が保有する投資資産やポートフォリオに関連する排出を含みます。
投資先の脱炭素化を支援し、ESG要件に適合するポートフォリオ管理が求められます。


Scope3の15カテゴリは、企業の直接活動にとどまらず、サプライチェーン全体や製品ライフサイクルを通じて発生する環境負荷を体系的に把握する枠組みです。
カテゴリごとに排出量を特定・削減することで、透明性の高い情報開示、規制対応、競争力強化につながり、同時に新しいビジネスチャンスの創出にも直結します。
Scope3排出量の算定方法と実務での活用ポイント
算定の意義
Scope3排出量の算定は、企業がサプライチェーン全体や製品ライフサイクルを通じた温室効果ガス(GHG)排出を正確に把握するための基盤です。
このプロセスを適切に行うことで、排出削減の重点領域を特定し、実効性のある気候変動対策や脱炭素戦略を設計できます。

Scope3算定は大きく次の3ステップで進められます。
1. 活動データの収集
まず、Scope3の15カテゴリーに関連する活動データを集めます。
- 調達した原材料や部品の使用量
- 物流における輸送距離と重量
- 製品使用時のエネルギー消費量
- 廃棄物処理の方法と量
特に注目されるのが一次データ(Primary Data)の活用です。
サプライヤーや顧客から得られる一次データは、業界平均値(2次データ)よりも実態を正確に反映し、施策効果の測定にも有効です。
環境省のガイドラインでも一次データの活用が推奨されており、データを安定的に収集できる体制の整備が、Scope3対応の成熟度を左右します。

2. 排出係数の適用
収集した活動データに、排出係数(Emission Factor)を掛け合わせて排出量を算出します。
- 輸送 → 「輸送距離 × 重量 × 排出係数」で計算
- 購入製品 → 「購入額や重量 × 排出係数」で推定
排出係数は国際基準や環境省、国立環境研究所が提供するデータベース(例:産業連関表やIDEA)を用いるのが一般的です。
これにより、地域や産業特性を反映した精度の高い算定が可能になります。
は何を使う?データベースの選び方と活用事例.jpg)
3. 算定結果の整理と活用
算定された排出量は、15カテゴリごとに分類・分析します。
多くの企業では、
- カテゴリ1(購入した製品・サービス)
- カテゴリ11(販売した製品の使用)
が全体排出量の大部分を占めます。
これらに重点を置いた削減計画を策定することが、戦略上の重要ポイントです。
分析結果は以下のように活用できます:
脱炭素製品開発や新規ビジネス機会の創出
削減目標の設定と進捗管理
サプライチェーン全体の改善アクション策定
ステークホルダーへの透明性ある情報開示
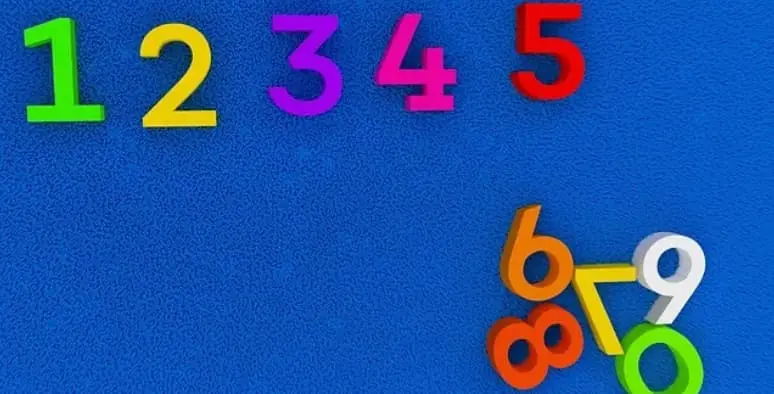
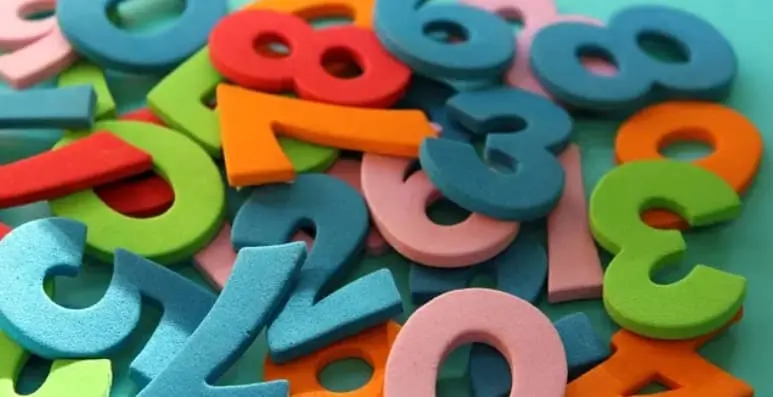
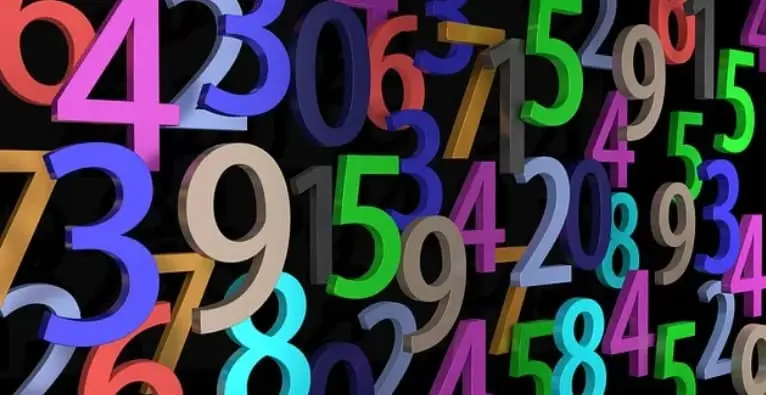
中小企業と大企業での算定アプローチの違い
- 中小企業:業界平均値や簡易モデルを活用し、負担を抑えつつ算定を実施
- 大企業:詳細データを収集・分析し、精度の高い算定と戦略的な削減施策を設計
Scope3算定は、単なる排出量の把握ではなく、持続可能な経営を実現するための基盤づくりです。
一次データの活用や信頼性の高い排出係数を用いた精度の高い算定により、企業は透明性を確保し、ステークホルダーの信頼を得られます。
さらに、算定結果を削減計画や新規事業に結びつけることで、環境責任の遂行と競争力強化を同時に実現できます。

▼出典:環境省 脱炭素ポータル 脱炭素社会の実現に向けた温室効果ガス排出量の算定(見える化)(1/2)
国際基準で加速するScope3義務化
Scope3の開示義務化は、企業がサプライチェーン全体の温室効果ガス(GHG)排出量を透明に報告することを求める大きな流れです。
2023年6月、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)が策定した新基準により、Scope1・Scope2に加えてScope3の開示が国際的に義務化されました。
これにより、上場企業は従来以上に包括的な排出量管理を求められるようになり、世界的な気候変動対策の加速につながっています。
日本における制度化の進展
日本でも、ISSB基準に整合した「日本版ISSB基準」の策定が進められています。
サステナビリティ基準審議会(SSBJ)は2025年3月に正式基準を公表、2026年4月から(2027年3月期)に適用開始される見込みです。
これにより、特にプライム市場上場企業を中心に、Scope1~3の包括的な排出量開示が求められるようになります。
この動きは単なる情報開示強化にとどまらず、企業がサプライチェーン全体を巻き込んだ排出削減を進めるための強力な枠組みとして位置づけられています。

企業に求められる対応
- 包括的な算定体制の整備:Scope3を含む排出量を正確に把握するためのデータ収集基盤の構築
- サプライヤーとの連携:一次データの活用を前提とした協力体制の強化
- 透明性ある情報開示:ステークホルダーからの信頼を獲得するための開示精度向上
- 戦略的な排出削減計画:開示義務に対応するだけでなく、競争優位性やレピュテーション向上につなげることが重要
2024年7月には、SSBJ基準案を解説するセミナーが開催され、特設サイトで動画や資料が公開されています。
こうした公的リソースを活用し、企業は制度開始前から体制を整えておくことが求められます。

▼出典:SSBJ基準案の概要
Scope3開示義務化の企業への影響
Scope3の開示義務化は、企業にとって単なる環境対応の枠を超え、経営戦略やサプライチェーン管理に直結する重要課題となっています。
ここでは、企業に及ぶ主な影響を整理します。
1. コスト増加とデータ管理の複雑化
Scope3はサプライチェーン全体や製品ライフサイクルにまたがるため、排出源が非常に広範囲です。
その結果、
- サプライヤーからのデータ収集
- 社内システムの整備
- 報告書作成や外部保証への対応
といったプロセスが不可欠になり、データ管理の高度化とコストの増加が避けられません。
特に正確性を確保するには、サプライヤーとの継続的な協力が求められます。
2. 規制遵守と信頼性確保へのプレッシャー
国内外で規制が強化される中、Scope3の開示は法令遵守とESG評価の両立を意味します。
不十分な開示は、法的リスクに加えて、投資家・顧客からの信頼低下につながり、市場競争力を失う可能性があります。
透明性ある報告は、今や企業価値の必須条件といえます。

3. サプライチェーン全体での対応強化
Scope3排出量の大部分はサプライチェーン上で発生します。
そのため、サプライヤーとのパートナーシップ強化が不可欠です。
排出削減目標の共有や改善支援を通じて、サプライチェーン全体で環境負荷を低減する体制づくりが企業の責務となります。
4. 投資家・顧客からの評価基準の変化
Scope3の開示は、投資家や顧客が企業を評価する新たな指標になりつつあります。
積極的に取り組む企業は「持続可能性を重視する企業」として高い評価を得られる一方、不十分な対応はブランド価値の低下や資金調達の不利に直結します。

▼出典:経済産業省 レジリエントなサプライチェーンの構築に向けて
企業が取るべき対応策
Scope3開示義務化に向けて、企業は以下のような具体的な取り組みを進める必要があります。
1. データ収集体制の構築
Scope3排出量を正しく算定するには、信頼性の高いデータ収集基盤の整備が不可欠です。
取引先やサプライヤーから効率的に情報を取得するために、デジタルツールやクラウドシステムの導入が推奨されます。
2. サプライヤーとの連携強化
Scope3の大部分はサプライチェーンで発生するため、サプライヤーとの協力体制が成否を分けます。
排出削減目標を共有し、改善策を一緒に進めることが重要です。
教育や支援の提供を通じて、取引先と共に持続可能なサプライチェーンを構築できます。
3. 戦略的な削減目標の設定
短期的な目標に加えて、中長期的な削減ロードマップを描くことが求められます。
進捗を定期的に評価し改善を重ねることで、投資家や顧客からの信頼性を高め、ESG評価の向上にもつながります。

4. 内部体制の強化
Scope3の算定・開示には、購買・物流・経営企画など複数部門の連携が必要です。
経営陣を巻き込んだ横断的な体制を整えるとともに、従業員教育を通じてScope3の重要性を社内に浸透させることで、全社的な取り組みを推進できます。
5. 外部の専門家の活用
環境コンサルタントや第三者機関を活用すれば、算定の精度と効率を高め、報告の信頼性を向上させることができます。
データ収集方法や削減計画の策定、報告書作成などを専門家と連携して進めることで、最新の規制や基準にも的確に対応できます。

Scope3の義務化は、単なる規制対応ではなく持続可能性を経営戦略の中核に組み込む転換点です。
サプライチェーン全体の排出量を可視化し削減に取り組むことで、企業は環境責任を果たしながら競争力を高められます。
また、透明性ある情報開示と実効性ある削減行動は、投資家や顧客からの信頼獲得につながります。
短期的にはデータ収集やコスト面の課題があるものの、長期的には持続的成長と市場での優位性を確保する大きなチャンスとなるでしょう。
企業事例に見るScope3への取り組み
Scope3排出量の削減は、企業が持続可能性を高め、グローバルな脱炭素社会へ移行するために欠かせないテーマです。
各業界では、サプライチェーン全体を巻き込んだ先進的な取り組みが進んでおり、企業価値向上や競争力強化につながる事例が増えています。
製造業:京セラのサプライチェーン改革
製造業においては、Scope3の削減が環境戦略の中心的な課題です。
京セラは特にカテゴリ1(購入した製品およびサービス)に注目し、サプライヤーとの協働を強化しています。
- サプライヤーに削減目標の設定を働きかけ
- 低炭素素材の調達を推進
- カテゴリ11(販売した製品の使用)では、省エネ設計を導入し、使用段階での排出削減を実現
これらの施策は短期的な対応にとどまらず、長期的な競争力の源泉として位置づけられています。

小売業:ローソンの物流効率化と店舗改善
小売業では、Scope3削減がサプライチェーン効率化の動きと重なっています。
ローソンはフランチャイズ店舗や配送ネットワークを含めた排出量の把握を強化。
- 取引先に対する定期的な排出量調査
- 物流ネットワークの最適化による配送効率の向上
- 容器包装プラスチックの削減、認証原料を活用した商品開発
- 店舗への省エネルギー型設備導入
これらの取り組みは、持続可能性と効率性を両立する戦略として評価され、消費者や投資家からの信頼を高めています。

▼出典:ローソン 地球環境保全の取り組み
飲食業:モスフードサービスの廃棄物削減と地域連携
飲食業では、店舗運営や食品廃棄がScope3排出の大きな要因です。
モスフードサービスは以下の施策を展開しています。
- 使い捨て製品の環境配慮型素材への切り替え
- 食品廃棄物のリサイクル仕組みの構築
- 地域社会と連携した環境教育活動
これらは環境負荷を減らすだけでなく、顧客満足度とブランド価値の向上にもつながっています。

▼出典:モスフード ESGデータ集
また、「グリーンカーテン」プロジェクトを通じて店舗の省エネ活動を促進し、地域社会と連携した環境教育活動も展開しています。
これらの取り組みは、顧客満足度の向上にもつながり、企業のブランド価値を高める一因となっています。

▼出典:モスフード「グリーンカーテンコンテスト2024」を開催中
京セラ・ローソン・モスフードサービスの事例から見える共通点は、Scope3削減を規制対応ではなく経営戦略の一部として位置づけている点です。
サプライチェーン全体で協力体制を築き、長期的な削減目標を掲げ、革新的な方法で実行することで、企業は新たな市場機会を切り開いています。
Scope3対応は、短期的にはコスト増を伴うものの、企業価値向上と持続可能な成長を実現する原動力となります。
今後のビジネス環境においてScope3は、競争優位性を左右する欠かせない要素となるでしょう。

Scope3の算定ツール
Scope3排出量の算定は、サプライチェーン全体における温室効果ガス(GHG)排出を正しく把握し、効果的な削減戦略を立てるために欠かせません。
その中核を担うのが「温室効果ガスの算定ツール」です。
これらのツールは、膨大で複雑なデータを効率的に処理し、企業が持続可能性を経営に組み込むための基盤を提供します。

算定ツールの主な機能
Scope3算定ツールは、排出量の算定と可視化を目的として設計されています。
- 信頼性の高いデータベースを基に、活動ごとの排出量を迅速に算出
- 15のカテゴリー別に排出量を特定し、重点的に削減すべき分野を明確化
- ダッシュボードやグラフで結果を直感的に表示し、社内外への説明や報告をサポート
これにより、企業は自社の環境影響を精緻に把握し、具体的な削減アクションにつなげやすくなります。
企業規模や業種に合わせた選定の重要性
Scope3算定ツールの導入効果を最大化するには、自社の規模や業種に合ったシステムを選ぶことが不可欠です。
- 大企業:詳細なデータ分析や多拠点管理が可能な高機能型ツールが適する
- 中小企業:操作性がシンプルで導入コストを抑えられるツールが好まれる
自社のニーズを明確にし、コストと機能のバランスを見極めることが成功の鍵となります。
導入時の参考情報
ツール選びに迷った場合は、比較サイトや専門メディアを活用すると効果的です。
以下のようなサイトでは、機能・費用・ユーザー満足度などの観点から複数の製品を比較できます。
▼参考:ITレビュー【2024年】CO2排出量管理システムのおすすめ10製品(全17製品)を徹底比較!満足度や機能での絞り込みも
▼参考:アスピック CO2排出量管理システム16選。自動計算で脱炭素化を効率的に
▼参考:キャククル CO2排出量管理ツール(システム)14選比較!見える化でコスト削減を実現
▼参考:ボクシル CO2排出量管理システムおすすめ比較!必要性や導入のメリット・選び方のポイント
これらを参考にしつつ、資料請求やデモ導入を経て実際の運用イメージを持つことが選定の近道です。
Scope3と環境省のガイドライン
Scope3と環境省のガイドライン
環境省が提供する「サプライチェーン排出量算定ガイドライン」は、Scope3排出量を正確に算定しやすくするための実務的な指針です。
このガイドラインは、企業がScope3の15のカテゴリーに基づいて排出量を計測し、管理できるよう設計されています。
1. ガイドラインの目的と特徴
このガイドラインは、データ収集が難しい部分でも実務的に対応できるように工夫されている点が特徴です。
日本の産業構造や業種特性を踏まえ、
- 活動データの収集方法
- 原単位データ(排出係数)の適用手順
- 排出量の算定方法
を段階的に解説しています。
さらに、データ不足の場合には業界平均値や推計値を活用する方法も提示されており、柔軟にScope3算定を進められる仕組みが整っています。
2. 算定プロセスを全面的にサポート
Scope3の算定は「活動データの収集 → 原単位の適用 → 算定結果の分析」という流れで行われます。
ガイドラインではこの一連のプロセスをわかりやすくサポートしており、算定結果を企業の環境戦略にどう統合すべきかも示しています。
特に、排出量の大部分を占めるケースが多い
- カテゴリー1(購入した製品およびサービス)
- カテゴリー11(販売した製品の使用)
については重点的に算定方法が解説されており、企業が優先的に取り組むべき領域が明確化されています。
3. 中小企業でも使いやすい仕組み
ガイドラインは大企業だけでなく、中小企業が取り組みやすいように配慮されています。
簡易入力形式や算定ツールが用意されており、リソースの限られた企業でもScope3算定を始めやすくなっています。
これにより、幅広い企業が脱炭素経営へと踏み出せる環境が整えられています。
これにより、Scope3算定のハードルが下がり、多くの企業が脱炭素経営に取り組みやすい環境が整備されています。

▼出典:環境省 グリーン・バリューチェーンプラットフォーム 排出量算定に関するガイドライン
環境省のグリーン・バリューチェーンプラットフォームとは?Scope3普及を後押しする仕組み
環境省が設立した「グリーン・バリューチェーンプラットフォーム」は、Scope3の普及促進と企業間の連携強化を目的としたオンラインプラットフォームです。
サプライチェーン全体での温室効果ガス(GHG)排出量を見える化し、削減を加速させる情報共有の場として活用されています。
1. プラットフォームの目的
Scope3の算定・削減を進めるためには、取引先やサプライチェーン全体との協力が欠かせません。
このプラットフォームは、企業同士のデータ連携を円滑化し、ベストプラクティスや成功事例を共有できる場として機能しています。
結果として、各企業が効率的にデータを収集・活用できる体制づくりを後押ししています。
提供されている機能(現状ベースでの実態)
グリーン・バリューチェーンプラットフォームには、
- 成功事例の公開・共有
国内外約110社の企業が、算定目的・方法・活用・課題を含む事例を掲載。
これにより、他社は自社の取り組み設計時の参考にできます。 - 算定に関する参考情報とガイダンス
Q&A、カテゴリー別算定方法、原単位データベース、ガイドライン関連文書など、実務者向け資料が整備され、算定プロセスの理解を支援。
上記により、初めてScope3算定に取り組む企業でも、手順を理解しやすい環境が整っています。


まとめ
Scope3は、調達から製品使用・廃棄まで企業活動のほぼすべてを映し出す鏡です。
国際基準(ISSB/SSBJやCSRD)により、バリューチェーン全体での開示は事実上の必須条件となりました。
算定にはコストやデータ管理の課題がありますが、そこで得られる知見は「規制対応」を超え、競争優位と新市場創出につながる資産になります。
実務で重要なのは三点です。第一に、平均値頼みから脱し、サプライヤーからの一次データ活用で精度を高めること。
第二に、カテゴリ1(購入した製品・サービス)やカテゴリ11(使用段階)のように影響の大きい領域に重点を置き、段階的に削減ロードマップを描くこと。
第三に、外部検証やプラットフォームを活用して開示の信頼性を確保することです。
環境省ガイドラインやグリーン・バリューチェーンプラットフォームの事例公開を活かせば、自社の取り組みを加速させられます。
Scope3対応は、短期的には負担でも、長期的には事業価値を高め、気候リスクをビジネス機会へ反転させる最短ルート。いま始める企業こそ、未来の市場で選ばれる存在になれるのです。
▼おすすめのお役立ち資料

▼算定についての無料相談はこちら!

