Scope3カテゴリ2-自社が購入または取得した資本財の製造や建設の原材料調達~製造について具体的に解説

企業が脱炭素経営を進めるうえで避けて通れないのが、サプライチェーン全体の排出量を把握するScope3です。
その中でも「カテゴリ2(資本財)」は、建物や製造設備、IT機器、車両、インフラ、さらには基幹システムやソフトウェアといった長期的に使用される資産に関わる排出量を対象としています。
これら資本財は企業活動を支える基盤であり、導入時の製造プロセスで大量のエネルギーや資源を消費するため、多くのCO2排出を伴います。
特に鉄鋼やセメントといった高炭素素材は「エンボディドカーボン(内包炭素)」として企業の環境負荷に大きな影響を与える要因です。
そのためカテゴリ2の排出量を正確に把握し削減施策を講じることは、長期的な脱炭素戦略の基盤となります。
本記事では、Scope3カテゴリ2の定義や計上ルール、算定方法を整理するとともに、設計・調達・使用・廃棄といった各段階における削減の具体的アプローチをわかりやすく解説します。
持続可能な経営を目指す企業にとって、資本財の排出管理をどう進めるかは競争力の源泉にもなります。

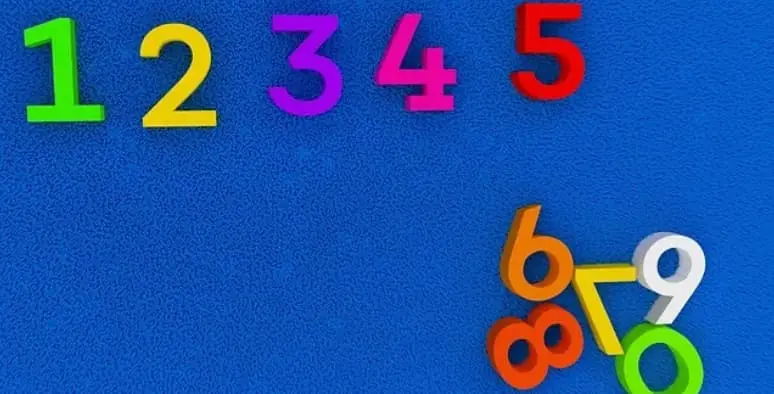

Scope3カテゴリ2とは?資本財におけるCO2排出量の重要性と企業への影響
Scope 3カテゴリ2は、企業が購入・取得する 資本財(Capital Goods) に伴う温室効果ガス(GHG)排出量を把握するための区分です。
資本財は企業活動を長期的に支える存在であり、その排出量を正しく管理することは、持続可能な経営を実現するうえで欠かせません。
資本財とは?
「資本財」とは、長期間にわたって利用される設備やシステムを指します。
- 有形資産:建物、製造設備、IT機器、車両、インフラなど
- 無形資産:ソフトウェアの購入費、基幹システムの開発費用など
いずれも、短期的に消費されるものではなく、企業が複数年にわたって活用する資産が対象となります。
カテゴリ2が注目される理由
Scope3カテゴリ2が特に重要視されるのは、資本財の製造段階がエネルギーや資源を大量に消費するためです。
例えば、鉄鋼やセメントといった高炭素素材を用いた建設や設備投資は、多くのCO2排出を伴います。
こうした排出量は「エンボディドカーボン(内包炭素)」とも呼ばれ、企業の環境負荷に大きく影響します。
さらに、資本財は一度導入すると長期的に使用されるため、初期調達時の排出量を正確に把握することが、長期的な脱炭素戦略の基盤となります。
計上のタイミング
資本財に関する排出量は、使用期間に分割して計上するのではなく、取得した年(月)または完成した年(月)に一括して計上します。
例えば、新しい工場やオフィスビルを建設した場合、その建物が完成した年度に排出量をまとめて報告する必要があります。
Scope3 カテゴリ2の算定方法
カテゴリ2の排出量を計算するには、購入した機械や車両の物量や販売単位を取得し計算する場合も多いですが、現状は、機械は車輛の購入金額や建物の建設金額から算定する場合が多くなっています。
具体的には、金額×業種(部門)毎に定まっている原単位で計算していきます。

ここでいう業種は、算定対象となる資本が形成された部門の業種(自社の業種)のことです。
例として、
食料品メーカーが機械を100万円で購入した場合は、
1[百万円]×3.14[tCO2eq/百万円]=3.14 [tCO2eq]
製材・木製品企業が社有車を320万円で購入した場合は、
3.2[百万円]×3.53[tCO2eq/百万円3.11.296 [tCO2eq]
農業サービスを行なっている企業が同じく社有車を320万円で購入した場合は、
3.2[百万円]×3.33[tCO2eq/百万円]=10.656[tCO2eq]
という形の算定になります。
▼出典:環境省HP 排出原単位データベース Ver.3.4 <2024年3月リリース>
資本財は、財務会計上は固定資産として扱われるものが該当することから、固定資産台帳などを見ながら購入金額を取得し算定していく場合が多いです。
▼おすすめのお役立ち資料

Scope3カテゴリ2を正確に把握するには?企業が取るべきステップ
Scope3カテゴリ2(資本財)の排出量を算定する際、サプライチェーンから具体的なデータを得られない場合は、上記の業界平均値や信頼性の高い排出原単位(排出係数)を用いた推計が一般的です。
しかし、より正確な把握を目指す企業は、サプライヤーとの協力を得て、以下のステップを踏むことが効果的です。
1. 資本財の特定
まず、自社が調達したすべての資本財を洗い出し、その内容を詳細に整理します。
- 設備の種類(例:製造ラインの機械、社用車、オフィスビル)
- 使用目的(生産効率の向上、物流インフラの整備など)
これにより、どの資産が排出量に大きな影響を与えるかを明確にできます。
例えば、製造業で導入する新しい工作機械や、建設業における大型インフラ設備などは、製造プロセスで多くの資源やエネルギーを消費します。
2. 製造時の排出量評価
次に、各資本財がどのような工程を経て製造されるかを把握し、ライフサイクルアセスメント(LCA)の手法で排出量を評価します。
- 原材料の採掘や加工
- 部品や機器の組み立て
- 製造・輸送プロセス
こうした「原材料調達から完成品になるまで」の工程を考慮することで、単なる金額ベースの推計よりも正確な排出量算定が可能になります。
3. データの収集と活用
理想的には、サプライチェーン全体から一次データ(製品ごとの具体的な排出量データ)を収集することです。
例えば、資本財を納品するメーカーが、自社製品の製造に伴うGHG排出量を算定して提供してくれる場合、それを直接利用することで高精度な算定が実現できます。
このようなプロセスを経ることで、企業はカテゴリ2に関する排出量をより正確に把握でき、サプライチェーン全体での脱炭素経営に向けた戦略立案にもつなげられます。
Scope3 カテゴリ2の削減施策
Scope3カテゴリ2の削減施策 ― 設計・調達段階でのアプローチ
Scope3カテゴリ2(資本財)は、建物や製造設備、IT機器、インフラなどの長期使用を前提とした資本財の製造プロセスにおける排出量を対象とします。
そのため、削減の出発点は「設計」と「調達」の段階から始まります。
設計段階での排出削減
最初の鍵となるのが、資本財の設計段階におけるCO2削減です。
ここでは「デザイン・フォー・サステナビリティ」という考え方が重要で、製品ライフサイクル全体を通じた環境負荷の最小化を目指します。
- 低炭素素材の活用:再生アルミニウム、グリーンスチール、バイオプラスチックなどの持続可能な資材を選定。
- 軽量化・モジュール化:原材料やエネルギー使用量を削減でき、将来的な再利用・リサイクルも容易に。
- 循環利用の設計:廃棄時を見据えた素材選定により、資源循環と排出削減を両立。

調達段階での排出削減
次に重要なのが「調達方針」です。企業はグリーン調達基準やサステナブル調達基準を設け、サプライヤーの環境対応力を評価する必要があります。
- 低炭素プロセスの採用:再生可能エネルギーを利用するサプライヤーや、省エネ技術を導入している企業を優先。
- 素材の見直し:自動車業界では、従来の高炭素鋼材を減らし、軽量かつ再生可能な素材を使用することで排出量削減を実現。
- サプライヤー協働:共同で再生可能エネルギー導入を進める事例も増加。結果として、排出量削減だけでなく、ステークホルダーからの信頼向上にもつながります。

👉 設計と調達は、資本財に伴う排出削減の「入口」であり、ここでの判断が将来のCO2排出に大きく影響します。
Scope3カテゴリ2の削減施策 ― 使用・廃棄段階でのアプローチと事例
資本財は導入後も長期にわたって利用されるため、「使用」と「廃棄」の段階においても排出量削減が求められます。
使用段階での排出削減
導入した資本財を効率的に運用することで、間接的な排出削減が可能です。
- IoT・AIの活用:設備稼働をリアルタイムで監視し、エネルギー使用を最適化。
- 再生可能エネルギーへの切替:工場やオフィスの電力を太陽光発電などでまかなう事例も登場。
- 効率改善の実例:工場全体の主要設備を再エネで稼働させ、GHG排出を実質ゼロに近づけている企業も存在します。

廃棄段階での排出削減
資本財のライフサイクル終了時には、リサイクルやリユースによる排出削減が中心的な施策となります。
- 建材の再利用:解体した建材を粉砕し、新たな建築物に活用。
- 部品の再加工:使用済み設備の部品を再利用して新製品の原材料に。
- 循環型プロジェクト:建設業や製造業では、廃材を資源循環に組み込む取り組みが広がり、廃棄物削減と排出削減を同時に達成しています。

サステナブル建築の事例
カテゴリ2削減の象徴的な取り組みが「サステナブル建築」です。
- 特徴:持続可能な材料の採用、断熱材や自然光活用によるエネルギー効率向上、雨水再利用や節水設備導入など。
- 国内事例:大林組の「Port Plus」(横浜市)―日本初の高層純木造耐火建築物として注目。
- 海外事例:コペンハーゲンの廃棄エネルギープラントなど、エネルギー効率とデザイン性を兼ね備えた施設が世界で増加中。
▼参考:モダンリビング 環境に優しく、美しい!世界の「サステナブル建築」22選

👉 使用・廃棄段階での工夫は、資本財を単なるコストではなく「持続可能な資産」へと変える大きなポイントで
まとめ
Scope3カテゴリ2は、企業が調達する建物や設備、IT機器、車両、インフラなどの資本財の製造段階で発生するCO2排出量を対象とする重要な領域です。
鉄鋼やセメントといった高炭素素材を多用するため、正確な算定と削減が企業の脱炭素経営に直結します。
算定では、購入金額と業種ごとの排出原単位を掛け合わせる方法が一般的ですが、LCAの活用やサプライヤーからの一次データ取得によって精度を高めることが可能です。
削減策は「設計・調達・使用・廃棄」の各段階で展開され、低炭素素材の採用、グリーン調達基準、IoTによる稼働効率化、リサイクル・リユースの推進などが効果的です。
特にサステナブル建築の事例は象徴的で、資本財を単なるコストから持続可能な資産へと転換する姿勢が企業価値を高めます。
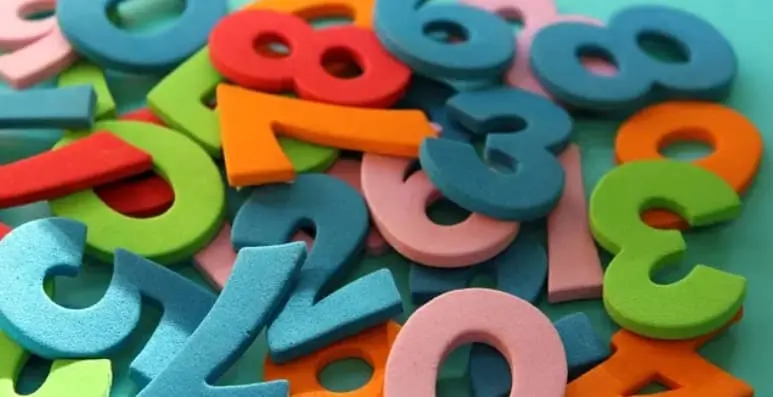
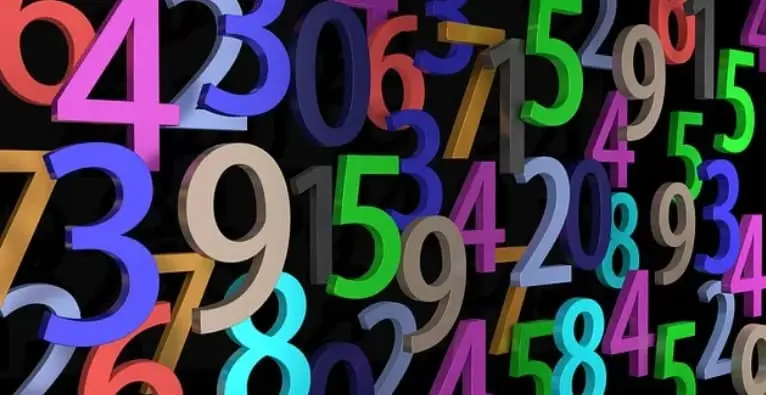
▼おすすめのお役立ち資料


