再エネ導入を考える企業必見|再生可能エネルギーの種類・導入方法・成功事例

世界的に脱炭素化の潮流が加速するなか、再生可能エネルギーの導入は企業にとって避けられない経営課題となりつつあります。
エネルギーコストの高騰や不安定化、カーボンプライシングや排出規制の強化、さらにはサプライチェーン全体での環境対応要求など、外部環境の変化は年々厳しさを増しています。
こうした背景のもと、再エネは単なる環境配慮の手段にとどまらず、企業価値を高め、事業リスクを低減する戦略的資源として位置づけられています。
とはいえ、「どの再エネが自社に適しているのか」「導入コストをどう抑えるか」といった疑問や課題に直面する担当者も多いのが実情です。
本記事では、再生可能エネルギーの基本的な定義や国際的な位置づけから、太陽光・風力・水力・地熱・バイオマスといった種類ごとの特徴、導入メリットと課題、さらに国内外の政策動向や先進企業の成功事例までを体系的に解説します。
技術革新や制度整備が進む今、再エネはもはや「将来の選択肢」ではなく、事業の持続性と競争力を左右する経営の中核要素です。
これからの戦略を検討する企業に向け、実務に役立つ視点と最新情報をご提供します。

再生可能エネルギーについて
再生可能エネルギーの定義と理解するポイント
再生可能エネルギーとは、自然界に存在し、持続的に再生される資源を利用したエネルギーを指します。
代表的なものとして太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスなどがありますが、これらに共通するのは「時間の経過とともに自然に回復・供給され続けるエネルギー源」である点です。
たとえば、太陽光は毎日地球に降り注ぎ、風は気圧差によって絶え間なく生まれ、水は水循環によって流れを維持し続けます。
これに対し、石炭や石油、天然ガスといった化石燃料は、形成に数百万年を要する有限資源であり、一度消費すると元に戻すことはできません。
再生可能エネルギーはこの点で、資源としての枯渇リスクが極めて低く、理論上は無限に利用可能なエネルギー形態と位置づけられます。
さらに、国際的にも共通の定義が採用されており、たとえば国際エネルギー機関(IEA)や国連の報告書では、「自然の過程で短期間に補充されるエネルギー」と明確に規定されています。
つまり、再生可能エネルギーは科学的・政策的に整理された枠組みのもと、脱炭素社会における中核的なエネルギー資源として認識されているのです。

企業が再エネを導入する際、この定義を正確に理解することで、エネルギー選定やCSR戦略において誤解や不整合を避けることができます。
また、サプライチェーンや取引先から求められる環境対応に対しても、正しい知識に基づいた判断が可能となり、信頼性ある意思決定に寄与します。


▼出典:資源エネルギー庁 再エネの導入
再生可能エネルギーの英語表現と国際的な視点
再生可能エネルギーは英語で「renewable energy」と表記されますが、この表現には単なる直訳を超えた背景があります。
国際的な議論においては、「renewable」の語には“繰り返し供給可能で、環境への影響が少ない”という概念が含まれており、単なる自然エネルギーとは一線を画します。
たとえば“clean energy(クリーンエネルギー)”や“green energy(グリーンエネルギー)”と混同されることもありますが、これらはあくまで環境負荷の少なさに着目した呼称であり、持続可能性という観点では「renewable energy」のほうがより厳密な分類になります。
また、再生可能エネルギーは国や地域によって適用範囲や分類が若干異なる場合もあります。
たとえば欧州連合(EU)では「再エネ指令(RED II)」に基づき、バイオマス燃料に対する持続可能性の基準が厳格化されており、単に“木を燃やす”行為が再エネと認定されるとは限りません。
一方、アメリカ合衆国では州ごとの定義が異なることもあり、再エネ証書(REC)の内容も多様です。
こうした定義の違いを把握することは、グローバル展開する企業や多国籍企業にとって特に重要です。
企業が英語圏や国際市場で再生可能エネルギーに関するレポートや開示資料を作成する際、「renewable energy」の正しい理解は情報発信の正確性を担保するうえで不可欠です。
また、RE100やCDP、SBTiなど国際的な枠組みと連携する場合も、英語での表現が評価に直結するため、用語の使い分けや定義の精緻さが信頼獲得に直結します。
グローバルな基準に沿った正確な理解と運用が、企業の国際的な競争力と透明性を高める鍵となるのです。



再生可能エネルギーの主な種類
太陽光エネルギー
太陽光エネルギーは、太陽から得られる光や熱を直接エネルギーへと変換する技術です。
代表的な例が太陽光発電(Photovoltaic、通称PV)で、半導体を利用した太陽電池により日射を電力へと変換します。
住宅や工場の屋根に設置する分散型設備から、メガソーラーと呼ばれる大規模な発電所まで幅広く展開されており、導入の柔軟性も魅力のひとつです。
また、太陽の熱を利用して温水を生成する太陽熱温水器や、鏡で太陽光を集めて蒸気を発生させる集光型太陽熱発電(CSP)といった方式も存在し、利用の幅は拡大しつつあります。


▼出典:資源エネルギー庁 再エネの導入
風力エネルギー
風の運動エネルギーを回転運動に変換し、電力を生み出すのが風力発電です。
広大な土地に複数の風車を設置する「風力発電所」は、陸上のみならず洋上にも展開されています。
近年では1基で数メガワット級の発電能力を持つ大型タービンの開発が進み、特に安定した風が得られる海上では、洋上風力が急成長しています。
風況調査や系統接続の整備が必要ではあるものの、用地確保が難しい地域でも実現性が高まっており、今後の拡大が期待されています。
水力エネルギー
水の落下や流れを利用して水車を回転させる水力発電は、再エネの中でも最も歴史が長く、かつ安定した出力が可能な電源です。
大規模なダム式に加え、河川の流れを直接活用する流れ込み式や、上下の貯水池間で水を移動させる揚水式といった方式が存在します。
特に揚水発電は、電力の需給バランスを調整する「蓄電池の代替」として機能し、他の再エネの不安定さを補完する役割も果たしています。

地熱エネルギー
火山帯などの地熱資源を利用する地熱発電は、地中深くから高温の蒸気や熱水を取り出してタービンを回す発電方式です。
立地に制限はあるものの、24時間稼働可能な「ベースロード電源」としての役割を担える貴重な再エネ資源です。
また、地中温度を活用した「地中熱ヒートポンプ」による冷暖房設備など、非発電用途での展開も広がっており、都市部への応用も注目されています。

バイオマスエネルギー
木材チップ、農業廃棄物、食品残さ、下水汚泥などの有機物を活用して発電するのがバイオマスエネルギーです。
直接燃焼による熱利用のほか、微生物の力でガス化して発電するバイオガス発電など、方法は多岐にわたります。
再生可能とはいえ、燃料の調達コストや持続可能性の確保が導入の鍵を握っており、資源循環や地域活性化との連携が重要視されています。


▼出典:資源エネルギー庁 再エネの導入
再生可能エネルギーの導入が企業にもたらすメリット
企業が再エネを導入する最大の理由は、コスト面・環境面・社会的評価のすべてにおいて優位性がある点にあります。
第一に、再エネは一度設備を設置すれば、運用コストの大半を占める燃料費が不要になります。近年では太陽光や風力の発電コストが急激に低下しており、太陽光パネルは2009年以降でおよそ90%価格が下落しました。
これにより、従来の火力発電よりも低コストで電力を調達できるケースも増えており、長期的な経営安定性の観点からも魅力的です。
さらに、再エネ電力はCO₂排出がほぼゼロであるため、直接的に温室効果ガス排出量の削減につながります。
これは企業の脱炭素戦略の中核となりうる要素であり、カーボンプライシングや排出規制の強化が進む中で、先手を打った対応ができるという利点もあります。

加えて、再エネへの積極的な取り組みは企業の環境意識や社会的責任(ESG)への配慮を社内外に示すものとなり、顧客・投資家・取引先からの信頼醸成にも貢献します。
特にRE100やCDPなどの国際的な評価基準に対応することで、グローバル市場における競争優位性の確保にもつながるでしょう。


▼出典:資源エネルギー庁 日本のエネルギー問題をグラフで学ぼう(後編)
導入時の課題とその解決に向けたアプローチ
一方で、再エネ導入には初期投資や技術的課題が伴います。
たとえば太陽光発電設備や風力タービンの導入には大きな設備投資が必要であり、企業によってはコスト回収期間の長さが導入判断の壁になることもあります。
こうしたハードルに対しては、国や自治体による補助金や税制優遇の活用、エネルギーサービス企業とのPPA契約による初期費用の回避といった手法が有効です。
また、太陽光や風力のような再エネは天候に左右されやすく、発電量が不安定であるという性質を持ちます。
これに対応するためには、蓄電池を併用した電力の安定供給や、需要側でのエネルギーマネジメント(ピークシフト・デマンドレスポンス)の導入が重要となります。
さらに、再エネ設備の立地条件も考慮すべき点です。風力発電には強風地域、地熱発電には高温地熱資源、水力には適した河川や地形が必要であり、都市部や狭小地では制約を受けやすい傾向にあります。
この課題に対しては、屋上・壁面への太陽光設置や、海上に浮かべるフローティング風力、地下空間を活用した地中熱など、省スペースでも機能する革新的な技術の導入が進められています。

世界各地域における再生可能エネルギー導入の現状と政策支援
再生可能エネルギーの導入は、世界中で急速に進展しています。
しかし、その導入スピードや政策的な後押しには地域ごとに明確な違いがあります。
ここでは、再エネを牽引する欧州・北米、急成長中のアジア、そして日本の状況について、それぞれの政策支援と導入動向を解説します。
欧州(ヨーロッパ)|再エネ先進地域の制度と実績
ヨーロッパは再生可能エネルギーの導入において世界をリードする地域であり、電力部門における再エネ比率も極めて高水準にあります。
欧州連合(EU)全体では、電力の約4割が再エネによってまかなわれており、なかでもデンマークやノルウェー、アイスランドといった国々では、風力・水力・地熱などを駆使し、ほぼすべての電力を再エネで賄う実績を築いています。
政策面では、EUが掲げる「2030年までに最終エネルギー消費の42.5%を再エネで達成する」という目標に向け、各加盟国が具体的な行動計画を策定中です。
この目標は従来の32%から大幅に引き上げられており、欧州が再エネ拡大に本腰を入れていることを示しています。
各国では、固定価格買取制度(FIT)、再エネ発電の優先接続、グリーン電力証書制度などが導入され、企業による再エネ活用が進みやすい環境が整っています。
特にドイツやスペイン、ポルトガルは、太陽光・風力の大量導入と電力系統の安定運用において豊富な知見を有しており、欧州全体としては2050年のカーボンニュートラルに向けて、再エネ比率のさらなる引き上げが計画されています。

北米(アメリカ・カナダ)|連邦・州レベルでの積極的な支援
アメリカもまた、再生可能エネルギーの導入が加速している地域のひとつです。
2022年の時点で、全米の電力の約27%が再エネ由来となっており、その主力は風力と太陽光です。特に風力発電においては世界第2位の発電量を誇り、太陽光も拡大が続いています。
アメリカ連邦政府は2022年に「インフレ抑制法(Inflation Reduction Act:IRA)」を成立させ、今後10年間で3,690億ドル規模の気候変動対策・再エネ支援を打ち出しました。
この法律により、太陽光や風力への投資税額控除(ITC)や生産税額控除(PTC)の延長・拡充が実現し、企業の再エネプロジェクトへの参入が加速しています。
さらに、カリフォルニア州をはじめとする多くの州が独自の再エネ義務化制度(RPS)を導入しており、2035年までに100%のクリーン電力を目指す動きも活発です。
隣国カナダでは水力発電が主要な電源となっており、再エネ比率の高さと電力の安定供給を両立しています。
北米全体として、政策支援と市場の成熟が再エネ拡大の大きな追い風となっています。

▼出典:国際環境経済研究所 再エネ導入が停電を引き起こしたカリフォルニア州 バランスがとれた電源開発が必要不可欠
アジア(中国・インド・新興国)|スケールと成長力が鍵
アジア地域では、再エネ導入の進捗に国ごとの差が見られますが、全体として世界の再エネ拡大を牽引する地域となりつつあります。
その中でも圧倒的な存在感を示すのが中国です。
中国は再エネ設備の導入量で世界最大となっており、2022年には太陽光発電の新規導入量だけで他国の合計に匹敵する規模を記録しました。
2023年にはその規模がさらに倍増し、世界市場の価格低減にも大きく寄与しています。
中国政府は2030年までに風力と太陽光で計1,200GW以上を導入するという目標を掲げており、すでにこの目標は前倒しで達成されつつあります。
また、再エネ分野のサプライチェーンにおいても、太陽光パネルや風力タービンの主要生産国として世界的に影響力を持つ国へと成長しています。

※中国の電源比率の変化

インドも再エネ拡大に積極的な国の一つで、2030年までに非化石電源容量500GWの達成を目指し、太陽光や風力の導入を国策として推進しています。
東南アジア諸国では再エネの普及はまだ初期段階ですが、近年は太陽光を中心に民間主導のプロジェクトが増加中です。
アジア全体の再エネ比率は約26%ですが、中国・インド以外の国では石炭火力への依存が依然として大きく、技術移転や国際的な資金支援が今後のカギを握ります。
日本|制度整備と課題解決の両立を模索
日本では、2011年の東日本大震災を契機にエネルギー政策が大きく見直され、再エネの導入が本格化しました。
2012年に導入された固定価格買取制度(FIT)により、太陽光発電の導入が急速に進み、2022年度には再エネ比率が21.7%まで上昇しています。
内訳としては、太陽光が約10%、水力が8~9%、風力・バイオマスが各2~3%、地熱は1%未満といった構成です。
政府は2050年のカーボンニュートラル達成に向けて、2030年度の電源構成における再エネ比率を36〜38%へと大幅に引き上げる目標を掲げており、これは従来の22〜24%からの抜本的な見直しです。
政策面ではFITに加え、FIP(市場連動型)制度の導入や、送電網への優先接続、有望な洋上風力エリアの指定といった施策が強化されています。
また、非化石証書やグリーン電力証書を通じた企業向けの選択肢も拡充されています。

ただし、日本は地理的制約や送電網の容量不足、蓄電設備の整備の遅れといった課題も抱えており、大量導入には系統インフラの抜本的な強化が不可欠です。
今後は、技術革新と制度改革の両面から持続可能な再エネ拡大を実現する必要があり、企業と政府の連携による市場形成が鍵を握るでしょう。
※2023年の電力部門における再生可能エネルギーの割合

▼参考:A look at world’s largest electricity producers and how much is from renewables
企業による再生可能エネルギー導入の事例とベストプラクティス
世界の主要企業は、温室効果ガスの削減とエネルギーコストの安定化を両立する手段として、再生可能エネルギーの導入を本格的に進めています。
中には、使用電力の100%を再エネで賄うことを掲げ、すでに実現に至っている企業もあります。
ここでは、国際的な代表企業の先進事例と、企業が実践する再エネ導入のベストプラクティスを紹介します。
Amazon|グローバルとローカルを両立する戦略
世界最大規模の再生可能エネルギー購入企業であるAmazonは、グローバルな脱炭素目標の達成に向けて、日本市場でも再エネ導入を急速に拡大しています。
2025年1月、Amazonは新たに4件の大規模太陽光発電所への出資を発表。
これにより、日本国内で関与する再エネプロジェクト数は合計25件、累計発電容量は211MWに到達し、わずか1年でその規模を2倍以上に拡大しました。
▼参考:Amazon、日本で4件の新たな再生可能エネルギープロジェクトを発表
Amazonは、2040年までにカーボンニュートラルを達成することを目指す国際誓約「The Climate Pledge」の共同創設者として、目標に対する説明責任と実行力の両立を掲げています。
25件の国内プロジェクトがすべて稼働すれば、年間32万MWhを超える再生可能エネルギーの供給が見込まれ、これは一般家庭約76,000世帯の年間使用電力量に匹敵します。
この供給電力は、Amazonが日本国内で運営する物流拠点やクラウドデータセンターの運用を再エネで賄うための基盤となっており、企業活動と環境配慮の両立を体現する先進モデルです。
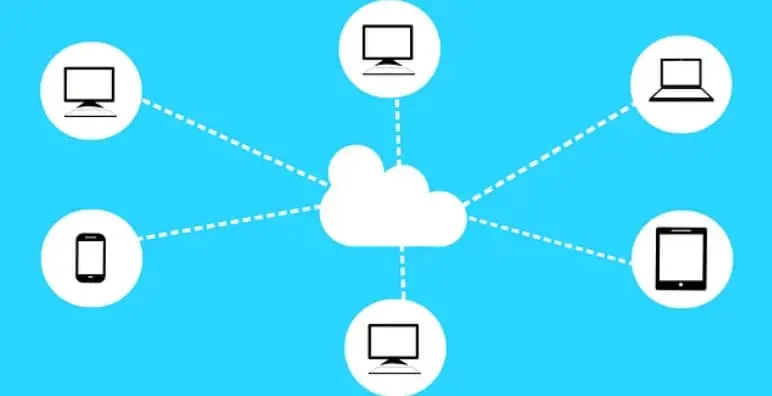
Google|24時間365日カーボンフリーを目指す先駆者
IT業界の巨頭であるGoogleは、2017年に年間消費電力量に相当する再生可能エネルギーを購入することで、実質的に「再エネ100%」を達成。
その後もこの水準を維持しています。2020年時点では、世界中で50以上の風力・太陽光発電プロジェクト(合計5.5GW)との長期電力購入契約(PPA)を締結し、自社のデータセンターやオフィスに供給してきました。
現在Googleはさらに踏み込み、「24時間365日すべての時間帯で、使用電力をカーボンフリー電力でまかなう」という高難度な目標に挑んでいます。
単なる年間総量の一致ではなく、時間単位で再エネ利用を一致させるという挑戦は、電力業界に革新的な影響を与えています。
▼参考:新しいクリーン エネルギー購入モデルで脱炭素化を促進
Apple|グローバルなクリーンエネルギー戦略を構築
Appleもまた、再生可能エネルギーの導入において世界をリードする企業の一つです。
2018年には、直営店、オフィス、データセンターなどを含む43か国すべての事業拠点で消費する電力を100%クリーンエネルギーでまかなったと公表しました。
自社所有の発電施設の建設だけでなく、各国のグリーン電力メニューの活用、証書の活用など、多様な戦略を組み合わせた成果です。
さらに注目すべきは、Appleが自社だけでなく、サプライヤーにも再エネ導入を強く求めている点です。
同社の報告によれば、2011年以降におけるScope1および2の温室効果ガス排出量は54%削減され、累計で210万トンのCO₂削減を達成しました。
2030年までにはバリューチェーン全体でのカーボンニュートラル化を目指しており、環境配慮の徹底ぶりが際立っています。
▼参考:Appleと世界中のサプライヤーが再生可能エネルギーを13.7ギガワットに拡大
IKEA|自社発電による「再エネの純売り手」へ
スウェーデン発の世界的家具ブランドIKEAを展開するIngkaグループは、自社による再エネ生産でも世界の最前線に立っています。
各国で運用する547基の風力タービン、10か所の太陽光発電所、さらに店舗や倉庫の屋根に設置した約93万5千枚のソーラーパネルを活用し、総発電容量は1.7GWに達しています。
これはグループ全体の電力需要を上回る規模であり、事実上「再エネの純売り手」となっている点が他企業と一線を画しています。
IKEAは2030年までに再エネ関連投資をさらに加速させ、総額40億ユーロの資金を蓄電池、水素などの次世代エネルギー技術に投入する計画も公表しています。
このように、再エネの導入をコスト削減ではなく「価値創造」として捉えている姿勢が、同社の競争優位性を支えています。
RE100への参加と企業による再エネ調達の多様化
世界中で400社以上の企業が参加する国際イニシアチブ「RE100」は、企業が自社の使用電力を100%再生可能エネルギーに切り替えることをコミットする枠組みです。
日本からはリコー、ソニー、富士通、セイコーエプソン株式会社などが加盟しており、2017年にリコーが日本企業として初めてRE100に参加したことは、国内でも象徴的な出来事でした。
これらの企業は、再エネ導入を実現するために次のような戦略を組み合わせています。
- 自社施設に太陽光パネルを設置し、発電した電力を自社で使用(オンサイト型)
- 発電事業者との長期契約(PPA)を通じて電力を直接調達(オフサイト型)
- トラッキング付き非化石証書やグリーン電力証書を活用し、実質的な再エネ利用を実現

特に都市部のように物理的な設備導入が難しい拠点では証書を活用し、地方の工場や倉庫では発電設備を活用するなど、拠点の特性に応じた戦略的な電源切り替えが進められています。
さらに、先進的な企業の多くは、自社だけでなくサプライヤーにも再エネ活用を求めており、バリューチェーン全体での温室効果ガス削減(Scope3対応)を進める動きも活発化しています。
これは企業のESG評価向上のみならず、取引先との信頼強化や、将来的な規制への備えという面でも大きな意味を持ちます。


将来展望と技術革新の方向性|再エネは「主力電源」へ進化する
技術革新が切り拓く再エネの未来
再生可能エネルギーは今後、発電コストや安定供給の面でさらに進化し、企業にとっても導入のハードルが大きく下がると予想されています。
実際、2023年時点で世界の発電電力の約3割が再エネによってまかなわれ、その中心を担ったのが太陽光と風力でした。
各国の脱炭素政策と市場成長を背景に、この比率は2030年代にかけてさらに上昇し、再エネが世界の主力電源の一角を占める時代が現実となりつつあります。
この流れを支えているのが、発電技術の進化です。
太陽光分野では、従来のシリコン型に代わる高効率な次世代太陽電池(ペロブスカイト型など)の開発が進み、発電効率と軽量性の両立が期待されています。
風力分野では、陸上に加えて浮体式洋上風力の実用化が進み、これまで設置できなかった深海域にも導入が広がっています。
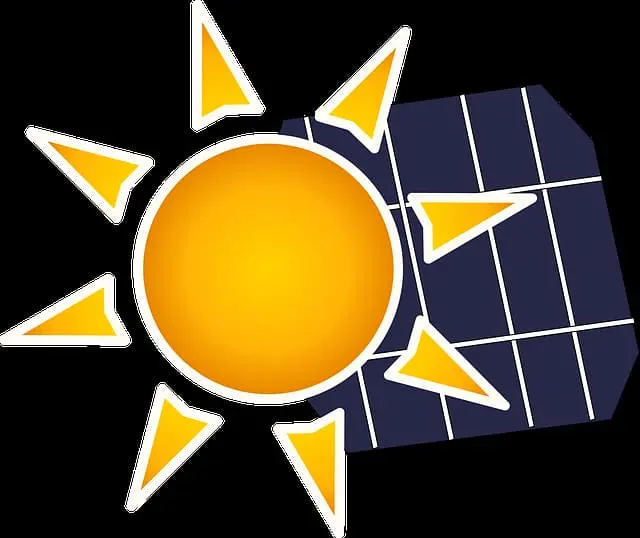
※ペロブスカイト太陽電池の用途や目的に応じた種類

▼出典:日本の再エネ拡大の切り札、ペロブスカイト太陽電池とは?(前編)~今までの太陽電池とどう違う?
また、地熱では「改良型地熱システム(EGS)」と呼ばれる新技術により、地熱発電の適用地域が大幅に広がる可能性が出てきました。
さらに、バイオマスの分野では、藻類や廃棄物を利用した燃料開発が加速しており、資源循環型のエネルギーとして注目を集めています。
蓄電・水素・デジタル技術が再エネの弱点を克服する
技術革新のもう一つの焦点は、再エネの構造的課題である発電量の不安定さを克服する領域にあります。
昼夜や天候によって出力が変動する再エネを、安定した電源として活用するには、蓄電技術と需給調整機能の強化が不可欠です。
近年は、大容量のリチウムイオン電池やレドックスフロー電池の価格が下がり、夜間利用やピーク電力の平準化がより現実的になっています。
さらに、再エネ由来の電力で水を電気分解し、CO₂を排出せずに製造する「グリーン水素」が、長期的なエネルギー貯蔵・運搬手段として世界的に注目を集めています。
水素やアンモニアを使って季節をまたぐ電力供給を可能にする構想も現実味を帯びており、次世代エネルギーの本命と目されています。

また、AIやIoTを活用した電力システムのスマート化も着実に進展しています。
需要予測や分散型電源の統合制御により、仮想発電所(VPP:Virtual Power Plant)の実証が各地で進んでおり、再エネを中心とした安定的な電力インフラの構築が視野に入っています。
これらの進展により、再エネは「高コスト・不安定」といった旧来の評価から脱却し、コスト競争力と信頼性を兼ね備えた戦略的電源へと変貌しています。
企業にとっても、再エネの導入は単なる環境配慮ではなく、競争力強化と経営リスク低減を実現する合理的な選択肢になりつつあります。


出典:2024年度定置用蓄電システム普及拡大検討会の結果とりまとめ
まとめ
企業が再生可能エネルギーを導入する意義は、単なる環境対応にとどまりません。
再エネは脱炭素経営の中核を担うと同時に、エネルギーコストの削減、社会的信頼の向上、国際競争力の確保に直結する「経営資源」となりつつあります。
本記事では、再エネの定義や種類、各種電源の特徴から、導入メリット・課題、世界と日本の政策支援、企業の先進事例、そして今後の技術革新の方向性まで、企業担当者が再エネ導入を検討する上で押さえておくべき全体像を体系的に解説しました。
再エネはもはや一部の先進企業だけの取り組みではなく、あらゆる業種にとって不可避の経営課題です。
将来を見据えた事業戦略の一環として、再エネ活用の選択肢を本格的に検討する時期に来ているといえるでしょう。
