オンプレミスからAWSクラウドに移行で温室効果ガスを削減
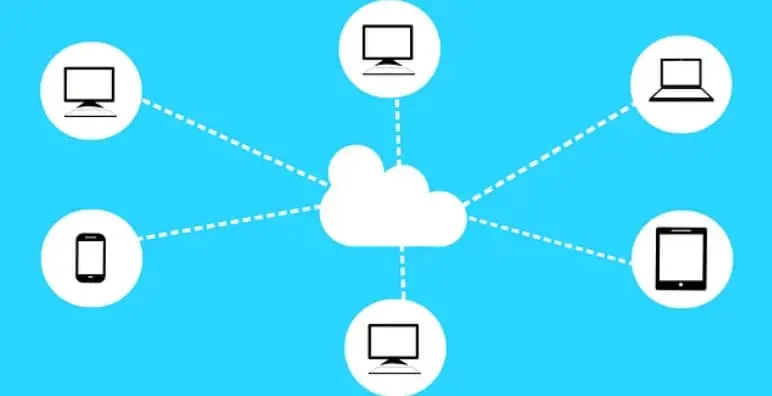
デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速やクラウドサービスの普及、AI・機械学習の利用拡大、5Gの普及とIoTの進展により、データセンターへの需要が世界的に高まっています。
この需要に伴う環境への影響や、ITインフラ全体の持続可能性についても、多くの関心が寄せられています。
こうした背景から、Amazon Web Services(AWS)は、企業のワークロードをオンプレミス環境からAWSクラウドへ移行し、さらにAWSクラウド上で最適化することで、エネルギー効率を高め、温室効果ガス(GHG)排出量を削減できる可能性についての調査レポートを2024年8月27日発表しました。
この調査は、アクセンチュアによって行なわれ、オンプレミス環境とAWSクラウドの持続可能性を詳細に比較しています。

オンプレミスとクラウドについて
オンプレミスとは、企業や組織が自社の敷地内にITインフラやソフトウェアを設置・運用する形態を指します。
具体的には、サーバー、ストレージ、ネットワーク機器、ソフトウェアなどを自社内のデータセンターやサーバールームに設置し、社内のITチームがこれらの機器やシステムを管理・運用します。
クラウドとは、インターネットを通じて、コンピュータリソース(サーバー、ストレージ、データベース、ネットワーキング、ソフトウェアなど)をオンデマンドで提供するサービスを指します。
クラウドコンピューティングでは、これらのリソースは物理的なハードウェアに依存せず、リモートにあるデータセンターで管理され、利用者はそのリソースを必要に応じて利用できます。

▼出典:総務相 情報通信分野の現状と課題
オンプレミスでは、初期費用が高いが、長期的には一定のコストで運用可能な点、セキュリティやコンプライアンス要件が厳しい場合や、ハードウェアやソフトウェアのカスタマイズを自由に行ないたい場合に選ばれます。
クラウド、初期投資が少なく、利用するリソースに応じた従量課金制が一般的で、簡単にスケールアップやスケールダウンが可能で活用する範囲を柔軟に設定できます。
また、ハードウェアやインフラの管理が不要で、迅速にサービスを展開できるところが好まれます。
世界的に、オンプレミスシステムからクラウドシステムへの移行は急速に進んでおり、デジタルトランスフォーメーションの一環として、企業や組織がクラウドを活用する動きが顕著になっています。
特に技術の進展やビジネスのグローバル化が、この移行をさらに後押しする要因となっています。
また、クラウド移行は単なる技術的な変革にとどまらず、ビジネスモデルの変革や競争力の強化にも寄与しています。

▼出典:総務相 情報通信分野の現状と課題
データセンターでのハードウェア効率化
データセンターにおけるハードウェアの効率化は、エネルギー消費の削減や運用コストの低減、パフォーマンスの向上を目的としてさまざまな技術やアプローチが採用されています。以下に、主な効率化手法を紹介します。
・仮想化技術
仮想化により、1台の物理サーバーで複数の仮想マシン(VM)を稼働させることができます。
これにより、サーバーの使用率が向上し、物理的なハードウェアの数を削減できます。結果として、消費電力と冷却コストも減少します。
・エネルギー効率の高いプロセッサーとコンポーネント
最新のCPUやGPUは、性能を向上させつつ、消費電力を抑える設計がされています。
たとえば、インテルやAMDの最新世代のプロセッサーは、パフォーマンスパーワットの向上を重視しています。
また、NVMe SSDなどの高速ストレージは、従来のHDDよりもエネルギー効率が高いです。
・パワー・マネジメント機能の活用
サーバーやネットワーク機器に搭載されているパワー・マネジメント機能を活用することで、使用していないリソースの消費電力を削減できます。
例えば、アイドル状態のコアを休眠状態にすることで、エネルギーを節約します。
・液冷システム
従来の空冷システムよりも効率的に熱を除去できる液冷システムを導入することで、データセンター内の温度管理が改善され、エネルギー消費を削減できます。
液冷技術は、特に高密度なサーバーラックや高性能コンピューティング(HPC)環境で効果を発揮します。
・廃熱の再利用
データセンターで発生する廃熱を再利用するシステムが開発されています。
例えば、廃熱を地域暖房や他の工業プロセスに利用することで、エネルギーの無駄を減らし、環境負荷を軽減します。
・次世代メモリ技術
低消費電力かつ高効率な次世代メモリ技術(例:DDR5、HBM)を導入することで、データ処理のパフォーマンスを向上させつつ、消費電力を削減できます。
・再生可能エネルギーの活用
データセンターの運営に再生可能エネルギーを使用することで、環境への影響を最小限に抑えると同時に、長期的にはエネルギーコストの削減も期待できます。
これらの技術やアプローチを組み合わせることで、データセンターにおけるハードウェアの効率化が可能となり、持続可能な運用が実現できます。
上記のような効率化を突き詰めているサービスの1つがAWSとなります。

AWS調査の主な結果
調査によれば、AWSクラウドはオンプレミスのインフラと比較して最大4.1倍のエネルギー効率を実現することができるとのことです。
また、AWSクラウド上でワークロードを最適化することで、関連するGHG排出量を最大99%削減できることが明らかになりました。
GHG排出量削減: ワークロードの種類に応じて、AWSへの移行により大幅なGHG排出量削減が期待できます。

たとえば、ファイル専用ストレージデバイスでの活用などストレージ負荷が高いワークロードでは、オンプレミス環境からAWSクラウドへ移行することでGHG排出量を最大88%削減でき、さらにAWSの最適化により追加の47%の削減が見込まれます。
これにより、合計で最大93%の削減が可能です。
一方、AIのトレーニングや複雑なシミュレーションなど計算負荷が高いワークロードでは、AWSクラウドへの移行によるGHG排出量の削減が最大94%に達し、さらにAWSのカスタムシリコンを使用することで、追加の81%削減が可能となり、合計で最大99%の削減が達成できます。
地域別の調査
調査では、各地域におけるAWSクラウドへの移行と最適化の効果も分析されています。
地域ごとの結果は以下の通りです。
米国・カナダでは、AWSクラウドへの移行により、オンプレミス環境と比べて最大でGHG排出量を99%削減することができます。
エネルギー効率は最大3.6倍向上します。
EU、欧州連合においても、AWSクラウドの使用により、GHG排出量を最大99%削減できることが示されており、エネルギー効率も3.3倍向上します。
アジア太平洋(APAC)では、GHG排出量が最大97%削減され、エネルギー効率が3.2倍向上します。
この地域では、高温多湿な気候条件により、データセンターのエネルギー効率が他の地域に比べて低いことから、AWSへの移行の効果が顕著です。
ブラジルでは、AWSクラウドへの移行によって最大96%のGHG排出量削減が可能であり、エネルギー効率も4.1倍向上します。
ブラジルの電力の90%以上がカーボンフリーであるため、オンプレミス環境における削減の余地が限られていますが、AWSの最適化によりさらに削減が進みます。

▼出典:総務相 情報通信分野の現状と課題
AWSインフラのメリット
AWSは、エネルギー効率を向上させるために、Graviton、Trainium、Inferentiaといったカスタムチップを開発しています。
これらのチップは、高性能でありながらエネルギー消費を抑え、運用上の炭素排出量を大幅に削減します。
たとえば、AWS Trainiumは機械学習モデルのトレーニングに要する時間とコストを大幅に削減し、生成AIの運用効率を高めます。
AWSは、2025年までに電力使用を100%再生可能エネルギーに転換することを目指しています。
2022年には19のAWSリージョンで100%再生可能エネルギーが使用されました。
これにより、AWSクラウドのデータセンターは、オンプレミス環境に比べて持続可能性の高い運用が可能です。
まとめ
データセンターの電力使用量が世界的に増加し続ける中、企業がエネルギー効率を高め、GHG排出量を削減するためには、AWSクラウドへの移行が効果的な手段であることが示されています。
AWSのインフラストラクチャは、エネルギー効率の向上やカーボンフリーエネルギーの調達により、環境への負荷を大幅に低減できます。
AWSクラウドの利用による持続可能性の向上は、企業がグローバルな環境目標を達成するための重要な要素となるでしょう。
▼参考:new-report-how-moving-onto-the-aws-cloud-reduces-carbon-emissions
https://sustainability.aboutamazon.com/carbon-reduction-aws.pdf
