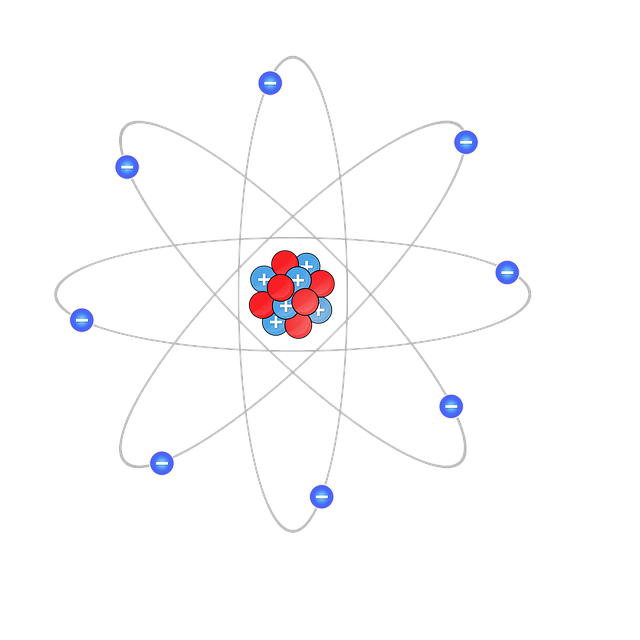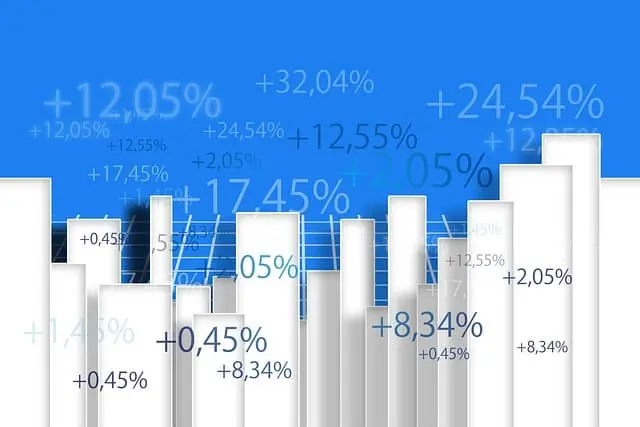ESG経営– category –
-

参加レポート│東洋経済主催【この統合報告書がすごい!】
― 統合報告書の“勝ち筋”を読み解く:企業価値を語るレポートづくりとは ― 統合報告書は、ここ数年で「CSR報告書の延長」から「企業価値を語る財務ドキュメント」へと大きく進化しました。一方で、 ESG投資への逆風 欧米を中心とした規制緩和の動き 日本に... -

企業の省エネ診断:導入メリット、診断プロセス、成功事例でわかるROI(投資利益率)
電気代やガス代がじわじわ上がり、「省エネをやらないと」と感じつつも、何から手を付ければいいのか分からない――そんな企業は少なくありません。 省エネ診断は、空調やボイラー、圧縮空気、照明などのエネルギーの使われ方をデータで可視化し、削減額と投... -

非上場企業・中小企業向け|SSBJ開示の波及効果と金融機関のサステナビリティ融資対応戦略
サステナビリティ開示は「上場企業だけの話」と思っていませんか。現実にはその影響はすでに非上場企業・中小企業へ波及しており、静かに経営条件を変え始めています。 大企業はSSBJやIFRS S2に対応する中で、Scope3排出量や移行計画を開示しなければなり... -

環境ラベル(マーク)の種類と取得基準|企業のサステナ経営に欠かせない認証制度を整理
環境配慮をうたう製品や企業が増えるなかで、「その主張は本当に信頼できるのか?」という問いが世界的に高まっています。そんな時代において注目されているのが、環境ラベル(エコラベル)です。 環境ラベルは、製品やサービスが環境負荷の低減にどれほど... -

カーボン(炭素)とは何か?脱炭素社会を支える科学的な基礎知識
炭素は、地球のあらゆる営みを支える“見えない骨格”です。空気中を漂う二酸化炭素として、生命の体をつくる有機物として、そして産業を動かすエネルギーとして——炭素は常に姿を変えながら、自然と人間社会の間を循環しています。 かつては「燃やすもの」と... -

LCAを学ぶなら知っておきたいISO 14040|ライフサイクルアセスメントの基本構造
持続可能な社会への転換が急速に進むいま、企業や自治体が環境対策を実行する上で欠かせないのが「ライフサイクルアセスメント(LCA)」です。その中核に位置する国際規格がISO 14040。 製品やサービスの誕生から廃棄・リサイクルまでの全過程を対象に、環... -

LCA(ライフサイクルアセスメント)とは?ISO規格と算定方法を専門家がわかりやすく解説
LCA(ライフサイクルアセスメント)は、製品やサービスが生まれてから廃棄されるまでのすべての過程を科学的に評価し、環境負荷を「見える化」する国際的な手法です。 原材料の採掘、製造、流通、使用、そしてリサイクルや廃棄まで――いわゆる「ゆりかごか... -

世界と日本のサステナブルツーリズム|観光地の事例から学ぶ持続可能な旅の形
観光産業は世界のGDPの約1割を占め、日本でも成長戦略の柱とされる重要な分野です。しかし、観光客の増加は必ずしも地域の幸福につながるとは限りません。交通機関による温室効果ガスの排出や自然景観の破壊、文化遺産への過剰な利用など、観光は環境や社... -

EUDR規制とは?最新動向、施行延期と簡素化ガイダンスのポイント解説
EUDR(EU森林破壊防止規則)は、EU市場に流通する製品が森林破壊や違法伐採に関与していないことを義務化する新しい国際規制です。 対象は牛肉、木材、天然ゴム、パーム油、大豆、カカオ、コーヒーの7産品とその派生製品で、日本の自動車、食品、化粧品、... -

FSCマークの意味と種類|FSC認証取得で広がる企業の信頼と市場機会
森林資源の持続可能な利用が世界的な課題となる中、国際的に広く認知されているのがFSC認証です。 製品やパッケージに付されたFSCマークは、違法伐採を排除し、森林を守りながら生産された素材であることを第三者が保証するシンボルであり、消費者にとって... -

企業が押さえるべき再生プラスチックの活用法|導入メリットと課題
世界的にプラスチックごみによる環境問題が深刻化する中、注目を集めているのが 再生プラスチック です。これは一度使われたプラスチックを回収し、再資源化して新しい原料として生まれ変わらせる仕組みであり、従来であれば埋立や焼却に回っていた廃棄物... -

温室効果ガス削減と経済原単位目標とは?日本の政策と企業の対応ポイント
気候変動が世界的に深刻化するなか、温室効果ガス(GHG)の削減は企業にとって避けられない経営課題となっています。 日本政府は2030年度に2013年度比で46%削減、さらに2035年度には60%、2040年度には73%削減という野心的な総量目標を掲げ、国際社会へ...