世界と日本のサステナブルツーリズム|観光地の事例から学ぶ持続可能な旅の形

観光産業は世界のGDPの約1割を占め、日本でも成長戦略の柱とされる重要な分野です。
しかし、観光客の増加は必ずしも地域の幸福につながるとは限りません。交通機関による温室効果ガスの排出や自然景観の破壊、文化遺産への過剰な利用など、観光は環境や社会に負の影響を及ぼすリスクを抱えています。
さらに京都やバルセロナに見られる「オーバーツーリズム」は、住民の生活環境を悪化させ、地域経済の収益が大手資本に偏るという問題も指摘されています。
こうした背景から注目されているのが「サステナブルツーリズム(持続可能な観光)」です。これは単に観光客数を増やすのではなく、環境保護・文化継承・経済循環の3本柱を両立させ、地域社会に長期的な価値を残す観光のあり方を意味します。
日本では観光庁がJSTS-Dを策定し、大洲市やみなかみ町が先進事例として評価されています。
海外でもハワイの「マラマハワイ」やカナダ・フォーゴ島の取り組みが成功を収めており、旅行者自身が資源を守る主体となる姿勢が広がっています。
一方で、グリーンウォッシングや資金不足、合意形成の難しさといった課題も残されています。
今後はAIやビッグデータによる混雑管理、透明性の高い認証制度、住民参加型の観光経営が求められるでしょう。
サステナブルツーリズムは、観光産業の未来を守るための必須条件であり、持続可能な社会を築くための重要な手段なのです。

サステナブルツーリズムとは
サステナブルツーリズム(持続可能な観光)とは、観光が環境・社会・経済に与える影響を考慮し、現在と未来の世代が持続的に利益を享受できるように設計された観光のあり方を指します。
国連の専門機関「UNツーリズム(旧UNWTO)」はその定義の中で、旅行者・観光産業・受け入れ地域・自然環境という四者の利益を調和させることを強調しています。
観光は地域活性化の手段であると同時に、自然破壊や文化摩耗の要因にもなり得ます。
そのため、単なる「観光客数の増加」ではなく、地域社会に長期的な価値をもたらす観光が求められているのです。
定義を支える「3本柱」
サステナブルツーリズムを理解するうえで欠かせないのが、以下の「3本柱」です:
- 環境の持続可能性
観光による自然環境への負荷を抑え、生態系や景観を守ること。
例:使い捨てプラスチック削減、再生可能エネルギーの導入、自然公園の保全。 - 社会文化の持続可能性
地域固有の文化や伝統を尊重し、観光を通じて継承・発展させること。
例:伝統工芸や祭りの支援、地域住民との交流を促進する観光プログラム。 - 経済の持続可能性
地域社会に安定した収益と雇用をもたらす仕組みをつくること。
例:地産地消の推進、観光収益を公共サービスや文化財保全に還元。
この三位一体の枠組みによって、観光は「短期的な利益追求」から「地域の未来を守る仕組み」へと変化していきます。

エコツーリズムやリジェネラティブとの違い
サステナブルツーリズムは広義の概念であり、そこから派生した形として「エコツーリズム」や「リジェネラティブ・ツーリズム」が存在します。
- エコツーリズム
自然環境に特化した観光形態。自然保護区や生態系を学びながら保全に貢献することを目的とする。 - グリーンツーリズム
農山漁村での滞在や交流を通じ、農業・地域文化を支える観光。 - リジェネラティブ・ツーリズム
サステナブルを超えた新潮流で、「現状維持」ではなく訪れる前より良い状態にして地域を残すことを目指す観光。
例:植林活動、サンゴ礁再生活動、文化遺産修復への旅行者参加。
つまり、サステナブルツーリズムが「害を最小化する観光」だとすれば、リジェネラティブは「善を生み出す観光」と表現できます。

なぜ今必要なのか
観光産業は世界のGDPの約1割を占める巨大産業であり、日本でも重要な成長エンジンとして位置づけられています。しかし、その一方で観光は環境破壊・文化摩耗・地域経済の不均衡といった負の影響を引き起こすリスクを抱えています。
持続可能な観光地経営を進めなければ、地域の資源は消耗し、観光そのものが立ち行かなくなる可能性があります。
こうした背景から、サステナブルツーリズムは今や「選択肢」ではなく「必須条件」になりつつあるのです。
観光と環境・文化への影響
従来の大量消費型の観光は、交通による温室効果ガス排出、自然景観の破壊、野生生物の生息域縮小など、地球規模の環境負荷を拡大させてきました。
また観光客の急増は、歴史的建造物や文化遺産への過剰な利用圧力を生み、地域の「真正性(オーセンティシティ)」を損なう危険性がありますサステナブル・ツーリズム調査報告。
そのため近年は、旅行者の行動を環境保護と文化継承に結びつける仕組みが求められています。
具体例としては、国立公園での利用制限や、観光収益を祭り・伝統工芸の保存に充てる地域の取り組みなどが挙げられます。
観光が環境や文化を守りながら経済を生み出す「循環型の仕組み」を築けるかどうかが重要なポイントです。


▼出典:京都サステナツーリズム
オーバーツーリズムと地域経済の課題
京都やバルセロナに代表されるように、観光客が集中する「オーバーツーリズム」は、渋滞・騒音・ごみ問題・住民の生活悪化といった深刻な課題を引き起こしますサステナブル・ツーリズム調査報告。
さらに、旅行者の増加が必ずしも地域経済の安定につながらない点も見逃せません。
大量の観光客が訪れても、大手資本のホテルやプラットフォームに収益が偏れば、地元経済に還元される割合は小さくなります。
この課題を解決するには、観光客数ではなく「質」に注目した戦略が必要です。
たとえば、閑散期の誘客や宿泊税・入場料の活用による観光収益の再投資、地域住民が関与する体験型観光の導入などが有効策とされています。
観光の利益が地元に循環する仕組みを整えることが、サステナブルツーリズム実現のカギとなります。

▼出典:京都サステナツーリズム
日本と海外の取り組み事例
日本におけるサステナブルツーリズム
日本では、観光庁が中心となって「JSTS-D(Japan Sustainable Tourism Standard for Destinations)」という日本版ガイドラインを策定しています。
これは国際基準であるGSTC(Global Sustainable Tourism Council)の枠組みを踏まえつつ、日本の地域性に合った形で観光地の持続可能性を評価・認証する仕組みです。
環境保護だけでなく、地域文化の保全や住民参加、経済的な持続性といった観点をバランスよく取り入れている点が特徴です。
具体的な先進事例として、次の2つが注目されています。
- 愛媛県大洲市
城下町の歴史的建造物を改修し、分散型ホテル「NIPPONIA HOTEL 大洲 城下町」として再活用。
宿泊客がまち全体を楽しむ仕組みをつくり、観光収益が地域に広く循環するモデルを実現しました。 - 群馬県みなかみ町
豊かな自然環境を活かし、エコツーリズムやラフティングを軸とした観光を展開。
2017年にはユネスコエコパークにも認定され、地域全体で自然と共生する観光の形を体現しています。
これらの取り組みは「観光客数の拡大」ではなく、地域資源を守りながら質の高い観光体験を提供する方向性を示しています。

海外におけるサステナブルツーリズム
海外では、サステナブルツーリズムの成功事例が観光政策や地域経営のモデルとして注目されています。
- ハワイ州「マラマハワイ」
「旅行者自身が自然と文化を守る一員になる」という考え方のもと、ビーチクリーンや植林活動、文化体験への参加を促すプログラムを展開。観光客が単なる消費者ではなく、地域再生の担い手になる仕組みを築いています。 - カナダ・ニューファンドランド島のフォーゴ島
過疎化に直面していた漁村で、ソーシャル・エンタープライズ「フォーゴ・アイランド・イン」が開業。
地元の大工・職人・アーティストを巻き込み、宿泊と文化体験を組み合わせた観光を展開。収益は地域社会に還元され、観光による経済再生と文化継承の好例となっています。
これらの事例に共通しているのは、地域資源を観光の核に据え、旅行者を「参加者」として巻き込む姿勢です。
日本でも応用可能な要素が多く、今後の地域観光戦略の参考になります。
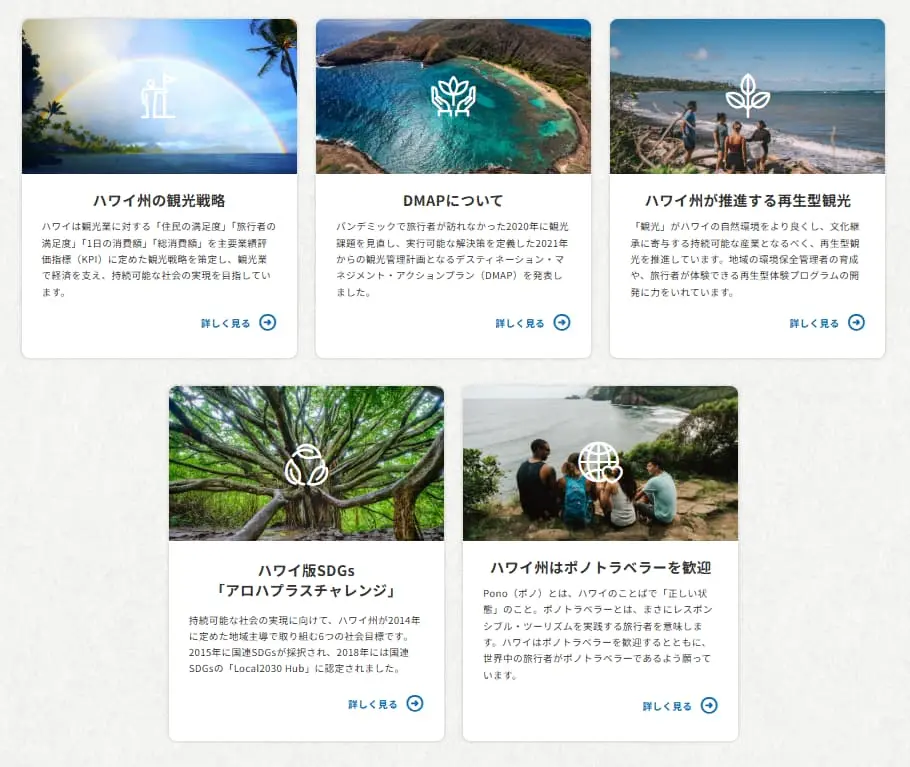
▼出典:ABOUT HAWAI‘I Mālama Hawaiʻi
直面する課題と解決策
サステナブルツーリズムの概念は広く浸透しつつありますが、実際の観光現場ではいくつもの課題が存在しています。ここでは代表的な問題と、それに対する解決の方向性を整理します。
オーバーツーリズム対策:分散とAI活用
観光客の集中による「オーバーツーリズム」は、渋滞や環境負荷、地域住民の生活への悪影響を引き起こします。
京都やベネチアなどでは世界的な課題となっており、観光地の持続可能性を脅かす最大のリスクの一つです。
解決のカギは「時間と空間の分散化」。観光庁や地方自治体では、閑散期の旅行を促すキャンペーンや、観光客の滞在を周辺地域へ広げる施策を導入しています。
さらに近年は、AIやビッグデータを活用した観光流動のリアルタイム管理が進みつつあり、混雑状況の可視化や人の流れの誘導に成果をあげています。

グリーンウォッシングと認証制度の信頼性
「サステナブル」を掲げながら実態が伴わない“グリーンウォッシング”も大きな問題です。
環境配慮をうたう宿泊施設やツアーが、実際には十分な対策を行っていないケースは少なくありません。
これは旅行者の信頼を損ない、サステナブルツーリズム全体の信憑性を揺るがすリスクとなります。
この課題に対しては、信頼できる認証制度の導入と透明性の確保が不可欠です。
国際的にはGSTC(世界持続可能観光協議会)が基準を策定しており、日本でもJSTS-Dがその枠組みに準拠しています。
今後は、旅行者が「どの認証を信頼できるのか」を簡単に判断できる仕組みづくりが求められます。

資金や合意形成の壁
持続可能な観光の仕組みを構築するには、施設改修や再生可能エネルギー導入、文化財保護への投資など、初期コストが高額になりがちです。
さらに、住民・行政・事業者といった多様なステークホルダーの合意形成も容易ではありません。
短期的な経済効果を重視する声と、長期的な持続可能性を重視する声のバランスをとることが難題です。
解決策としては、観光税や入域料を観光資源の保全に充てる仕組み、PPP(官民連携)による資金調達、住民参加型の意思決定プロセスが効果的とされています。
経済・環境・社会を同時に支える仕組みをどう作るかが、次世代の観光戦略における重要な論点です。
まとめ
サステナブルツーリズムとは、観光がもたらす環境・社会・経済への影響を最小化し、地域に長期的な価値を残す観光のあり方です。
その基盤は「環境・社会文化・経済」という3本柱であり、旅行者・地域・産業が共に利益を享受できる仕組みが不可欠です。
日本では観光庁の「JSTS-D」や大洲市・みなかみ町の先進事例が注目され、海外でもハワイの「マラマハワイ」やカナダ・フォーゴ島の取り組みが成功を収めています。
一方で、オーバーツーリズムやグリーンウォッシング、資金や合意形成の壁といった課題は依然として大きなハードルです。
今後はAIやデータを活用した混雑管理、透明性ある認証制度、住民参加型の観光経営が重要になります。
サステナブルツーリズムは「選択肢」ではなく、観光産業の未来を支える必須条件であり、地域と旅行者が共に育む新しい観光モデルとして広がりを見せています。
