注意すべきグリーンウォッシュの企業事例と解説

企業があたかも環境に配慮しているかのように見せかけ、実態の伴わない主張を行う「グリーンウォッシュ」は、近年ますます社会問題として注目されています。
環境に優しいイメージを演出しても、それが事実と異なれば、消費者は正しい選択ができず、投資家も誤った判断に導かれてしまいます。
その結果、本来支援されるべき持続可能な企業の取り組みが見えにくくなり、社会全体の脱炭素の流れを妨げる要因にもなりかねません。
実際に、曖昧な訴求や根拠のない表示が発覚した企業では、ブランド評価の失墜、株価下落、取引停止、不買運動など、深刻なリスクが顕在化しています。
こうした状況を受け、EUでは根拠なき「環境に優しい」「生分解性」などの表現を禁止する“グリーンウォッシング禁止法”が採択され、日本でも消費者庁が誤解を招く環境表示に対する摘発を強化しています。
これからの企業に求められるのは、単なる広告表現ではなく、透明性ある情報開示と科学的根拠に基づく環境主張です。
第三者認証や標準化された算定ルールを適切に活用しながら、誤解のない形で自社の取り組みを示すこと。
それこそが、ESG経営の信頼性を守り、ステークホルダーから選ばれ続ける企業となるための重要な条件となっています。

1. グリーンウォッシュとは
1-1. グリーンウォッシュの定義
グリーンウォッシュ(Greenwashing)とは、企業が実態以上に「環境に優しい」ように見せる誤解を招く表現や広告、発信行為を指します。
本来の環境配慮とは関係のない情報を強調したり、都合の良い一部分だけを切り取ってPRしたりすることで、消費者や投資家に誤った印象を与えてしまう点が特徴です。
例えば、製品のごく一部にエコ素材を使っているだけなのに、あたかも製品全体が環境負荷の低いものであるかのように伝えるケースが該当します。
環境配慮に関する主張は企業の信頼に直結するため、実態と乖離した“環境アピール”は企業倫理や情報開示の観点から重大な問題とされています。
この言葉自体は近年よく聞かれるようになりましたが、実は1980年代後半にはすでに存在していた概念です。
もともと人権問題に対する「ホワイトウォッシュ(Whitewashing)」に由来し、「Green(環境)」と組み合わせて作られた造語と言われています。
また現在では、環境領域に限らず広く使われるようになり、
・SDGsウォッシュ
・ESGウォッシュ
・サステナビリティウォッシュ
など、持続可能性や社会課題を“見せかけだけ”で語る行為全般を指す言葉も派生しています。

▼出典:国際自然保護連合日本委員会(IUCN-J) グリーンウォッシュとは
1-2. なぜ問題なのか
グリーンウォッシュが深刻な問題として扱われるのは、単なる広告表現の問題にとどまらず、消費者の選択をゆがめ、投資判断を誤らせ、結果的に社会全体の脱炭素の進展を妨げてしまう可能性があるためです。
ここではその理由を大きく二つに整理して解説します。
まず一つ目は、消費者が本当に環境配慮された製品や企業を選べなくなることです。
企業が実態以上の“エコ”を装うと、誠実に環境対策へ取り組む企業の努力が見えにくくなり、市場の健全な競争が損なわれます。
本来、環境配慮には追加コストや技術投資が必要ですが、正しい情報が届かなければ、実直な取り組みが評価されず、消費者が持続可能な選択をする機会も奪われてしまいます。
もう一つは、投資家の意図とは異なる資金配分を生むリスクです。
近年はグリーンボンドやESG投資など、環境改善や社会課題の解決に資金を振り向ける仕組みが急速に広がっています。

しかし、企業が不正確なデータや誇張された環境主張を開示した場合、投資家は誤った情報をもとに意思決定を行うことになります。
その結果、本来支援されるべき低炭素技術やサステナブルな事業に資金が行き届かず、気候変動対策そのものが遅れる原因にもなりかねません。
こうした背景から、企業の環境情報に対する社会の目はますます厳しくなっており、「その主張は事実に基づいているのか」「どの範囲のデータを使っているのか」という透明性が重要視されています。
グリーンウォッシュという言葉が改めて注目されているのは、まさにこの“情報の信頼性”を問う機運が世界的に高まっているためです。
2. グリーンウォッシュのリスク
グリーンウォッシュが発覚した場合、企業が受ける影響は想像以上に大きく、短期的な炎上にとどまりません。
信頼性の低下は、事業継続や市場での競争力にも直結する重大なリスクとなります。
2-1. 企業リスク
指摘を受けた企業が直面するリスクは多岐にわたり、近年はその深刻度も増しています。
代表的なものとしては以下のような影響が挙げられます。
● 企業ブランドの毀損
環境配慮を掲げる企業ほど、誤った主張が明らかになった際の批判は大きく、ブランド価値の低下につながります。
● 消費者の不買や信頼喪失
SNSの拡散によって不買運動や炎上が起きるケースも多く、消費者の信頼を取り戻すには長い時間が必要になります。
● 投資家からの評価低下・株価への影響
ESG投資が主流化する中、誤った環境主張は財務リスクとして扱われ、投資判断のマイナス材料となります。
● 取引先との契約停止・サプライチェーンからの排除
サプライチェーン全体での環境コンプライアンスが求められるため、誤情報を発信する企業は取引先から敬遠される可能性があります。
● 従業員の士気低下や離職
企業の価値観と実際の行動の不一致は、従業員のエンゲージメント低下につながり、人材流出の原因にもなります。
これらのリスクは互いに連鎖し、「一度の不正確な環境主張」が企業の中長期的な経営に大きな影響を与える点が特徴です。
2-2.グリーンウォッシュの7つの罪
カナダの調査会社 TerraChoice が2010年に発表した「グリーンウォッシュの7つの罪」は、
“どのようなときにグリーンウォッシュと判断されるのか”を理解する実務的な指標として現在でも広く参照されています。
| 7つの罪 | 説明 | 例 | |
| 1 | 隠れたトレードオフの罪 | 一部の属性に基づいて製品が環境に優しいと主張し、他の重要な環境問題を無視すること。 | 持続可能な森林からの紙が、必ずしも環境に優しいとは限らない。製造過程での温室効果ガス排出や漂白における塩素の使用などが問題。 |
| 2 | 根拠がない罪 | 簡単に確認できる証拠や信頼できる第三者の認証がない環境主張。 | 再生紙を含むと主張するティッシュやトイレットペーパーが証拠を提供していないなど。 |
| 3 | 曖昧さの罪 | 定義が不十分または広すぎて、消費者が誤解する可能性のある主張。 | 「全て自然」という主張。自然発生の有毒物質(ヒ素、ウラン、水銀、ホルムアルデヒドなど)も含まれる。 |
| 4 | 偽りのラベル崇拝の罪 | 実際には存在しない第三者の承認を言葉や画像で示す製品。 | 偽のラベルを使用している製品。 |
| 5 | 無関係の罪 | 真実ではあるが、消費者が環境に優れた製品を選ぶ際に重要ではなかったり、関係無いポイントを主張。 | モントリオール議定書によりCFC(フロン類)が禁止されているにもかかわらず、「CFC不使用」を強調する例。 |
| 6 | 比較による錯覚の罪 | 環境への悪影響が大きい製品と比較することで、環境影響度を小さく見せる主張。 | 有機タバコや低燃費のスポーツカーなど。 |
| 7 | 嘘をつく罪 | 単に虚偽の環境主張。 | 認証または登録を偽って主張している製品。 |
これらの“7つの罪”はいま見ても本質を突いており、EUのグリーンウォッシュ禁止法や各国の広告規制の基礎になっている考え方です。
企業が環境主張を行う際は、これらのパターンを避けることで、後続の法規制パートにもつながる「透明性と根拠ある説明」が求められます。
3.グリーンウォッシュへの規制
世界では、グリーンウォッシュを防止するための規制が急速に強化されています。
環境配慮をうたう製品やサービスが増える一方で、根拠のない主張や誇張された広告が社会問題となり、政府が明確なルールを設け始めたためです。
フランスでは、2023年1月に金融商品や消費財における環境広告の規制が開始され、「根拠のないエコ主張」を法律で制限しました。
イギリスでも2021年にGreen Claims Codeが制定され、企業に対して環境表示の根拠提示や明確な表現を求めています。
また韓国でも、2023年1月に虚偽・誇張された環境主張に対し企業へ罰金を科す法案が可決され、アジア地域でも取り締まりが強化されつつあります。
こうした国際的な動きの中でも、もっとも影響が大きいのがEUによるグリーンウォッシュ禁止法(Greenwashing Ban)です。
以下では、この欧州の新たな指令案について詳しく解説します。
3-1.欧州のグリーンウォッシング禁止法
EU理事会は2024年2月、グリーンウォッシュを防止するための指令案を正式に採択しました。
この指令案は、企業が環境主張を行う際の「禁止事項」を明確に定め、消費者保護と市場の公平性を確保することを目的としています。
指令案で禁止された主な内容は次の通りです。
● ① 実証できない一般的な環境主張の禁止
例:「環境に優しい」「グリーン」「自然に優しい」「生分解性」「バイオベース」など、
データや明確な証拠が伴わない曖昧な表現を広告に使うことを禁止。
● ② 一部分のみの環境配慮を、全体であるかのように見せる行為の禁止
製品や企業活動の“ごく一部の要素”だけ環境に優しい場合、それを全体の主張に拡大してはいけないと規定。
● ③ カーボン・オフセットのみに基づく環境配慮主張の禁止
カーボンクレジット購入のみで「脱炭素」「低炭素化」と謳うことを禁止し、実際の排出削減努力が伴うことを求めています。
● ④ 非公的な認証ラベルの氾濫を防ぐための規制
公的機関が承認していない持続可能性ラベルの使用を禁止。
独自ラベルの乱立による誤認を防ぐのが目的です。

この指令は“広告の言葉づかい”だけでなく、商品の循環性(リサイクル率や耐久性の主張)に関する表示にも厳しい基準を設けています。
とくにEU市場で製品を販売する企業は、日本国内で問題にならない表現でも、EUでは法令違反となる可能性があるため注意が必要です。
グリーンウォッシュ規制は、今やヨーロッパだけの話ではありません。国際的に環境表示への透明性と根拠を求める動きが進んでおり、企業はこれまで以上に科学的根拠に基づいた正確なコミュニケーションが求められています。
▼参照:JETRO EU、グリーンウォッシング禁止法を採択、根拠ない「環境に優しい」など表示禁止
4. グリーンウォッシュの具体的な事例
ここからは、実際に行政措置や訴訟に発展したグリーンウォッシュの事例を紹介します。
抽象的な概念として語られることが多いグリーンウォッシュですが、企業の宣伝文句や商品表示がどのように問題視されるのかを知ることは、今後のリスク管理に非常に重要です。
4-1. 事例1:日本消費者庁がプラスチック製品取り扱い10社を摘発
日本でもグリーンウォッシュの取り締まりが本格化し始めています。
2022年12月、消費者庁は根拠を示せない環境表示を行っていたプラスチック関連製品の販売事業者10社に対し、景品表示法に基づく再発防止命令を出しました。
問題となったのは、ごみ袋やプラスチックカトラリー、釣り用品、エアガン用BB弾といった製品に対して掲げられていた以下のような表示です。
「約3カ月で土や海の中で分解され、自然に還る」
「環境中の微生物により速やかに分解する」
一見、環境配慮型の生分解性プラスチックであるかのような表現ですが、消費者庁が根拠資料の提出を求めたところ、科学的な裏付けが一切示されなかったことが判明。
その結果、「優良誤認」にあたるとして措置命令が出されました。

公表されたのは以下のカテゴリーの事業者です。
- ごみ袋の販売事業者
- プラスチックカトラリーの販売事業者
- 釣り用具の販売事業者
- エアガン用BB弾の販売事業者
このケースは、日本でも環境表示に対する目が厳しくなっていることを象徴する事例です。
「生分解する」「自然に還る」といった表現は、条件(温度・湿度・設備)によって大きく異なるため、科学的根拠や具体的な試験データが求められます。
環境配慮をアピールする際は、根拠が曖昧な言葉を使うほどリスクが高いことを示しており、企業は広告・ECサイト・商品パッケージなど、あらゆる表示で透明性を確保する必要があります。
▼参照:消費者庁 ニュースリリース令和4年12月 日本経済新聞 偽の「エコ」に世界の目厳しく 消費者庁も初の摘発
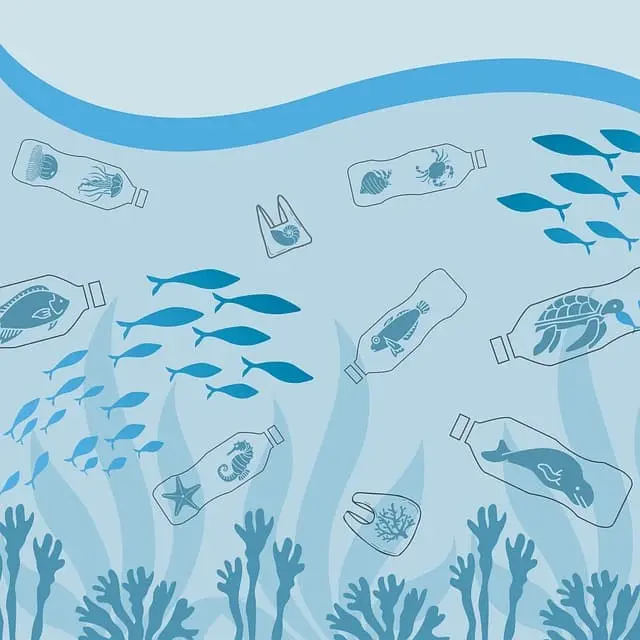
2-2. 事例2:ニューヨーク州が牛肉生産会社のJBS USAを訴訟
アメリカでも、環境主張に対する取り締まりが急速に強まっています。
2024年2月、ニューヨーク州司法長官は、世界最大級の食肉加工企業 JBS USA に対し、誤解を招く環境広告を行ったとして訴訟を提起しました。
問題となったのは、同社が掲げた次のようなメッセージです。
「2040年までに温室効果ガス排出量をネットゼロにする」
一見、先進的な脱炭素目標に見えますが、州側はこの主張には実質的な裏付けがなかったと指摘しています。
訴状によれば、JBSは自社の全排出量を正確に算定する前の段階から大規模な広告キャンペーンを展開しており、達成可能性を検証しないまま、“野心的に見えるが実現性に乏しい”目標を宣伝に利用していたとされます。
ニューヨーク州は、これが消費者・投資家の判断を誤らせる虚偽または欺瞞的なマーケティング行為に該当すると主張。訴訟では以下の措置を求めています。
- 虚偽の環境主張を伴う広告の中止
- 金銭的罰則の付与
- 不当に得た利益(ill-gotten gains)の返還
JBSの事例は、企業が「ネットゼロ」や「脱炭素」を掲げる際、
① 排出量の算定が正確に行われているか
② 実現可能な計画が裏付けとして存在するか
③ 達成に必要な前提条件を明示しているか
といった透明性が極めて重要であることを示しています。
欧米では特に、こうした“科学的根拠のない気候主張”が法的責任につながるケースが増えており、企業の環境コミュニケーション戦略に大きな影響を与える象徴的な事例と言えます。
▼参照:ESG Journal ニューヨーク州、世界最大の牛肉生産者JBSに対するグリーンウォッシュ訴訟を開始

2-3. 事例3:韓国環境団体がエネルギー大手のSK E&S社を提訴
アジアでもグリーンウォッシュの取り締まりが本格化しています。
2022年3月、韓国の環境団体「Solutions for Our Climate(SFOC)」は、エネルギー大手 SK E&S 社 を相手取り、「CO₂排出ゼロ(Zero Carbon LNG)」と宣伝した液化天然ガス(LNG)事業は事実に基づかないとして提訴しました。
問題視されたのは、SK E&Sが実際には多量のCO₂を排出するLNG事業について、まるで排出ゼロであるかのように主張していた点です。
韓国環境省もこれを虚偽または誇張の可能性がある表示として警告を行い、同社は後にウェブサイト上の文言を「低炭素(Low Carbon)」に修正しました。
このケースは、化石燃料産業が“カーボンニュートラル”を名乗る場合に求められる透明性の高さを示す重要な事例であり、アジア圏でも環境表示に対する法的リスクが急速に拡大していることを象徴しています。
韓国ではすでにグリーンウォッシュに対して罰金を科す法案が審議されており、今後はより厳格な規制が導入される見通しです。
▼参照:REUTERS 焦点:豪アジアでグリーンウォッシュ取り締まり強化、罰則も
欧州の調査結果が示す“グリーンウォッシュの構造的問題”
こうしたアジア・米国での事例の背景には、国際的に「環境主張の信頼性」が重大なテーマとなっている事実があります。
欧州委員会が2020年に実施した調査では、EU域内で確認された環境主張のうち、
- 53.3%が曖昧で誤解を招く可能性がある
- 40%が虚偽または欺瞞的な内容を含む可能性がある
という衝撃的な結果が報告されました。
この調査を受け、欧州委員会は「自主ルールや企業の自己申告だけでは不十分」であり、グリーンウォッシュが市場競争を歪め、誠実な企業の不利益につながっていると強く警鐘を鳴らしています。
EUの新たな規制:グリーンウォッシュ禁止法(2026年施行予定)
この流れを受け、EUでは2026年に「グリーン移行のために消費者に権限を与える指令(Greenwashing Ban)」が施行される予定です。
同指令は、消費者を誤解させる恐れのある環境主張を禁止し、違反した企業に対して厳しい罰則を科すことを目的としています。
重要なのは、この規制が EU域内企業だけでなく、EU市場に商品・サービスを提供するすべての企業に適用される 点です。
もちろん日本企業も例外ではありません。
この新たな指令は、
- 消費者の信頼回復
- 持続可能な企業活動の支援
- 環境主張の透明性向上
を目指すもので、企業が環境情報を開示する際の基準を一段と高水準に引き上げる転換点となるでしょう。

▼出典:CFP表示ガイドの作成に向けて 国際的なグリーンウォッシュ規制の動向
日本企業がEU規制で特に注意すべき3つのポイント
EUのグリーンウォッシュ規制は、EU域内企業だけでなくEU市場に製品・サービスを提供する海外企業にも直接適用されるため、日本企業にとっても避けて通れないテーマです。
特に注意が必要なのは、次の3つのポイントです。
① カーボン・オフセット依存の禁止——“削減努力なしのネットゼロ”は通用しない
EU規制が最も厳しく見ているのが、オフセットだけで環境配慮を主張する行為です。
従来、日本企業では
- カーボンクレジットの購入
- 植林事業への出資
- 排出権の取得
などによって「CO₂ゼロ」「カーボンニュートラル」と表現するケースが少なくありませんでした。
しかしEUでは、以下のような主張は禁止対象となります。
- 「製品のCO₂排出ゼロ」→ 実際にはオフセットで相殺しているだけ
- 「ネットゼロ達成」→ 排出量削減の計画(Scope1/2/3)や進捗データが不足
- 「クレジットの利用=環境配慮」と誤認させる訴求
EUが求めているのは、
“オフセットに頼らず、サプライチェーン全体の実排出を減らす努力”
という透明性と具体性です。
そのため日本企業は、排出量の算定精度(LCA、GHGプロトコル)と、削減計画の実効性を示すことが極めて重要になります。


② 曖昧ワードのNG化——“エコ”“自然に優しい”“生分解性”はもはや危険
EU規制では、消費者に誤認を与える曖昧表現を広範囲に禁止しています。
特にNGとなるのは次のようなワードです。
- 「環境に優しい(Environmentally friendly)」
- 「エコ」「グリーン」「サステナブル」
- 「自然に優しい」
- 「生分解性」「バイオベース」
- 「低炭素」としつつ根拠データなし
これらは、日本の広告・商品パッケージ・ECサイトで広く使われています。
問題は“言葉自体ではなく、裏付けのなさ”です。
EUでは、こうした一般的な環境ワードを使う場合でも、
- どの条件で?(温度・湿度・設備)
- どの範囲で?(製品全体か、一部か)
- どのデータをもとに?(試験法・試験期間)
といった具体的な根拠を明示できなければ、違法表示と判断される可能性があります。
③ 認証ラベルの乱立禁止——“独自ラベル商法”が通用しなくなる
EUは、環境ラベルが乱立し、消費者が本物か偽物か判断できなくなることを強い問題として認識しています。
そのため、新しい指令案では以下を禁止または制限しています。
- 公的機関が承認していないサステナビリティラベルの使用
- 企業独自の自社認証マークの乱用
- 第三者確認のない“なんちゃってエコラベル”の表示
日本企業では
- “独自の環境評価ラベル”
- “自社が策定したサステナビリティマーク”
を商品につけるケースがよくありますが、EUではこれらが誤認表示のリスクと認識されます。
EUが求めるのは、
透明性のある認証(ISO 14024 / Type I)を優先し、根拠なきラベルの利用を避けること。
たとえば日本の「エコマーク」や「エコリーフ(CFP)」のように、国際基準に適合した第三者認証であれば問題ありませんが、自社がデザインした“独自エコラベル”は原則NGとなります。

日本企業は何をすべきか?——3つの実務アクション
EU規制への対応で重要なのは次の3点です。
- オフセット依存ではなく、実排出削減の根拠データを揃える
- 環境表現は曖昧ワードを避け、条件・範囲・基準を明記する
- 国際規格に準拠した第三者認証ラベルを採用し、独自ラベルは排除する
これらは、単なる広告リスクの回避にとどまらず、
今後のESG評価・海外事業・サプライチェーン取引にも直結する必須条件です。
5. グリーンウォッシュを回避する方法
グリーンウォッシュを避けるうえで最も重要なのは、環境主張が正確なデータと検証可能な根拠に基づいていることを明確に示すことです。
EUでの調査(2021年)では、企業サイトの環境表示のうち半数が根拠不十分と判断されており、ウェブサイトや広告がとくに誤認リスクの高い領域であることが明らかになっています。
そのため企業は、商品特性・サプライチェーン・排出量データなどの“裏付け”を可視化し、第三者が確認できる形で情報を開示することが求められます。
単に環境に良さそうな言い回しを避けるだけでなく、なぜそう言えるのか、その根拠をどのように取得したのかを説明できる状態にしておくことが、グリーンウォッシュ防止の最大のポイントです。
▼参照:European Commission Screening of websites for ‘greenwashing’: half of green claims lack evidence
そのため企業は透明性のある活動で説得力ある主張をすることが重要です。

出典:CFP表示ガイドの作成に向けて 国際的なグリーンウォッシュ規制の動向
5-1. ガイドラインや認証の活用
環境主張の信頼性を高めるためには、国際基準に沿ったラベリングや認証を活用することが極めて有効です。
国際的に広く採用される ISO 14020 シリーズは、環境ラベルの透明性と科学的根拠を担保するための枠組みで、企業の環境コミュニケーションにおける“信頼の基盤”として機能します。
- ISO 14021(自己宣言型/Type II)
製品の「再生材○%」「リサイクル可能」などの自社主張を行う際に準拠すべき基準。
→ 自主表示の根拠や条件を明確化し、誤解を避けるために必須。 - ISO 14024(第三者認証型/Type I)
「エコマーク」など、公的・第三者機関が認証した環境ラベル。
→ 消費者向け製品で、高い信頼性を担保する際に最適。 - ISO 14025(製品カテゴリー規則/PCR/Type III)
「エコリーフ」など、LCA(ライフサイクル全体の環境負荷測定)に基づく専門的な環境宣言。
→ BtoB領域や国際取引での“証拠性の強い表示”に用いられる。
さらに近年では、ISO 14068(カーボンニュートラリティ規格)が新たなガイドラインとして注目されています。
カーボンニュートラルを主張する際に、
- 排出量算定の方法
- 削減計画の必須項目
- オフセット利用のルール
を明確に定めた国際規格であり、曖昧な“ゼロカーボン”主張の抑制に役立ちます。

また、カーボンフットプリント(CFP)の算定と第三者認証も、製品単位の排出量を定量的に示すための有効な手段です。
CFPはサプライチェーン全体の排出を見える化するため、EU市場で求められる透明性基準との親和性が高く、誤認リスクの低い環境主張に直結します。

6. まとめと今後の展望
環境配慮を打ち出す企業活動は、今やブランド価値の向上や投資家からの信頼獲得に欠かせない取り組みです。
しかしその一方で、環境主張が不正確だったり、根拠の不十分なまま発信されてしまうと、意図せずグリーンウォッシュと受け止められ、企業の信用や取引機会を大きく損なう可能性があります。
これからの企業に求められるのは、単に「環境に良い」とアピールすることではなく、その裏付けを透明性高く示し、消費者や投資家が判断できる情報を提供することです。
特に欧州を中心として規制が強化される中、企業は環境主張の根拠や算定方法、影響範囲を一貫した基準で示していく姿勢が不可欠になります。
その指針として参考になるのが、英国の「Green Claims Code」です。ここでは、環境主張は真実で正確であること、消費者が誤解しない明確な表現であること、そして製品やサービスの実際の環境影響と関連していることが求められます。
また、主張には信頼できる証拠が必要であり、他社比較を行う際も公平性と根拠が必須とされています。
さらに、部分的なメリットだけを強調するのではなく、ライフサイクル全体を考慮した“全体像としての環境影響”を示すこと、そして根拠や前提条件を開示する透明性も重要です。
こうした海外基準は、今後の国際市場でより一般的なものとなり、日本企業も例外ではありません。
誇張のない表現やデータに基づく開示を積み重ねることで、企業の取り組みは確かな信頼へと結びつきます。
グリーンウォッシュを避けるという視点は、単なるリスク回避ではなく、持続可能な企業としての姿勢を示し、ステークホルダーとの信頼関係を築くための重要なプロセスです。
今後は、環境データの可視化や第三者認証の活用、国際基準との整合性など、より高度な取り組みが求められるでしょう。
透明性と根拠に裏打ちされた環境コミュニケーションこそが、これからの企業価値を左右する大きな鍵となります。
