カーボンクレジットとは?その種類と違い:どれを選べばいいのか?

2024年10月11日に市場開設1周年を迎えた東京証券取引所カーボン・クレジット市場ですが、徐々に参加者数や累積売買高が増えてきています。

そういった流れを受けて
・そもそもカーボンクレジットとは?
・カーボンクレジットと再エネ証書との違いは?
・カーボンクレジットはどういったものをどこで購入すれば良いか?
・J-VER制度やJクレジット制度との違いは?
というご質問をいただく機会が増えています。
この記事では、Jクレジットをはじめとした、カーボンクレジットについて解説します。
今後の脱炭素活動にお役立ていただければ幸いです。

カーボンオフセット(Carbon Offset)
カーボンオフセットは、地球温暖化対策として注目される取り組みであり、排出した温室効果ガス(GHG)の削減努力を補完する仕組みです。
環境負荷を可能な限り削減したうえで、残った排出分を別の場所で削減するプロジェクトを支援することで埋め合わせるという考えに基づいています。
これにより、排出量を実質的にゼロに近づける「炭素中立(カーボンニュートラル)」を実現することを目指します。

まず、カーボンオフセットの基本的な流れについて説明します。
企業や個人が自らの排出量を測定することから始まり、その排出量に相当するカーボンクレジットを購入します。
このクレジットは、例えば再生可能エネルギーの導入、森林再生、メタンの回収などのプロジェクトを通じて生成され、国際的に認証された仕組みによってその効果が保証されています。
この仕組みを活用することで、自身が排出したGHGを間接的に削減することが可能となります。

具体例を挙げると、航空会社が乗客にカーボンオフセットプログラムを提供するケースがあります。
これは、フライト中に排出されるCO₂を計算し、それをカーボンクレジット購入によって相殺するものです。
同様に、製造業やサービス業の企業がサプライチェーン全体での排出を測定し、オフセットを実施する例もあります。
これらの取り組みは、単なる環境対策にとどまらず、持続可能な経営の一環として、企業価値を高める手段にもなります。
カーボンオフセットを効果的に活用するには、いくつかの重要な要素があります。
まず、信頼性の高いクレジットを選ぶことが大切です。Verified Carbon Standard(VCS)やGold Standardといった国際的な認証を受けたプロジェクトからクレジットを購入することで、その削減効果が実際に実現されていることを保証できます。
また、オフセットは排出削減の「代替手段」ではなく、削減努力を補完する「最終手段」として位置づけるべきです。
企業や個人は、自らの排出削減努力を最大限行った上で、残余の排出量に対してオフセットを利用する姿勢が求められます。
さらに、透明性と説明責任がカーボンオフセットの成功には欠かせません。
企業がオフセットを行う場合、どのプロジェクトを支援し、どれだけのCO₂を削減したのかを明確に公表する必要があります。
これにより、消費者や投資家との信頼関係を構築でき、企業の環境への貢献を効果的に伝えることが可能となります。
この点では、サステナビリティレポートや公式ウェブサイトでの情報開示が有効な手段となります。
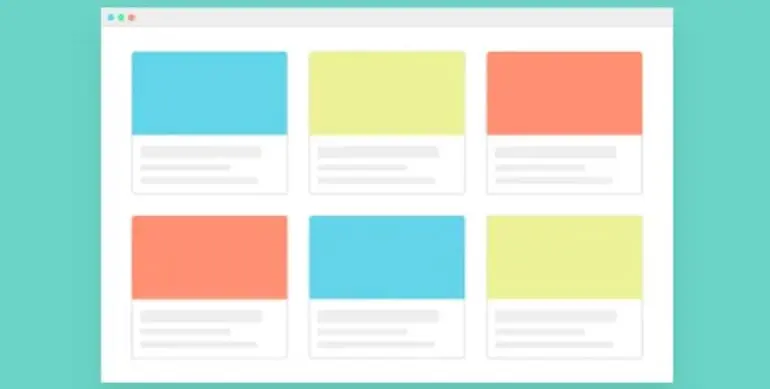
一方で、カーボンオフセットには限界もあります。
批判の一つとして、オフセットが「排出削減の免罪符」として利用される可能性が挙げられます。
これは、排出削減の努力を怠り、表面的にクレジットを購入して「責任を果たした」と主張するようなケースです。
このような懸念を払拭するためには、企業や個人が真に持続可能な削減努力を行い、オフセットを補完的に活用することが重要です。
また、カーボンオフセットが支援するプロジェクトには、その長期的な環境効果だけでなく、地域社会への貢献も求められます。
例えば、森林再生プロジェクトでは、地域の生態系保護や住民の生活改善といった付加価値も考慮すべきです。
こうした要素を取り入れることで、単なる温室効果ガス削減以上の価値を創出することができます。
カーボンオフセットは、気候変動対策の柱の一つであり、個人や企業が自らの排出削減努力を補完し、地球規模の課題解決に貢献する手段として広がりつつあります。
しかし、その効果を最大限に引き出すためには、科学的根拠に基づいた取り組み、透明性のある運用、そして倫理的な責任が求められます。

カーボンクレジット(Carbon Credit)
カーボンクレジットは、カーボンオフセットを実現するための中心的な仕組みとして機能し、地球規模の気候変動対策において不可欠な役割を果たしています。
このクレジットは、温室効果ガス(GHG)の排出削減量や吸収量を単位化したもので、1クレジットが1トンのCO₂削減または吸収に相当します。
企業や個人は、排出量を相殺する目的でこれを購入し、実質的な排出ゼロを目指します。
カーボンクレジットの仕組みと市場
主に規制市場(Compliance Market)と自発的市場(Voluntary Market)で取引されています。
規制市場は、政府や国際的な枠組みに基づくもので、EU排出量取引制度(EU ETS)や京都議定書の下で設けられたクリーン開発メカニズム(CDM)が代表的です。
これらの制度では、企業が排出上限を超過した場合、クレジットを購入することで規制を遵守しつつコスト効率の良い排出削減を実現できます。
一方、自発的市場は、企業や個人が自主的にクレジットを購入して排出削減に貢献する場です。
この市場の成長は、特に企業のESG(環境・社会・ガバナンス)意識や気候変動に対する社会的な関心の高まりによって加速しています。

Verified Carbon Standard(VCS)やGold Standardなどの国際的な認証スキームを通じて発行されるクレジットは、科学的に裏付けられた削減効果を保証し、透明性と信頼性を提供します。
カーボンクレジットの生成と認証プロセス
カーボンクレジットが発行されるまでには、厳格な認証プロセスを経る必要があります。
まず、プロジェクト開発者が具体的な削減計画を設計し、認証機関に提出します。
計画には、再生可能エネルギーの導入、森林再生、生態系の保護、廃棄物の効率的処理など、実際の排出削減または吸収に寄与する活動が含まれます。
この計画が第三者機関によって厳密に検証され、削減量が測定されることでクレジットが発行されます。
このプロセスは、単なる削減活動を超え、地域社会や生態系に付加価値を生み出す可能性を秘めています。
たとえば、森林保全プロジェクトは、生物多様性の保護や地域住民の雇用創出を促進します。
また、再生可能エネルギープロジェクトは、持続可能なエネルギー供給の確立や地域のエネルギー自立を支える重要な役割を果たします。
このように、カーボンクレジットは単なる取引可能な環境資源ではなく、社会的・経済的な価値を創出するツールでもあります。
カーボンクレジットの課題と解決策
カーボンクレジット市場は、持続可能な未来を実現する可能性を秘めていますが、いくつかの課題も存在します。
第一に、プロジェクトの環境効果の過大評価や二重計上といった不正確性が問題視されています。
これに対処するためには、認証基準をさらに厳格化し、監査体制を強化することが求められます。
特に、ブロックチェーン技術の導入は、クレジットのトレーサビリティを高め、透明性を確保するための有望な手段となります。
第二に、クレジットを購入する企業や個人の責任が重要です。カーボンクレジットは「免罪符」として使われるべきではなく、排出削減努力を補完する手段であるべきです。
たとえば、企業がクレジット購入に先立ち、エネルギー効率の改善や再生可能エネルギーの導入といった具体的な削減策を講じることが望まれます。
また、購入したクレジットの利用目的や支援プロジェクトの詳細を公表することで、透明性を高め、信頼性を築くことができます。
カーボンクレジットの仕組みは大きく分けて2つ
ベースライン&クレジット制度
ベースライン&クレジット制度は、温室効果ガス(GHG)の排出削減を促進するための市場メカニズムの一つです。
この制度では、各プロジェクトや企業が設定された「ベースライン」と呼ばれる基準となる排出量を基に、その排出量をどれだけ削減できたかを評価します。
削減できた排出量は「クレジット」として認証され、取引可能な形で市場に出されます。
一般的なカーボンクレジットとはこのベースライン&クレジットを指します。
具体的には、まずベースラインを設定します。ベースラインは、通常、過去の実績や業界平均の排出量などを基にして決定され、企業やプロジェクトが何もしなかった場合に予想される排出量の水準を示します。
これに対して、再生可能エネルギーの導入やエネルギー効率の改善などの取り組みにより、実際の排出量がこのベースラインよりも少なくなれば、その差分が「削減量」として計算されます。
この削減量が「クレジット」として認証され、他の企業がこれを購入することで、購入者の排出量をオフセットすることが可能になります。
ただ、ベースラインを設定するのは難しく、何を「通常の状態」と設定するかの過程で、過去のデータや業界の平均値を使って基準を設けるのが一般的ですが、企業の活動は季節的な変動や経済状況の影響を受けることが多く、その「通常」が常に一定しているわけではありません。
他にも、業界の平均値を採用するにも企業毎に事情は異なり、企業が新しい技術を導入して効率を上げた場合、それは個別の企業の努力によるもので、業界全体のベースラインを変更すべきではないかもしれません。
しかし、その企業の排出量が基準に比べて大幅に低くなった時、どこまでをその企業の削減努力と見なし、どこからを一般的な基準として取り入れるかの判断が難しいのです。
また、設定したベースラインが高すぎたり低すぎたりすることで、制度が持つインセンティブのバランスが崩れる可能性もあります。
高すぎるベースラインは、実際にはそれほどの努力をしていないのに、企業が簡単にクレジットを獲得できてしまう状況を生み出し、排出削減を本気で目指している企業との公平性が損なわれます。
逆に、基準が厳しすぎると、どれだけ努力をしてもクレジットが得られないため、企業が取り組む意欲を失わせてしまいます。
こうした複雑さを克服するためには、ベースラインの設定プロセスにおいて透明性を確保し、適正なデータ収集と検証が求められます。
独立した第三者機関がこのプロセスを監督し、企業がデータを意図的に操作することを防ぐことも重要です。
上記のような難しさはありますが、ベースライン&クレジット制度は、企業が排出削減のために投資した取り組みの成果を可視化し、さらにそれを取引可能な資産として活用できる点が特徴です。
これにより、排出削減が単に環境保護の観点だけでなく、経済的なインセンティブにもつながる仕組みとなっており、企業が積極的に気候変動対策に取り組む動機づけにもなります。

キャップ&トレード制度
キャップ&トレード制度は、温室効果ガス(GHG)の排出を抑制するための市場メカニズムで、政府が経済全体の排出量に「キャップ(上限)」を設定し、その枠内で企業が排出権を取引できる仕組みです。
この制度は、環境保護と経済活動の両立を目指して設計され、企業が排出削減を進めるインセンティブを生み出します。
仕組みの基本的な考え方は、まず政府が特定の産業セクターや経済全体に対して年間の温室効果ガス排出量の上限を設けることから始まります。
この上限は、社会全体としての温室効果ガスの削減目標に基づいて設定され、時間とともに徐々に引き下げられていくことが一般的です。
そして、政府はその排出量の上限に基づいて、企業ごとに「排出枠(クレジット)」を割り当てます。
各企業は、自社に割り当てられた排出枠の範囲内で温室効果ガスを排出することが許されており、枠を超えて排出したい場合は、市場で他の企業から余った排出枠を購入する必要があります。
逆に、企業が自社の排出量を削減して、割り当てられた枠を使い切らなかった場合、その余った排出枠を他の企業に売ることができるのです。
これにより、排出削減を達成した企業には経済的な利益がもたらされ、さらに削減努力を促進する動機づけとなります。
キャップ&トレード制度の最大の特徴は、このような市場メカニズムを通じて、コスト効率よく全体の排出削減を実現する点にあります。
たとえば、ある企業が新しい技術を導入して排出量を大幅に減らすことができた場合、その企業は排出枠を他社に売ることで利益を得ることができます。
一方、削減が難しい企業は、必要な排出枠を市場から購入することで、排出量の管理を行うことができるのです。
この柔軟性により、各企業が自社にとって最もコスト効率の高い方法で排出削減を進めることができるようになっています。
さらに、キャップ&トレード制度は、全体的な排出量を確実に管理できるという利点もあります。
政府が設定したキャップ(上限)が変わらない限り、経済全体での排出量はその上限を超えません。
これにより、政府は社会全体の排出削減目標を確実に達成するためのツールを手にすることになります。
また、キャップの水準を年々引き下げることで、長期的に見た排出削減を段階的に進めることも可能です。
しかし、キャップ&トレード制度には課題もあります。
例えば、初期の排出枠の割り当て方法が不公平だと、特定の企業が有利になる可能性があります。
さらに、排出枠の価格が極端に変動することがあるため、市場の安定性を確保するための調整メカニズムが必要です。
また、制度の導入初期には、適切なモニタリングと報告の枠組みを整備するためのコストもかかります。
それでも、キャップ&トレード制度は、世界中でさまざまな形で導入されており、特に欧州連合(EU)の「EU排出量取引制度(EU ETS)」がその代表例です。
この制度の成功は、温室効果ガスの削減を促進し、さらに新しい技術や産業の発展を支える力にもなっています。
キャップ&トレード制度は、企業にとっても政府にとっても、効果的で柔軟な排出管理の方法であり、今後も気候変動対策の主要な手段の一つとして期待されています。
▼参考:JETRO EU ETS 世界をリードするEUのカーボン・プライシング
ベースライン&クレジットとキャップ&トレードの違いは以下のようになります。

Jクレジット制度
Jクレジットは、日本国内での温室効果ガス(GHG)削減や吸収活動をクレジット化し、取引可能にする国の認定制度です。
環境省、経済産業省、農林水産省が共同で運営しており、再生可能エネルギーの導入、エネルギー効率の向上、森林吸収量の増加といった多様なプロジェクトを対象としています。
この仕組みは、地域資源を活用し、温暖化対策と地域経済の活性化を両立させる点が特徴です。
たとえば、地方自治体や中小企業が主体となる再生可能エネルギー事業や森林保全活動は、環境保護だけでなく地域社会への貢献をもたらします。
企業にとっては、Jクレジットを購入することで自社の排出削減目標を達成しつつ、ESG投資やSDGs達成への姿勢を示す手段として活用されています。
Jクレジットの生成には、厳密な手続きが必要です。
プロジェクト提案者が削減計画を提出し、第三者認証機関がその妥当性を審査、活動後に実績を測定・検証することでクレジットが発行されます。
対象プロジェクトには、太陽光発電や風力発電といった再生可能エネルギーの活用、高効率設備の導入、森林保全活動などが含まれます。
この一連のプロセスは透明性を確保しており、信頼性の高いクレジットの取引を支えています。
ただし、Jクレジットには課題もあります。認証手続きが複雑で、中小企業や地方自治体にとって負担が大きいこと、国内市場が限定的で流動性が低いことがその一例です。
また、削減量の測定が不正確な場合もあり、二重計上や効果の過大評価といったリスクも指摘されています。
こうした課題に対処するには、手続きの簡素化や技術革新が求められます。
AIやブロックチェーンを活用することで測定や取引の効率化と透明性向上が期待されています。
Jクレジットの今後には大きな可能性があります。
地域資源を活用したプロジェクトがさらに広がることで、地方創生と気候変動対策の両面で効果を発揮し、国際市場との連携によって日本の環境技術やノウハウを輸出するチャンスも生まれるでしょう。
また、デジタル技術による効率化が進むことで、より多くの企業や自治体が参加しやすくなり、市場の拡大が期待されます。
Jクレジットは、日本がカーボンニュートラルを実現し、持続可能な社会を構築するための重要なツールとしてさらなる発展が期待されています。

▼出典:J-クレジット制度 https://japancredit.go.jp/about/outline/
その他のカーボンクレジットについて
国連主導のカーボンクレジット
■京都メカニズムクレジット
他国での排出量の削減をクレジットとして購入し、自国の議定書における目標達成に含めることができる制度。京都メカニズムクレジットは主に以下の3種類があります。
- 共同実施(JI:Joint Implementation)→先進国同士が共同で削減プロジェクトを行った上での取引制度。
- クリーン開発メカニズム(CDM:Clean Development Mechanism)→途上国と先進国が共同で削減プロジェクトを行った上で、途上国が販売側、先進国が購入側となる制度。
- グリーン投資スキーム(GIS:Green Investment Scheme)→先進国同士のクレジット取引によって得られた利益を環境問題対策にのみ充てる制度。
政府主導のカーボンクレジット
■二国間のカーボンクレジット制度(JCM:Joint Crediting Mechanism)
先進国と途上国が共同で温室効果ガスの排出の削減を行う制度。主に先進国は途上国に対し、低炭素技術や製品、システム、インフラ等を提供します。
そして、削減できた排出量をカーボンクレジットとして二国間で分け合います。
途上国のメリット:低炭素への移行ができる
日本のメリット:技術の提供により得られた削減効果を、日本の削減目標の達成に含めることができる。
民間主導のカーボンクレジット(ボランタリークレジット)
前述したカーボンクレジットは、国連や政府によって発行されています。
一方で、ボランタリークレジットは民間がクレジットを発行します。主にNGOや企業、団体、個人などが主体となります。
■VCS (ヴェリファイド・カーボン・スタンダード)
ヴェリファイド・カーボン・スタンダードは世界で最も取引量が多いボランタリークレジットです。温室効果ガス排出量の削減に対し、VCS事務局がクレジットを発行します。
クレジットの創出方法は「エネルギー」「工業プロセス」「建設」「輸送」「廃棄物」「工業」「農業」「森林」「草地」「湿地」「家畜」「家畜と糞尿」の11種類が認められています。
また、11種類に該当しない独自の方法論の提案も可能です。
※国際排出量取引協会や世界経済人会議等、民間企業が参加している団体により設立されました。現在はカーボンオフセット基準を管理する米団体「Verra」によって運営されています。
■GS (ゴールド・スタンダード)
ゴールド・スタンダードは、クレジットの発行を行うとともに、国連主導のCDMやJI等、各プロジェクトの「質」の高さに関する認証も行っています。
よって、GS認証を受けたプロジェクトは、本質的な持続可能な開発への貢献が保証されています。
※2003年にWorld Wide Fund for Natureなどの環境NGOによって設立されました。
ゴールドスタンダードは、さまざまな種類のプロジェクトに対応しており、生可能エネルギー(風力、太陽光、バイオマスなど)、エネルギー効率の改善(省エネ機器やクリーン調理ストーブの導入など)、水の浄化、廃棄物管理、森林保護と植林プロジェクトなどが含まれます。
例えば、アフリカやアジアの地域でクリーンな調理ストーブを普及させるプロジェクトは、温室効果ガスの排出を削減するだけでなく、住民の健康状態を改善し、森林の減少を防ぐ効果があります。
このようなプロジェクトがゴールドスタンダードの認証を受けると、単にカーボンクレジットを提供するだけでなく、社会的・環境的に高い価値を生み出していることを証明するものとなります。

■ACR(アメリカ気候行動レジストリ)
アメリカ気候行動レジストリは、世界で初めての民間クレジット登録機関です。自主炭素市場と規制炭素市場の両方で活動しています。
主にオフセットプロジェクトの登録、検証監督、オフセット発行を行っています。
また、科学に基づいた厳格なカーボンオフセット基準と方法論の開発を強みとしています。
※1996年にNPO法人のWinrock Internationalによって設立されました。
多様なカーボン削減プロジェクトの認証を担っており、特に北米における森林保護、農業、エネルギー効率の向上、再生可能エネルギーの導入など、幅広い分野をカバーしています。
例えば、森林保護プロジェクトでは、森林の管理を通じて炭素の貯留を増加させることができる一方、メタンガス削減プロジェクトでは、廃棄物処理場や農業活動からのメタン排出を抑えることが目標となります。
また、新しい技術や革新的な方法を取り入れたプロジェクトの開発にも積極的で、先進的な技術による排出削減を支援することに力を入れています。
このような多様性は、企業が自社のカーボンオフセット戦略に適したプロジェクトを選びやすくし、効果的な気候変動対策を進めることができます。
■CAR(クライメート・アクション・リザーブ)
クライメート・アクション・リザーブのカーボンクレジットプログラムは、独自の厳格な基準に基づいて設計されています。
プロジェクトがカーボンクレジットを発行するためには、詳細な監査プロセスを経て、そのプロジェクトが本当に温室効果ガスの削減を実現しているかどうかが検証されます。
これにより、クレジットの信頼性が確保され、市場参加者が安心して取引できる環境が整えられています。
例えば、森林保護プロジェクトやメタン削減プロジェクト、農業による土壌炭素隔離など、多様なプロジェクトが対象とされており、どのプロジェクトも認証を受けるためには、実際に追加的な(ビジネス通常の活動から得られる以上の)排出削減を証明する必要があります。
このような厳格なプロセスがあるため、CARのクレジットは信頼度が高く、市場でプレミアム価格で取引されることが多いです。
※2001年にカリフォルニア州によって創設されたCalifornia Climate Action Registryが基となった機関です。
カーボンクレジットプロジェクトの種類
カーボンクレジットにはさまざまな種類があり、それらは温室効果ガスの排出をどのように削減するか、あるいはどのように吸収・貯留するかによって分類されます。
大きく分けると、「排出回避・削減」と「固定吸収・貯留」の2つのカテゴリーがあり、それぞれに自然ベースのアプローチと技術ベースのアプローチが含まれています。
以下、それぞれの種類について詳しく説明します。

▼出典:経済産業省 カーボン・クレジット・レポートの概要 参考資料4 (p.19)
排出回避・削減型カーボンクレジット
排出回避・削減型のカーボンクレジットは、温室効果ガスの排出を減らす、または防ぐプロジェクトから生まれるクレジットです。
このタイプのクレジットは、エネルギー消費の効率化や再生可能エネルギーの導入によって、従来の化石燃料による排出を回避したり削減したりすることを目指します。
自然ベースの排出回避・削減
自然ベースのアプローチでは、自然環境の管理を通じて排出削減を達成します。
例えば、森林保護プロジェクトは、森林の伐採を防ぎ、炭素が大気中に放出されるのを避けることで排出を回避します。
その他には、持続可能な農業や草地の管理を通じて土壌の炭素貯留を維持し、排出を防ぐ取り組みも含まれます。
これらのプロジェクトは、炭素排出の回避だけでなく、生物多様性の保護や地域コミュニティの支援といった、幅広い環境・社会的なメリットももたらします。
そのため、こうしたプロジェクトからのカーボンクレジットは、持続可能な開発の一環として高く評価されることが多いです。
技術ベースの排出回避・削減
技術ベースのアプローチでは、技術的な革新を用いて排出削減を実現します。
典型的な例としては、再生可能エネルギー(風力発電や太陽光発電など)の導入によるクレジットがあります。
これにより、従来の化石燃料に依存したエネルギー生産を再エネに切り替え、排出を回避します。
また、エネルギー効率の向上も技術ベースの排出削減に含まれます。
例えば、工場の設備を最新のエネルギー効率の高い機器に更新することで、同じ製品を作るのに必要なエネルギーを減らし、排出量を削減します。
こうした技術的な取り組みは、特に都市部や産業集積地での大規模な排出削減に効果的です。
固定吸収・貯留型カーボンクレジット
固定吸収・貯留型のカーボンクレジットは、大気中の二酸化炭素を直接吸収し、長期的に貯留するプロジェクトから生まれるクレジットです。
このタイプのクレジットは、地球の自然の炭素循環を活用することで、大気中のCO2濃度を減らすことを目指します。
自然ベースの固定吸収・貯留
自然ベースのアプローチでは、植物や生態系が持つ自然の炭素吸収能力を利用します。
最も一般的なプロジェクトは植林や再植林です。
新しい森林を植えたり、荒廃した土地に再び木を植えることで、大気中のCO2を吸収し、木々に炭素として固定します。これにより、炭素の長期貯留が可能になります。
また、湿地の再生や草原の保全も、炭素吸収と貯留に有効です。湿地は非常に高い炭素貯留能力を持つため、その保護や復元によって大気中の炭素を自然に貯留できます。
こうした自然ベースのプロジェクトは、炭素の吸収だけでなく、生態系の復元や水質改善、地域の生物多様性の保護にも貢献します。
技術ベースの固定吸収・貯留
技術ベースのアプローチには、Direct Air Capture(DAC:直接空気回収技術)や炭素の地下貯留(Carbon Capture and Storage, CCS)などがあります。
これらの技術は、直接大気中のCO2を吸引し、化学的に捕集・分離して地下深くに貯留する方法です。
こうした技術は、特に産業プロセスや発電所からの大量排出に対応するために有効です。
さらに、新しい技術として、二酸化炭素をコンクリートや建材に閉じ込める「炭素利用・貯留(Carbon Capture, Utilization, and Storage, CCUS)」が開発されています。
この技術は、建材に炭素を封じ込めることで、長期的な貯留を実現するもので、将来の持続可能なインフラ構築にも寄与する可能性があります。

カーボンクレジットと再エネ証書、非化石証書、グリーン証書の違い
クレジット、再エネ証書、グリーン証書、非化石証書にはそれぞれ異なる特性と目的があり、どれを選ぶかは、企業や団体が目指す環境目標によって変わります。
これらの違いを理解することで、どの方法が最も適しているかを判断しやすくなるでしょう。
再エネ証書は、再生可能エネルギーから生成された電力の「環境価値」を証明するものです。
風力、太陽光、地熱などから作られた電気には、それ自体がクリーンで環境に優しいという価値がありますが、その電気を直接利用することが難しい場合も多いです。
そこで、再エネ証書を購入することで、企業は実際の電源がどこであれ、再生可能エネルギーの利用を間接的に支援したと見なされます。
再エネ証書の購入は、企業の電力消費における環境負荷を軽減し、再エネ導入を促進するメカニズムです。
ただし、これによって温室効果ガスの削減効果を直接示すことはなく、電力のクリーンな利用を促進する役割を果たしています。
グリーン証書は、日本特有の仕組みで、再エネ証書と似ていますが、より包括的です。
再エネ証書が電力の環境価値に焦点を当てているのに対し、グリーン証書はバイオマスや小規模水力、太陽光といった特定の再生可能エネルギーからの電力の利用を認証し、その環境価値を購入者に提供します。
これにより、企業は再生可能エネルギーに関連する地域経済や新技術の支援をしていることを示せます。
グリーン証書の選択は、特定の地域資源や小規模な再エネプロジェクトの支援を重視する場合に適しています。

非化石証書は、日本のエネルギー市場において、非化石エネルギーから作られた電力の環境価値を示すもので、主に再生可能エネルギーや原子力発電が対象です。
この証書を購入することで、企業は自らの消費する電力が非化石エネルギー由来であることを証明できます。
特に、日本のエネルギー政策に沿った脱炭素化の動きを支援したい場合には、非化石証書の利用が適しています。
ただし、再エネ証書とは異なり、必ずしも全てが再生可能エネルギーというわけではなく、原子力発電も含まれるため、選択の際はその点に留意が必要です。

これらの証書やクレジットの違いを考えると、何を優先したいかが選択のポイントになります。
例えば、直接的な温室効果ガスの排出を補いたいなら、実際の削減活動を支援するカーボンクレジットが適しています。
最近では、どのSDGSの課題に対応しているかがカーボンクレジットプロジェクトの紹介と共に示されており、自社の企業特性に合ったSDGSを達成しているカーボンクレジットを選ぶ、自社が関係深い地域や国(自社工場があるなど)のプロジェクトを選ぶなどカーボンクレジットを選ぶ時代になっています。

証書では、電力のクリーンな使用を示したいなら、再エネ証書やグリーン証書が役立ちますし、日本の脱炭素政策や非化石エネルギー全体の推進を支援したいなら、非化石証書を検討する価値があります。
また、カーボンゼロ商品を実現するための視点で見ると、カーボンクレジットはScope1~3の排出量を補うことができますが、各証書は成り立ちの性質上Scope2部分の排出量のみ補えないというルールになっており、これらの違いを理解し、適切に組み合わせることが大事です。

まとめ
カーボンオフセットは、企業が持続可能なビジネスを目指すための一つの方法として、また消費者が日常の中で環境に配慮した選択をするための手段として、重要な役割を担っています。
グローバルな気候変動対策においては、すべての活動が排出ゼロを実現するのは難しいため、カーボンオフセットを通じた柔軟な対応が求められています。
しかし、まだまだカーボンクレジット市場やカーボンクレジットの組成については未発達な所もあることから、カーボンオフセットの導入には慎重さを求める声もあります。
今後、カーボンクレジット全体でカーボンニュートラルへの実効性を高めていかなければならないフェーズにあるのではないかと思います。
▼出典
2) 経済産業省 京都メカニズム情報コーナー「京都メカニズムの仕組み」
3) Climate Action Reserve 「About us」
