Scope3 カテゴリ9~13について徹底解説!各カテゴリの概要と排出量算定方法をわかりやすく紹介
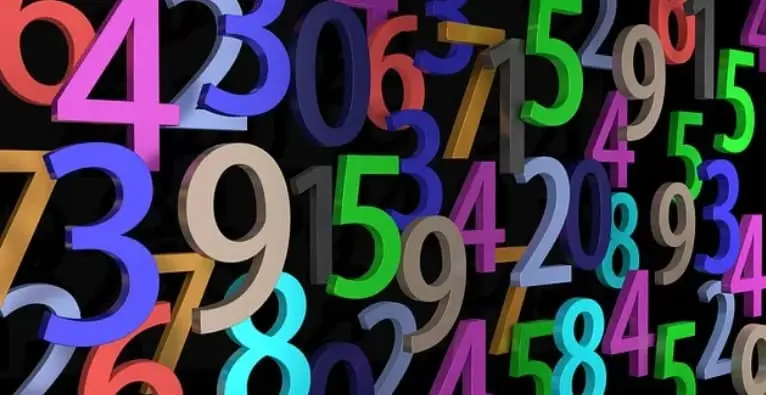
企業の脱炭素経営において、サプライチェーン全体の排出量をどこまで正確に把握できるかは大きな課題です。
特に見落とされがちなのが、製品が自社を出た後に発生する 「下流工程の排出」。
物流から使用、廃棄、リースまで、Scope 3カテゴリ9~13に分類される領域は、データ収集が難しい反面、ライフサイクル全体での環境負荷を左右する重要なステップです。
カテゴリ9では顧客や納入先への輸送、カテゴリ10は販売した中間製品の加工、カテゴリ11は消費者による使用、カテゴリ12は最終的な廃棄、そしてカテゴリ13はリース資産の利用に伴う排出が対象となります。
これらは一見把握が難しい領域ですが、適切に算定できれば物流の効率化や製品設計の改善、省エネ設備導入といった具体的な削減アクションにつながります。
本記事では、それぞれのカテゴリが持つ意味と算定方法を整理し、企業がどのように取り組むべきかをわかりやすく解説します。
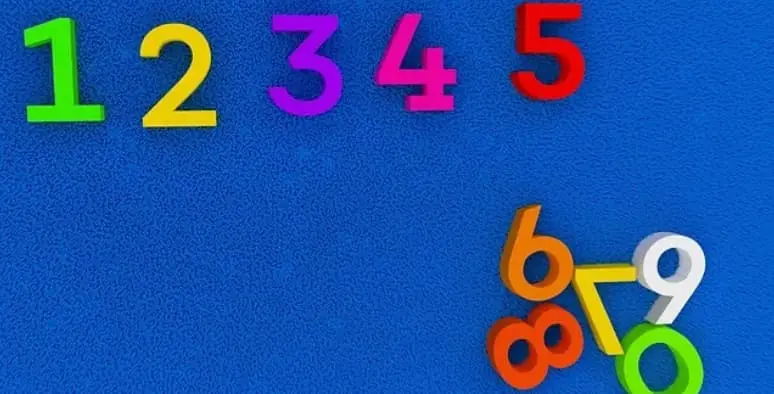
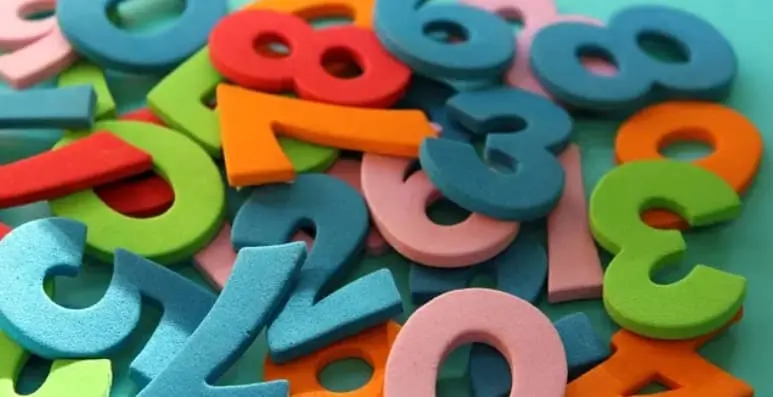
本記事では、上長や社内の関係者へ説明できる水準でScope3の各カテゴリ9~13について説明していきます。

Scope 3カテゴリ9(輸送〔下流〕)の重要性と算定方法
カテゴリ9とは?
Scope 3カテゴリ9(輸送〔下流〕)は、自社から顧客や納入先に製品を届ける過程で発生する温室効果ガス(GHG)排出量を対象とします。
倉庫や物流拠点でのエネルギー使用に伴う排出も含まれますが、算定対象となるのは「自社が費用負担していない輸送部分」です。
一方で、自社が費用を負担する輸送はカテゴリ4(輸送〔上流〕)で計上します。
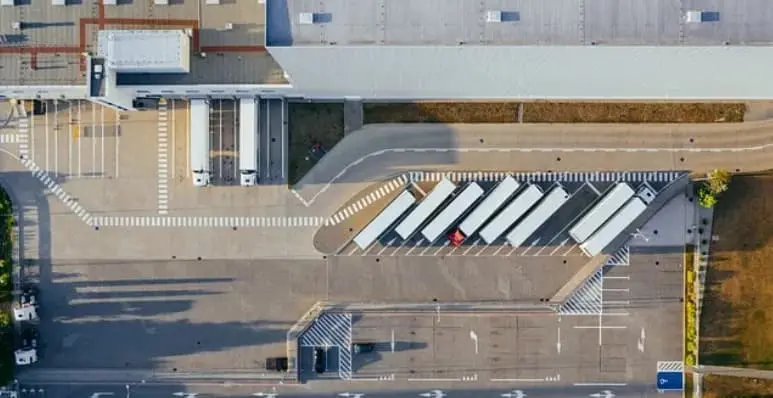
算定方法
輸送(下流)の排出量は、上流と同様に以下の3つの方法が推奨されています。
- 燃料法:輸送に使用された燃料量を把握し、その消費量に基づいて算定
- 燃費法:輸送距離・車種・燃費データを基に算定(ただし距離把握が難しい場合が多い)
- トンキロ法:貨物重量と輸送距離を掛け合わせ(トンキロ)、車種別の排出原単位を適用して算定
実務上の課題
カテゴリ9は、自社が直接費用を負担しない物流が対象であるため、データ収集が非常に困難です。
取引先や顧客側の輸送実態に依存するため、正確な距離や重量の把握が難しく、算定作業が進みにくいのが現状です。
除外されるケース
環境省のガイドラインでは、以下の条件に該当する場合は算定から除外できるとされています。
- 排出量が小さく、サプライチェーン全体への影響が軽微な場合
- 必要なデータの収集が極めて困難な場合
このため、多くの企業ではカテゴリ9をScope 3算定から除外しているのが実情です。
企業にとっての意義
カテゴリ9を把握できれば、製品の配送過程に潜む間接排出を可視化し、物流効率化や環境配慮型の輸送手段導入につなげることが可能です。
ただし、データ収集の難易度が高いため、業界ガイドラインや取引先との協力体制を整えることが算定の第一歩となります。

▼おすすめのお役立ち資料

Scope 3カテゴリ10(販売した製品の加工)の重要性と算定方法
カテゴリ10とは?
Scope 3カテゴリ10(販売した製品の加工)は、自社が販売した中間製品が他社によってさらに加工される過程で発生する温室効果ガス(GHG)排出量を対象とする項目です。
たとえば、自社が提供した素材や部品が別のメーカーで組み立て・加工される場合、その工程で使用される電力や燃料による排出がこのカテゴリに含まれます。
対象範囲の具体例
- 化学メーカーが出荷した樹脂が、自動車部品メーカーで加工される際に発生するエネルギー由来の排出
- 鉄鋼メーカーが供給した鋼材を建設業者が加工・使用する際に発生する排出
このように、自社の製品が直接消費者に渡るのではなく、中間製品として次の工程に利用されるケースが対象となります。
データ収集の難しさ
カテゴリ10の算定では、加工を行う取引先やサプライチェーンの詳細なデータが必要になります。
しかし、現実には以下の課題があります。
- 加工段階が複数の事業者にまたがるため、排出量の把握が困難
- 加工工程ごとのエネルギー使用量や排出係数が公開されていない場合が多い
- 自社の管理範囲を超える活動であるため、推計に依存するケースが多い
このため、ガイドラインでも「排出量が小さく影響が軽微」「データ収集が極めて困難」と判断される場合には、算定対象外とすることが認められています。
今後の展望
近年、Scope 3算定の透明性や精度向上が求められており、カテゴリ10も例外ではありません。
各企業でのライフサイクル排出量の可視化が進むにつれて、将来的には加工段階の排出データも取得可能になると期待されています。
これにより、より正確な算定とバリューチェーン全体での排出削減が実現できるでしょう。
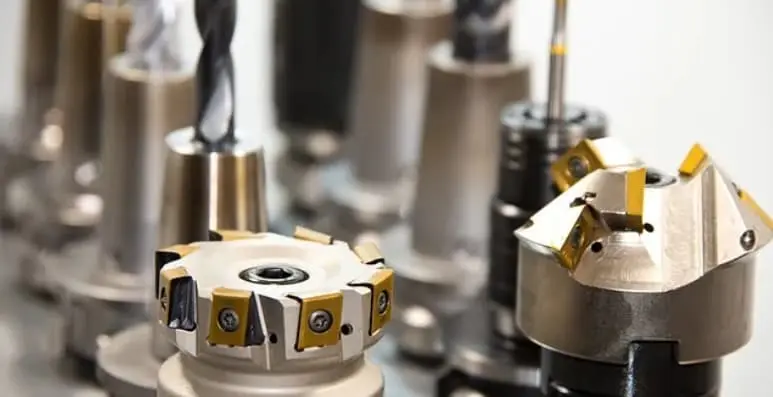
Scope 3カテゴリ11(販売した製品の使用)の重要性と算定方法
カテゴリ11とは?
Scope 3カテゴリ11(販売した製品の使用)は、自社が販売した製品が利用者によって使用される過程で発生する温室効果ガス(GHG)排出量を対象とする項目です。
特にエネルギーを消費する製品(家電、電子機器、自動車など)を扱う企業にとっては、使用段階での排出が製品ライフサイクル全体に占める割合が大きく、非常に重要なカテゴリとなります。

対象範囲の具体例
- 家電メーカーが販売したドライヤーが、消費者の使用により消費する電力量
- 自動車メーカーが販売した車両の燃料使用に伴う排出
- IT機器メーカーが販売したPCやサーバーの稼働による電力消費
このように、販売後に顧客が利用する過程での排出量がカテゴリ11の対象となります。
算定方法
カテゴリ11の算定は、利用実態が多様であるため一律ではありませんが、一般的には以下のようなシナリオ設定型の算定方法が用いられます。
- 製品の平均使用頻度を仮定(例:1日あたりの使用時間)
- その際に消費されるエネルギー量を算出(例:1日〇〇kWh)
- 年間使用量に換算(〇〇kWh × 365日)
- 製品の平均耐用年数を掛け合わせ、生涯使用エネルギーを算定
- そのエネルギー使用量に排出係数を掛け合わせ、GHG排出量を算出
例えば、ドライヤーを平均8年間使用すると仮定した場合、1日あたりの消費電力量 × 365日 × 8年がその製品のライフサイクルでの電力使用量となり、そこから排出量を計算します。
実務上の工夫
- 製品ごとの使用実態をすべて網羅するのは困難なため、代表的なモデルや主力製品に絞って算定を開始する企業が多いです。
- 使用条件の不確実性を補うために、業界平均データやLCAデータベースを活用するケースもあります。
- 製品カテゴリごとに典型的なシナリオを設定することで、算定の透明性と再現性を確保することができます。
は何を使う?データベースの選び方と活用事例.jpg)
企業にとっての意義
カテゴリ11を適切に算定することで、以下のメリットが得られます。
ESG評価・報告の強化:顧客や投資家への透明性を高め、企業価値向上に寄与。
ライフサイクル全体での排出量の把握:使用段階が環境負荷の最大要因である製品も多いため、排出削減の優先領域を特定可能。
製品開発へのフィードバック:省エネ性能の向上や長寿命化による環境負荷削減につながる。

カScope 3カテゴリ12(販売した製品の廃棄)の重要性と算定方法
カテゴリ12とは?
Scope 3カテゴリ12(販売した製品の廃棄)は、自社が販売した製品が使用後に廃棄される過程で発生する温室効果ガス(GHG)排出量を対象とします。
対象となるのは消費者や取引先が行う廃棄処理で、焼却・埋立・リサイクル・堆肥化といった方法に伴うCO₂やメタン排出が含まれます。
自社が直接関与しない工程であるため、Scope 3の中でも重要な間接排出カテゴリのひとつです。

算定方法
カテゴリ12の算定は、販売重量を基準に行うのが一般的です。
- 例:ある製品を1か月に1,000kg販売した場合、その1,000kgが最終的にどの処理方法(焼却・リサイクル・埋立など)で廃棄されるかを想定して算定。
- 算定手法は、Scope 3カテゴリ5(事業から出る廃棄物)と同様に、処理方法別の排出原単位を掛け合わせて算出します。

実務上の課題
製品の廃棄方法は利用者や地域の制度によって異なるため、比率の把握が難しいことが大きな課題です。
- 一部はリサイクルされるが、残りは焼却や埋立に回るなど、処理方法の内訳を明確にすることが困難。
- そのため、企業は廃棄プロセスを調査した上でシナリオを設定し、排出量を推定するケースが多くなっています。
企業にとっての意義
カテゴリ12の算定は、製品ライフサイクル全体の環境負荷を明らかにするうえで不可欠です。
特に近年は、製品企画段階から「最終的にどう廃棄・リサイクルされるか」までを考慮することが一般的になりつつあります。
これにより、以下の効果が期待されます。
ESG報告や顧客への説明責任における信頼性向上
リサイクル可能な素材や設計の導入による排出削減
廃棄時の環境影響を織り込んだ持続可能な製品戦略の策定

Scope 3カテゴリ13(リース資産〔下流〕)の重要性と算定方法
カテゴリ13とは?
Scope 3カテゴリ13(リース資産〔下流〕)は、自社が賃貸事業者として所有し、他者に貸し出しているリース資産の運用に伴う温室効果ガス(GHG)排出量を算定するカテゴリです。
対象となるのは建物や設備、オフィススペースなどのリース物件で、第三者が利用する際の電力消費や燃料使用といったエネルギー起因の排出が含まれます。
リース事業を行っていない企業には該当しない点が特徴です。
販売契約との違い
実務でよく課題となるのが、販売契約とリース契約が混在しているケースです。
例えば、自社製品をリースと販売の両方で提供している場合、Scope 3ルール上はカテゴリ11(販売した製品の使用)にまとめて計上して良いとされており、多くの企業が実務的に一括算定を行っています。
算定方法のステップ
カテゴリ13の算定は、リース資産に関するデータの取得状況に応じて次の3つの方法に分けられます。
- エネルギー種別の消費量が把握できる場合
電力・燃料などの種類ごとに排出係数を掛け合わせて精緻に算定。 - 総エネルギー消費量は分かるが、内訳が不明な場合
平均的な配分を想定し、全体量から推計。 - エネルギー消費量そのものが分からない場合
床面積などの代替データを活用して推計。
実務では③のケースが最も多く、特に建物リースでは床面積あたりの排出原単位を使う方法が一般的です。
算定例
事務所の排出原単位が「0.083t-CO₂/m²・年」とされている場合、100m²のオフィスをリースしていれば:
100(m²) × 0.083(t-CO₂/m²・年)= 8.3t-CO₂/年
と算定されます。
企業にとっての意義
カテゴリ13を正しく算定することは、リース事業を展開する企業にとって以下の効果をもたらします。
- サステナビリティ報告やESG開示の透明性確保
- 低炭素建材や省エネ設備導入など、環境改善施策の推進
- 投資家や顧客からの信頼強化
リース資産は利用期間が長く、環境負荷が継続的に発生するため、バリューチェーン全体での排出削減戦略に直結する重要な領域です。

まとめ
Scope3のカテゴリ9~13は、いずれも製品が顧客に届いた後の段階で排出される温室効果ガスを捉えるもので、サプライチェーン全体を俯瞰するうえで欠かせません。
たとえばカテゴリ9(輸送下流)では、自社負担ではない物流を対象とし、重量や距離をもとに算定しますが、データ入手が難しく除外されるケースもあります。
そこからさらに、カテゴリ10(販売した製品の加工)では中間製品が顧客企業で加工される際のエネルギー消費を、カテゴリ11(販売した製品の使用)では家電や自動車などが実際に使われる過程での消費電力を扱い、特に排出量が大きくなる可能性があります。
その後のカテゴリ12(販売した製品の廃棄)は、リサイクル・焼却・埋立といった処理方法ごとに想定を置いて算定し、製品設計時から考慮すべき視点として重視され始めています。
最後のカテゴリ13(リース資産下流)は、自社が貸し出す建物や設備の利用時排出を対象に、エネルギー消費量や床面積原単位で算定します。
これらは一見把握が難しい領域ですが、製品のライフサイクル全体で責任を持つという観点から、今後の脱炭素経営において重要性を増していく部分です。
▼参考:サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.4)

▼おすすめのお役立ち資料

