Scope3カテゴリ12-販売した製品の廃棄について具体的に解説

Scope3カテゴリ12「販売した製品の廃棄時の処理」は、企業が販売した製品が使用後に廃棄される際に発生する温室効果ガス(GHG)排出を対象とします。
焼却、埋立、リサイクルといった処理方法により排出量が変動し、企業はこれを正確に把握し、削減策を講じる必要があります。
特に、製品設計の段階からリサイクル性を考慮し、分解しやすい構造や環境負荷の少ない素材を採用することが重要です。
また、リサイクルシステムの構築や回収ネットワークの整備により、資源循環を最大化し、廃棄時の排出を削減する取り組みも求められます。
本記事では、カテゴリ12の排出量算定方法や削減施策について詳しく解説し、持続可能な製品ライフサイクルの構築に向けた戦略を探ります。
事前に、こちらの記事を見ていただくと内容を理解しやすくなります。

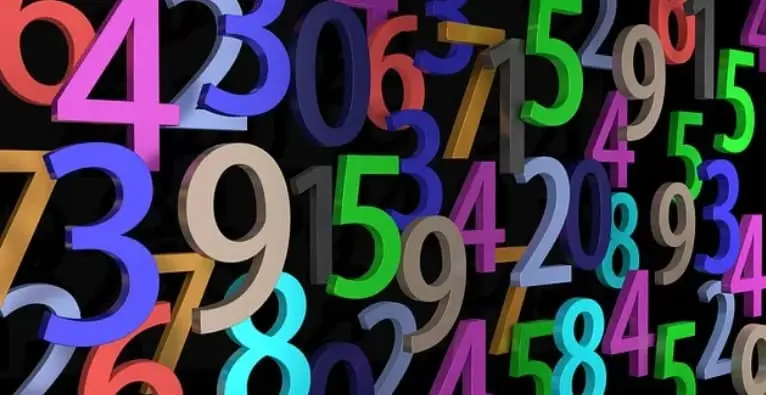

Scope3カテゴリ12の概要
対象となる活動と基本的な考え方
Scope3カテゴリ12(販売した製品の廃棄時の処理)は、顧客使用後に発生する解体・分別・リサイクル・焼却・埋立といった工程に伴うGHG排出を扱います。
対象は処理に直接使うエネルギーだけでなく、分別・輸送など間接的に紐づく排出も含むのがポイント。
たとえばプラスチックの焼却に伴うCO₂や、金属リサイクル時の電力消費が該当します。
環境負荷の低減は、廃棄の現場だけでなく設計段階から始まります。
解体しやすさやリサイクル性を織り込むことで、廃棄時の作業・エネルギーを圧縮できます。
具体例としては、
- 接合方法の見直しで分解時間を短縮(ネジ・接着剤の最適化、スナップ構造の採用 など)
- 単一素材化や有害物質の削減により選別の難易度を下げる
- リサイクル可能材やバイオベース材の採用で埋立・焼却依存を低減
素材特性の理解も重要です。金属は一般に回収・再資源化の効率が高い一方、プラスチックは処理方法の選択で排出量が大きく変わります。
製品ごとの素材ポートフォリオを把握し、最適な処理ルートを前提に設計へ“戻す”視点が、カテゴリ12の本質です。

▼出典:環境省 サプライチェーン排出量算定に関する説明会 Scope3 〜算定編〜
実務対応:廃棄システムの“現実”を反映し、設計→回収→算定を回す
カテゴリ12の算定精度は、地域差と処理実態の取り込みで決まります。
分別率・リサイクル率・焼却設備の熱回収の有無・埋立の比率は国や自治体で大きく異なるため、想定シナリオを明示し、根拠を文書化しましょう。
実務では次の手順が有効です。
- 製品を素材・部品に分解し、処理ルート(リサイクル/焼却/埋立)を整理
- 地域別の実態データ(処理比率・技術水準)を反映して廃棄シナリオを作成
- 処理ごとの排出係数を適用(データベース・法令基準の出典を必ず明示)
- 寿命・廃棄タイミングを販売履歴から推計し、対象年度の廃棄量に掛け合わせる
設計面の施策は算定結果に直結します。
易解体・単一素材化・再生材活用・軽量化は、処理工程のエネルギーや焼却量を減らし、指標(t-CO₂e/台・kg)で効果が可視化できます。
加えて、回収ネットワークの整備は実態データの取得にも寄与し、平均係数依存からの脱却(一次データ化)を後押しします。
耐久財ではリース/サブスクとの連動で、回収率と再資源化率の同時向上が狙えます。
▼おすすめのお役立ち資料

Scope3 カテゴリ12の算定方法
Scope3カテゴリ12の算定の基本フローと考え方
Scope3カテゴリ12「販売した製品の廃棄時の処理」は、報告対象年に企業が販売した製品本体および容器包装が、使用済みとなった際に廃棄・処理されるときの温室効果ガス(GHG)排出を算定対象とします。
ここでのポイントは「報告年度に販売した分」を基準に扱うことであり、将来の廃棄タイミングを考慮して年をずらす必要はありません。
算定方法はシンプルで、販売した製品量 × 各処理方法の排出係数によって総排出量を求めます。
例えば、ある年度に販売した製品1,000トンのうち80%が焼却、20%が埋立処理されると仮定します。
焼却の排出係数を2.5tCO₂e/トン、埋立を0.5tCO₂e/トンとした場合、排出量は次のとおりです。
- 800トン × 2.5tCO₂e/トン = 2,000tCO₂e
- 200トン × 0.5tCO₂e/トン = 100tCO₂e
- 合計=2,100tCO₂e
また、精度を高めるためには素材特性ごとに処理ルートを設定することが欠かせません。
例えば、プラスチックは焼却、金属はリサイクルといった実態に合わせ、それぞれに対応した排出係数を適用します。容器包装材についても同様に、リサイクル率や処理比率を反映させる必要があります。
は何を使う?データベースの選び方と活用事例.jpg)
このようにカテゴリ12の算定は、販売量・素材・処理方法の組み合わせを前提にモデル化し、報告年度ごとの排出量を明確に把握することが基本的な流れとなります。
精度向上に欠かせない地域差・リサイクル効果・透明性
算定を現実的なものにするには、地域ごとの廃棄物処理の違いを織り込むことが欠かせません。
先進国ではリサイクル率が高く、焼却時にサーマルリカバリー(熱回収)が行われることも多い一方、新興国では埋立中心の処理が主流です。
こうした違いは、同じ製品でも処理場所によって排出量が変わる大きな要因になります。
さらに、リサイクルの効果も評価すべき要素です。
金属やガラスは新規製造に比べリサイクル時のエネルギー消費が大幅に少なく、廃棄時点での排出削減効果を見積もることが可能です。
プラスチックでもマテリアルリサイクルやケミカルリサイクルの導入で、従来の焼却依存から環境負荷を下げることができます。
加えて、焼却で得られる熱エネルギーも一部を削減効果として評価し、総合的な環境影響を把握する視点が求められます。
最後に、透明性の確保は信頼性を高める要件です。
廃棄シナリオの設定根拠、排出係数の出典(環境省やIDEAデータベース等)、処理業者とのデータ連携などを文書化することで、第三者が検証可能な算定プロセスになります。
これにより開示の妥当性が増し、社外ステークホルダーからの信頼を得られます。

算定方法は定期的に見直し、最新のデータや処理技術を反映させることが重要です。
継続的な更新を行うことで、カテゴリ12は単なる報告義務ではなく、廃棄段階の排出削減戦略に直結する経営ツールへと進化します。

▼出典:一般社団法人循環経済協会 循環経済について
Scope3カテゴリ12の削減施策
Scope3カテゴリ12「販売した製品の廃棄時の処理」に伴う排出削減は、単に廃棄段階の効率化だけでは不十分です。
設計・素材選定・回収・リサイクル・ユーザー教育といったライフサイクル全体を視野に入れ、統合的に取り組むことが不可欠です。ここでは削減施策を2つの大きな柱に分けて整理します。
製品設計と素材選定による排出削減
削減の出発点は製品設計です。代表的なアプローチが易解体設計(デザイン・フォー・ディスアセンブリー)で、スナップフィット構造を導入することで分解時間を短縮し、リサイクル工程でのエネルギー使用を削減できます。
ある家電メーカーの事例では、解体作業に要する時間を半分に短縮し、それに伴いCO₂排出を製品1台あたり約0.2kg削減する効果が確認されています。
また、複雑な複合材料を避け、単一素材の活用を増やすことで、分別効率を20〜30%高め、再資源化率の改善につなげたケースもあります。
次に重要なのが素材選定の最適化です。アルミニウムのような高リサイクル素材や、生分解性プラスチック、バイオベース樹脂を採用することで、廃棄時のCO₂排出を大幅に抑制できます。
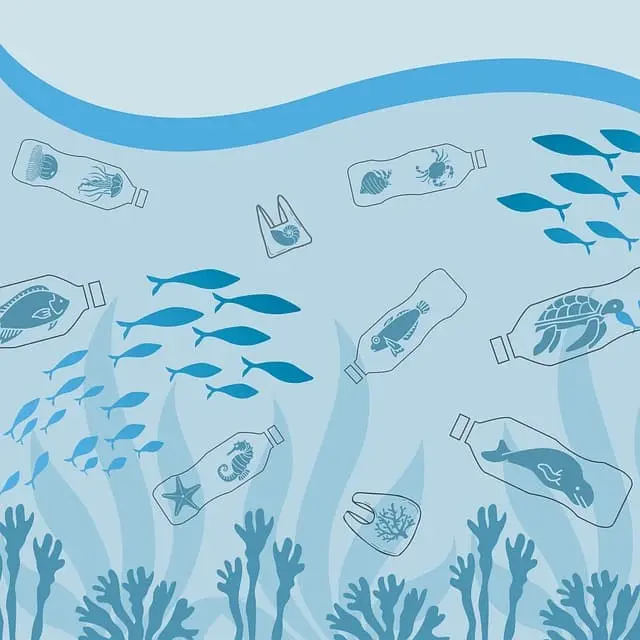
例えば、従来の石油由来プラスチックをバイオベース素材に切り替えた食品容器では、ライフサイクル全体でのCO₂排出を最大40%削減したと報告されています。
さらに、アルミニウムの再生利用は新規生産に比べて約95%のエネルギー削減となり、製品1トンあたり数トン規模のCO₂削減貢献につながります。
このように、設計と素材の工夫は廃棄段階の排出を根本から抑制する最も有効な手段であり、同時に削減貢献量を定量的に示すことができる分野です。
企業が算定結果と結びつけて効果を明示することで、環境施策の透明性と信頼性が高まり、製品ライフサイクル全体における持続可能性を確実に強化する第一歩となります。

回収・リサイクル体制とユーザー参画の強化
設計だけでなく、使用後の回収とリサイクル体制の整備も欠かせません。
企業が独自の回収ネットワークを構築すれば、不適切な処理を防ぎ、リサイクルや再利用を確実に実施できます。
例えば、専用施設で回収・処理を行うことで、一般廃棄物として処理される場合に比べて20%以上のCO₂削減を達成した事例もあります。
特に耐久消費財では、リースやサブスクリプションと組み合わせることで、ライフサイクル全体を企業が管理し、回収率を高めることが可能です。

さらに、リサイクル技術の高度化は排出削減を大きく後押しします。廃プラスチックの高度な材料リサイクルやケミカルリサイクルを導入すれば、従来の焼却処理と比べて最大60%の排出削減が可能です。
加えて、処理業者と連携して焼却の熱回収効率を高めたり、省エネ型のリサイクル設備を導入することで、処理プロセス自体の環境負荷を下げられます。
そして忘れてはならないのがユーザー教育です。
取扱説明書やWebサイトに廃棄方法を明示し、製品にリサイクルマークを表示することで分別精度を高め、リサイクル率向上を促します。
こうした啓発活動は廃棄物管理の効率化だけでなく、消費者の環境意識を引き上げる効果も期待できます。
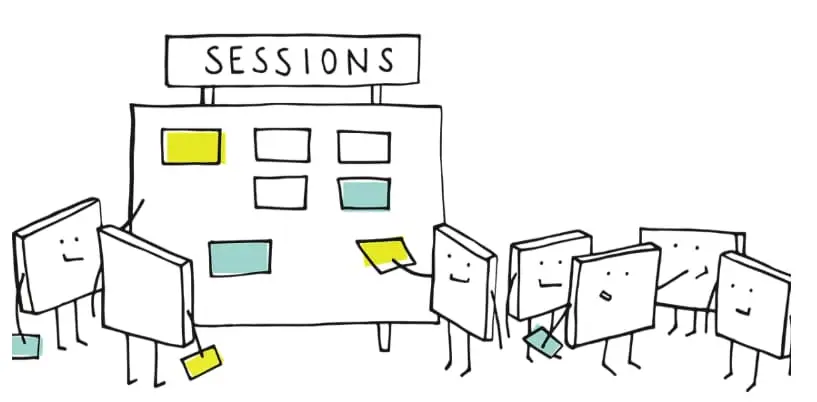
まとめ
Scope3カテゴリ12「販売した製品の廃棄時の処理」は、設計・素材選定・回収・リサイクル・ユーザー参画を通じてライフサイクル全体で取り組むべき重要領域です。
排出量は「販売量 × 処理方法の排出係数」で算定できますが、精度を高めるには地域差や素材特性を反映したシナリオ設計が不可欠です。
企業は、易解体設計やリサイクル可能素材の採用といった設計段階からの工夫、専用の回収ネットワーク整備やリサイクル技術の高度化といった廃棄段階での最適化を進めることで、廃棄時の温室効果ガス排出を大幅に抑制できます。
さらに、削減効果を定量的に把握し「削減貢献量」として示すことで、ステークホルダーへの説明責任を果たし、透明性と信頼性を高めることができます。
カテゴリ12の取り組みは単なる報告義務にとどまらず、循環型経済の実現と企業価値向上を同時に達成する経営戦略です。
持続可能な製品ライフサイクルを構築するために、各社が積極的に取り組むことが求められています。
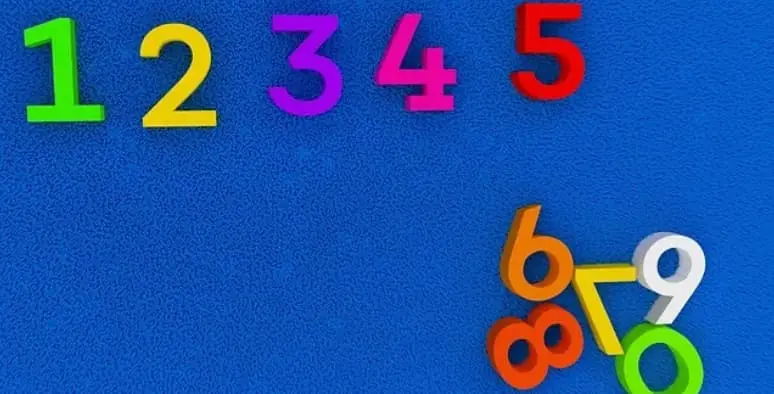
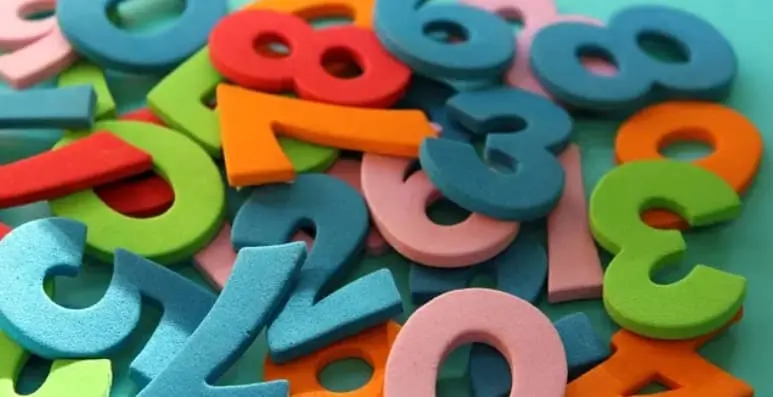
▼おすすめのお役立ち資料


