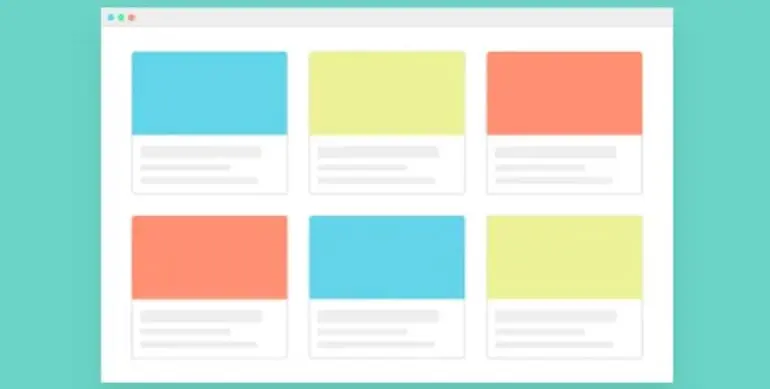温室効果ガス算定結果の第三者認証(保証)を依頼するときに抑えておきたいポイント

サステナビリティ経営やESGへの注目が高まるなかで、企業の非財務情報の正確性と透明性が、これまで以上に問われるようになっています。
温室効果ガス(GHG)の排出量やCSR活動の実績などを公表する際、第三者機関による認証を受けることで、その信頼性は格段に高まります。
これは、投資家や顧客、取引先といったステークホルダーからの評価向上につながるだけでなく、市場競争力や企業ブランドの強化にも直結します。
しかし一方で、第三者認証の取得には、データの整理・報告書の作成・機関対応など、多くの準備と判断が求められます。
本記事では、認証取得のメリットから具体的なプロセス、機関選定のポイントまでを、初めて検討する企業担当者にもわかりやすく解説。
信頼される情報開示に向けた第一歩を、確実に踏み出すための実践的なガイドとしてお届けします。

第三者認証とは
企業のサステナビリティやCSR、ESG報告の重要性が高まっている中、こうした非財務情報の開示情報の正確性や網羅性を第三者機関にチェック、是正アドバイスを行なってもらう第三者保証を取得することで、情報開示に対する信頼性が高まり、株主や顧客、取引先からの評価向上に繋げられます。

温室効果ガスの算定においては、ISO 14064( 温室効果ガスの測定と報告のための国際標準。)、GHGプロトコル(世界中の企業や政府が利用するGHG排出量の報告基準)といった基準、フレームワークを用いて第三者認証行なわれます。
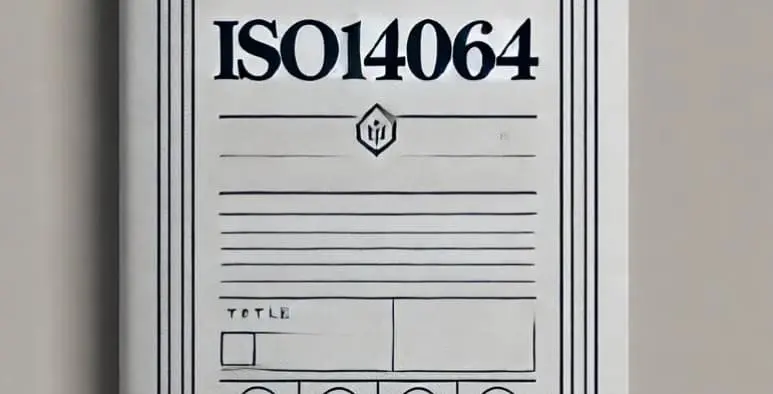
CSR・環境報告書などの非財務情報をチェックする際の国際基準としては、国際会計士連盟の国際監査・保証基準審議会(IAASB)が公表している「ISAE3000」と、英国のNGO、AccountAbilityが公表している「AA1000」などがあります。

それぞれ特徴があり、ISAE3000は、財務審査基準をベースとした内部統制、サステナビリティ、法律および規制の遵守を監査するための規格で従来の財務監査の流れを汲んだものになります。
一方、AA1000は、CSR活動の評価行為をベースとし、ステークホルダーへのアカウンタビリティ(説明責任)を果たし、さらにその取り組みを向上させることを目的とした新しい考え方によるものと分類できます。
第三者認証の必要性
上記のような第三者認証が必要な理由として以下の4点があります。
- 信頼性と透明性の向上: 第三者認証を行なうことで透明性の向上は勿論ですが、信頼がある機関から認証を受けることで、顧客や投資家などステークルホルダーに対しての信頼感を高められます。
- 市場競争力の向上: 第三者認証を取得しているという企業という形でブランド価値を向上させ競争力強化を得られます。
また、顧客は信頼性とセキュリティに配慮した企業やサービスを選ぶ傾向にあり、その面からも競争力の強化を見込めます。 - 業界基準と規制の遵守: 第三者認証を受けることで、企業がCSRや環境に対する取り組みに対する業界基準や規制に準拠していることを証明できます。
- 企業担当者の負担軽減:開示(開示内容)に対してルールの変更が頻繁に行なわれる中、企業の担当者がそれを全て把握することは困難です。
その部分を専門家の認証を得られることで負担の軽減と安心感を得れます。
第三者認証機関を選定するポイント
第三者認証のサービスを提供している機関は、大手監査法人、会計事務所、ISO審査機関などが行っていますが、費用は100万~1,000万円と高額で、さらに各社からさまざまな価格帯で見積りが出てくることが多く、担当者が戸惑われるケースも多いです。
大手企業で海外での取引なども多い場合は、外国人投資家の厳しい視線がありますので、ネームバリューがある(取り組みを確実に行なうことが大前提ではありますが、海外の投資家が安心します)大手監査法人の下、グローバル対応も行なってもらいながらの第三者認証を選択する方が良いと考えられます。
予算をそこまで出せない、まずはどういったものかを試したいという場合は、柔軟に応えてくれる企業や機関を探して、面談やメールで質問してみましょう。
訪問なしでオンライン上で完結させる、全てをチェックするのではなくランダムチェックで行う、Scope1・2のみで行なう、Scope3の不安な部分をまずはお願いする…などのパターンで対応できる企業や機関もあります。



第三者からの認証をもらうことはもちろん大事ですが、第三者認証を行なうことを意思表示することがまずは大切になり、対外的にも評価を得られますので、大きな見積もり金額が出た時点で断念しないようにご注意ください。
また、機関選定において実績の確認も大きなポイントです。
説明ページで実績を公表している会社もあるのでそちらを確認するか、第三者保証をしている会社はHPなどで発表していますので、同業他社がどの機関でやっているか、ベンチマークにしたい会社がどの機関に頼んでいるかを探してみましょう。
スケジュールについては、昨今はニーズも増えていることから認証機関も多忙になっています。なるべく早めに依頼することをお勧めします。
認証を依頼する範囲、業種、タイミングなどに応じて1ヵ月ほどで認証を受けられることもありますが、長い場合ですと4か月以上かかることもあります。
▼参考:第三者認証機関の紹介
温室効果ガスの第三者認証プロセス
第三者認証のプロセスは以下のような6つのプロセスで行われます。
1. データ収集
データの収集は、自社の活動に伴う温室効果ガス(GHG)排出量を測定します。
排出源としては、エネルギー使用(燃料消費、電力消費)、製造工程、廃棄物処理、輸送などが含まれます。
データの整理と分析:収集したデータを整理し、排出量を計算します。
この際、ISO 14064-1やGHGプロトコルなどの国際基準に従います。
排出量は、スコープ1(直接排出)、スコープ2(購入エネルギーに伴う間接排出)、スコープ3(バリューチェーンに伴うその他の間接排出)に分類されます。
報告書の作成:データと計算結果を基に、詳細な報告書を作成します。
この報告書には、測定方法、計算過程、結果、ならびに不確実性や仮定についての説明が含まれます。

2. 第三者機関の選定
候補機関の調査:認証機関の信頼性、経験、認定状況(例:ISO認定)を調査します。
比較と選定:各機関の提供サービス、費用、プロセス、過去の実績を比較し、最適な認証機関を選定します。
契約の締結:認証機関と契約を締結し、認証の範囲、目的、スケジュールを確定します。
3. データレビューと評価
初期レビュー:認証機関が提出した報告書とデータを初期レビューし、全体の整合性と完全性を確認します。
追加情報の要求:必要に応じて、企業に追加のデータや証拠(例:元データ、計算シート、測定装置の記録)を要求します。
詳細評価:提出されたデータを詳細に評価し、使用された測定方法や計算方法が国際基準に適合しているかを確認します。
4. 現地訪問(必要に応じて)
現地訪問の計画:認証機関が現地訪問を計画し、訪問のスケジュールや目的を企業と調整します。
現場検証:現地訪問時に、データの信憑性を確認するために、以下の活動を行います
・測定装置やシステムの検査
・データ収集プロセスの確認
・重要なデータポイントの再計算
・関連する担当者へのインタビュー
・現場検証報告書の作成:
以上の現場訪問の結果を報告書にまとめ、企業に提出します。
5. 報告書の作成
評価結果の整理:認証機関がすべてのレビューと現地訪問結果を統合し、最終的な評価結果を整理します。
報告書の作成:認証機関は、詳細な評価結果をまとめた報告書を作成します。
この報告書には、データの正確性、透明性、不確実性、ならびに改善提案が含まれます。
フィードバックセッション:認証機関が企業に評価結果を説明し、必要に応じて改善点や推奨事項を共有します。
6. 認証の発行
最終評価:認証機関が最終的に、提出されたデータが正確で信頼できると判断した場合、認証書を発行します。
認証書の発行:正式な認証書を企業に発行し、認証の範囲と有効期間を明示します。
公表と報告:認証を受けた企業は、認証書をステークホルダーに公表し、信頼性の高いGHG排出データを報告します。
このプロセスを通じて、企業は温室効果ガス排出データの正確性と信頼性を高め、環境パフォーマンスの向上に貢献することができます。
まとめ
第三者認証を実際に受けるとなると、数値の裏付け資料の取りまとめ提出、工場等の現場でのアポイント調整、現地同行、機関からのインタビュー対応、指摘事項や修正事項があった時の対応などの工数がかかります。
対応には一定数の工数が必要ですが、このように認証を受けるための作業を確実に行なうことで、自信をもってステークホルダーに結果を開示できるという結果につながります。
是非一度チャレンジしてみてはいかがでしょうか。