Scope 1とは?企業が押さえるべき温室効果ガスの直接排出と削減対策を徹底解説

企業の持続可能性を問う声が高まる中、温室効果ガス(GHG)の排出管理は、もはや経営戦略の中心的課題となっています。
その中でも、Scope 1は、企業が直接排出するGHGのカテゴリーとして、削減に向けた最も基本的かつ重要な領域です。
本記事では、Scope 1の定義や具体的な排出源を整理し、算定方法から実践的な削減施策までを詳しく解説します。
ボイラーや発電機からの燃料燃焼、企業所有車両の排出、工業プロセス由来のCO₂、さらには冷媒ガスの漏洩など、多様な排出源にどう対応すべきかを掘り下げます。
また、近年注目されるエネルギー効率の向上や電動車両の導入、冷媒ガスの管理、製造プロセスの見直しといった先進企業の削減事例を交えながら、企業が実際に取り組むべき対策を具体的に示します。
さらに、正確なScope1の算定がESG評価や投資家からの信頼向上につながる点にも焦点を当て、ビジネスの成長と環境配慮を両立する戦略を提案します。
Scope 1の削減は、単なる環境対応ではなく、競争力強化の鍵となる時代。
企業が取るべき具体的なステップを、ぜひ本記事で確認してください。



Scope1とは
工場や事務所のボイラーや発電機からの燃料燃焼、企業所有の車両による排出、冷媒の漏れなどがScope 1に該当します。
これらの排出は、企業自身の活動が直接の原因であるため、その管理や削減は企業の責任範囲とされます。
Scope 1は、企業が温室効果ガス削減目標を設定する際の基本的な出発点となり、排出量の計測や削減活動の進捗を正確に把握するために欠かせない要素です。

▼出典:経済産業省 資源エネルギー庁 知っておきたいサステナビリティの基礎用語~サプライチェーンの排出量のものさし「スコープ1・2・3」とは
Scope 1の具体例
燃料燃焼による排出
工場のボイラーや発電機、暖房設備など、燃料(天然ガス、石油、石炭など)を直接燃焼させる際に発生する温室効果ガスが該当します。
たとえば、製造業では生産工程に必要なエネルギーを供給する設備からの排出が典型例です。
企業所有の車両による排出
企業が所有または管理する配送用トラック、営業車両、社用車などの燃料使用に伴う排出です。
これらは、輸送活動に密接に関連しており、車両の燃費向上や電動化が削減の鍵となります。
工業プロセスによる排出
特定の工業プロセス(例: 化学反応や製造過程)から発生する排出もScope 1に含まれます。
例えば、セメント製造では、原料の分解過程で大量の二酸化炭素が排出されます。
また、二酸化炭素以外の温室効果ガスも発生します。
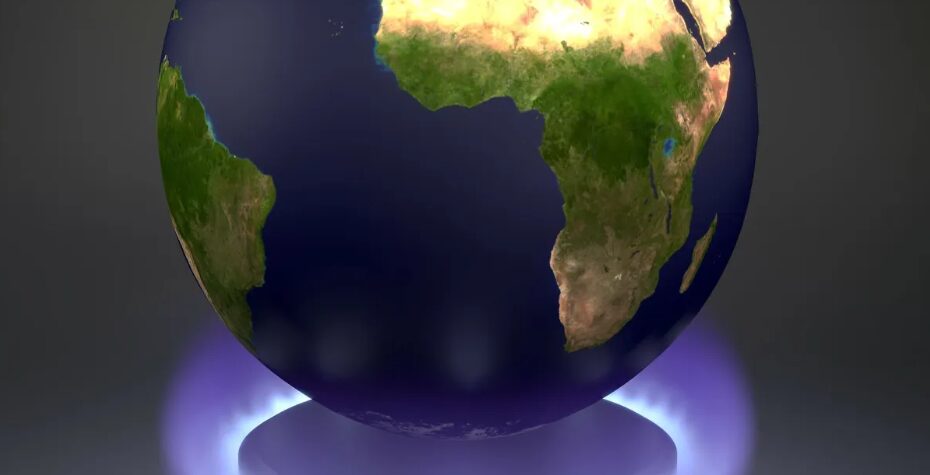
冷媒ガスの漏洩
空調設備や冷蔵機器に使用される冷媒ガスが漏洩する場合、高い地球温暖化係数(GWP)を持つフロンガスが大気中に放出されます。
これらの排出は、機器の適切なメンテナンスや低GWP冷媒の採用により削減が可能です。

Scope1の排出量削減について
Scope 1の排出削減は、企業の環境対策における最初のステップとなり、持続可能な経営を実現するための重要な施策の一つです。
具体的な削減方法としては、エネルギー効率の向上、再生可能エネルギーへの転換、省エネ設備の導入などが挙げられます。
これらの施策を積極的に推進することで、企業は環境負荷を軽減しながらエネルギーコストの最適化や業務の効率化を実現することができます。
さらに、Scope 1の削減は、企業の環境責任を明確に示す重要な指標となります。
近年、投資家や消費者は企業の脱炭素への取り組みを評価する傾向が強まり、Scope1の排出管理はESG(環境・社会・ガバナンス)評価においても重要な要素となっています。
実際に、企業がScope 1の排出を削減することで、持続可能な経営の姿勢を示し、ブランド価値や社会的信用の向上にもつながります。

このように、Scope1の削減は単なる環境対策にとどまらず、コスト削減、事業競争力の強化、企業価値の向上といった幅広いメリットをもたらすため、戦略的に取り組むことが求められます。
Scope1の算定プロセス
Scope1の算定方法は、企業が直接的に排出する温室効果ガス(GHG)を正確に測定し、その削減に向けた具体的な行動を支えるために必要不可欠なプロセスです。
この算定には、排出源の特定、データの収集と管理、排出量の計算、不確実性の評価、そして報告の各段階が含まれます。
それぞれの段階で、国際基準や科学的手法に基づく高い精度と透明性が求められます。
排出源の特定
Scope1の算定は、排出源を特定することから始まります。
Scope1に該当する排出は、企業が所有または管理する施設や活動から直接発生するものに限定されます。
- 燃料燃焼設備:工場のボイラー、発電機、暖房機器など。
- 企業所有の車両:トラックや営業車両など。
- 工業プロセス:セメント製造や化学反応に伴う排出。
- 冷媒ガスの漏洩:空調や冷蔵設備からのフロンガスなど。
排出源の特定には、企業活動全体を包括的に把握し、どの設備や活動がScope 1に該当するかを詳細に調査する必要があります。
この段階での正確な特定が、後続のデータ収集や算定の精度に直結します。

▼参考:CDP 排出量算定・スコープ1, 2の 考え方について
特に工業プロセスは、温室効果ガスが出ると担当者が認識できていないプロセスがあることがあります。
以下のような、業種でどういった工業プロセスがあるかを参考に示している対照表を参考に自社での抜け漏れが無いかをチェックするのが重要です。

▼出典:第Ⅱ編 温室効果ガス排出量の算定方法(上記は32ページ)
正確な算定を支えるデータ収集
排出源を特定した後は、算定に必要なデータを収集します。
このデータには、燃料使用量、エネルギー消費量、冷媒の使用・補充記録、工業プロセスにおける材料使用量などが含まれます。
たとえば、工場で使用されるボイラーの燃料使用量を記録し、それをもとに排出量を算出します。
収集されたデータの信頼性を確保するためには、データが適切に記録され、管理されていることが不可欠です。
エネルギーモニタリングシステムやIoT技術の活用は、データ収集の効率性と精度を向上させるための有効な手段です。
また、冷媒ガス漏洩のように測定が難しい排出源については、冷媒管理計画や過去の実績データを活用し、推定値を補完する方法が取られます。
工場の担当者とのリレーションを構築しておくことが重要なプロセスであると言えます。
排出量の算定
データ収集が完了したら、次に排出量を計算します。
この段階では、燃料やプロセスに応じた「排出係数」を適用し、収集したデータをもとに温室効果ガス排出量を算定します。
排出係数は、燃料や活動ごとに異なる値が設定されており、政府機関や国際機関が提供する標準値が使用されます。
具体的には、以下のような計算式が用いられます。
- 燃料燃焼に伴う排出量 = 燃料使用量 × 排出係数
- 冷媒ガス漏洩の排出量 = 漏洩量 × 冷媒の地球温暖化係数(GWP)
- 工業プロセスにおける排出量 = 原材料使用量 × 排出係数
これらの計算を通じて、Scope 1に該当する各排出源からの温室効果ガスの排出量が定量的に算出されます。

▼出典:環境省 算定方法及び排出係数一覧
例:軽油を5kⅼ使った場合は、
5×2.62=13.095t-CO₂e
といった形で算定します。

不確実性の評価と調整
算定された排出量には、データの不正確さや排出係数のばらつきなどの要因による不確実性が伴う場合があります。
このため、不確実性を評価し、必要に応じて調整を行うことが求められます。
たとえば、冷媒ガス漏洩のデータが完全でない場合、業界の平均値や信頼できる推定値を補完的に使用することで、算定の精度を向上させます。
不確実性の評価は、Scope 1の算定結果に対する透明性と信頼性を確保する重要なステップであり、外部のステークホルダーへの説明責任を果たす上でも欠かせません。
算定結果の報告と検証
最後に、算定された排出量を適切に報告し、必要に応じて第三者機関による検証を受けます。
報告は、企業の温室効果ガス排出量をステークホルダーや規制当局に説明するための重要なプロセスであり、ISO 14064などの国際基準に準拠した形式で行われることが一般的です。
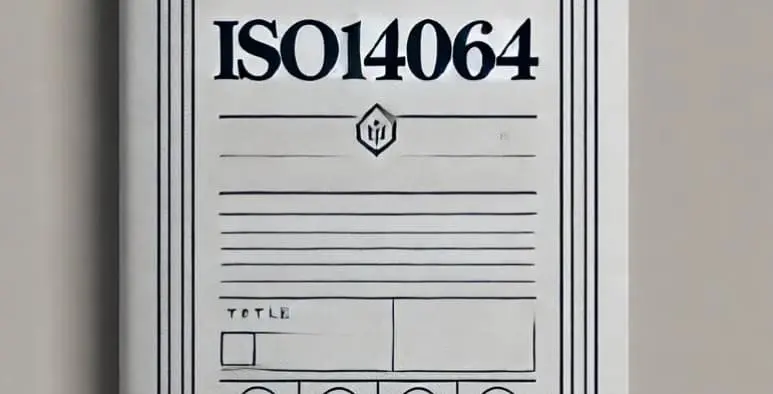
第三者による検証は、算定結果の信頼性を高め、企業の環境対策に対する透明性を強化するために不可欠です。
これにより、投資家や消費者からの信頼を築き、企業の持続可能性への取り組みを強調することができます。

Scope1の削減事例
エネルギー効率向上による削減
多くの企業が、エネルギー効率の改善を通じてScope 1の排出削減に成功しています。
たとえば、工場や事務所におけるボイラーや発電機のアップグレードは、直接的な削減効果を生む施策の一つです。
製造業の企業では、旧式のボイラーを高効率モデルに置き換えることで、年間の燃料使用量を20%削減し、これに伴うCO₂排出量を大幅に削減しました。
また、燃料燃焼プロセスの最適化を行うために、IoT技術やデジタル制御システムを導入し、エネルギー消費をリアルタイムでモニタリングすることで、さらなる効率化を実現しました。
このような取り組みは、短期間で結果が得られることが多く、初期投資を回収しながら長期的な削減効果を享受できる点が特徴です。
車両の電動化と燃料転換
輸送に関わる排出削減も、Scope 1の取り組みで重要な要素です。多くの企業は、ガソリンやディーゼル車両をハイブリッド車や電気自動車(EV)に置き換えることで、直接排出量の大幅削減を実現しています。
たとえば、大手物流会社では、全車両の30%を電気自動車に更新し、配送活動における排出量を年間数千トン削減しました。
さらに、一部の企業は、車両に使用する燃料を化石燃料からバイオ燃料に切り替えることで、排出削減を進めています。
バイオ燃料はカーボンニュートラルと見なされるため、化石燃料由来のCO₂排出を効果的に回避する手段となります。

冷媒ガスの管理と置き換え
冷媒ガスの漏洩はScope 1の主要な排出源の一つですが、この分野でも多くの成功事例があります。
大手小売業者では、店舗の冷蔵設備における高GWP(地球温暖化係数)冷媒を低GWP冷媒に置き換えることで、排出量を約50%削減しました。
また、冷媒管理システムを導入して漏洩を迅速に検知し、メンテナンスを効率化することで、さらなる削減を実現しました。
このような冷媒ガスに関する取り組みは、環境負荷を軽減するだけでなく、冷媒コストの削減や機器の寿命延長といった経済的なメリットも提供します。
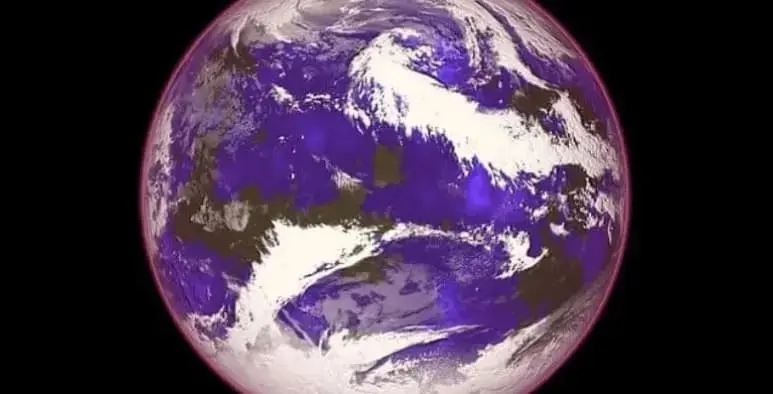
プロセスの改善とイノベーション
一部の製造業では、製品の製造プロセス自体を改良することで、Scope 1排出量の削減に成功しています。
たとえば、セメント業界では、従来の製造方法に代わり、低排出型の原材料を使用する技術が導入されました。
この技術により、製造プロセスでのCO₂排出量を30%以上削減することが可能となりました。
また、化学産業では、触媒の改良により化学反応プロセスを最適化し、排出量の低減を実現する事例もあります。
このようなイノベーションは、Scope 1削減の持続可能な解決策として注目されています。
まとめ
Scope 1の算定は、企業が直接管理する温室効果ガス排出量を正確に把握し、それを削減するための具体的な行動計画を支える基盤です。
このプロセスを適切に実施することで、企業は環境負荷を軽減するとともに、規制への対応やESG(環境・社会・ガバナンス)評価の向上、さらには持続可能な成長の実現に向けた確かな一歩を踏み出すことができます。
正確で透明性のあるScope 1の算定は、地球規模の気候変動対策に貢献するだけでなく、企業自身の競争力や社会的信用を向上させる重要な要素です。
これにより、企業は持続可能な未来を築くためのリーダーシップを発揮し、長期的な価値創造を実現することが期待されます。

