ISO14064とは?シリーズの説明とISO14064-1について詳しく解説
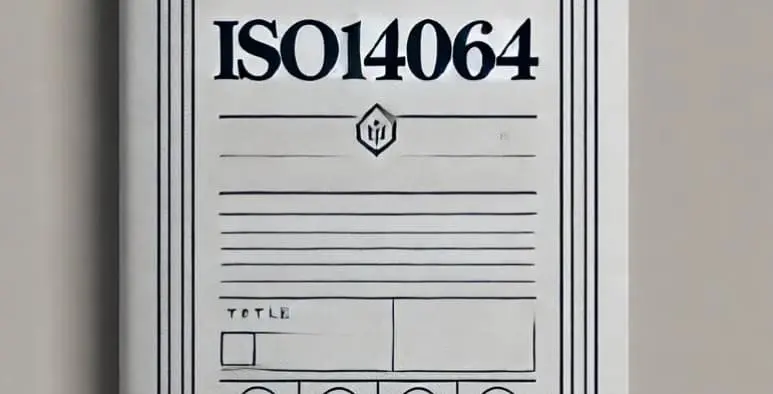
ISO14064は、温室効果ガス(GHG)の排出量を透明かつ客観的に算定・報告・検証するための国際規格です。
企業の脱炭素経営が求められる中、GHG排出量の適正な管理と報告の重要性が高まり、各国の規制や投資家の要請に対応するための基準として策定されました。
本記事では、ISO14064が誕生した背景やシリーズごとの役割(ISO14064-1~3、ISO14065、ISO14066)を解説し、企業がどのように活用できるかを明らかにします。
また、ISO14064-1を例に、企業単位でのGHG排出量算定の具体的なプロセスや要求事項を詳しく紹介し、ISO取得のポイントを分かりやすく説明します。
ISO14064の理解を深め、効果的なGHG管理を実践することで、企業の信頼性向上やサステナビリティ経営の強化につなげましょう。

ISO14064が生まれた背景
ISO14064は、温室効果ガス(GHG)の排出量を透明性・客観性を持って算定することの重要性が高まったことを背景に生まれました。
以下のような課題に対応するために策定されたものです
透明性と信頼性の確保:
GHG排出量を一定のルールに基づいて算定し、その結果を正確かつ明確に報告することで、報告の信頼性を向上させる必要がありました。
第三者機関による検証を受けることで、企業は報告の誤りによるリスクを低減し、ステークホルダーは算定結果の透明性と信頼性を確保できます。
検証業務の基準化:
検証を行うプロセスにも一貫したルールが必要であり、さらにその検証を行う機関にも公平性や専門性を確保する条件が求められるようになりました。
国際的な基準の必要性:
各国や組織がGHG排出量を算定・報告・検証する際に、統一された枠組みが求められるようになりました。
これらの背景から、ISO14064は、GHG排出量の算定ルール、検証ルール、そして検証機関に対する要求事項を明確にするために策定されたのです。

ISO14064シリーズについて
ISO14064-1(更新年 2018)
組織における温室効果ガスの排出量及び吸収量の定量化及び報告のための仕様並びに手引
・何に着目をして、どのように算定するのか(組織の範囲、排出係数など)
・どのようにモニタリング(測定)をすれば適切な算定ができるのか
・記載されているのはあくまで考え方のみ。具体的な方法は制度等で示されるガイドラインを参照する(14064-2も同様)。
要するに、CO2算定の認証取得基準(企業単位)について
ISO14064-2(更新年 2019)
プロジェクトにおける温室効果ガスの排出量の削減又は吸収量の増加の定量化、監視及び報告のための仕様並びに手引
・プロジェクトによる削減・吸収量を算定する際の考え方、方法
要するに、CO2算定の認証取得基準(プロジェクト単位)について
ISO14064-3(更新年 2019)
温室効果ガスに関する主張の妥当性確認及び検証のための仕様並びに手引
・検証機関はどのような条件を満たす必要があるか(力量、独立性、公平性など) 検証の際はどのような点をチェックすべきか
要するに、算定結果を検証するためのガイドライン(取得するものではない)について
ISO14065(更新年 2020)
認定又は他の承認形式で使用される温室効果ガスの妥当性確認及び検証機関に対する要求事項
GHG検証機関に対する要求事項(具体的な規定の例)
・力量(検証に必要な専門知識やスキル)
・公平性(利害抵触の回避、組織内の定期的な評価の実施など)
・マネジメントシステム(規格に則った手続きを実施しているか、文書管理、内部監査等の仕組みが整備されているかなど)
日本では(財)日本適合性認定協会(JAB)が検証機関に対してISO14065に基づく認定を実施。
要するに、検証機関を保証するための基準について
ISO14065の動向
国内
日本品質保証機構(JQA): 2011年3月に国内で初めてISO14065の認定を取得
海外
・EUの排出量取引スキーム(EU-ETS)の認定は2011年末を目途にISO14065認定に改訂される見通し
・米国でもボランタリースキームでISO14065導入の機運が高まっている
・認定機関のGHGに関する相互認証(MLA)を開始(PAC-MLA:アメリカ、日本、オーストラリア・ニュージーランド、台湾、カナダ、メキシコ、インド、中国等)
※PAC:Pacific Accreditation Cooperation(太平洋認定機関協力機構)

▼出典:環境省_温室効果ガス排出量の算定と検証について(ISO14064, 14065関連)
JQA:ISO14065(JISQ14065:2020)
ISO14066(更新年 2023)
温室効果ガス(GHG)の妥当性確認および検証に関与するチームの力量と能力に関する要求事項を定めた国際規格です。
この規格は、GHGインベントリや削減プロジェクトの妥当性確認や検証を行う組織に対し、関与する人材が適切な知識・技術を持っていることを保証するための基準を提供します。
要するに、検証チームを保証するためのガイドライン(取得するものではない)について
※言葉の定義:「機関」と「チーム」の違い

表:弊社で作成
▼出典:JISQ 14066:2012 (ISO 14066:2011)
※JISQ14066はISO14066を日本国内向けに翻訳・採用した規格です
学校で例えるISO14064
それぞれの関係性がよりイメージしやすいように、学校を例にとってご説明します。
生徒 = GHG算定者(企業やプロジェクト)
生徒が問題を解き、解答(GHG排出量の算定結果)を作成
問題用紙 = ISO14064-1、2
生徒が取り組むべき内容を示した問題用紙
└ ISO14064-1: 組織全体に関する問題用紙
└ ISO14064-2: プロジェクト単位の問題用紙
教科書 = ISO14064-3
生徒が問題の解答をチェックするために参照する教科書
問題用紙(ISO14064-1、2)の答え方や確認方法が記載
先生 = ISO14065
先生が教科書(ISO14064-3)を基に、生徒(算定者)の解答を採点・検証
校長先生 = ISO14066
先生(ISO14065)が適切に採点できるように、先生を教育・管理する人
先生のスキルや知識を確保するための基準を示す
少しでもこれらの関係性がイメージしやすくなれば幸いです。
また、ISO14064-3とISO14066はガイドラインのため、「取得するものではない」という点もご認識ください。
ISO14064-1の要求事項と適用事例
下記に全体構想を示します。
出典元の資料だと、回答項目なのか概念の項目なのか、必須回答なのか、任意回答なのか分かりづらかったため弊社で()を追記しています。
全体の構成
• 1 適用範囲(概念)
• 2 用語定義(概念)
• 3 原則(概念)
• 4 GHGインベントリの設計及び開発
4.1 組織の境界(回答必須)
4.2 活動の境界(回答必須)
4.3 GHGの排出量及び吸収量の定量化(回答必須)
• 5 GHG インベントリの構成要素
5.1 GHGの排出量及び吸収量 (回答必須)
5.2 GHGの排出量の削減又は吸収量の増加を図る組織の活動(回答任意)
5.3 基準年のGHGインベントリ (回答必須)
5.4 不確かさの評価及び削減 (回答必須)
・6 GHG インベントリの品質管理
6.1 GHGの情報管理(回答必須)
6.2 文書保持及び記録保管(回答必須)
・7 GHG報告
7.1 一般(回答任意)
7.2 GHG報告書の計画(回答任意)
7.3 GHG報告書の内容 (回答必須)
・8 検証に関する組織の役割
8.1 一般(回答任意)
8.2 検証の準備(回答任意)
8.3 検証の管理(回答任意)
次から全体構想の1~8章を詳しく説明していきます。
1 適用範囲(概念)
目的:
ISO14064-1は、組織が温室効果ガス(GHG)の排出量や吸収量を算定・報告するための一貫したフレームワークを提供することを目的としています
適用範囲の特徴
組織全体を対象:
組織が所有または管理するすべての活動、設備、排出源が対象
具体例: 工場のエネルギー使用、事業所の燃料消費
透明性の確保:
算定・報告において、透明性、一貫性、正確性を保証する。
他の規格との補完性:
ISO14064-2(プロジェクトレベルのGHG算定)やISO14064-3(検証基準)と連携
主な対象:
温室効果ガス排出量および吸収量を管理し、外部報告や削減計画を実行する企業・団体
2 用語定義(概念)
目的:
ISO14064-1で使用される主要な用語を統一的に定義し、規格内での解釈に一貫性を持たせる
主な用語の例:
GHG(温室効果ガス):地球の放射エネルギーバランスに影響を与えるガス
例: 二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N2O)
GHG排出量:温室効果ガスが大気中に放出されること
GHG吸収量:森林や土壌による温室効果ガスの吸収
組織境界:GHG算定の対象となる組織の物理的または操作的な範囲
活動境界:直接排出(Scope 1)、間接排出(Scope 2)、その他間接排出(Scope 3)の分類
3 原則(概念)
適切性:
意図した利用者のニーズに適したGHGの排出源、吸収源、貯蔵庫、データおよび方法を選択する
(利用者(国、自治体、消費者等)の目的に適した組織境界の設定、モニタリング・算定方法、排出係数を選択するなど)
問題となるケース:
企業間の比較を目的としたが、企業間で子会社の扱いなど組織境界の設定の考え方が異なる
規定すべき項目:
・算定の目的
・組織境界の考え方
・排出量の定量化方法(排出係数や算定ルール)

完全性:
すべての適切なGHGの排出量及び吸収量を含める
(敷地境界内の排出源が漏れなく特定され、算定対象となる全排出源についてGHG排出量を漏れなく算定するなど)
問題となるケース:
企業が任意で、排出量の多い主要な設備のみをピックアップして算定を行っている
規定すべき項目:
・算定対象活動の設定
・排出源の特定方法
一貫性:
算定結果について有意義な比較を可能にする
(同一の方法やデータ類を使用し、各算定対象年度において排出量が比較可能なように算定が行うなど)
問題となるケース:
経年変化を評価することが目的にも関わらず、年度によって用いるモニタリング方法や排出係数が異なる
規定すべき項目:
・定量化方法(排出係数や算定ルール)
・情報管理や算定手順の文書化・レビュー
は何を使う?データベースの選び方と活用事例.jpg)
正確性:
可能な限り不確かさを減らす
問題となるケース:
計測機器が適切に精度管理されていない
規定すべき項目:
・モニタリング方法の規定
・要求するモニタリング精度の設定
透明性:
意図した利用者が合理的な確信をもって判断を下せるように、十分かつ適切なGHG関連の情報を開示する
問題となるケース:
適用した算定方法や排出係数等について十分な情報公開を行っていない
規定すべき項目:
GHG報告書への記載項目の規定GHG報告書記載内容に関する公開範囲の規定
4 GHGインベントリの設計及び開発
この章からは、出典資料では分かりづらい部分について「著者の解釈」を付け加えて解説します。
4.1 組織の境界(回答必須)
単数の組織から構成しても、複数の組織から構成しても良い。
次のアプローチのいずれかを用いて、施設レベルでのGHG排出量を連結しなければならない。
a. 支配力基準
支配する施設(関連企業)からの排出量 ⇒100%算入
b. 出資比率基準
関連企業の出資比率分の排出量を算入
著者の解釈)
目的:GHGインベントリの対象となる組織の範囲を明確化する
内容:
1)物理的境界の設定
例: 工場、事業所、店舗などの物理的な施設
2)操作的境界の設定
操作権限(管理権)に基づいて境界を設定
例: 完全所有の施設だけでなく、合弁事業の一部も含めるか
3)境界設定の説明
なぜその範囲を選択したのか、選択基準を文書化
4.2 活動の境界(回答必須)
a. 活動境界の設定
組織境界内で算定対象となる排出源・活動を特定する
b. 算定対象となる排出
•直接排出– 化石燃料の使用に伴うGHG排出– 製造工程におけるGHG排出
•間接排出–他者から購入し使用した電気、熱又は蒸気の生成段階での間接的なGHG排出
著者の解釈)
目的:
GHG排出量や吸収量をどの活動範囲で算定するかを決定する
内容:
1)Scope 1(直接排出)
組織が直接排出する温室効果ガス
例: 燃料燃焼、化学プロセス
2)Scope 2(間接排出:購入エネルギー)
外部から購入した電力や蒸気などの間接排出
例: 購入電力に基づくCO2排出
3)Scope 3(その他間接排出)
サプライチェーンや廃棄物処理などのその他の間接排出。
例: 物流、従業員の通勤



4.3 GHGの排出量及び吸収量の定量化(回答必須)
a. 排出源及び吸収源の特定
b. 定量化方法の選択(例)
• 計算(燃料使用量×発熱量×排出係数等)
• 測定(濃度計等による直接測定)
• 両者の組み合わせ
c. データの選択
・収集
d. 排出係数又は吸収係数の選択又は開発※係数選択
・開発の際の条件(一部抜粋):
• 一般に認められた出所をもつ
• 該当する排出源又は吸収源に対して適切である
• 用途と一貫性がある
e. 排出量及び吸収量の計算
著者の解釈)
目的:
組織のGHG排出量と吸収量を数値で明確化
内容:
1)排出源と吸収源の特定
排出源:燃料燃焼、製造プロセス
吸収源:森林、土壌
2)算定方法の選択
排出係数を使用して計算
例: 燃料使用量 × 排出係数
3)データの収集と管理
必要な活動データ(例: 燃料使用量、電力消費量)を収集
5 GHG インベントリの構成要素
5.1 GHGの排出量及び吸収量 (回答必須)
各種の排出源からの排出量(トンCO2で表示)
(施設や組織レベルでの文書化が望ましい)
著者の解釈)
目的:すべての排出量と吸収量を算定し、正確に記録する
内容:
1)各スコープ別の排出量算定
Scope 1, 2, 3の排出量を明確に区分
2)吸収量の算定※1
森林や土壌による吸収量を計算
3)漏れの排出源の説明
排出対象外とした理由を明確に説明
※1)吸収量の算定について
森林や土壌の吸収量は技術的・コスト的な面から算定難易度が高いです。そのためISO14064-1に取り組む企業の多くは、吸収量に関して以下のような形で対応しています
1. 吸収量の算定は「実施可能性」に基づいて実施
多くの企業ではScope 1, 2, 3の排出量算定を優先し、吸収量の算定は必要最低限の範囲(例えば、自社で所有する森林や特定プロジェクト)に限定しています。
例: 自社が管理する森林プロジェクトだけを対象に吸収量を計算
2. デフォルト値や簡易モデルの活用
土壌吸収量や森林の吸収量に関しては、IPCCガイドラインや国の提供するデフォルト値を使用する企業が多いです。吸収量を厳密に算定するのではなく、参考値を使用して概算レベルで報告。
3. 吸収量を算定しないケースもある
ISO14064-1では「排出量と吸収量の完全性(Completeness)」を求めていますが、適用範囲を明確に限定すれば、吸収量を含めない報告も可能です。
例: 自社の活動が吸収量と無関係であることを明示し、排出量の算定だけに集中。

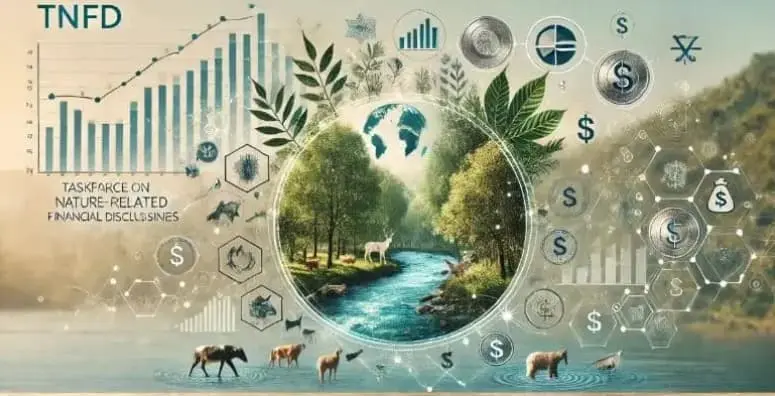

5.2 GHGの排出量の削減又は吸収量の増加を図る組織の活動(回答任意)
• 直接的に削減・吸収に寄与する活動(directed action)自社の削減、吸収取組み
(例:省エネ活動、燃料転換、植林)
• GHGプロジェクト(ISO14064-2)GHGプロジェクトから購入するGHG削減、吸収量
著者の解釈)
目的:排出削減や吸収増加に向けた取り組みを整理し、必要に応じて報告
内容:
1)削減活動の特定
例: エネルギー効率向上、再エネ導入
2)吸収量増加プロジェクトの報告
例: 植林活動、炭素貯留
3)活動の成果の測定
実施したプロジェクトの削減・吸収量を数値で示す

5.3 基準年のGHGインベントリ (回答必須)
5.3.1 基準年の選択及び設定
・基準年のGHG排出量・吸収量の定量化
・検証可能なGHG排出量・吸収量のデータを入手できる
・基準年を選択基準年の選定についての説明
・GHGインベントリ作成
5.3.2 GHGインベントリの再計算
・活動境界の変更
・GHG排出源、吸収源の重要な変更
・定量化方法の変更
著者の解釈)
目的:削減進捗を比較するための基準となる年のインベントリを設定
内容:
1)基準年の選択
利用可能なデータが十分で信頼性が高い年を基準年に選定
2)基準年の変更の記録
境界の変更やデータ改善があった場合、その理由を文書化
3)基準年データの検証
基準年データの正確性を確保


5.4 不確かさの評価及び削減 (回答必須)
算定に関わる不確かさを評価し、不確かさを可能な限り低減する。
(例)昨年の排出量との比較、計測装置の校正の実施、内部監査の実施
著者の解釈)
目的:GHG算定結果の不確かさを評価し、可能な限り削減する
内容:
1)不確かさの要因特定
データの欠損、排出係数の精度。
2)不確かさの定量化
例:統計的手法を用いて算定結果に含まれる不確かさを評価
3)削減措置の実施
データ収集方法の改善、測定装置のキャリブレーション実施
6 GHG インベントリの品質管理
6.1 GHGの情報管理(回答必須)
・チェック作業の規定
・インベントリの記録の文書化と保存
・各種レビュー
著者の解釈)
目的:GHGインベントリに含まれる情報の正確性、一貫性、信頼性を確保するためのプロセスを管理
内容:
1)データ収集と記録のルール設定
必要な活動データ(例: 燃料消費量、電力使用量など)を定義し、収集・保存
例: 燃料使用データは月次で記録し、年度末に集計
2)チェック体制の整備
データの記録方法や算定手法が適切であるかを内部的にレビューする仕組みを設置
例: 部門別の担当者が入力データを定期的に検証
3)手順書の作成
データ収集や計算のルールを明文化し、関係者間で共有
6.2 文書保持及び記録保管(回答必須)
文書保持、記録保管のための手順を確立、運用
著者の解釈)
目的:データや算定結果を適切な形で保存し、必要に応じて第三者検証や内部監査に対応可能な状態を維持
内容:
1)文書の種類と保管期間の明確化
保管対象:活動データ、算定方法、使用した排出係数、算定結果
例:活動データと算定結果を5年間保存
2)デジタルおよび物理的保管の組み合わせ
重要なデータはデジタル形式で保存し、バックアップを実施
例: クラウドストレージと社内サーバーにデータを保管
3)アクセス管理
文書やデータへのアクセス権限を明確化し、セキュリティを確保
7 GHG報告
7.1 一般(回答任意)
GHG報告書の内容、構造、配布方法などの決定
GHG報告書を公表する際には、独立した第三者による検証声明書の公表
著者の解釈)
目的:GHG報告全体の目的と基本的な方針を示す
内容:
1)報告の目的の明確化
例:温室効果ガス排出量削減の進捗報告、規制遵守、ステークホルダーへの透明性の向上
2)報告範囲の設定:組織境界や活動境界に基づいて報告の対象範囲を設定
7.2 GHG報告書の計画(回答任意)
著者の解釈)
目的:報告書の作成過程やスケジュール、必要なデータを整理
内容:
作成スケジュールの策定
例: データ収集完了→内部レビュー→報告書作成→最終承認→公表
報告書作成に必要なリソースの配分:
担当者、必要なデータ、ソフトウェアを明確化
7.3 GHG報告書の内容 (回答必須)
a)報告組織について
b)責任者
c)報告対象期間
d)組織境界(4.1)
e)-i) GHGインベントリ ⇒(4.2)
h)算定対象外としたGHG排出源、吸収源の説明(4.3.1)
j) 基準年のGHGインベントリ(5.3.1)
k)基準年の変更や再計算が行われた場合、説明(5.3.2)など
著者の解釈)
目的:ステークホルダーに信頼性のある情報を提供
内容:
1)基本情報
報告組織の名称、対象期間、組織境界、活動境界
2)排出量の詳細
各スコープ(Scope 1, Scope 2, Scope 3)別の算定結果
3)算定における不確かさや対象外項目の説明
データの不確かさや算定外の排出源について明記
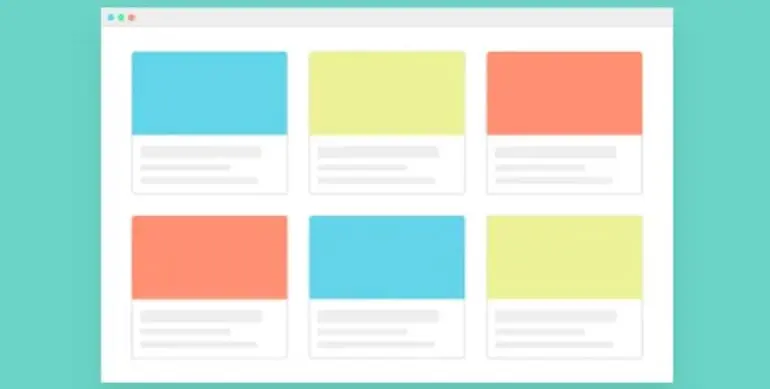
8 検証に関する組織の役割
8.1 一般(回答任意)
意図した利用者の要求事項に基づき適切な保証水準を決定する
意図した利用者のニーズ並びにISO14063-3の原則及び要求事項によって検証を行う
著者の解釈)
目的:検証プロセス全体で組織が果たすべき役割を定義
内容:
1)検証の目的と期待する成果を明確化
例: 報告書の信頼性向上、ステークホルダーへの説明責任の履行
8.2 検証の準備(回答任意)
検証の範囲・目的設定、保証水準(後述)の決定、検証機関との合意 等
著者の解釈)
目的:検証プロセスを円滑に進めるためのデータや体制の準備
内容:
1)必要データの整理
検証対象データを分類し、検証機関に提出可能な状態にする
2)内部レビューの実施
データが適切に整理されているかを確認
8.3 検証の管理(回答任意)
検証計画の策定と実施
検証者の力量確認
著者の解釈)
目的:検証プロセスを円滑に進行させ、結果を適切に反映する
内容:
1)検証機関とのコミュニケーション
検証中の問い合わせ対応、データ補足の提供
2)検証結果の記録と改善策の実行
検証後のフィードバックを基に改善策を立案
まとめ
今回の内容を改めて学校を例にしてまとめます。
問題用紙(ISO14064-1、2):生徒が解答を書く基準
教科書(ISO14064-3):解答を確認するための指針
先生(ISO14065):解答を採点する人
校長先生(ISO14066):先生が正しく採点できるように管理する人
※ISO14064-3とISO14066はガイドラインのため取得するものではない
今回はISO14064の中でも、ISO14064-1(企業単位のCO2排出量)について解説しました。
上記の(回答必須)を全て満たすことで、ISO14064-1は取得できます。

