環境省の新ガイドラインで変わるScope3|1次データで削減努力を“見える化”

Scope3排出量の削減は、多くの企業にとって避けて通れない経営課題です。
しかし、従来の算定手法では、業界平均に基づいた2次データに頼らざるを得ず、実際に削減努力を重ねたとしても、それが数値に反映されないという矛盾が現場を悩ませてきました。
こうした閉塞感を打破する鍵として、環境省が2025年3月に公表した『1次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド』が注目を集めています。
本ガイドは、サプライヤーなどから直接得られる1次データの活用を通じて、削減行動を正当に評価できる仕組みを提示しています。
本記事では、Scope3算定の本質的な課題と、1次データの意義、そしてその具体的な導入ステップを、企業の実務担当者の視点から詳しく解説します。

Scope3削減を算定で表すのはなぜ難しい?
【業界平均の排出原単位に頼るしかない現状】
現在、多くの企業がScope3排出量を算定する際に用いているのが、業界平均の排出原単位を収録した2次データです。
これは公的なデータベースやLCAデータ集に基づいており、手軽に使える一方で、自社特有の調達構造やサプライヤーの排出実態を反映できないという欠点があります。

そもそも2次データは「標準的な排出」を示すにすぎず、個別の改善努力や工程の違いが排除された、平均化された数値です。
そのため、企業がScope3の透明性向上や削減目標の正当化を目指す中で、この手法の限界が徐々に明らかになってきました。
は何を使う?データベースの選び方と活用事例.jpg)
【削減努力が反映されず、インセンティブも働かない】
仮にサプライヤーが再生可能エネルギーの導入や製造工程の見直しなどを通じて排出量を大幅に削減したとしても、顧客企業が業界平均の2次データで算定を行っている限り、これらの努力は排出量に反映されません。
つまり、「実態と数字の乖離」が生じるのです。
この構造は、サプライチェーン全体での削減行動に対する評価と報酬を遮断しており、サプライヤー側の取り組み意欲を損ねる要因にもなっています。
長期的に見れば、こうした評価の不在は脱炭素経営の本質的な推進力を弱めるリスクを孕んでおり、正確な算定手法への移行の必要性が徐々に表れてきています。

▼出典:環境省 1次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド- 「削減努力が反映されるScope3排出量算定」へ -(Ver1.0)
環境省ガイドラインが示す解決策
【「1次データ活用」というアプローチ】
環境省が提示したガイドラインの核心は、Scope3算定における「1次データ」の戦略的活用にあります。
これは単にデータの形式を変えるという話ではなく、これまで“平均的な仮定”に過ぎなかった排出量を、現実の取引や製造のプロセスに即した“実像”として捉え直す試みです。

企業がサプライヤーから直接得た排出情報を用いることで、従来は見えていなかったサプライチェーン上の排出差異や強みが可視化され、調達や設計の判断がより環境合理的に進められるようになります。
これは、排出量をただ「報告する」だけの時代から、「経営に活かす」フェーズへの移行を意味しています。

▼出典:環境省 1次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド- 「削減努力が反映されるScope3排出量算定」へ -(Ver1.0)
【削減努力が正当に評価される算定へ“脱炭素の動機づけ”を内包】
従来の2次データによるScope3算定では、サプライヤーがどれだけ脱炭素に取り組んでも、企業側の排出量に変化はなく、改善の成果が伝わりませんでした。
環境省ガイドラインはこの不均衡を是正し、削減行動が算定値に反映される“公正な算定”の仕組みを提示しています。
たとえば、再エネ100%で製造された部品と、従来のエネルギー源を使った部品の違いが、排出量として数字に表れるようになれば、サプライヤーにとっては努力が報われる明確なインセンティブになります。
これは単なる算定精度の向上ではなく、脱炭素の推進力そのものを算定ロジックの中に組み込む設計といえるでしょう。

▼出典:環境省 1次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド- 「削減努力が反映されるScope3排出量算定」へ -(Ver1.0)
【国際・国内の枠組みと連携した“実装可能な標準化”】
環境省のガイドラインは、日本独自の取り組みであると同時に、グローバルな整合性を意識した構造を持っています。
特に、世界経済人会議(WBCSD)が主導する「Pathfinder Framework(PACT)」とは親和性が高く、企業間で製品ベース排出量を安全かつ信頼性のある形で交換する国際ルールとの連携が想定されています。
また、国内でも「Green×Digitalコンソーシアム」が提供するCO₂可視化フレームワークとの整合性により、ITツールや中小企業支援策と組み合わせた日本版の実装環境が整いつつあります。
こうした連携により、1次データの活用は理念にとどまらず、すでに“運用フェーズ”に突入している実践知として、企業が安心して取り組める土壌が築かれつつあるのです。
1次データって具体的に何?
【製品ベースの1次データ:排出量を“製品1個単位”で把握する】
製品ベースの1次データは、特定の製品や部品について、その生産過程における温室効果ガス排出量を定量的に示したものです。
一般的には「Cradle to Gate」=資源採取から製品出荷までのライフサイクルを対象とし、1個あたり何kgのCO₂が排出されているかを示します。
ISO 14067に基づくCFP(カーボンフットプリント)や、SuMPO-EPDなどの環境宣言制度が活用されることもあります。
こうしたデータは、製品の選定や調達方針において定量的な比較を可能にし、より環境負荷の小さい製品を選ぶ根拠となります。
製造業をはじめとする多くの業種にとって、製品単位の可視化はScope3削減の第一歩となる有効な手段です。

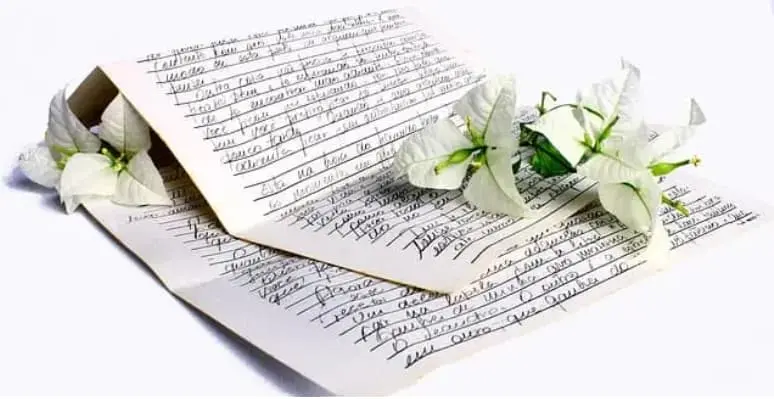

▼出典:環境省 1次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド- 「削減努力が反映されるScope3排出量算定」へ -(Ver1.0)
【組織ベースの1次データ:Scope1〜3を“顧客ごとに按分”して受け取る方法】
一方で、すべてのサプライヤーが製品単位の排出量を提示できるわけではありません。
そこで実務上よく用いられるのが、組織ベースの1次データです。
これはサプライヤー全体のScope1~3排出量をもとに、売上高や取引量などを基準にして、顧客企業ごとに排出量を按分する手法です。
たとえば、あるサプライヤーの年間GHG排出量が500t-CO₂であり、そのうち自社への売上が全体の5%であれば、25tを自社のScope3カテゴリ1に計上するという考え方です。
この手法は精緻さに欠ける一方で、導入のハードルが低く、特に中小規模の取引先を多く抱える企業にとって、現実的なスタート地点となり得ます。

▼出典:環境省 1次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド- 「削減努力が反映されるScope3排出量算定」へ -(Ver1.0)
【「Tier1から取得したデータ」のみが1次データとみなされる理由】
Scope3の算定において「1次データ」と見なされるためには、そのデータが自社の直接取引先(Tier1サプライヤー)から提供されたものであることが前提となります。
環境省のガイドラインは、GHGプロトコルの定義を踏まえつつ、企業が実務でデータを扱いやすいよう、現実的な運用ルールを提示しています。
ここで重要なのは、そのデータがサプライヤーによって収集・算定された時点で、たとえ2次データ(排出原単位など)を使っていたとしても、自社がTier1から直接受け取ったものであれば、それは1次データとして扱われるという点です。
つまり、「そのデータがどれだけ上流の実測に基づいているか」は問われず、「誰が誰に提供したか」が基準となるのです。
この柔軟な定義には、重要な背景があります。
理想では、Tier1がTier2から、Tier2がTier3から…というように、サプライチェーンの最上流まで1次データが伝達される構造が望ましいとされます。
しかし現時点では、多くの企業がそこまでのデータ収集体制を整えられておらず、過度に高い要件は実務導入の障壁になりかねません。
そこで、まずは“自社から見た1次データ”の定義を明確にすることで、現実的な普及促進と信頼性の両立を図っているのです。
この考え方を理解しておくことで、企業は過度な精度を求めてデータ収集を諦める必要がなくなり、信頼可能なデータ連携を現実的な範囲から段階的に構築することが可能になります。

▼出典:環境省 1次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド- 「削減努力が反映されるScope3排出量算定」へ -(Ver1.0)
まず取り組むべきはScope3カテゴリ1
【多くの業種にとって最大の排出源:「購入した製品・サービス」の影響力】
Scope3の15カテゴリの中でも、カテゴリ1(購入した製品・サービス)は最も排出量が大きくなる傾向があります。
特に製造業や建設業、小売業などでは、部品・原材料・製品などの外部調達が事業活動の中心にあり、それに伴う上流排出が全体の7~8割を占めることも珍しくありません。

企業がどれほど自社設備の排出削減に取り組んでも、調達先の排出が見えていなければ、脱炭素経営は片手落ちになってしまいます。
環境省のガイドラインがカテゴリ1からの着手を強く勧めるのは、多くの企業にとってこの領域が「削減インパクトの源泉」だからです。
【製品ベース or 組織ベースで段階的に始める:現実的な取り組み方】
Scope3カテゴリ1に対して1次データの活用を始める際、重要なのは完璧さではなく“段階的な進め方”です。
たとえば、まずは主要な部品や高額な取引先から製品ベースのCFPを収集し、比較的排出量の大きい調達先にフォーカスすることで、効率よくインパクトのある可視化が可能です。
一方で、製品ごとのデータ取得が難しい場合は、組織ベースでのScope1~3排出量を按分した情報でも構いません。
こうした柔軟な選択肢を認めたガイドラインの設計は、さまざまな規模・業態の企業が無理なくScope3算定を高度化できる実装性の高さを物語っています。

▼出典:環境省 1次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド- 「削減努力が反映されるScope3排出量算定」へ -(Ver1.0)
【完璧を求めず、できるところから着実に進める】
1次データによるScope3算定は、確かに理想的な手法ですが、すべてのサプライヤーがすぐに対応できるわけではありません。
だからこそ、ガイドラインでは「まず取りかかること」そのものに価値があるとしています。
すべての取引先に1次データを求めるのではなく、排出インパクトの大きい先から始めたり、2次データとの併用を認めたりすることで、完璧主義に陥らずとも前進が可能になります。
企業による実務的な取り組みの積み重ねが、やがて業界全体のデータ水準を引き上げる起点となるでしょう。
脱炭素の第一歩は「すべてをやる」ことではなく、「やれるところから始める」ことなのです。

▼出典:環境省 1次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド- 「削減努力が反映されるScope3排出量算定」へ -(Ver1.0)
サプライヤーエンゲージメントの実践:協力を得るためのアプローチとは?
【削減目標の共有・支援・共創:サプライヤーを“巻き込む”のではなく“仲間にする”】
Scope3削減は、自社単独では決して完結できないテーマです。
だからこそ、サプライヤーとの信頼関係をベースに、共通のゴールを共有し、ともに前進する姿勢が欠かせません。
単に「排出量データをください」と求めるのではなく、「自社としてこのような脱炭素目標を掲げている」「その達成に向けて御社の取り組みが重要である」といった背景と意図を明確に伝えることで、パートナーとしての協働意識が生まれます。
あわせて、算定ツールの紹介や、外部支援制度の情報提供など、サプライヤー側のリソースや知識不足に寄り添う支援姿勢が、持続的な連携の基盤になります。

【社内の調達部門・経営層も巻き込む体制づくり:孤立した環境担当では限界がある】
Scope3の取り組み、とりわけ1次データの取得は、環境部門だけで完結できるものではありません。
現実には、調達部門の理解と協力なくしてサプライヤーとのコミュニケーションは成立せず、また経営層の関心がなければ戦略的な取り組みに昇華しません。
環境省のガイドラインでも、組織横断的な連携体制の構築が成功の鍵であると明示されています。
社内での情報共有会議、経営層への定期的なレポーティング、調達方針への脱炭素基準の組み込みなど、組織としてScope3に取り組む“体温”を高める仕掛けが必要です。
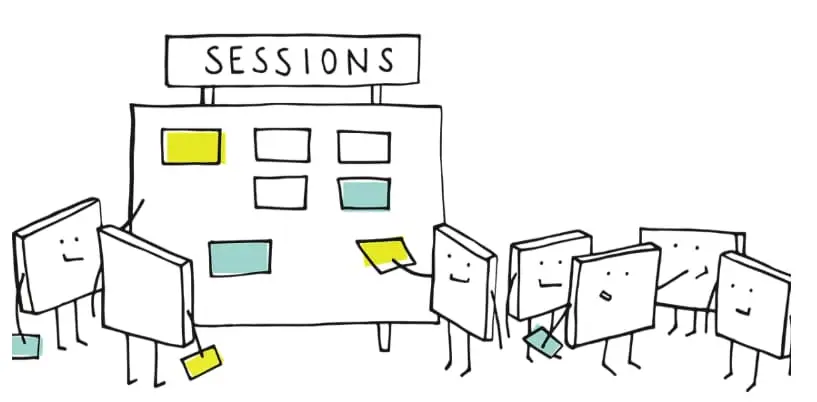
【合理的なデータ提供依頼の方法:信頼を築く“情報の渡し方”が鍵】
1次データの提供を依頼する際に重要なのは、一方的な要求ではなく、相手にとって納得感のある依頼をすることです。
たとえば、「なぜこの情報が必要なのか」「何に使われるのか」「どの程度の精度を求めているのか」といった背景や用途を丁寧に説明することで、サプライヤー側の不安や疑念を軽減できます。
さらに、フォーマットや提出期限を明確にしたうえで、すでに入手している他社事例や環境省のガイドラインの抜粋などを添えると、説得力と信頼性が高まります。
こうした対応を通じて、単なる取引先ではなく「環境パートナー」としての関係性を築くことが、1次データ活用の継続的な実践に不可欠です。

▼出典:バリューチェーン全体の脱炭素化に向けたエンゲージメント実践ガイド 令和6年度改訂版
社会全体で広がる影響
【1次データ活用が引き起こす“排出削減の連鎖”:可視化が生む連動の仕組み】
1次データの活用が広がると、企業ごとの排出実態がより正確に把握され、バリューチェーン全体の排出構造が“面”で見えるようになります。
たとえば、あるメーカーが特定の原材料の排出量を正確に可視化した結果、それを供給しているサプライヤー側でも改善活動が促されます。
さらにその上流にあたる素材メーカーでも削減への動機が生まれる──こうした連鎖反応は、企業単体の取り組みでは生まれにくいものです。
1次データは、その“つながり”を可視化することで、上流から下流まで削減行動を連動させる仕組みとして機能し、Scope3削減が現実味を帯びてきます。

【脱炭素経営が競争優位に:取引条件そのものが変わり始めている】
従来、価格や納期といった経済条件が優先されてきたサプライチェーンの評価基準に、カーボンパフォーマンス(排出削減能力)という新たな軸が加わりつつあります。
1次データに基づいて正確な排出量を提示できるサプライヤーは、顧客企業のScope3削減に直接貢献できる存在として高く評価され、今後の取引選定で優位に立てる可能性が高まります。
また、企業自身もこうした排出量の把握と開示が進めば、CDPスコアやSBT認定、さらにはESG投資の評価にも好影響をもたらします。
脱炭素の取り組みが“経営戦略”として評価される土台が、1次データによって着実に形成されているのです。

【インセンティブ設計としての「可視化の力」:排出量が“通貨”になる時代へ】
温室効果ガスの排出量が企業活動における“新たな尺度”となる中で、その可視化が持つ意味はますます重要になっています。
1次データによって精緻な排出情報が得られれば、取引先への報酬体系や、カーボンプライシング、インターナルカーボンプライスの導入といった制度設計そのものに活用できるようになります。

たとえば、排出量の少ない企業にインセンティブを与えるような調達ルールを設定すれば、削減行動が経済的利益と結びつき、行動変容が加速します。
このように、1次データは単なる「見える化」のツールにとどまらず、社会全体の脱炭素を加速する“設計思想の中核”として機能しはじめているのです。


▼出典:バリューチェーン全体の脱炭素化に向けたエンゲージメント実践ガイド 令和6年度改訂版
まとめ
Scope3排出量の算定は、もはや開示義務にとどまらず、企業の持続可能性と競争力に直結する戦略課題です。
環境省が示した1次データ活用のガイドラインは、サプライチェーン全体で削減努力を“正当に可視化する”ための現実的な解決策です。
業界平均では見落とされてきた努力を数字に反映し、公平な評価と経済的なインセンティブの連動を実現する手段として、1次データは大きな可能性を秘めています。
重要なのは、完璧を求めるのではなく、カテゴリ1など影響の大きい領域から段階的に取り組むこと。
脱炭素経営の基盤を強化する第一歩として、1次データの活用が今求められています。
