期限迫るSDGs(持続可能な開発目標)│現在の進捗について最新レポートを解説
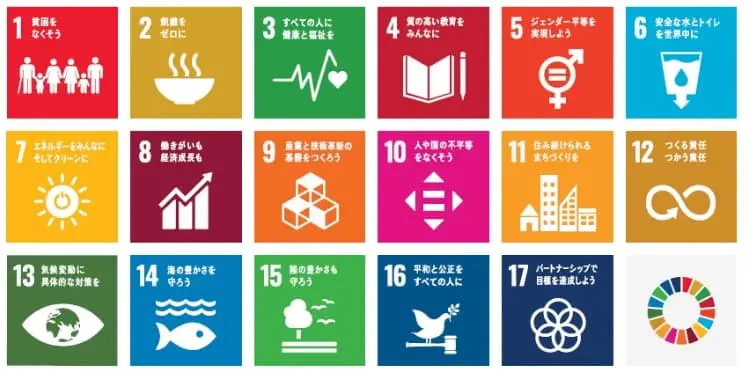
2015年から始まったSDGs(持続可能な開発目標)ですが、その達成期限となる2030年が迫ってきました。
今の達成状況はどうなのでしょうか。
17つある目標のなかでも気候変動や脱炭素の影響が大きい、目標6「安全な水とトイレを世界中に」、目標7「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」、目標13「気候変動に具体的な対策を」の3つについて、最新の進捗状況と課題を共有しながら、達成に向けて日本企業が出来ることについても紹介していきます。

SDGs全体の進捗
SDGs17の目標のうち、現時点(2024/6/28発行レポートより)で達成に向けた軌道に乗っているのはわずか17%であり、半数近くは最低限かわずかに進捗、3分の1以上は停滞または後退していることが明らかになりました。
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の長引く影響、紛争の悪化、地政学的緊張、気候カオス(大混乱)の拡大により、進捗が大きく妨げられています。
目標6_安全な水とトイレを世界中に

清潔な水と衛生は、健康的な生活の基盤であり、社会の安定に欠かせない要素です。
しかし、世界中で安全な飲料水と衛生設備を利用できる人々の数は依然として不足しており、特に低所得国や紛争地域での状況は深刻です。
安全な飲料水を利用できる人は増えているが、何十億人の人々が依然として
2022年のデータによると、世界人口の73%(2015年から+4%)が安全に管理された飲料水を利用できるようになりましたが、それでも27%の人々が清潔な水を手に入れることができていません。
また、35億人が十分な衛生設備を利用できておらず、その中で6億5,300万人は依然として野外排泄を強いられています。
2030年までに普遍的な飲料水普及率を達成するには、現在の進捗率の6倍も必要となります。
水質悪化は世界的な傾向と考えられますが、データの乖離が理解と行動を妨げている
水質の悪化は、環境だけでなく、健康にも深刻な影響を与えています。特に低所得国では、廃水の適切な処理が行われていないことが多く、水源の汚染が広がりやすい状況にあります。
このような状況を改善するためには、廃水処理施設の整備や水質モニタリングの強化が求められています。
2023年、120カ国、91,000の水域で56%が良好な水質ということが明らかになりました。
この指標に関する報告は2017年の71カ国から2023年には120カ国に増加しています。
(高所得の40カ国はこれらの水域の75%について報告し、他の80カ国が残りの25%について報告しています)
しかしデータ収集における技術的な課題から、湖沼や地下水(各71ヵ国)よりも河川(101ヵ国)をモニタリングする国の方が上回りました。これは懸念点と捉えるべきです。
湖沼は重要な生態系である一方、地下水は淡水の中で最も大きな割合を占めていることが多いです。
そのため重要な水源のモニタリングが十分に行われていないと、汚染の進行や水質の悪化に対する対応が遅れる可能性があり、その結果、淡水資源の枯渇や生態系の破壊が進むことが懸念されます。
また、農業活動においても肥料や農薬が雨水などで流され、未処理の廃水と共に水質を悪化させる原因となります。
特に農業から放出される過剰な栄養素(例えば窒素やリン)は、川や湖、地下水に流れ込み、藻類の異常発生(アオコなど)や酸素欠乏などを引き起こし、水生生物に悪影響を与えることがあります。
そのため、農業活動は未処理の廃水とともに水質に対する主要な脅威とされています。

目標7_エネルギーをみんなに そしてクリーンに

「エネルギーをみんなに そしてクリーンに」の達成に向けては、かなりの進展がありました。電気を利用できない人々の数は、2015年の9億5800万人から2022年には6億8500万人に減少。
同様に、クリーンな調理用燃料を利用できない人々の数も、同期間に28億人から21億人に減少しました。
再生可能エネルギーから電力を生成するための世界的な設備容量は前例のない速度で拡大し始めており、この傾向は今後も続くと予想されています。
電気にアクセスできない人の数が10年ぶりに増加
2022年には、世界全体の電力アクセス率は91%で安定していましたが、それでも6億8500万人が電気を利用できていません。
これは2021年よりも1000万人増加しており、その主な要因は人口増加です。これは過去10年間で初めての増加で、この後退は主にCOVID-19パンデミックやウクライナ紛争によるエネルギー価格と市場の混乱に起因しています。
電気が届いていない人々は主に低所得世帯や遠隔地に住む人々です。
特に発展途上国におけるクリーンエネルギーの国際的な資金流入は不足しています。
このままでは、2030年までに約6億6000万人が依然として電気を利用できず、約18億人がクリーンな調理用燃料や技術を利用できない状態が続くと予想されています。
エネルギー効率を改善するためには、世界的な投資を3倍に増やす必要がある
「世界の一次エネルギー単価は、2015年の4.9 MJ /ドル(2017年購買平均)から2021年には4.6MJ / ドルに改善しました。
しかし、2021年のエネルギー単価の改善率はわずか0.8%であり、パンデミック後の強力な経済回復やエネルギー集約型産業へのシフトが影響しています。この改善率は、過去5年間の平均である1.2%を下回っています。
2030年までに目標7のエネルギー効率目標を達成するためには、年間の改善率が平均で約4%に達する必要があります。主要なアクションとしては、最終用途の電化やクリーンな調理の普及など、より効率的な燃料への切り替えが含まれます。
また、機器やプロセスの技術的効率を向上させ、エネルギーや材料の使用をより効率的にすることも重要です。さらに、エネルギー効率へのグローバルな投資は、2030年までに3倍に増加する必要があります。
しかし、特に新興市場や発展途上国では、金利の高騰が新しいプロジェクトの資金調達をより困難にしており、大きな課題となっています。」
クリーンエネルギーへの国際的な公的資金は2022年に回復したが、依然として不十分
2022年には、発展途上国におけるクリーンエネルギーを支援する国際的な公的資金の流入が154億ドルに回復し、2021年に比べて25%増加しました。
しかし、2016年のピークである285億ドルの約半分にとどまっています。
この減少傾向は、特に発展途上国(LDCs)、内陸開発途上国(LLDCs)、および小島嶼開発途上国(SIDS)において、目標7の達成に向けた進展を妨げる可能性があります。
資金の配分はわずかに広がりつつあります。2021年には、80%の資金が19か国に集中していましたが、この数字は2022年には25か国に増加しました。
過去10年間の技術動向により、投資は水力発電から太陽光エネルギーやその他の再生可能エネルギーへとシフトしています。
2022年には、資金のほぼ半分が複数の再生可能エネルギーおよびその他の再生可能エネルギーに向けられました。太陽光エネルギーは35%、風力エネルギーは11%、水力発電は7%の割合を受け取っています。
目標13_ 気候変動に具体的な対策を

気候変動対策は、持続可能な未来を確保するために最も重要な課題の一つです。
2022年の温室効果ガス排出量は記録的な57.4 ギガトンに達し、気温上昇を1.5°C以内に抑えるための取り組みが急務となっています。
しかし、化石燃料の使用が依然として大きな課題であり、世界中での気候変動対策が進展している一方で、その効果はまだ不十分です。
先進国による年間1000億ドルの気候資金提供の約束は一歩前進ですが、これだけでは十分ではありません。
特に開発途上国においては、適応策のための資金が不足しており、気候変動の影響に対する脆弱性が高まっています。
洪水や干ばつなどの自然災害が頻発する中で、これらの地域での適応策を強化するためには、さらなる資金提供と技術支援が必要です。
また、自然災害に対するリスク管理の強化も重要であり、災害の影響を軽減するための取り組みが求められています。
過去最⾼の温室効果ガス排出量は、世界が気候⽬標を達成できなかったことを示している
2022年、世界の温室効果ガス排出量は574億トンのCO2相当量に達し、過去最高を記録しました(国連環境計画の『エミッションギャップレポート2023』による)。
排出量の約3分の2は、化石燃料の燃焼と産業プロセスによるCO2が占めています。
交通分野を除いて、すべての主要なセクターの排出量はパンデミック以降に回復し、現在では2019年の水準を上回っています。
エネルギー部門は、世界のCO2排出量の86%を占める最大の貢献者であり、石炭およびガス火力発電の拡大によって主導されています。
政府は、2030年までに1.5°Cの温暖化抑制と一致するレベルを110%も上回る化石燃料を生産する計画を立てています。
温暖化を1.5°Cに抑えるためには、2030年までに温室効果ガス排出量を42%削減し、年率8.7%の減少が必要です。
2°Cに抑えるには、2030年までに28%の削減、すなわち年率5.3%の減少が求められます。
これに匹敵する削減は、パンデミック中の2019年から2020年にかけての4.7%の減少のみです。
現在の各国の政策では、地球の気温は3°C上昇する軌道にあります。国別削減目標(NDC)はこれを2.5°Cに抑えるものの、すべてのネットゼロ宣言を考慮しても2°Cの温暖化にとどまると予測されますが、これらの宣言には不確実な部分が多いです。
現在、1.5°Cに温暖化を抑える確率はわずか14%しかなく、今すぐ加速された行動を取って、今後の10年間で排出量を大幅に削減することの緊急性が強調されています。
1000億ドルの気候変動対策資⾦⽬標達成は重要だが、各国の行動計画には何兆ドルも必要
気候資金は、地球規模の緩和と適応の取り組みを支えるために極めて重要です。
先進国は、2020年から2025年にかけて、発展途上国向けに年間1000億ドルの気候資金を動員することを約束しました。経済協力開発機構(OECD)は、この約束が初めて2022年に達成されたと報告しています。
2022年には気候資金が2021年から30%増加し、1159億ドルに達しました。このうち60%が緩和対策に割り当てられました。また、適応資金は2016年の101億ドルから324億ドルに増加しました。
2021年のグラスゴー気候合意では、先進国に対し、2019年のレベルから2025年までに発展途上国向けの適応資金を倍増するよう求めています。OECDのデータによれば、2022年までに先進国はこの目標に向けて約半分の進捗を達成しました。
2025年以降の新たな気候資金目標を策定するための交渉が進行中であり、最低でも年間1000億ドルから始め、発展途上国のニーズと優先事項を考慮に入れる予定です。
国連気候変動枠組条約(UNFCCC)は、2030年までに発展途上国の気候行動計画には約6兆ドルが必要と見積もっており、資金を大幅に増加させる必要性が強調されています。
SDGs目標6、7、13の達成に向けて、日本企業ができること
目標6_安全な水とトイレを世界中に
企業ができること
・水使用の効率化
企業は製造プロセスや日常業務において水の使用効率を高めることができます。
例えば、節水技術の導入やリサイクル水の使用拡大などが考えられます。
・水質保護活動への参加
水源の汚染防止や河川の浄化活動に参加し、地域社会との協力を通じて安全な水資源の確保に貢献することが求められます。
・サプライチェーンでの水管理
サプライチェーン全体での水使用を管理し、特に水ストレスが高い地域での持続可能な水管理を促進します。
・水使用データの開示と改善計画の策定
自社の水使用状況を把握し、データを透明に公開するとともに、水使用削減の目標を設定し、計画的に実行することが重要です。
・水教育プログラムの実施
社員や地域社会に対して、水資源の重要性や節水方法についての教育プログラムを提供し、意識の向上を図ります。
目標7_エネルギーをみんなに そしてクリーンに
企業ができること
・再生可能エネルギーの導入
自社のエネルギー源を再生可能エネルギーにシフトすることで、CO2排出削減に寄与します。
特に、太陽光発電や風力発電の導入を進める企業が増えています。
・エネルギー効率の改善
省エネ技術や設備の導入を進め、エネルギー効率を向上させることが、コスト削減と環境負荷低減の両方に貢献します。
・スマートグリッドの活用
スマートグリッド技術(ITを活用して電力の流れを供給側、需要側相互に監視・制御し最適化する電力網)を活用し、エネルギーの供給と需要のバランスを最適化し、エネルギーの無駄を減らします。
・エネルギー使用データのモニタリングと公表
エネルギー使用の現状を把握し、定期的にデータを公開することで、ステークホルダーに対する透明性を確保し、改善活動を促進します。
・社員教育と啓発活動
社員に対して、エネルギー効率の重要性や再生可能エネルギーの利点についての教育を行い、全社的にエネルギー削減に取り組む文化を醸成します。

目標13_気候変動に具体的な対策を
企業ができること
・CO2排出量の削減
企業の事業活動全体にわたってCO2排出量を削減するため、エネルギーの効率化や再生可能エネルギーの導入、製品のライフサイクル全体でのカーボンフットプリント削減を進めます。

・気候リスクの評価と適応戦略の策定
気候変動によるリスクを評価し、企業活動への影響を最小限に抑えるための適応戦略を策定します。特に、極端な気象条件や自然災害に備えることが重要です。
・国際的な気候変動対策への参加
SBT(Science Based Targets)やRE100といった国際的なイニシアチブに参加し、科学に基づいた気候変動対策を推進します。

・気候関連の開示と報告
CDPなどのガイドラインに従い、気候変動が企業に与えるリスクと機会を報告することで、投資家やステークホルダーに対する信頼を高めます。

・サプライチェーンのカーボンニュートラル化
自社だけでなく、サプライチェーン全体のカーボンニュートラル化に取り組み、パートナー企業と連携して持続可能な生産を目指します。

まとめ
ここまでSDGsについてお話してきましたが、果たして企業は「地球を守るために、SDGs達成のために」行動することができるでしょうか。
これらの変化を「経済レギュレーション(取り締まり)」と捉えて、ビジネスをするうえでルールが変わったからそれに対応する。
その対応の1つとして気候変動対策に取り組む、という動機でも良いと思います。
人によって、企業によって、それぞれ納得できる動機のもとに、何かしらの行動に移すことが重要だと思っています。
▼出典:The-Sustainable-Development-Goals-Report-202406

