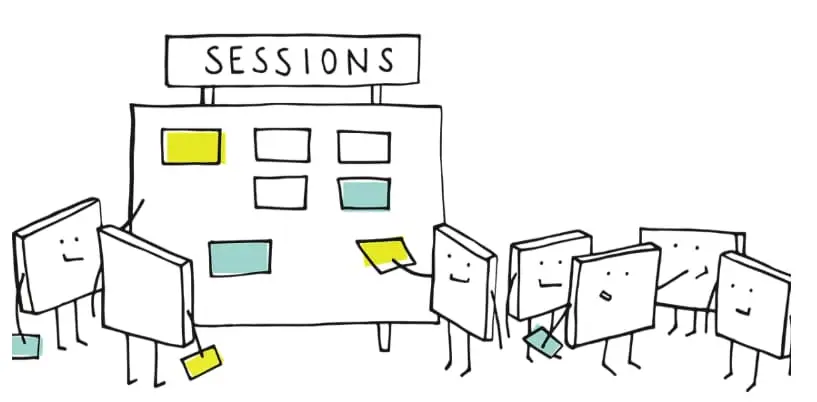企業が脱炭素経営やサステナビリティ方面に力を入れる中、取り組みが一部で留まらないように社内教育が重要になってきますが、いざ実行するとなるとどのように行なえばよいか分からないということは多々あります。
実行できても、国内の従業員には一通り行えたが役に立っているかが見えにくい、国外のメンバーへの教育がまだ行なえていないなど課題も一定残ります。
弊社にも社内教育についてのお問い合わせ、GX研修やサステナビリティ研修の依頼が来ることがありコンテンツを作って提供していますが、一般的には、主にワークショップ、ケーススタディ、外部講師によるセミナー、eラーニングの活用などを通して教育を行っていくことが多いです。
本記事では、脱炭素、サステナビリティの社内教育について重要性や弊社での取り組みについて紹介します。
脱炭素経営のためのCO2排出量見え…
GX研修の必要性とは?カーボンニュートラル時代に企業がすべき対策 – 脱炭素経営のためのCO2排出量見える化…
GX(グリーントランスフォーメーション)は、脱炭素化と経済成長の両立を図る国家的戦略であり、企業にとって競争力維持の必須条件です。本記事では、GX研修の目的や重要性…

目次
サステナビリティに関する社内教育の重要性と利点
サステナビリティ教育がもたらす文化と人材への効果
サステナビリティに関する社内教育は、企業が持続可能な成長を実現するための基盤となります。
単に知識を伝えるだけではなく、従業員一人ひとりが「自分の行動が環境や社会にどのように影響するか」を理解し、日常業務に反映できることが重要です。
例えば、製造現場での廃棄物削減やエネルギー効率改善は、企業の環境目標に直結する具体的な行動です。
教育を通じて自身の役割と企業戦略の結びつきを認識することで、社員の責任感や行動意欲が高まります。
さらに、教育は企業文化の変革を後押しします。部署を越えた対話が自然に生まれ、「持続可能性を意識することが当たり前」という文化が社内に定着します。
これにより、社員間の連携が強化され、新しいアイデアや取り組みが生まれやすい風土が整います。
特に若手世代は社会的意義のある仕事を重視する傾向が強いため、教育によってモチベーションやエンゲージメントの向上にも直結します。
脱炭素経営のためのCO2排出量見え…
サステナビリティ研修の成功事例|企業向け7つのワークショッププログラム – 脱炭素経営のためのCO2排出量…
企業や教育機関で注目されるSDGs研修を徹底解説。座学で終わらず行動変容を促す体験型プログラムの効果や特徴を、TBM社の社内研修、「CircularityDECK」や「2030SDGs」カー…
戦略的投資としての教育―競争力・イノベーション・信頼の強化
サステナビリティ教育はコストではなく、企業にとっての戦略的投資です。
教育によって培われた知識と行動力は、イノベーションやリスク管理、社会的信頼の強化へとつながります。
例えば、営業部門が顧客の環境目標に沿った提案を行えば新しいビジネス機会が生まれ、開発部門が環境配慮型の素材を採用すればブランド価値の向上につながります。
こうした実践は、持続可能性を核としたビジネスモデルを構築する力となります。
また、規制や社会的要請に迅速に対応できる社員がいることで、企業はリスク管理能力を高めると同時に競争優位性を確保できます。
さらに、教育を受けた社員が地域社会や取引先と積極的に対話し、持続可能性の価値観を伝えることで企業への信頼感やブランドイメージの向上にも寄与します。
実際にTMBでは、毎年「サステナビリティ研究会」を開催し、社員が知見を深める取り組みを続けています。
改めて学ぶ時間を持つことで、自身の仕事の意義を再認識し、企業全体での持続可能性推進に弾みをつけています。
▼参考:前編|サステナビリティ社内浸透施策を公開!組織拡大と自分ゴト化を両立する研究会とは
▼参考:後編|サステナビリティ社内浸透施策を公開!組織拡大と自分ゴト化を両立する研究会とは
また、社内のゴミの分別についても力を入れて社員1人1人が分別の意識を持つことや、アースデイや国際女性デーでの取り組みでもサステナビリティを身近に感じられます。

※TBM社の分別
他にも、情報のキャッチアップについては、週に1回のサステナビリティ部からの社内へのメルマガや毎日のGoogleアラートでの記事紹介などがあります。
脱炭素経営のコンテンツ
サンプルになりますが、脱炭素経営のコンテンツと資源循環のコンテンツを一部紹介します。