Scope3 カテゴリ6~8,14,15を徹底解説 !各カテゴリの概要と排出量算定方法をわかりやすく紹介
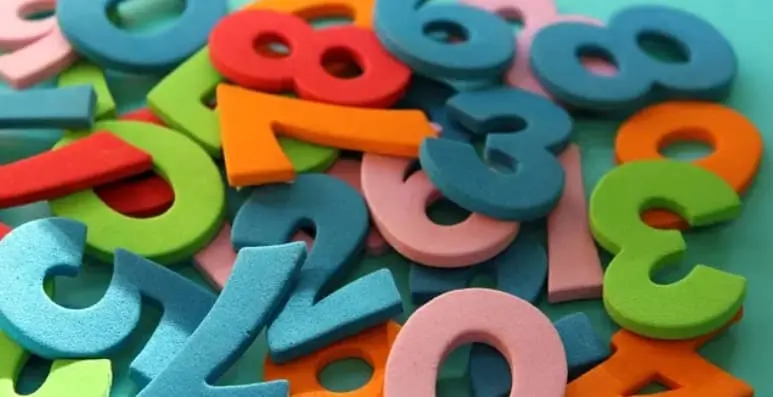
企業の温室効果ガス(GHG)排出量を包括的に把握するために欠かせないのがScope3算定です。
直接排出(Scope1)や購入電力に伴う排出(Scope2)に加え、バリューチェーン全体の間接排出を対象とするScope3は、15のカテゴリに細分化されています。
その中でもカテゴリ6~8および14・15は、業務出張、従業員の通勤、リース資産の利用、フランチャイズ店舗、さらには投資活動といった企業活動の広範な側面を対象としており、事業規模や業態によって影響度が大きく異なるのが特徴です。
例えば、カテゴリ6では飛行機や鉄道による出張に伴う排出、カテゴリ7では自動車通勤や公共交通機関利用に関連する排出を算定します。
また、カテゴリ14はフランチャイズ加盟店のScope1・2排出、カテゴリ15は投資先の排出を出資比率で按分するなど、企業にとって説明責任や透明性が問われる領域です。
本記事では、これら5つのカテゴリの概要と算定方法をわかりやすく整理し、担当者が上長や経営層へ説明できる水準で解説します。
カテゴリ1~5とカテゴリ9~13については、こちらで解説しております。
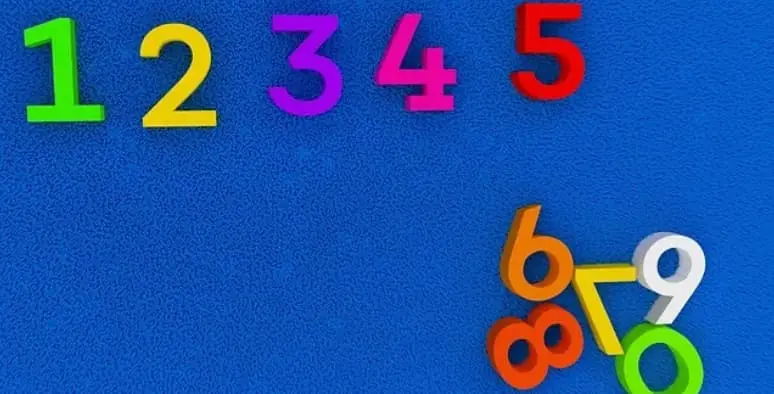
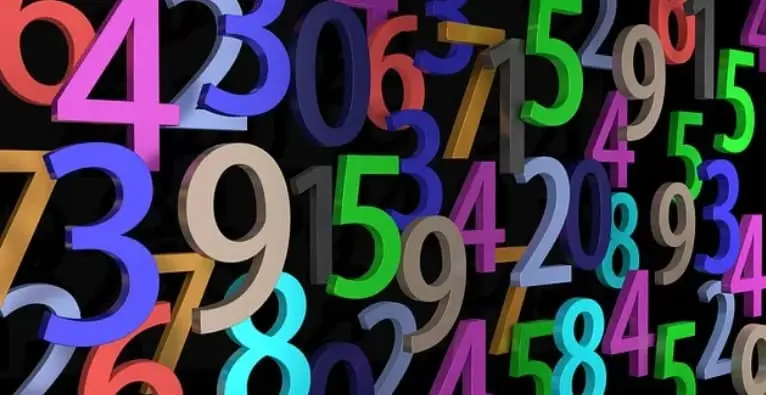
本記事では、上長や社内の関係者へ説明できる水準でScope3の各カテゴリ(この記事ではカテゴリ6~8,14,15)について説明していきます。
▼おすすめのお役立ち資料

Scope 3カテゴリ6(出張)の重要性と算定方法
カテゴリ6とは?
Scope 3カテゴリ6(出張)は、従業員の出張に伴って発生する温室効果ガス(GHG)排出量を算定する項目です。
対象となるのは、飛行機や鉄道、バス、車といった交通手段の利用に加え、出張先での宿泊や滞在に伴う排出も含まれます。
企業活動に不可欠な出張ですが、その環境負荷を定量的に把握することが求められています。

算定方法の種類
カテゴリ6の排出量は、利用データの入手状況に応じて複数の方法で算定できます。
代表的な算定方法は以下の通りです。
- 距離ベース算定:出張距離(例:飛行機のフライト距離、鉄道の乗車距離)に基づき計算
- 燃料ベース算定:使用燃料量を把握し、その排出係数を掛け合わせる方法
- 金額ベース算定:交通費や宿泊費の金額に排出原単位を掛け合わせて推計
- 従業員数・日数ベース算定:出張者数や日数に応じた推計
実務では、経理部門のデータを活用できる金額ベース算定が多く用いられています。
金額ベースの算定例
旅客航空機(国内線)の排出原単位は、0.00525kg-CO₂/円とされています。
例えば、国内出張で航空機に100万円を支出した場合、次のように算定されます。
1,000,000(円) × 0.00525(kg-CO₂/円)= 5.250t-CO₂eこのように、会計データから比較的容易に算出できる点が金額ベース算定の強みです。
実務上の課題と工夫
出張に伴う排出量算定でよくある課題の一つが、交通手段別のデータが区分されていないケースです。
例えば、経理上で「交通費」として飛行機・鉄道・バスが一括計上されている場合、そのままでは正確な算定ができません。
この場合は仕分け作業が必要となり一定の工数がかかりますが、経費精算の段階から交通手段を分けて記録する仕組みを導入すれば、次回以降の算定を大幅に効率化できます。
企業にとっての意義
カテゴリ6を正しく算定することで、企業は以下のような取り組みにつなげられます。
ESG評価やサステナビリティ報告書における透明性の確保
出張規模や交通手段の見直しによる排出削減の余地を特定
オンライン会議や鉄道利用へのシフトによる低炭素化戦略

Scope 3カテゴリ7(雇用者の出勤)の重要性と算定方法
カテゴリ7とは?
Scope 3カテゴリ7(雇用者の出勤)は、従業員が自宅から勤務先へ通勤する際に発生する温室効果ガス(GHG)排出量を対象とする項目です。
対象となるのは、電車やバスといった公共交通機関の利用だけでなく、自家用車通勤や社用バス利用など、多様な通勤手段に伴う排出です。
企業が直接管理できない活動であるため、間接排出(Scope 3)の一部として扱われます。

算定方法の種類
雇用者の出勤に伴う排出量は、利用できるデータに応じてさまざまな方法で算定されます。
- 距離ベース算定:従業員の自宅と会社間の距離を基に、通勤回数を掛け合わせて算定
- 従業員数・勤務日数ベース:人数と出勤日数から平均的な通勤排出を推定
- 燃料ベース算定:車通勤の場合、使用燃料量を基に排出量を算定
- 金額ベース算定:交通費や通勤手当の金額に排出原単位を掛けて推計
実務上は、経理や人事データを活用できる金額ベース算定が最も多く用いられています。
車通勤における課題と対応
実際の相談でよく見られるのが、ガソリン代補助金を定額で支給している企業における算定の難しさです。
この場合、以下のような工夫が行われています。
- 従業員の車種と燃費データを収集し、通勤距離を把握する方法
- 補助金額をガソリン単価で割り、推定される燃料使用量を算出して排出量に換算する方法
多くの企業では後者のように、支給額 ÷ ガソリン単価 = 使用燃料量 として簡便に算定するケースが一般的です。
企業にとっての意義
雇用者の出勤に伴う排出量は、企業の直接的な活動範囲外にありますが、従業員数が多い企業や自動車通勤の割合が高い企業では無視できない規模となることがあります。
適切に算定することで、以下のようなメリットがあります。
ESG報告やサステナビリティレポートにおける透明性の確保
公共交通機関やシャトルバスへの切り替えによる排出削減の余地を特定
テレワークやフレックス制度の導入効果を定量的に把握
Scope 3カテゴリ8(リース資産〔上流〕)の重要性と算定方法
カテゴリ8とは?
Scope 3カテゴリ8(リース資産〔上流〕)は、企業が賃借しているリース資産の操業に伴って発生する温室効果ガス(GHG)排出量を算定する項目です。
対象となるのは、自社が所有せずリース契約によって利用している設備や建物の使用に伴う排出です。

他カテゴリとの違い
「リース資産」というと、オフィスで使用するコピー機なども対象ではないかと考えられがちです。
しかし、多くの場合、コピー機の稼働に伴う電力使用はすでにオフィス全体の電力消費としてScope 2に計上されています。
そのため、環境省のガイドラインでも「リース資産(上流)」をわざわざScope 2と切り分けて算定する必要はないとされています。
実際にカテゴリ8を算定している企業はごく少数です。
算定が必要となるケース
とはいえ、特定の条件下ではカテゴリ8での算定が必要になります。
例えば、以下のようなケースです。
- 倉庫やオフィスの一部をリースしている場合:借用している面積に基づいて排出量を按分
- 特定のリース契約に基づくエネルギー使用がScope 2に含まれない場合:該当する資産の排出をカテゴリ8で算定
こうしたケースでは、賃借面積や契約条件を考慮して排出量を適切に算定することが求められます。
企業にとっての意義
カテゴリ8は、他のカテゴリに比べると実務での重要度は低いものの、リース資産を多用する企業や特定の契約形態を持つ企業にとっては無視できない領域です。
正しく扱うことで、Scope 1・2・3の重複や漏れを防ぎ、サステナビリティ報告における透明性を高めることにつながります。
Scope 3カテゴリ14(フランチャイズ)の重要性と算定方法
カテゴリ14とは?
Scope 3カテゴリ14(フランチャイズ)は、フランチャイズ事業を展開している企業が、加盟店の活動に伴って発生する温室効果ガス(GHG)排出量を算定する項目です。
対象となるのは、フランチャイズ加盟店のScope 1(自社が直接排出する燃料の燃焼など)とScope 2(購入電力や熱の使用に伴う排出)です。
そのため、フランチャイズ事業を行っていない企業には該当しないカテゴリとなります。

算定方法
フランチャイズ加盟店の排出量は、企業の状況や入手できるデータに応じて複数のアプローチがあります。
- 実測データに基づく方法
加盟店ごとに聞き取り調査を行い、電力使用量や燃料使用量の実データを収集して算定する方法。 - 代表店舗を基にした推計
典型的な規模の店舗単位で排出量を策定し、それを全体の店舗数に掛け合わせて推計する方法。
後者はすべての加盟店から正確なデータを集めることが難しい場合に広く使われています。
企業にとっての意義
フランチャイズ加盟店は、企業のブランドやサービス提供の一端を担う存在であり、その環境負荷も本部企業のサステナビリティ責任の一部として捉えられます。
カテゴリ14を適切に算定・開示することは、以下のような効果につながります。
加盟店への環境改善支援によるブランド価値向上
フランチャイズ全体での排出削減戦略の策定
ESG評価やサステナビリティレポートにおける透明性の確保
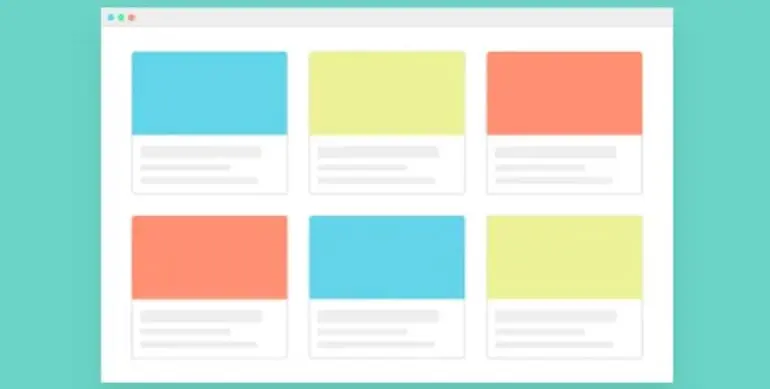
Scope 3カテゴリ15(投資)の重要性と算定方法
カテゴリ15とは?
Scope 3カテゴリ15(投資)は、企業が行う投資活動に関連して発生する温室効果ガス(GHG)排出量を算定する項目です。
株式投資、債券投資信託、プロジェクトファイナンスなどが対象となり、投資先企業や事業が生み出すScope 1・2の排出量を、自社の投資比率に応じて按分して計上します。
このカテゴリは、特に金融機関や投資事業を持つ企業にとって重要な領域であり、投融資活動を通じた間接的な環境影響を可視化する役割を果たします。

算定方法
カテゴリ15の基本的な算定式は以下の通りです。
投資先のScope 1・2排出量 × 出資比率 = 自社が計上すべき排出量算定例
例えば、ある企業が投資先に30%を出資しており、その投資先のScope 1・2合計が 30,000t-CO₂e だった場合:
30,000 × 0.3 = 9,000t-CO₂eこのように、自社の投資シェアに応じて排出量を按分して計上します。
データが得られない場合の対応
投資先企業がScope 1・2の排出量を公表していない場合もあります。
その場合は以下の方法で推計を行うことが一般的です。
- 業界平均の排出原単位を用いた推計
- 投資額や企業規模(売上・従業員数など)に基づくモデル算定
- LCAデータベースや公開情報を活用した補完
これにより、データ不足のリスクを補いながら、できる限り正確に排出量を算定することが可能です。
企業にとっての意義
カテゴリ15を正しく算定することは、金融機関や投資を行う企業にとって投融資ポートフォリオ全体の気候影響を把握する上で不可欠です。
さらに以下の効果が期待されます。
国際的な開示基準への準拠:PCAF(金融業界向けGHG会計基準)やISSB基準などへの対応
投資先企業の環境リスク管理:高排出事業への依存度を把握
ESG投資やグリーンファイナンスへの対応:投資判断にサステナビリティ要素を組み込む

まとめ
Scope3カテゴリ6~8、14、15は、出張や通勤といった身近な活動から、フランチャイズや投資といった経営レベルの意思決定まで幅広くカバーする領域です。
カテゴリ6「出張」では交通機関や宿泊に伴う排出を扱い、交通費データを活用した算定が一般的です。
カテゴリ7「雇用者の出勤」は通勤手段に応じた排出を算定し、特に自家用車利用の取り扱いが実務上の課題になります。
カテゴリ8「リース資産(上流)」は企業が賃借する設備や施設の排出を対象としますが、多くはScope2で計上されるため、該当ケースは限定的です。
カテゴリ14「フランチャイズ」は加盟店のScope1・2排出をカバーし、フランチャイズ展開企業にとって不可欠な項目です。
そしてカテゴリ15「投資」は投資額や出資比率を基準に投資先の排出を算定し、金融機関や大企業にとって重要な報告対象となります。
これらを正しく把握することで、Scope3全体の抜け漏れを防ぎ、社内外への説明責任を果たすことにつながります。
出典)環境省 サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.4)

▼おすすめのお役立ち資料

