EcoVadis(エコバディス)の活用法 | サプライチェーンの持続可能性を評価する方法
の活用法-サプライチェーンの持続可能性を評価する方法.jpg)
サプライチェーンの“見える化”が世界的に求められる今、「取引先を選ぶ力」こそが企業競争力を左右する時代になりました。
そんな中、世界185か国・15万社以上が採用する国際評価プラットフォームがエコバディス(EcoVadis)です。
2007年にフランスで創業し、日本でも2019年に上陸。
リコーや三井化学などの大手企業が次々と導入し、グローバル調達の新しい常識となりつつあります。
エコバディスの特徴は、CDPやTCFDが投資家向けの開示であるのに対し、サプライヤー(仕入先)とバイヤー(買い手)を直接つなぐ「実務型のサステナビリティ評価」であることです。
評価は「環境」「労働と人権」「倫理」「持続可能な調達」の4分野に基づき、スコアとメダルで明確に可視化。
さらに、改善のための具体的なアクションプランも提示されます。
欧州型の調達では、従来のQCD(品質・コスト・納期)にS=サステナビリティを加えることが当たり前に。
エコバディスのスコアは、取引機会の拡大やブランド信頼の向上に直結し、サステナブル経営の“証明書”ともいえる存在です。
この記事では、エコバディスの仕組みと評価の流れ、そして企業が得られる実務的メリットをわかりやすく解説します。

EcoVadis(以下 エコバディス)とは
サプライヤー(仕入先)の「持続可能なサプライチェーン管理」を評価する会社で、2007年にフランスで創業。
本社をパリに構えながら、現在はアメリカ、ドイツ、オーストラリアなど11カ国に拠点があります。
日本もエコバディス・ジャパン株式会社(東京都千代田区)として2019年にオープンしています。
エコバディスの採用実績
グローバルなサプライチェーンにおけるリスク管理や透明性の確保が重視される中、エコバディスの活用はますます広がりを見せています。
2025年4月時点で、同社の評価を受けた企業数は世界185か国・250業種以上、累計15万社を突破。サステナビリティ評価の世界標準としての地位を確立しつつあります。
特に注目すべきは、その利用が大企業にとどまらず、中小企業にも広がっている点です。
サプライヤー企業の多くが評価を受けることで、自社の取り組みを国際的に証明し、持続可能な取引機会を得ています。
日本国内でも、エコバディスの導入は着実に進んでいます。
例えば、リコーは2025年3月に初のプラチナ評価を獲得し、世界の上位1%の企業として選ばれました。
また、データセンター運営のアット東京も2年連続で最高評価を取得するなど、インフラ分野でも活用が進んでいます。
さらに、海外企業の日本法人による評価取得も見られ、ベトナムのIT大手FPTは2025年3月、日本を拠点とした活動を通じてシルバーレベルの評価を達成しました。
こうした事例は、エコバディスの評価が単なるCSR指標にとどまらず、実際のビジネス価値や競争力に直結する指標であることを示しています。
今後、取引先の選定やサプライチェーン全体の戦略設計において、エコバディスの評価が重要な判断材料となる流れはさらに加速するでしょう。
なぜエコバディスを活用するのか
なぜ、いま多くの企業がエコバディスを導入しているのでしょうか。
その理由は、サプライチェーン全体の信頼性と透明性を高める唯一の評価基盤として注目されているからです。
CDPやTCFDなどの国際イニシアチブが投資家向けの情報開示を目的としているのに対し、エコバディスは「企業間」――つまりサプライヤー(仕入先)からバイヤー(買い手)に向けた実務的な開示を行います。
評価の焦点は、製品の品質や価格だけでなく、環境・人権・倫理といった持続可能性の分野にも広がっています。

たとえば、GHG(温室効果ガス)排出削減や森林保全、児童労働の禁止など、国際的に求められる基準を体系的に管理できるのがエコバディスの強みです。
こうした枠組みを通じて、資源の持続可能な調達やエシカルなビジネス慣行を推進し、リスク低減と信頼性向上を同時に実現します。

また、バイヤー企業にとっては、サプライヤーをESGの観点から効率的に比較・評価できる点が大きなメリットです。
一方のサプライヤー側も、バイヤーごとに重複回答する手間を省きながら、国際基準に沿った自社の強みをアピールできるという利点があります。
さらに、エコバディスは評価後に改善提案を提示してくれるため、企業は世界標準に近づくための具体的なステップを学ぶことができます。

このように、双方にとって効率的かつ有益な仕組みであることから、エコバディスの導入企業は年々増加。
今や、「持続可能なサプライチェーン構築の出発点」として、グローバル企業を中心に広く採用が進んでいます。
欧州型(未来型)の調達プロセスはQCD + S
いま、グローバル調達の常識は「QCD」から「QCD+S」へと進化しています。
従来のQCD――品質(Quality)・コスト(Cost)・納期(Delivery)に加えて、サステナビリティ(Sustainability)が新たな競争軸として組み込まれているのです。
これは単なる流行ではなく、欧州を中心に定着しつつある“未来型の調達モデル”といえます。
ここでのサステナビリティとは、単に環境配慮にとどまりません。責任ある調達、CSR調達、持続可能なサプライチェーン管理といった広い概念を含み、企業活動全体に社会的責任を組み込むことを目的としています。

具体的には、
製品やサービスの品質面では信頼性・耐久性の向上を図りつつ、製造や物流における環境負荷の削減を重視します。
コスト面では、短期的な価格だけでなく、廃棄や再利用まで含めたライフサイクルコストの最適化を重視する姿勢へと変化しています。
納期の観点では、地政学リスクや環境規制が厳しい地域に対応できる柔軟なサプライチェーン構築が鍵となります。
そしてS(サステナビリティ)では、調達先企業の環境対策や労働条件、地域社会への貢献までを評価対象とし、企業全体の環境目標達成に寄与する仕組みが整えられています。
つまり欧州型の調達は、「安く・早く・良い」から「責任をもって持続可能に」へと価値軸がシフトした形です。
環境と経済の両立を実現し、企業の信頼性を高めるこのQCD+Sの考え方こそ、次世代の調達戦略の基盤になりつつあります。
バイヤー(買い手)がサプライヤー(仕入先)に評価を依頼するメリット
リスクを見える化し、持続可能な調達体制を構築できる
エコバディスを通じてサプライヤーに評価を依頼する最大のメリットは、サプライチェーン全体のリスクを早期に把握・管理できる点にあります。
近年は環境問題、労働人権の侵害、法規制違反など、サプライヤー由来のリスクが企業価値を揺るがすケースが増加しています。
エコバディスは、世界共通の評価基準で各サプライヤーの環境・社会・倫理的取り組みをスコア化するため、どの取引先がリスクを抱えているのか」を一目で把握できます。
これにより、リスクの高い取引先を早期に特定し、安定した調達体制を確保することが可能です。
さらに、評価結果は企業のサステナビリティ目標の進捗確認にも活用できます。多くの企業が掲げるカーボンニュートラルや責任ある調達の実現は、サプライチェーン全体の協働が不可欠です。
エコバディスは、その目標達成に向けた「行動指針」として、効率的かつ戦略的な調達判断を支えます。

透明性と信頼性を高め、企業価値を向上させる
もう一つの大きなメリットは、サプライチェーンの透明性と信頼性の向上です。
バイヤーが評価を依頼することで、サプライヤーの環境・社会的取り組みが可視化され、取引の透明性が飛躍的に高まります。
これは特に、多国籍企業など複数拠点を抱えるバイヤーにとって欠かせない仕組みです。
エコバディスのスコアカードを活用すれば、複数のサプライヤーを同一基準で比較でき、より信頼できるパートナー選定が容易になります。
さらに、評価を共有することでサプライヤーとの信頼関係が強化され、長期的な協働や新規ビジネス創出にもつながります。
また、レピュテーションリスク(評判リスク)の軽減にも直結します。
不適切なサプライヤーの行動がブランド価値を損なう前に、評価結果をもとに早期対応を取ることが可能です。
結果として、企業は責任あるリーダーとしての地位を確立し、投資家・顧客・従業員からの信頼を一層高めることができます。
サプライヤー(仕入先)が評価を受けるメリット
リスクを可視化し、強固なサプライチェーンを構築できる
エコバディスを活用してサプライヤーに評価を依頼することは、単なる情報収集ではなく、リスク管理と持続可能な調達戦略の中核を担う取り組みです。
近年は、環境破壊・人権侵害・法規制違反といった問題が、取引先を通じて企業全体の信用や業績に影響を及ぼすケースが増えています。
こうした背景のもと、バイヤーにとって最も大きなメリットは、サプライチェーン全体のリスクを早期に把握し、管理できる点にあります。
エコバディスは、環境・労働と人権・倫理・持続可能な調達の4分野を基準に、各サプライヤーの取り組みをスコア化。
これにより、リスクの高い取引先を定量的に把握でき、安定的かつ透明性の高い調達体制を確立できます。
また、評価結果を活用することで、バイヤーは自社のカーボンニュートラルやESG目標の達成度を可視化でき、全体のサステナビリティ戦略を効率的に推進することが可能になります。

透明性と信頼性を高め、企業価値を向上させる
もう一つの大きなメリットは、サプライチェーンの透明性と信頼性を高められることです。
バイヤーがエコバディスを通じて評価を依頼すると、サプライヤーの環境・社会・倫理的取り組みが明確に可視化され、取引の信頼性が格段に向上します。
特に、複数の国や地域で事業を展開するグローバル企業にとっては、統一基準で比較できる信頼性の高いデータを得られる点が大きな強みです。
さらに、評価結果をもとに改善提案を共有することで、サプライヤーとの関係が深化し、長期的な協働や新しいビジネス機会の創出にもつながります。
加えて、早期の課題発見によってレピュテーションリスク(企業評判の損失)を未然に防ぐことができ、ブランド価値の保全にも寄与します。
エコバディスのスコアは業界内のベンチマークとしても機能するため、競合他社との比較や社内改善にも活用可能です。
結果として、バイヤー企業はリスクの低減と信頼の最大化を同時に実現し、サステナブルな調達を推進するリーダーとして市場での競争優位性を確立できるのです。
評価方法(採点の流れ)
サプライヤー(仕入先)はエコバディスが用意した質問票に回答します。質問は21のサステナビリティ基準を「環境」「労働と人権」「倫理(コンプライアンス)」「持続可能な調達」の4項目に分けています。
企業の規模、ロケーション、業種に関する重要な問題について、カスタマイズした質問票を作成しており、その内容は200人以上のサステナビリティ・アナリストが検証しています。
回答結果はスコアカード(プラットフォームからアクセス)にまとめられ、0から100のスコアと、該当するメダル(プラチナ/ゴールド/シルバー/ブロンズ)が記載されます。
※エコバディス:スコアカードサンプル

さらにスコアカードには、強みと改善点に関するガイダンスも示されています。
評価を受けた企業はこのスコアカードを活用してサステナビリティに関する取り組みに注力し、是正措置計画を策定してCSRパフォーマンスを改善することができます。
評価だけでなく、具体的な改善提案があるという点は特徴の1つと言えます。

エコバディスメダル

プラチナ – 上位1%(総合得点が81点以上)
日本企業:株式会社ブレインファーム(3年連続)、株式会社アット東京、株式会社リコー

ゴールド – 上位5%(総合得点が73点以上)
日本企業:三井化学株式会社、三好化成グループ、TDK株式会社

シルバー – 上位15%(総合得点が66点以上)
日本企業:株式会社GARDE、株式会社日経BPコンサルティング、株式会社トキワ

ブロンズ – 上位35%(総合得点が58点以上)
日本企業:飯野海運株式会社、住友重機械工業株式会社、株式会社東洋ゴムチップ
昨年までブロンズメダルは、上位50%の企業に付与されていましたが、2024年の基準変更により現在は上位35%の企業に付与されるようになりました。
メダル獲得の門戸が年々厳しくなっていっており、メダルを獲得するだけでも評価は得られ、さらにシルバー以上の認定を受けている企業は非常に希少になっています。
※総合得点については、随時変更されていますので正式なものは最新情報をエコバディスにお問い合わせください。
エコバディスのサポート
エコバディスの主なコミットメントは以下のとおりです。
・ビジネスパートナーのサステナビリティパフォーマンスに関して、現在進行中のモニタリングのために、拡張可能なクラウドベースのプラットフォームを提供
・ビジネスパートナーの統合やオンボーディングのプロセスを管理
・ビジネスパートナーのサステナビリティ慣行に関する明確で信頼できるデータを提供
・評価プロセス中は、エコバディス内部の多言語に対応したサポートチームがビジネスパートナーをサポート
・担当のアカウントマネージャーを任命し、Enterpriseプランのクライアントの管理に併せて四半期ごとの運営委員会をセットアップ
2019年に東京に設立されたエコバディスの日本オフィスでは、主に日本企業のサステナビリティ評価や、サプライチェーンにおけるサステナビリティリスクの管理をサポートしています。
日本企業のエコバディス事例一覧
サプライヤー、バイヤーのそれぞれのページに取り組みにのきっかけや申請時の大変さ、具体的なメリット、社内での取り組みなどがまとめられています。
サプライヤーの事例一覧については、以下で、
▼参考:ecovadis 評価受審企業のお客様
バイヤーの事例一覧については、以下で
▼参考:ecovadis 評価依頼企業のお客様
それぞれ、確認できます。
事例が掲載されている以外のエコバディス評価受信、評価依頼企業については、
自社から積極的に発信されているケースが多いので、プレリリースなどで確認することができます。
サプライヤー(仕入先)が評価を受ける手順
1) 登録
登録プロセスでは、法人名、ロケーション、企業規模、業種を含む、自社の基本情報を提供します。
登録先の会社向けにカスタマイズした質問票を作成するために重要な情報となります。
エコバディスの評価依頼を受けた場合は、評価依頼メールのリンクをクリックして登録を行います。
これにより、評価を依頼した企業は貴社の最新の進捗状況を把握できます。
また、貴社の評価が完了すると評価結果が評価を依頼した企業に自動的に共有されます。
2) 質問票
登録メールから登録を完了すると、お客様のユーザー名が記載された自動通知メールが届きます。
このメールにあるリンクをクリックすると、エコバディスのプラットフォームにアクセスするためのパスワードを作成できます。
プラットフォーム上で、貴社のCSR質問票への回答を開始できます。

– 登録プランと料金
質問票に回答した後、ご希望の登録プランを選択し、お支払い情報を入力して分析のために質問票と証明書類を送信します。
料金を含む、利用可能な登録プランの詳細については、EcoVadis 価格とプランを参照してください。
3) 専門家による分析
質問票と証明書類を送信すると、エコバディスのCSRアナリストが貴社の回答と証明書類の評価を行います。
専門家による分析は6~8週間かかることがあります。
エコバディスの評価手法は、グローバル・レポーティング・イニシアチブ(GRI)インデックス、ISO 26000、国連グローバル・コンパクトの指導原則をはじめとした、国際規格に基づいています。
4) 結果
貴社のスコアカードが公開されると、通知メールが届きます。スコアカードはエコバディスのプラットフォームからアクセスできます。
取引先から評価依頼を受けた場合、貴社のスコアカードは取引先にも共有されます。
スコアカードの有効期限は発行日から12か月間で、PremiumまたはCorporateプランの場合は、エコバディスのプラットフォーム外の関係者とスコアカードを共有することができます。
エコバディスのスコアを向上させるためには
エコバディスのスコアを向上させるためのポイントは、以下の4つの評価分野における具体的な取り組みを強化することです。
・環境
温室効果ガス(GHG)排出削減計画を策定し、再生可能エネルギーの利用を拡大する。
省エネ対策や廃棄物管理の効率化に取り組む。

・労働と人権
労働者の健康と安全を確保し、平等な労働条件を提供する。
労働者の権利保護のためのポリシーを文書化し、適切に運用する。
▼参考:経済産業省:責任あるサプライチェーンおける人権尊重のためのガイドライン
・倫理
贈収賄防止、コンプライアンスの徹底を図り、透明なビジネス慣行を実施する。
倫理的な行動規範を策定し、内部監査を強化する。

・持続可能な調達:
サプライヤーにもサステナビリティ基準を求め、持続可能な資材調達を実施する。
サプライチェーン全体で環境・社会リスクを管理し、透明性を高める。
さらに、改善点に対して積極的に対応し、定期的に評価を受けることでスコアの向上が期待されます。
また、EcoVadisが提供するeラーニングやウェビナーを活用し、社内のサステナビリティ理解を深めることも重要です。
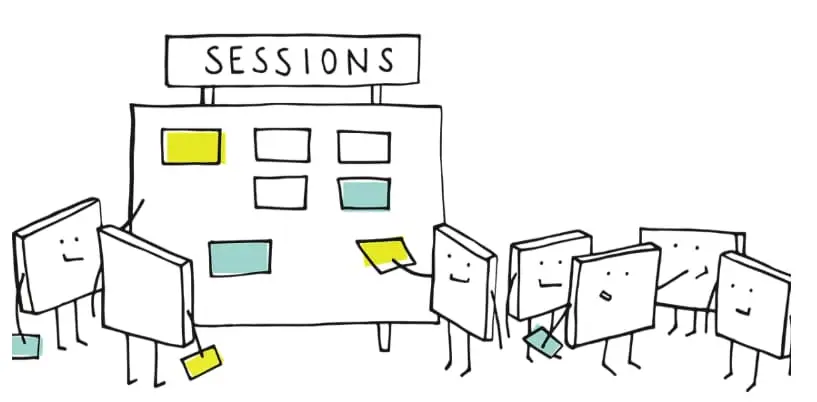

まとめ
・エコバディスとは、サプライヤー(仕入先)の「持続可能なサプライチェーン管理」を評価している会社のこと
・エコバディスが行う評価はサプライヤー(仕入先)がバイヤー(買い手)に向けて開示するもの
・評価はエコバディスが用意した質問票にサプライヤー(仕入先)が回答する。質問票は21の基準を4項目(環境、労働と人権、倫理(コンプライアンス)、持続可能な調達)に分けて用意。特徴的なのは業界ごとに質問票の内容(4項目の比重)が変わっているという点。
・評価はスコアとメダルで可視化し、評価だけでなく具体的な改善施策までフィードバックしてくれる。
国際イニシアチブは機関投資家向けの開示になるため、企業単位のサステナビリティ評価や投資・融資を受ける際に向いてます。
一方、エコバディスはサプライヤー(仕入先)がバイヤー(買い手)に向けた「持続可能なサプライチェーン管理」の評価となるため、新しい取引先とマッチングする可能性もあると思います。
エコバディスの方がより事業的なメリットがありそうという捉え方もできるため、今後利用する企業は更に増えていくのではないでしょうか。
▼出典:
エコバディスHP サステナビリティ評価 https://ecovadis.com/ja/suppliers/
エコバディスヘルプセンター https://support.ecovadis.com/hc/ja


