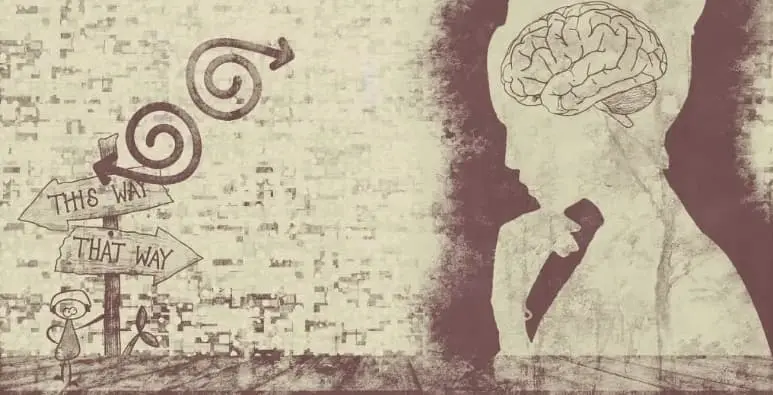scopex-admin– Author –
-

IT業界の省エネ化と脱炭素 | 期待される役割と取り組み
IT業界はデジタルテクノロジーの進化によって社会を大きく変えてきました。 製造業のように工場で燃料を使うわけではなく、テレワークも浸透しやすいため、表面的には温室効果ガスの排出が少ない業界だと考える人も少なくありません。通勤による排出が削減... -

カーボンプライシングとは?メリットとデメリット:企業が知っておくべきポイント
気候変動対策が世界的に加速する中で、「カーボンプライシング」が注目を集めています。これは、温室効果ガス(GHG)の排出にコストをかけることで、企業や個人が排出削減に取り組むインセンティブを作り出す仕組みです。 すでに多くの国が導入しており、... -

CO2以外の温室効果ガスの種類とその特性について
地球温暖化の要因として知られる温室効果ガスは、二酸化炭素(CO₂)をはじめ、メタン(CH₄)、一酸化二窒素(N₂O)、HFC、PFC、SF₆、NF₃など多岐にわたります。 本来、これらのガスは地球を適温に保つ役割を担いますが、人為的な排出の増加により、そのバ... -

EcoVadis(エコバディス)の活用法 | サプライチェーンの持続可能性を評価する方法
持続可能な社会の実現が企業に求められる今、取引先の環境・社会リスクを可視化し、サプライチェーン全体の信頼性を高める取り組みが急速に進んでいます。そうした中で、世界175か国・10万社以上が活用するサステナビリティ評価プラットフォーム「エコバデ... -

企業が温室効果ガス削減目標を設定する際の重要なポイント
気候変動への対応が企業経営にとって避けては通れない時代となり、温室効果ガス(GHG)削減の数値目標を明確に設定することは、単なるCSRではなく経営戦略の中核を担う行為へと変わりつつあります。 国際的にはパリ協定やSBT(Science Based Targets)など... -

脱炭素経営の始め方完全ガイド|短期・中期・長期の戦略と実行ロードマップ
気候変動対策が企業経営の重要課題となる中、脱炭素経営はもはや選択肢ではなく、事業の持続可能性を左右する要素となっています。 環境規制の強化、投資家や取引先の要請、競合企業の動向など、さまざまな要因が企業に脱炭素化を求めています。この流れに... -

経営戦略に活かす!脱炭素のための正しい情報収集と活用のポイント
脱炭素経営は、企業の持続可能性や競争力を高めるうえで不可欠な戦略となっています。しかし、近年の情報量の急増により、どの情報を収集し、どのように活用すればよいのか迷うケースも少なくありません。 本記事では、脱炭素経営を進めるうえで必須となる... -

脱炭素経営推進、サステナビリティインセンティブ導入のメリット
CDPの回答を行なうにあたって、初期に躓く回答に『気候関連問題の管理のために提供されるインセンティブの詳細について』という回答を挙げられる方は多いのではないかと思います。 弊社では、社長を始めとした経営幹部に気候関連プロジェクトを含む持続可... -

環境問題に関心がある人必見!身近な脱炭素アクションで始める持続可能な生活
異常気象の増加、猛暑の常態化、そして海洋プラスチックごみの拡大——こうした環境問題は、もはや遠い未来の話ではなく、私たちの生活に直接影響を与える「今そこにある課題」です。 例えば、エアコン使用による電力消費の増加や、食品価格の高騰、大気汚染... -

カーボンクレジットとは?その種類と違い:どれを選べばいいのか?
2024年10月11日に市場開設1周年を迎えた東京証券取引所カーボン・クレジット市場ですが、徐々に参加者数や累積売買高が増えてきています。 そういった流れを受けて ・そもそもカーボンクレジットとは? ・カーボンクレジットと再エネ証書との違いは? ・カ... -

脱炭素経営に向けたサステナビリティ委員会の設立ガイド
近年、サステナビリティ経営の重要性が高まる中で、日本企業におけるサステナビリティ委員会の設置が加速しています。かつてはCSR(企業の社会的責任)活動の一環として捉えられることが多かった持続可能性の取り組みですが、現在では企業の中核戦略に直結... -

【グローバル比較】主要国の脱炭素戦略と企業の対応ポイントを解説
気候変動の影響が年々深刻化する中で、脱炭素はもはや環境政策にとどまらず、企業や国家の競争力を左右する“経済戦略”へと進化しています。 欧州、米国、中国など主要国は、法規制・投資・技術を組み合わせた独自のアプローチで脱炭素化を推進しており、日...



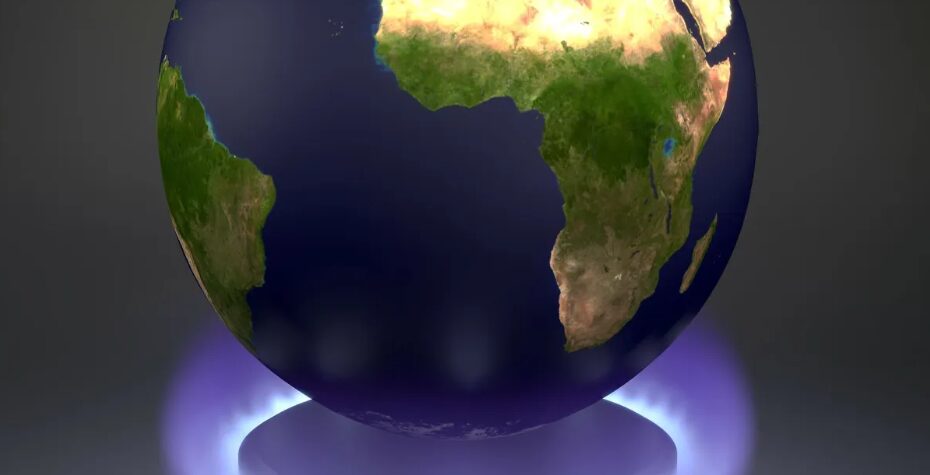
の活用法-サプライチェーンの持続可能性を評価する方法.jpg)