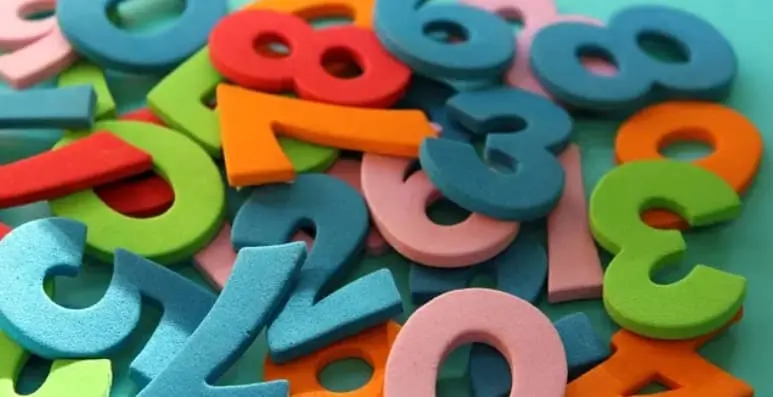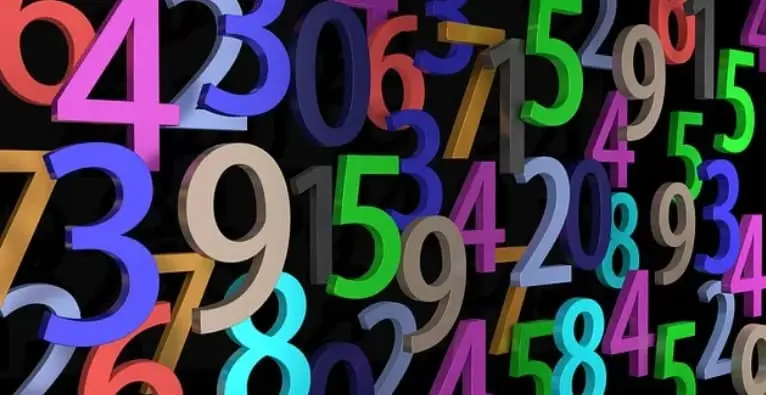Scope3カテゴリ1-購入した商品やサービスの温室効果ガス算定について具体的に解説

企業が気候変動対策を進める上で、Scope 3カテゴリ1(購入した製品・サービスの排出量) の管理は極めて重要です。
これは、企業が外部から調達する原材料や部品、外部委託したサービスに伴う排出量を指し、多くの企業にとってサプライチェーン全体の排出量の中で最も大きな割合を占めることが一般的です。
カテゴリ1の排出削減には、持続可能な調達基準の策定 や サプライヤーとの連携強化、データ活用による可視化、イノベーションの導入 など、多面的なアプローチが求められます。
世界的に見ても、消費者が環境負荷の少ない製品を選択しやすくする取り組みが進んでおり、企業はこうした変化に適応しながら競争力を高める必要があります。
本記事では、カテゴリ1の算定方法や具体的な削減施策、導入事例を詳しく解説し、企業が効果的な環境戦略を構築するための実践的なアプローチを紹介します。
事前に、こちらの記事を見ていただくと内容を理解しやすくなります。

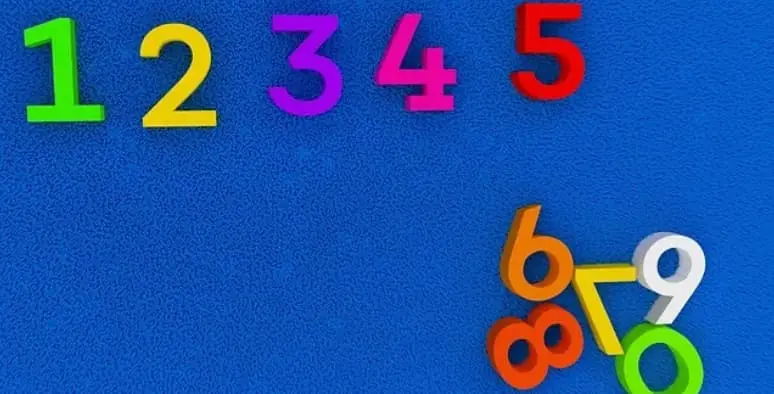

Scope3 カテゴリ1の概要
Scope 3のカテゴリ1(購入した製品・サービス)は、サプライチェーンにおける企業の間接的な排出量のうち、上流で発生する排出量に該当します。
具体的には、企業が外部から調達するすべての原材料、部品、容器、包装、機械、IT機器などの製品に関連する温室効果ガス(GHG)排出量が含まれます。
企業が製品を生産するために調達する原材料(例:金属、鉱石、樹脂、化学薬品など)や部品は、その製造段階で大きなエネルギーを消費することが多く、温室効果ガス排出量も非常に高くなる可能性があります。
製造工程における使用エネルギーの種類(化石燃料や再生可能エネルギーなど)や生産国のエネルギー効率が、Scope 3カテゴリ1の排出量に大きな影響を与えます。
サービスもScope 3カテゴリ1に含まれます。
たとえば、ソフトウェアやIT、法律、会計、マーケティングなどの専門的なサービス、外部のコンサルティング、メンテナンスサービスなどを利用する場合、そのサービスを提供する企業が使用するオフィスの電力消費や移動に伴う排出量なども含まれます。
このように、目に見えないサプライチェーン上の排出量をすべて含むことが重要です。
購入する原材料や部品の生産時の温室効果ガスの排出
例)
素材会社:鉱石、樹脂、荷造包装費、水道代
食品会社:小麦粉、麦芽、砂糖、コーンスターチ
物流会社:段ボール、ユニフォーム、タイヤ
農業法人:苗、肥料、農業用具
小売会社:野菜、食肉、魚介類、スナック菓子
建設会社:建具、壁紙、コンクリート、ガラス
など会社によって様々です。
・アウトソーシングしたサービス利用で生じる排出
(例:コンサルティング、法務関係のサービス、業務委託費、研究開発費)
▼おすすめのお役立ち資料

Scope3 カテゴリ1における1次データと2次データ
カテゴリ1における算定における算定係数には1次データと2次データという考えがあります。
1次データについて
一次データとは、企業がサプライヤーなどの取引先から直接取得する、特定の製品やサービスに関連する具体的な活動量や温室効果ガス(GHG)排出量の情報を指します。
例えば、企業が調達する製品の製造過程で使用された電力や燃料の量、排出されたGHGの量などを、製造元から直接入手するケースが該当します。
これらのデータは、サプライチェーン全体の排出量を正確に算定し、実効的な削減対策を講じる上で不可欠です。
2025年3月に環境省が公表した『一次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド(Ver1.0)』では、一次データの活用が強調されています。
同ガイドによれば、一次データの活用により、サプライヤーの排出削減努力を自社のScope3排出量算定に反映させることが可能となり、サプライチェーン全体での脱炭素化を促進できるとされています。
一次データの活用が重要視される背景には、従来の二次データ(業界平均値など)を用いた算定方法の限界があります。
二次データでは、サプライヤー個別の排出削減努力が反映されず、調達量の削減以外の方法で排出量を減らすことが困難でした。
一次データを活用することで、サプライヤーの具体的な削減活動を評価し、より精緻な排出量算定が可能となります。

2次データについて
一方で、2次データは、企業が直接収集したデータではなく、一般的なデータベースや公開された文献、産業平均などの統計データから取得されるものです。
これには、政府機関やNGOが提供する排出係数や、ライフサイクルアセスメント(LCA)データベースなどの情報が含まれます。
日本の企業が良く使っているデータベースは、環境省がとりまとめている産業連関表ベースの排出原単位や日本の環境影響評価やライフサイクルアセスメント(LCA)において使用される、国産のライフサイクルインベントリ(LCI)データベースであるIDEAなどがあります。


▼出典:グリーン・バリューチェーンプラットフォーム排出原単位データベース
現状は、2次データベースで算定を行っている企業が多い中、徐々に1次データを取得している企業も増えています。
全てが1次データであることが理想ではありますが、全てのサプライヤーに一次データを求めることは非常に困難なため上位サプライヤーは一次データにて算定、それ以外は2次データで算定というハイブリッドな状況を目指していく流れになっています。
は何を使う?データベースの選び方と活用事例.jpg)
Scope3 カテゴリ1の算定方法(2次データを活用)
カテゴリ1の排出量を計算するには、購入した商品やサービスに関連する情報が必要で、原材料の重量や、製品の購入量や購入金額を用いて算定していきます。
以下は産業連関表の重量ベースと金額ベースの原単位を使った算定の時に使う原単位になります。
産業連関表ベースの排出原単位を使う場合
肉加工品ですと
1t購入すると:9.858t-CO₂e排出 百万円購入すると:5.381t-CO₂e排出
セメントですと
1t購入すると:0.758t-CO₂e排出 百万円購入すると:101.602t-CO₂e排出
段ボールですと
1千m2購入すると:0.382t-CO₂e排出 百万円購入すると:6.316t-CO₂e排出
化学肥料ですと、
1t購入すると:0.719t-CO₂e排出 百万円購入すると:13.084t-CO₂e排出
肉加工品ですと、
1t購入すると:9.598t-CO₂e排出 百万円購入すると:5.381t-CO₂e排出
生コンクリートですと
1m3購入すると:0.316t-CO₂e排出 百万円購入すると:19.530t-CO₂e排出
法務・財務・会計サービスですと
百万円購入すると:0.640t-CO₂e排出
基本的には多くの企業は、購入者価格ベース(消費者が購入する段階での流通コストを含んだ価格。算定事業者が商社/小売等を介して購入する場合に使用する)の原単位を使うケースが多いと思われます。
ですが、生産者価格ベース(生産者が出荷する段階での販売価格。算定事業者が生産者から直接購入する場合に使用する。)にしかない以下のような係数もあるので注意が必要です。
一般飲食店(除喫茶店) ですと
百万円利用すると:3.30t-CO₂e排出
喫茶店ですと
百万円利用すると:3.19t-CO₂e排出
上記のような、接待交際費や会議費で使うような原単位はかなり粒度を細かく設定している場合くらいでしか活用しないので、基本的にはあまり使われないです。
▼出典:環境省HP排出原単位データベース Ver.3.5(EXCEL/6.72MB)<2025年3月リリース>
上記のように様々な製品、サービス毎に原単位が存在しており活用されていますが、特定の商品やサービスに関する詳細な排出係数がない場合もあるため、近似値を使用する必要がある場面もあります。
Scope3 カテゴリ1の削減施策
Scope 3カテゴリ1「購入した製品・サービス」の削減は、企業がサプライチェーン全体の環境負荷を軽減し、温室効果ガス(GHG)排出量を削減する上で不可欠な取り組みです。
このカテゴリは、企業が調達する原材料や部品、外部サービスの生産段階で発生する排出量を対象としており、多くの業界でScope 3排出全体の中で最大の割合を占めることが一般的です。
削減の実現には、サプライヤーとの連携や技術革新、持続可能な調達方針の策定など、包括的なアプローチが求められます。
カテゴリ1削減の背景と重要性
排出量の特性と削減の必要性
Scope 3のカテゴリ1(購入した製品・サービスに伴う排出)は、企業のサプライチェーン全体で発生するため、直接的な管理が難しい領域です。
しかし、製造プロセスや原材料調達、物流などにおける排出量は企業の温室効果ガス(GHG)排出全体の大部分を占めるケースが多く、削減への取り組みが企業全体の環境負荷低減に大きく貢献します。
グローバルな規制と企業の責任
国際的な気候変動対策(例:パリ協定)やESG投資の拡大により、企業にはサプライチェーン全体での環境負荷軽減が求められています。
投資家や消費者は、持続可能な調達・製造を行う企業を重視しており、企業の社会的責任(CSR)を示す重要な要素となっています。

競争力向上の機会
カテゴリ1の排出削減は、企業のブランド価値向上と市場競争力の強化につながります。
環境負荷低減に取り組むことで、サステナブルな企業としての評価を得られるだけでなく、調達・生産プロセスの最適化によりコスト削減も実現できます。
削減の具体的なアプローチ
1. 持続可能な調達戦略の構築
企業は、調達する製品やサービスの環境負荷を削減するため、持続可能な調達基準を明確に策定する必要があります。
- 再生可能またはリサイクル素材の使用
原材料調達において、再生可能資源やリサイクル素材を優先的に採用することで、生産段階での排出量を大幅に削減できます。
- 環境認証製品の選定
FSC(森林認証)やISO14001などの認証を取得した製品を調達基準に組み込むことで、サプライチェーン全体の環境パフォーマンスを向上させます。
- ローカル調達の推進
地域内での原材料調達や生産を優先することで、輸送に伴う排出量を削減します。


2. サプライヤーとの連携強化
Scope 3カテゴリ1の削減には、サプライヤーとの協力が不可欠です。
単独での取り組みではなく、サプライチェーン全体を巻き込むことが成功の鍵です。
- トレーニングと支援
サプライヤーに対し、環境負荷削減のための具体的な方法を教える研修を提供し、能力向上を支援します。
- 環境基準の導入
サプライヤー選定の際に、環境パフォーマンスを評価基準に組み込み、持続可能な製造プロセスを推進します。
- インセンティブの提供
サプライヤーが低炭素技術や再生可能エネルギーを導入する際に、資金援助や契約の優遇を提供することで排出削減を促します。
3. 製品設計の最適化
製品の設計段階で環境負荷を低減する取り組みを進めることも効果的です。
- 軽量化と資源効率の向上
製品設計を見直し、原材料の使用量を削減することで、製造プロセス全体の排出量を減らします。
- ライフサイクル設計
耐久性やリサイクル可能性を向上させる設計を採用することで、廃棄物や追加生産による排出を抑えます。
- サプライチェーンの統合
生産段階での無駄を削減し、効率的な工程設計を通じて環境負荷を最小限に抑えます。

4. デジタルツールとデータ活用
デジタル技術を活用して、サプライチェーン全体の排出量をモニタリングし、削減計画を最適化します。
- データ収集と可視化
カーボンフットプリント計算ツールを使用し、各サプライヤーや製品ラインの排出量を測定します。
- データ共有プラットフォーム
サプライチェーン全体で環境データを共有し、透明性を確保することで、共同で削減を進めます。
- 予測モデルの活用
データ分析に基づき、削減効果をシミュレーションし、最も効果的な戦略を選定します。
5. イノベーションによる削減
新しい技術やプロセスを導入することで、カテゴリ1の排出量削減を加速します。
- 低炭素技術の採用
再生可能エネルギーや廃熱利用など、低炭素な生産プロセスを採用するサプライヤーを優先します。
- 循環型経済の導入
廃棄物削減やリユース、リサイクルを推進することで、サプライチェーン全体での環境負荷を削減します。

・製品の軽量化やコンパクト化

得られる成果と課題
主な成果
- 環境パフォーマンスの向上
サプライチェーン全体の排出量削減を通じて、企業のカーボンフットプリントが大幅に減少します。
- ブランド価値の向上
持続可能な調達と削減活動は、消費者や投資家からの信頼を高め、企業の競争力を向上させます。
- 効率化によるコスト削減
無駄を省くことで、原材料費やエネルギーコストの削減が実現します。
主な課題
- データ収集の困難さ
サプライチェーンが複雑である場合、正確な排出量データを収集するのが難しい。
- サプライヤー間の差異
サプライヤーの規模や技術力にばらつきがあるため、全体で均一な削減努力を行うのが難しい。
- コスト負担
技術導入やプロジェクト実施には初期投資が必要であり、中小企業では負担が大きい場合があります。
▼参考:石井食品HP 石井食品とTBM、環境配慮素材LIMEX を使用した世界初の食品包材用シーラントフィルムを開発

まとめ
カテゴリ1の排出に関する情報を公開し、その削減の取り組みを進めている企業は年々増えています。
世界を見るとイギリスなどでは、飲食店に行くとコーヒーやハンバーガーなどの一般的なメニュー表に、この食品は完成までにこれくらい温室効果ガスが出ているというのが記入されており、なるべく排出量の少ない製品を気軽に選べる世界が実現しています。
日本でも近い将来そういった世界が実現するかもしれません。