Scope3の算定はなぜ必要?投資家・取引先が求める理由と企業の対応策

企業が温室効果ガス(GHG)排出を削減する上で、Scope3の管理は避けて通れない重要な課題となっています。
Scope3とは、企業が直接排出するGHG(Scope1)や購入したエネルギーに伴う間接排出(Scope2)に加え、サプライチェーン全体にわたる間接排出を指します。
特に、多くの企業ではScope3が全排出量の大半を占めることが多く、適切な算定と管理なしに気候変動対策を語ることはできません。
Scope3の排出量を正確に把握することで、どのカテゴリに削減余地があるかを特定し、効率的な削減施策を講じることが可能になります。
また、サステナビリティ経営を推進し、ESG評価の向上を目指す企業にとっても、Scope3の管理は不可欠です。
さらに、SBT(Science Based Targets)認証を取得するためには、Scope3の排出量算定が必須となる場合もあり、企業が持続可能な成長を遂げる上での戦略的な取り組みとして、今後ますます重要性を増していくでしょう。

Scope3とは?
Scope3とは、企業が自ら直接管理できない領域を含め、バリューチェーン全体で発生する温室効果ガス(GHG)の間接排出を包括的に管理するための概念です。
企業の気候変動対策において、Scope3の正確な把握と効果的な削減は、ますます重要な役割を担っています。

温室効果ガスの排出量算定は、国際的に「Scope(スコープ)」という枠組みによって分類されています。
このうち、Scope1は企業が燃料の燃焼や事業活動によって直接排出するGHGを、Scope2は企業が使用する電力や熱などエネルギー生産に伴う間接排出を指します。
一方でScope3は、企業が直接的には排出していないものの、自社の活動が誘発するサプライチェーン上流・下流における間接排出を含むため、より幅広く複雑な管理を求められます。


具体的にScope3は、企業活動の「上流」と「下流」にまたがり、合計15のカテゴリに分類されています。
上流カテゴリには、原材料や資材の調達、外部委託による物流や輸送、従業員の出張や通勤、購入したサービスや設備の利用などが含まれます。
一方で下流カテゴリには、自社製品・サービスを顧客が使用した際の排出、販売した製品の廃棄処理、リースや投資資産の運用に伴う排出などが挙げられます。
特に製造業や消費財企業においては、製品のライフサイクル全体にわたりScope3排出量が企業全体のGHG排出量の大部分を占めるケースが少なくありません。
Scope3を正確に把握・管理するためには、自社単独の取り組みだけではなく、サプライチェーン全体での連携や協働が必要となります。
例えば、自社製品を製造するサプライヤーや輸送事業者との情報共有体制を構築し、定期的なデータ収集や進捗管理を行うことが求められます。
また、顧客が自社製品を使用する際の環境負荷についても、顧客への啓発活動や省エネ製品の開発など、幅広いアプローチでの削減努力が不可欠です。
Scope3の算定方法は、カテゴリごとに特性や実情に応じて適切な手法を選択する必要があります。
データ収集が困難な場合には、産業別の平均的な排出係数や一般的な推計値を活用することも可能ですが、精度の向上を目指すためには、可能な限り自社やサプライヤーから収集した一次データを優先して利用することが望ましいとされています。
は何を使う?データベースの選び方と活用事例.jpg)
最近では、Scope3への取り組み状況が企業価値評価にも大きく影響するようになっています。
投資家やESG格付機関は、企業がScope3排出を適切に把握し、管理・削減できているかを重視し、企業の気候変動リスクに対する対応力を評価する重要な指標として捉えています。
さらに、Scope3の積極的な管理は、リスク軽減だけでなく、競争優位性の獲得や新たなビジネスチャンスの創出につながる可能性もあります。

今後、世界的な規制の強化や社会的関心の高まりを背景に、Scope3の重要性はますます増加すると予測されています。
企業には長期的な視点でScope3排出の管理体制を整備するとともに、デジタルテクノロジーの活用によるデータ収集精度の向上、サプライチェーン全体での協働促進、継続的な改善プロセスの導入といった、具体的かつ戦略的な施策が求められるでしょう。
Scope3への真摯な取り組みは、単なる温室効果ガスの削減にとどまらず、企業の持続可能性を強化し、中長期的な企業価値向上にも直結する重要な経営課題となっています。

▼出典:グリーン・バリューチェーンプラットフォーム Scope3排出量とは
Scope3を算定する理由とその重要性
Scope3排出量の算定が企業に求められる理由は多岐にわたりますが、主に以下の3つのニーズに整理できます。
いずれも企業の持続可能な経営を支える重要な要素であり、戦略的な取り組みが求められています。
①削減対象を特定し、効果的な気候変動対策を進めたい
Scope3の算定が必要になる最大の理由は、企業が実効性のある削減対策を進めるために、削減すべきポイントを明確に特定することです。
企業のバリューチェーン全体で発生する温室効果ガス(GHG)のうち、Scope3排出量が占める割合は非常に大きく、業種によっては全排出量の70〜90%以上を占める場合もあります。
特に製造業においては、原材料の調達(カテゴリ1)や顧客が製品を使用する際の排出(カテゴリ11)が大きな割合を占める傾向があります。


Scope3を算定すると、これらのカテゴリごとの排出量を把握し、どこに最も削減余地があるかを具体的に特定できます。
さらに、算定した排出量に基づき、「削減ポテンシャル」と「実現可能性」の評価が可能になります。
排出量が大きくても削減が難しい分野より、排出量が中規模でも容易に削減できる領域を優先するなど、戦略的な判断が可能になります。
また、規制動向や市場ニーズを予測し、将来的な規制強化が予想される領域に先手を打つことで、リスクを抑えながらビジネスチャンスにもつなげられます。
さらに、削減施策の実施によるコスト削減や新たなビジネス機会の創出といった相乗効果を考慮し、ステークホルダーの期待にも応える形で取り組みを展開できます。
このようにScope3算定は、企業が最適な削減施策を立案し、効率的かつ実効性のある気候変動対策を実現するために不可欠です。

②サステナビリティ経営を方針として明確に打ち出したい
企業がサステナビリティを経営戦略の中心に据える上でも、Scope3算定は極めて重要な役割を果たします。

Scope3の排出量算定により、企業活動が環境に与える影響を包括的に可視化することができます。
これにより、抽象的な理念や目標ではなく、定量的で具体的な環境負荷の削減目標を設定できるようになります。
こうした明確な削減目標を掲げることは、企業のサステナビリティへの取り組みをステークホルダーに対して効果的に発信し、信頼を高めることにもつながります。
また、算定プロセスを通じて、調達、生産、物流、営業など幅広い社内部門や、サプライヤー・顧客とのコミュニケーションが促進されます。
これにより、企業内外でサステナビリティに対する意識が共有され、組織全体の一体的な取り組みへと発展します。
特に、ESG投資が一般化し、投資家や評価機関がScope3の排出量開示を重視するようになっているため、算定・開示は企業の長期的な評価向上にも直結します。
Scope3の管理状況は、企業の気候変動リスクへの対応力を示す指標として、投資判断や企業評価の重要な基準となっているのです。
したがって、Scope3算定は単なる環境施策にとどまらず、サステナビリティ経営を実践する企業としてのブランド価値を高め、競争優位性を構築するための戦略的な取り組みと位置付けられます。
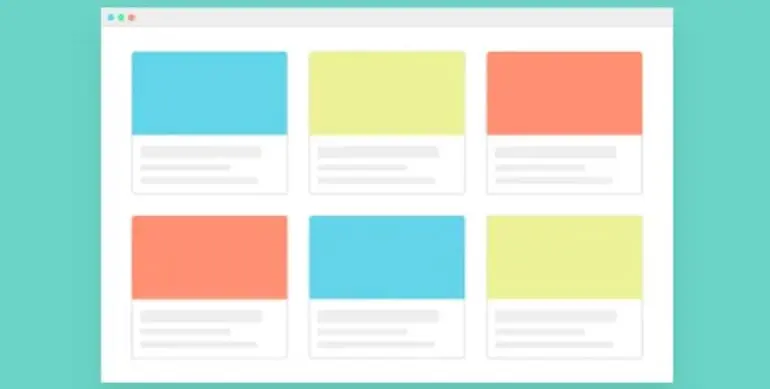
③取引先などからSBT認証を求められるケースに対応したい
近年、多くの企業がSBT(Science Based Targets:科学的根拠に基づく目標設定)の認証取得を取引条件やパートナー選定の条件として求める傾向が強まっています。
このSBT認証を取得するためには、Scope3排出量が全排出量の40%以上を占める場合、Scope3の排出量算定とそれに基づく削減目標の設定が必須となります。
SBT認証を申請する際には、Scope3排出量の全体像を事前に正確に把握し、科学的根拠に基づいた具体的な削減目標を設定することが求められます。
さらに、目標の妥当性や達成可能性を示すために、主要な排出カテゴリにおける削減施策を具体的に提示する必要があります。
また、認証取得後は継続的に進捗状況をモニタリングし、PDCAサイクルを回す体制整備が不可欠となります。
年次でのScope3排出量の計測、削減施策の実行と効果の検証、必要に応じた見直しや改善を繰り返し行うことで、目標達成に向けての取り組みを着実に進めていくことができます。
このプロセスを通じて得られた知見は、単なる認証取得のために終わらせるのではなく、サプライチェーン全体で環境負荷を低減する取り組みへと広げることが可能です。
その結果、企業の競争力強化やステークホルダーからの評価向上にもつながります。

まとめ
Scope3とは、企業が直接管理できないサプライチェーン上の間接的な温室効果ガス排出を含む概念です。
排出量を算定することで、具体的な削減対象を特定でき、効率的かつ戦略的な気候変動対策が可能になります。
また、サステナビリティ経営の推進や企業価値向上にも大きく貢献し、特に投資家からのESG評価に影響を与えます。
さらに、取引先からのSBT認証取得の要請に対応するためにも、Scope3の算定と管理は今後ますます重要性を増していくでしょう。
▼合わせて読みたい記事
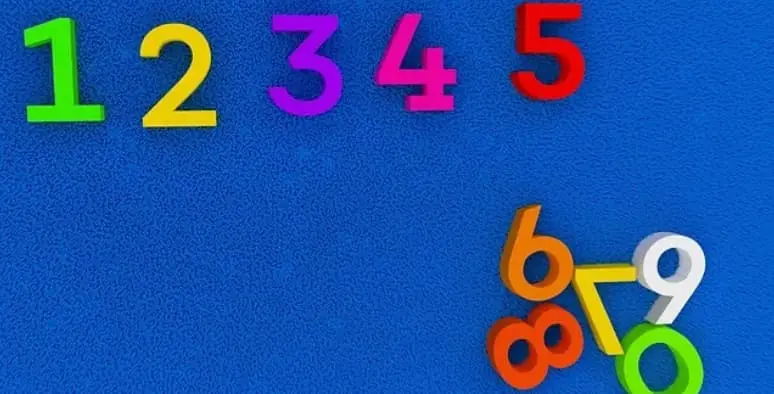
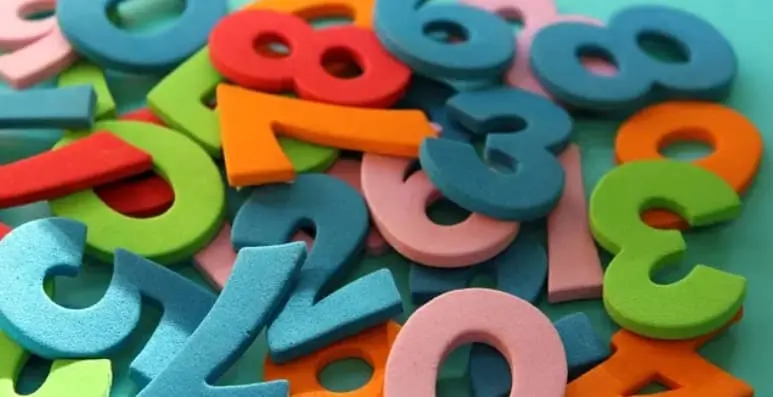
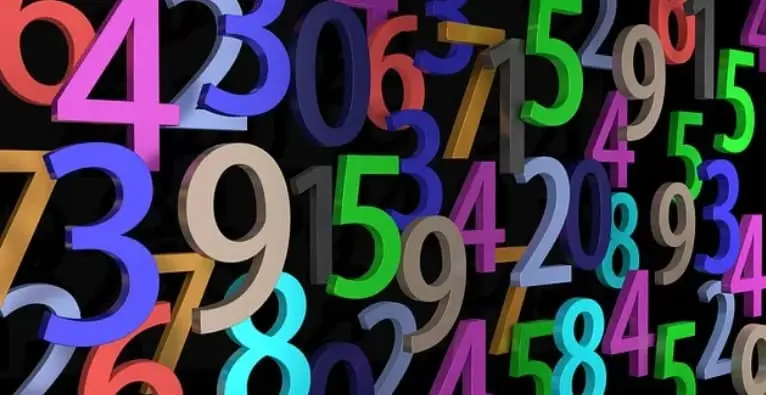
▼おすすめのお役立ち資料

