グローバル標準を目指す日本のCO2削減貢献量(Scope4、カーボンハンドプリント)の考え方

気候変動対策が企業の持続可能性と競争力を左右する現代において、「削減貢献量」は単なる環境指標ではなく、企業価値を高める重要な要素となっています。
削減貢献量とは、企業が取り組む温室効果ガス削減活動によって達成された具体的な排出削減量を指し、透明性のある数値として示すことで、投資家や消費者との信頼関係を強化し、ESG評価の向上にも寄与します。
また、削減貢献量の測定と報告を適切に行うことで、規制対応の強化、コスト削減、イノベーション創出といった経営面でのメリットも生まれます。
日本では、GX戦略の一環として削減貢献量の定量化が推進され、企業による先進的な取り組みが加速しています。
本記事では、削減貢献量の重要性や算定方法、企業事例を通じて、その戦略的活用の可能性を探ります。
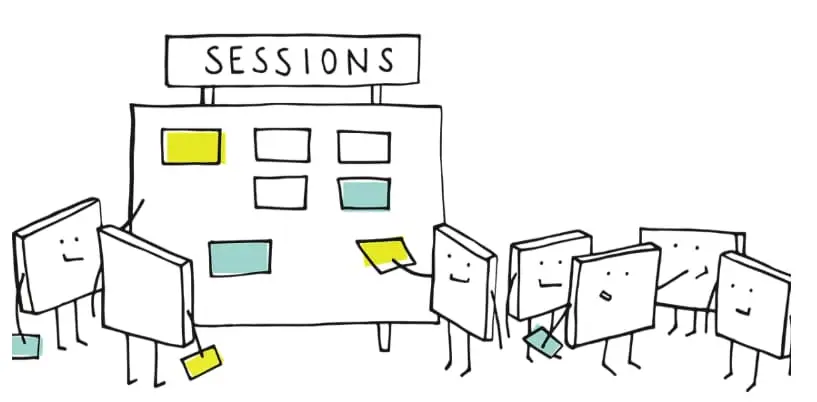

企業における削減貢献量の重要性
削減貢献量とは、企業が実施する温室効果ガス削減活動によって達成される具体的な排出削減量を意味します。
この概念を適切に理解し、活用することは、企業が社会的責任を果たすだけでなく、競争力を高め、新たな価値を創造するための基盤となります。その重要性を多角的に説明します。
まず、削減貢献量は、企業が気候変動対策への真摯な取り組みを証明する「信頼の基盤」です。
パリ協定をはじめとする国際的な枠組みのもと、温室効果ガス削減は全世界的な課題として認識されています。
この中で、企業が自社の削減貢献量を正確に測定し、公表することは、投資家、規制当局、消費者との信頼を構築するうえで欠かせません。
具体的な数値データを示すことで、企業は「責任ある行動主体」としての地位を確立し、ESG投資の対象としての魅力を高めることができます。

また、第三者認証を受けることで透明性と信頼性をさらに高め、環境配慮型ビジネスにおける競争優位性を獲得することが可能です。
次に、削減貢献量は、企業の競争力を向上させる「差別化の要素」として機能します。
現在、多くの消費者が環境への配慮を重視しており、環境負荷の低い製品やサービスを提供する企業が市場での支持を得やすい傾向にあります。
例えば、再生可能エネルギーを使用した製品やカーボンニュートラルなプロセスで生産されたサービスは、企業のブランド価値を高め、環境意識の高い顧客層を引きつけます。
削減貢献量の実績を明確に伝えることで、企業は持続可能性を競争力の源泉として活用することができます。

また、削減貢献量は、内部の運営効率を高める「改善の指標」としても重要です。
削減活動を通じて、エネルギー効率の向上や資源使用の最適化、廃棄物の削減といった具体的な効果が得られます。

これにより、運営コストを削減しながら、環境負荷を低減することが可能になります。
さらに、こうした取り組みは、企業全体での意識改革を促進し、従業員が環境目標に主体的に関与する文化を醸成します。
この結果、企業内でのイノベーションが活発化し、新たな製品やサービスの開発が進むことが期待されます。

▼出典:資源エネルギー庁 イノベーションを通じた企業の課題解決力を計る、「削減貢献量」とは?
規制対応の観点からも、削減貢献量は重要な役割を果たします。
各国で温室効果ガス排出に関する規制が厳格化する中、企業が削減貢献量を正確に把握し、報告することは、規制遵守の前提条件となっています。
これにより、罰則や信用リスクを回避するだけでなく、先行的な対応を通じて規制を競争優位性に転換することも可能です。
さらに、削減貢献量のデータは、新たな規制が導入された際にも迅速な適応を可能にし、企業の柔軟性と持続可能性を高める要素となります。
他にも削減貢献量は、サプライチェーン全体での連携を促進する「協働のツール」としての役割を果たします。
企業が自社の削減活動にとどまらず、取引先やパートナー企業と連携してScope 3(バリューチェーン全体の排出量)の削減を目指すことは、サプライチェーン全体の透明性と持続可能性を向上させます。
この協働によって、業界全体での削減効果を最大化することが可能となり、企業の社会的責任の履行と競争力の向上を同時に達成できます。

最後に、削減貢献量は、新しいビジネスチャンスを創出する「イノベーションの推進力」としても重要です。
企業が削減目標を達成するために新技術を採用し、再生可能エネルギーの活用や循環型経済の促進を進めることで、新たな市場や事業モデルが生まれます。
これにより、環境と経済の両方に利益をもたらす形で持続可能な発展が実現されます。
結論として、削減貢献量は、企業にとって単なる排出削減の指標ではなく、透明性の向上、競争力の強化、効率的な運営、規制対応の促進、サプライチェーンでの協働、そして新たな価値創造の基盤として機能します。
削減貢献量を戦略的に活用することで、企業は気候変動対策を通じて社会に貢献しながら、持続可能な未来を築くリーダーとしての地位を確立することができるのです。

・削減貢献量算出のイメージ

▼出典:資源エネルギー庁 イノベーションを通じた企業の課題解決力を計る、「削減貢献量」とは?
・建材メーカーが従来よりも断熱性能の⾼い断熱材を開発した場合

日本の削減貢献量に対するスタンス
削減貢献量は、日本が進める「グリーントランスフォーメーション(GX)」戦略の中心を成す概念です。
GXは、気候変動対策を単なるコストではなく、経済成長の起爆剤と位置づけています。

再生可能エネルギーへの転換や水素エネルギー技術の導入などは、国内の産業基盤を強化し、新しい市場を創出する手段とされています。
削減貢献量はこれらの成果を数値的に示すものであり、GXの効果を測定し、国内外の投資家を引き付ける役割を果たします。

例えば、日本は電気自動車(EV)や蓄電池技術の開発に注力しており、これらの分野での技術革新が削減貢献量の増加に寄与しています。
また、企業レベルでも、省エネルギー技術や循環型経済モデルを採用することで、効率的な資源利用を推進し、経済的利益と環境保全の両立を実現しています。
日本における企業の削減貢献量に対するスタンスは、データの透明性と正確性を重視する点で特徴的です。政府や関連機関は、企業が提出する削減貢献量データの信頼性を担保するための厳格な管理体制を整備しています。
また、このデータは、国内外のステークホルダーに対して企業の気候変動対策の進捗を示す重要な指標として活用されています。
データの透明性が保証されることで、削減貢献量は単なる計測値にとどまらず、企業の持続可能性と信頼性を象徴するものとなっています。

▼出典:〈みずほ〉削減貢献量フォーカスレポート -削減貢献量が拓く持続可能な未来-
削減貢献量のガイドライン
日本は長年にわたり、温室効果ガス削減貢献量の評価と報告の重要性を提唱してきました。
経済産業省は、2018年に「温室効果ガス削減貢献定量化ガイドライン」を策定し、グローバル・バリューチェーンを通じ削減貢献の透明性向上とその取組の普及を目指しています。
このガイドラインは、企業が製品やサービスを通じてどの程度温室効果ガス削減に寄与しているかを明確に示すための指針を提供します。
▼参考:グローバル・バリューチェーンを通じた温室効果ガスの削減貢献
また、日本LCA学会では、2015年に「温室効果ガス排出削減貢献量算定ガイドライン」を発表し、2022年にはその改訂版を公開しました。
イドラインでは、産業界や地方自治体が環境負荷削減貢献量を正確に算定するための手法を提供し、その活動を支援しています 。
▼参考:日本LCA学会 ガイドライン
GHGプロトコルを世界資源研究所(WRI)と協力して開発した世界経済人会議(WBCSD)も削減貢献量のガイダンスを策定しています。
企業が削減貢献量を訴求していくにあたっての国際的なガイドラインで、SBTiの最新のガイドラインに適合していることをベストプラクティスにおいており、SBTi取得企業に取って整合性の取りやすいガイドラインになっていると言えます。
▼参考:WBSCD削減貢献量ガイドライン

COP29における経済産省・WBCSDの共催イベントでは『産業及び金融分野における削減貢献量の標準化に向けて』という内容で、削減貢献量の国際化を進める動きが活発化しています。
▼参考:GXリーグ COP29において経済産業省が削減貢献量についての講演・パネルディスカッションを開催。削減貢献量の標準化に向けて活発な議論が行われました。

他にも、国際電気標準会議(IEC)において、日本の提案を基に削減貢献量の算定方法が規格化される作業が進められています。
この標準化により、企業が削減貢献量をより信頼性のある方法で報告できるようになり、グリーンウォッシュのリスクを軽減することが期待されています

※ガイドラインではないですが、以下のような(仮想)事例集もあり削減貢献量の算定をどのように行うかの一助となります。

算定のアプローチについて
削減貢献量の算定には、ベースラインアプローチとフローベースアプローチという手法が存在し、それぞれ異なる視点から削減量を評価する重要な手法であり、削減活動の成果を正確に示すための科学的基盤を提供します。
ベースラインアプローチの概要と適用方法
ベースラインアプローチは、削減活動が行われなかった場合に予測される排出量(ベースライン)を基準として、削減活動による実際の排出量との差分を削減量として算出する手法です。
このアプローチは、削減活動の全体的な成果を明確に示すために適しており、以下のプロセスで進められます。
ベースライン排出量の設定
削減活動が実施されなかった場合に予想される排出量を基準として設定します。
これには、過去のデータや業界平均、または予測モデルが用いられます。
たとえば、エネルギー使用量に基づく排出量を基準とする場合、過去3年のデータを平均化してベースラインとすることがあります。
さらに、外部要因(市場動向、規制の変更、地域特性など)を考慮し、現実的かつ妥当な値を設定することが求められます。
削減活動の実施と排出量の測定
削減活動後の実際の排出量を測定します。
この測定は、プロジェクトの性質に応じた指標(例: エネルギー消費量、生産単位当たりの排出量)を使用し、透明性と精度を確保するために現場でのデータ収集を重視します。
たとえば、再生可能エネルギーを導入した工場では、削減後の電力使用量を正確に測定します。
削減貢献量の算出
ベースライン排出量から実際の排出量を差し引くことで、削減貢献量を算出します。
この差分が、削減活動による成果を直接的に示すものです。
たとえば、従来のエネルギー源から再生可能エネルギーへの切り替えによる削減量を明確に示すことができます。
利点と課題
ベースラインアプローチの最大の利点は、削減活動の効果を明快に可視化できる点です。
しかし、ベースラインの設定が不適切であれば、削減量が過大または過小に評価されるリスクがあります。
従って、信頼性の高いデータと科学的な算定手法を採用することが不可欠です。

フローベースアプローチの概要と適用方法
フローベースアプローチは、削減活動によって変化した特定のフロー(エネルギー消費、原材料使用、排出プロセスなど)を評価し、その変化量を基に削減量を算定する手法です。
このアプローチは、複雑なプロセスやサプライチェーン全体の排出削減を評価するのに適しており、以下のステップで実施されます。
評価対象フローの特定
削減活動の対象となる具体的なフローを特定します。これには、電力使用量、燃料消費量、廃棄物処理量などが含まれます。
たとえば、製造業では、製品1単位当たりのエネルギー使用量や物流における燃料消費量が評価対象となることが一般的です。
基準フローの設定
削減活動実施前の基準フローを測定し、これを基準値として設定します。基準値は、削減活動が行われなかった場合に予想されるプロセスの通常の流れを反映しています。
たとえば、製品1単位の生産に必要な平均的な電力量を基準フローとして採用します。
削減後フローの測定
削減活動後に同じフローを測定します。
これにより、削減活動がもたらした具体的な変化を把握することができます。
たとえば、新しい省エネルギー機器を導入した後のエネルギー消費量を測定します。
削減量の算出
基準フローと削減後フローの差分を算出し、それに排出係数を適用して削減量を評価します。
この方法により、プロセスのどの部分が削減に最も寄与したかを詳細に分析することができます。
利点と課題
フローベースアプローチは、削減プロセス全体を細かく分析できるため、削減活動の改善点を特定するのに適しています。
一方で、フローの測定が複雑で、特に多段階プロセスではデータ収集が難しい場合があります。これを補うためには、詳細なプロセス分析や適切なデータ収集体制が必要です。
また、上記の両アプローチ共にシナリオ策定や算定に当たっては、グリーンウォッシュの懸念を抱かせないように、以下の原則を元に取り組んでいく必要があります。
【目的適合性(Relevance)】
・評価対象製品・サービス等の削減貢献量を、報告対象となる組織内外の各ステークホルダーのニーズに応えられるよう、適切に算定・報告すること。
【完全性(Completeness)】
・削減貢献量の定量化に影響を与える可能性がある情報を検討し、目的に適合させて報告すること。 除外する情報がある場合には、それを開示し、その正当性を述べること。
【一貫性(Consistency)】
・有意義かつ有効な比較分析を可能にするデータや手法、基準、前提条件を用いること。
【透明性(Transparency)】
・削減貢献量に関連する前提条件を開示し、定量化方法、及び用いたデータ源を適切に言及すること。
・検証を行う場合には、報告する削減貢献量の信頼性を評価するため、検証実施者に明確で十分な情報を提供すること。
【正確性(Accuracy)】
・削減貢献量の定量化に用いる排出量が、実際の排出量より過大や過小にならないようにし、不確実性を可能な限り減らすこと。
・報告する情報の完全性の点について、CO2削減貢献量の利用者が合理的な保証で判断を行えるように、十分な精度を得ること。
ベースラインアプローチとフローベースアプローチは、それぞれ異なる特徴を持ちながら、削減貢献量の正確な算定を可能にする重要な手法です。
ベースラインアプローチは削減活動の全体的な効果を明示するのに適しており、フローベースアプローチは詳細なプロセス分析を通じて改善の方向性を示します。
これらの手法を適切に適用し、必要に応じて組み合わせることで、削減活動の効果を科学的かつ透明性のある形で示すことができます。
最終的に、これらのアプローチは、持続可能な社会の構築に向けた取り組みを支える強力な基盤として機能し、国際的な気候変動対策において重要な役割を果たします。
▼参考:グローバル・バリューチェーンを通じた温室効果ガスの削減貢献
具体的な企業の取り組み
パナソニックグループ
パナソニックグループは各事業単位で、CO2の削減貢献している事業を定めており、2020年には28事業を、2022年度には49事業を可視化し削減貢献の進捗を報告されています。
CO2削減に貢献する商品を紹介するページでは、エアコンや給湯器、生ごみ処理機などどのように削減貢献がされているかが詳細に説明されています。
▼出典:
パナソニックグループ 環境:中長期環境ビジョン
https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/environment/vision.html
CO2削減に貢献する商品
https://holdings.panasonic/jp/corporate/sustainability/environment/vision/product.html
ダイキン
ダイキンはCO2削減貢献量として冷媒R32の特許を無償開放することによって技術支援で3.5億tの削減に貢献やヒートポンプによる削減、インバータエアコンの普及貢献、フロンの回収処理、再エネ事業などを取り組みとして挙げています。
R32のエアコンの全社全世界での販売台数は、累計2.3億台(2022年度12月時点)ということでエアコンに温室効果ガスの削減技術を確実に組み込むことはかなりの削減になることが分かります。
▼出典:ダイキン工業のGX推進例
https://www.kansai.meti.go.jp/3-9enetai/energypolicy/details/saveene/R5sympodaikin.pdf
メルカリ
メルカリは、事業を通じて環境へのポジティブな影響を追求しており、その一環として削減貢献量を算出しています。
2024年度の報告によれば、日米合計で年間約61万トンの温室効果ガス(GHG)排出を回避しました。
これは、東京ドーム約250杯分の容積や、約6,900万本の杉の木が1年間に吸収するCO₂量に相当します。
まとめ
気候変動が経営の持続可能性と競争力を左右する今、削減貢献量は企業価値を高める戦略的指標として注目されています。
これは単なる温室効果ガス削減の数値ではなく、投資家や消費者に対する信頼の証となり、ESG評価やブランド力の向上に直結します。
正確な算定と透明性ある開示は規制対応やリスク管理の基盤となり、同時にコスト削減やイノベーション促進にもつながります。
日本ではGX戦略の一環として削減貢献量の定量化が進められ、国際ガイドラインや標準化の動きも加速しています。
パナソニックやダイキン、メルカリなどの先進企業は、技術開発や循環型モデルを通じて具体的な削減実績を示し、社会的責任と成長を両立。
削減貢献量を活用することは、企業が持続可能な未来の実現においてリーダーシップを発揮するための重要な手段といえます。
▼参考事例


