脱炭素経営にてCO2排出量可視化後の、検討するべき削減対策とは?大手企業の事例をまとめ
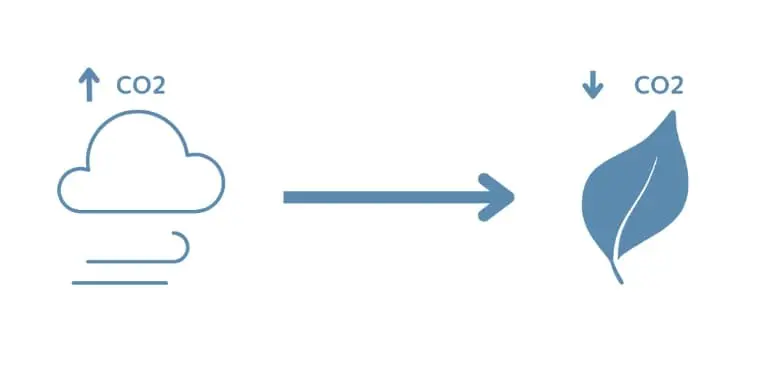
温室効果ガスの削減は、世界的な潮流の中で企業にとって避けられない経営課題となっています。
日本政府は2030年度に2013年度比46%削減、さらに2035年度60%、2040年度73%という新たな中間目標を掲げ、国内排出量の約8割を占める産業部門に大きな変革を求めています。
これを実現するための第一歩が、自社のCO₂排出量を正しく“見える化”することです。Scope1・2だけでなく、サプライチェーン全体を含むScope3まで把握して初めて、どこから取り組むべきかが見えてきます。
続く段階では、オペレーション改善、省エネ・再エネの導入、残余分を補うカーボンオフセットといった施策を戦略的に組み合わせ、削減サイクルを継続的に回していくことが重要です。
削減は設備投資だけではなく、日々の業務の改善から始まるという視点が成果を左右します。
本記事では、現状把握から計画策定、モニタリングまでの流れを解説し、ソニーやイオン、花王など先進企業の事例から学ぶヒントも紹介します。
脱炭素経営を検討する企業に向けて、具体的に何から始めれば良いのかを整理した実践ガイドです。


CO2排出量削減サイクルとは
日本政府は、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた中間目標として、2030年度までに温室効果ガスを2013年度比で46%削減することを掲げています。
さらに、2024年12月には新たな目標案が示され、2035年度までに同基準で60%削減、2040年度までに73%削減を目指す方針が打ち出されました。
これらの目標達成には、国内排出量の約8割を占める産業部門の積極的な取り組みが不可欠です。
Step 1|現状把握:排出量を正しく“見える化”することから始まる
CO₂削減への第一歩は、自社がどれだけ温室効果ガスを排出しているかを定量的に把握することです。
特に、Scope1(自社直接排出)、Scope2(購入した電力等による間接排出)だけでなく、Scope3(サプライチェーン全体の排出)までを含めた全体像の可視化が求められます。

この現状把握の精度が、以降の削減計画の方向性を大きく左右するため、単なる確認作業ではなく、戦略的な基盤づくりとして捉える必要があります。

▼出典:環境省 グリーン・バリューチェーンプラットフォーム サプライチェーン排出量全般
温室効果ガスの算定方法は、大きく2つのアプローチに分かれます。
1つ目は、「重量ベース」での算定です。
これは、使用した燃料や資材などの“物理量”をもとに、品目ごとに定められた排出係数を掛け合わせる方法です。比較的高い精度で算定できる一方、使用量の把握や集計に一定の工数がかかることがあります。
2つ目は、「金額ベース」での算定です。
これは、購入金額に対して排出原単位(100万円あたりのCO₂排出量など)を適用する方法で、特に間接排出(Scope3)の可視化に適しています。
勘定科目単位で集計しやすいため、初期段階ではこのアプローチが現実的な場合も多くあります。
いずれの方法においても、信頼性のある排出原単位を用いることが不可欠です。
たとえば、環境省が提供する「排出原単位データベース」など、公的機関や第三者機関が提供する正式なデータソースを活用することで、信頼性と対外的説明力を確保できます。
「何から始めればよいかわからない」という方へ
Scope1〜3を含む排出量の可視化には、対象範囲の明確化・必要データの整理・算定手法の選定など、押さえるべきポイントが数多く存在します。
初めて取り組む場合は、社内の情報部門・財務部門・調達部門などとの連携が重要となり、部門横断的な体制構築も成功のカギを握ります。
詳しい算定フローや必要なステップについては、こちらの記事で図解付きでわかりやすく解説しています。あわせてご参照ください。

Step 2|削減計画の策定:無理なく、効果的に減らすには
排出量の全体像を把握したら、次はどのように削減していくかの戦略設計です。
ここでは3つのアプローチが重要になります。
1. オペレーション改善による削減
まず着手すべきは自社の業務プロセスそのものの見直しです。
特に製造業では、工場の電力・燃料使用量が全体の排出量の大半を占めるケースが多く、ここを最適化することで大幅な削減が期待できます。
・生産ラインの見直し
・エネルギー効率の低い設備の稼働時間削減
・照明・空調・換気設備の使用適正化
こうした日常業務の改善だけでも、中長期的に見れば大きな削減効果をもたらします。
2. 省エネ設備・再エネ導入
次に検討すべきは、設備そのものの更新です。
たとえば、高効率ボイラーやインバータ付き機器への切り替え、再生可能エネルギー(太陽光パネルなど)の導入が挙げられます。
ただし設備投資には初期費用が伴うため、国や自治体の補助金・助成金制度を活用することが重要です。
経済産業省や環境省が提供する支援策も多数あります。
▼参考:補助金事例:ゼロエミッション化に向けた省エネ設備導入・運用改善支援事業
3. カーボンオフセットの活用
あらゆる対策を講じても削減しきれない排出分については、カーボンクレジットの活用によるオフセットが有効です。
これは、再エネ発電事業や森林保全など、他のプロジェクトによって削減された温室効果ガスをクレジットとして購入し、自社の排出分と相殺する仕組みです。
自社の事業との親和性が高いSDGs分野のクレジットを選ぶことで、CSRやブランド価値向上にもつながります。

Step 3|定期的なモニタリングと見直し
削減施策を実行した後も、排出量の定期的な見直しと再評価が必要です。
CO₂排出量は季節要因や景気変動などによって変動するため、定点観測の体制が不可欠です。
とくに、国際的な気候変動対策フレームワークであるScience Based Targets initiative(SBTi)を活用すれば、自社の業種・規模・排出実態に応じて科学的根拠に基づいた目標設定とモニタリングが可能です。
SBTiでは、数値目標の設定だけでなく、継続的な進捗報告や目標のアップデートも求められるため、本気で排出量削減に取り組む企業にとって信頼性の高い枠組みとなります。


▼出典:環境省 企業の脱炭素経営とサステナビリティ バリューチェーン全体の排出量削減に向けた環境省の取組(令和7年7月11日)
大手企業の取り組み事例
ソニーの環境戦略に学ぶ、CO₂削減の最前線
温室効果ガスの大幅な削減が求められる中、グローバル企業の取り組みは、他の企業にとって重要な指針となります。
なかでも、ソニーグループが示す脱炭素経営の実践例は、製造業を中心とした多くの企業にとって極めて示唆に富むものです。
ソニーは、環境分野を「持続可能な社会の実現」に不可欠な要素と捉え、2050年までに環境負荷をゼロにする長期目標「Road to Zero」を掲げています。
さらに、2040年までにバリューチェーン全体でのカーボンニュートラルを達成するという明確な中間目標も設定し、その実現に向けて段階的に施策を展開しています。
その取り組みの中でも、特に注目すべきは次の4つのアプローチです。
1|再生可能エネルギーの導入拡大
まず、事業活動における直接排出(Scope1・2)を削減するため、再生可能エネルギーの調達と自社発電の強化を進めています。
国内外の事業所において太陽光パネルを積極的に導入し、必要に応じて再エネ由来電力の調達契約を活用することで、電力起因のCO₂排出量を大幅に削減しています。
これらの取り組みは、単なるエネルギー切り替えにとどまらず、地域社会との協調や再エネの安定供給体制の整備にも貢献している点が特長です。
2|製品ライフサイクルでの排出削減設計
ソニーの環境配慮は、製品設計の段階から徹底されています。たとえば、家電製品や電子機器では、省エネルギー設計や長寿命化技術を導入することで、使用時のCO₂排出量を抑える工夫がなされています。
さらに、製造工程ではリサイクル素材の採用や部品点数の最適化に取り組み、原材料調達から廃棄までのライフサイクル全体での環境負荷低減を目指しています。
こうした全体最適の視点は、カーボンフットプリント管理の理想形と言えるでしょう。

3|バーチャルプロダクションによる映像制作の脱炭素化
映像事業を手がけるソニー・ピクチャーズ エンタテインメントでは、LEDディスプレイとリアルタイムCGを組み合わせたバーチャルプロダクション技術を導入しています。
この技術により、従来のロケ撮影に伴う輸送・宿泊・発電機の使用などが不要となり、最大で約52%のCO₂排出削減効果があることが確認されています。
コンテンツ制作という分野においても、ソニーは環境と創造性の両立を追求しています。
4|HDDの高密度化によるデータセンターの省エネ化
近年、爆発的に増加するデジタルデータの保管に伴い、データセンターの電力消費が環境課題の一つとして注目されています。
これに対し、ソニーは高記録密度のHDD(ハードディスクドライブ)を開発することで、必要な機器数を削減し、電力消費とCO₂排出量の抑制に寄与しています。
これらの技術革新は、ソニーが単なる製造企業にとどまらず、社会全体のサステナビリティを支える技術提供者としての立場を担っていることを物語っています。
高い目標を掲げ、段階的に成果へ
ソニーの削減施策は、いずれも単発的な取り組みではなく、ロードマップに基づく戦略的な実行である点が特徴です。
2030年、2040年、そして2050年という時間軸の中で、達成すべきマイルストーンが明確に設定されており、外部評価機関やステークホルダーへの透明な説明責任も果たされています。
企業が温室効果ガスの排出削減に取り組むうえで重要なのは、「どの技術を導入するか」だけではなく、「自社の事業構造にどのようにフィットさせるか」という視点です。
ソニーの事例は、そのヒントを多く与えてくれます。

イオングループが描く脱炭素への道筋――地域と共生する持続可能な環境戦略
流通業界においても、温室効果ガスの削減と持続可能な事業運営の両立が求められる時代となりました。
日本を代表する小売グループであるイオンは、単なる店舗運営の効率化にとどまらず、地域社会と共に歩む脱炭素経営を実践しています。
イオングループは「環境」「地域」「人」のつながりを重視しながら、2050年までの脱炭素社会実現を見据えた中長期戦略を展開。
その柱となるのが、以下のような多角的なCO₂削減施策です。
1|再生可能エネルギーの導入拡大で、店舗を“省エネ発電所”に
イオンでは、全国各地の店舗・物流センターの屋根や敷地内に太陽光発電設備を積極的に導入しています。
これにより、店舗運営に必要な電力の一部を再生可能エネルギーでまかなう仕組みを構築。
一部の商業施設では、再エネ比率100%の電力による運営を達成するなど、単なる電力購入にとどまらず、自らが発電しながら脱炭素を進める姿勢が際立っています。
2|自然冷媒の導入で冷蔵設備の排出を根本から見直し
流通業の中で意外と見落とされがちなのが、冷蔵・冷凍設備による温室効果ガス排出です。イオンではこの課題に対し、地球温暖化係数の低い自然冷媒(CO₂、アンモニアなど)を順次導入。
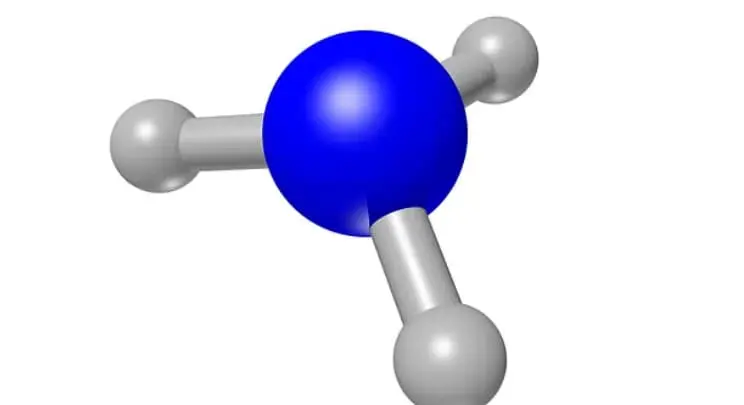
従来のフロン類を使用した設備に比べ、大幅な排出削減効果を持つこの取り組みは、グループ全体の中でも優先度の高いテーマとして位置づけられています。
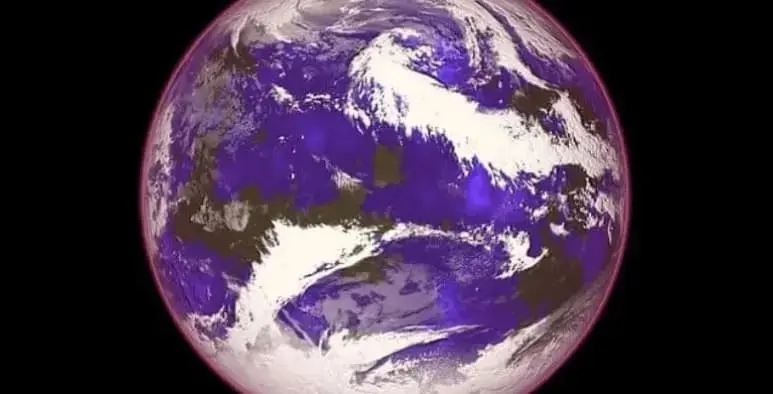
3|地域と育む「ふるさとの森づくり」――緑による吸収源の創出
環境施策において“削減”だけでなく“吸収”にも力を入れている点も、イオンの特徴です。
新規出店時には地元住民と協力し、店舗周辺に地域の在来種を中心とした植樹を行う「ふるさとの森づくり」を継続的に展開。
これまでに全国で90万本を超える植樹が行われており、単なる環境美化にとどまらず、CO₂吸収源の形成や生物多様性の保全にも貢献しています。
環境と地域との共創を実現する好例といえるでしょう。
4|食品リサイクルループで資源循環型社会を体現
イオンの環境施策は、サーキュラーエコノミーの観点でも進化を続けています。
店舗から排出される食品廃棄物を回収し、それを堆肥に加工。
さらにその堆肥を用いて栽培した農産物を店舗で再び販売するという、食品リサイクルループを構築しています。
この取り組みは、廃棄物削減だけでなく、農業との共創や地産地消の促進という社会的価値も同時に生み出している点で高く評価されています。

脱炭素と地域共生を両立する、イオンならではの環境経営
イオングループの削減施策には一貫して、「企業単独ではなく、地域とともに未来をつくる」という姿勢が貫かれています。
単にCO₂排出量を下げるだけでなく、持続可能な地域社会の基盤を強化するような取り組みが多いことが、他企業にはない大きな特長です。
このようなアプローチは、今後脱炭素経営を検討する企業にとって、単なる削減の枠を超えた“社会価値創出型の環境戦略”として大いに参考となるモデルケースです。

花王が描くカーボンニュートラルへの挑戦――製造から消費者までを貫く環境戦略
企業に求められる脱炭素の取り組みが高度化する中、花王グループは化学・日用品メーカーとしての特性を活かし、バリューチェーン全体でのCO₂排出削減に取り組んでいます。
「Kirei Lifestyle Plan」を中核とするサステナビリティ戦略において、環境負荷の低減は“企業活動の根幹”と位置づけられており、エネルギー起点の改善だけでなく、製品設計やサプライヤーとの連携を通じた多角的なアプローチが進められています。
1|エネルギー起点の削減努力──毎年1%の継続的な改善
花王は、2013年を基準年として、全拠点におけるエネルギー使用量を毎年1%ずつ削減するという明確な目標を掲げ、継続的な改善を重ねています。
これは、単なる節電施策ではなく、設備投資・オペレーション見直し・従業員教育を組み合わせた全社的な改善運動として展開されています。
この姿勢は、“現場主導で積み上げる脱炭素”の優良モデルとして、他業種にも応用可能な示唆を与えています。
2|RE100加盟企業としての活動──再エネ100%目標の実現へ
2021年にはグローバル環境イニシアチブ「RE100」に加盟し、花王は以下の野心的な目標を掲げました:
- 2025年までに購入電力の100%を再エネ由来に切り替え
- 2030年までに使用電力の100%を再エネ化
すでに国内主要拠点では再エネ電力への切り替えが進行しており、一部の生産拠点ではグリーン電力証書を活用した実質ゼロ化を実現。
環境目標と経営意思決定が強く結びついている点が、RE100加盟企業の中でも特筆すべき特徴です。

3|原材料調達段階からの排出削減──Scope3カテゴリ1への実効的対応
花王のライフサイクル分析によると、製品起点のCO₂排出の約4割が原材料調達段階(Scope3カテゴリ1)に起因しています。
この課題に対し、花王は原材料サプライヤーとの協働による脱炭素化支援を本格化させています。
環境影響の小さい原料の選定や、トレーサビリティの確保、そして排出原単位の改善など、サプライチェーン全体を巻き込んだ削減構造の再設計を行うことで、単体での限界を超える成果を追求しています。
4|サステナブル商品の開発──環境負荷と使いやすさの両立へ
製品そのものの環境配慮にも注力している花王は、生活者の利便性を損なうことなく環境負荷を下げる商品開発を進めています。
代表的な事例が、「アタック ZERO パーフェクトスティック」。
この製品は、独自の中空構造粉末技術を用い、計量不要のスティック形状にすることで、洗剤の使用効率と包装の簡素化を両立しています。
従来品と比較して、水・プラスチックの使用量削減に成功しており、花王の「環境と生活の質の両立」という哲学を体現した製品と言えます。

脱炭素の軸を“企業価値の中枢”に据える花王の戦略
花王の温室効果ガス削減への取り組みは、単なるCSRではなく、事業戦略そのものに深く組み込まれている点が非常に重要です。
生産拠点や商品の設計段階にとどまらず、原材料調達や使用後の社会的影響までを見据えた構造的アプローチは、製造業における次世代サステナビリティ戦略の先進事例として高く評価されています。

今後、企業が脱炭素経営を推進するうえで参考とすべきは、目標の掲げ方ではなく、その目標を「どう実装し、どう定着させるか」という点です。
その意味で、花王が実践する多層的な施策は、まさにESG経営の本質を体現する好例であるといえるでしょう。

▼出典:花王統合レポート2024
不二製油グループの脱炭素戦略──“つくる責任”を果たす、食の未来づくり
食品素材メーカーとしてグローバルに展開する不二製油グループは、「食の力で、持続可能な社会の実現に貢献する」という企業理念のもと、製品を“つくる”工程における環境負荷の削減に注力しています。
とくに温室効果ガス(GHG)の削減については、事業活動のあらゆる側面を見直すことで、製造業としての責任を果たす姿勢を明確にしています。
ここでは、同社が推進する主な施策を紹介します。
1|再生可能エネルギーの導入拡大:現場から始まる脱炭素の実行力
不二製油グループは、生産拠点の脱炭素化を進めるにあたり、太陽光発電設備の導入と再エネ電力の積極活用を軸に据えています。
国内外の主要工場において順次設備導入を進めており、一部では再生可能エネルギー比率の100%達成を視野に入れた計画的な運用がなされています。
こうした取り組みは、単にコスト削減にとどまらず、企業の長期的競争力と環境リスク管理の両立を目指すものです。
2|エネルギー効率の継続的な改善:製造工程における“無駄の最小化”
製造業のGHG排出の多くは、工場のエネルギー使用に起因します。
不二製油はこれを正面から捉え、高効率設備への更新や、生産プロセスの最適化によるエネルギー使用量の削減を着実に進めています。
具体的には、稼働状況に応じた運転制御や、排熱の再利用といった運用レベルでの改善も含めた包括的な省エネ活動を展開しています。
これにより、コスト効率と環境配慮を両立する“見える削減”を実現しています。
3|サプライチェーン全体への視野拡大:原材料から排出量を見直す
GHG削減の真価は、自社の敷地内(Scope1・2)だけでなく、サプライチェーン全体(Scope3)への責任をどう果たすかにあります。
不二製油はこの視点を重視し、持続可能なパーム油調達をはじめとする原材料選定の厳格化や、輸送の効率化を含む物流網の見直しを推進。
さらに、サプライヤーとの連携による排出量データの可視化と共有も進めており、業界横断的な削減の仕組みづくりに貢献しています。
4|廃棄物削減と循環利用:製造副産物に“第二の役割”を
工場での環境負荷低減は、排出される廃棄物の処理にも及びます。
不二製油では、製造過程で発生する副産物を再資源化し、できる限り廃棄を回避する方針を掲げています。
たとえば、食品残渣の飼料化やエネルギー利用など、循環型社会の形成に向けた活用策を構築。
このように「廃棄しない設計」が前提となった製造体制は、資源の有効利用と温室効果ガスの間接的な削減に寄与しています。

不二製油グループの環境施策は、単なる技術導入の積み重ねではなく、食に携わる企業としての倫理的責任と将来世代への配慮に根ざしています。
再生可能エネルギーの活用、省エネ技術、サプライチェーンとの共創、資源循環の仕組み──いずれもが、長期的な環境価値と企業競争力を両立する設計となっています。
今後、脱炭素経営を進めようとする企業にとって、不二製油の事例は「自社起点でありながら、社会全体の価値向上に資する環境戦略」の一つの理想形といえるでしょう。

鉄鋼業における脱炭素の先駆者──東京製鐵が描く循環型・低炭素社会へのロードマップ
鉄鋼業は、エネルギー多消費型産業の代表格として、温室効果ガス排出削減の観点から大きな責任を負っています。
そうした中で、東京製鐵は電炉メーカーとしての特性を活かし、従来の高炉方式に比べて大幅にCO₂排出量を抑えた鉄づくりを実践。
環境負荷の少ない鉄鋼製品の安定供給を通じて、脱炭素と資源循環の両立を追求する独自の戦略を打ち出しています。
1|EcoVision 2050:持続可能な未来を描く長期環境ビジョン
東京製鐵は、2050年を見据えた長期戦略「Tokyo Steel EcoVision 2050」を策定。
このビジョンでは、「脱炭素社会」と「循環型社会」の同時実現を掲げ、電炉鋼材の普及を通じて、日本全体のCO₂排出削減に貢献することを明確に示しています。
このビジョンのもと、東京製鐵は単に自社の排出削減にとどまらず、鉄スクラップという資源を循環させるシステムそのものの再構築に取り組んでいる点が特筆に値します。
2|高付加価値製品の電炉化──難素材への挑戦が業界を変える
電炉による鉄鋼製造は、従来はH形鋼や厚鋼板などの高付加価値製品の製造には適さないとされてきました。
しかし、東京製鐵はその常識を覆すべく、高精度な生産技術の開発を通じて、電炉でのH形鋼や鋼板の安定供給を実現。」
これにより、建設・自動車など幅広い産業における脱炭素型材料への移行を可能にし、業界全体のCO₂排出量削減を後押ししています。
まさに、自社の競争力強化と社会的責任の両立を果たす革新的な取り組みです。
3|ISO14001に基づく環境マネジメント──改善の仕組みを企業文化に
環境対応を一過性の活動に終わらせないために、東京製鐵はISO14001認証に基づく環境マネジメント体制を全拠点で構築。
原料調達から製品出荷に至るあらゆる工程で、省エネルギー・省資源・環境保全を実現するためのPDCAサイクルを徹底しています。
こうした取り組みは、現場レベルでの実行力を高めると同時に、経営層から現場まで一貫した環境意識の醸成にもつながっており、東京製鐵の企業文化の中核を形成しています。

4|廃棄物から資源へ──電気炉によるリサイクルの高度化
鉄スクラップの再資源化だけでなく、東京製鐵は廃乾電池などの廃棄物を電気炉で無害化し、有用資源として再利用する高度なリサイクル技術にも取り組んでいます。
とくに岡山工場では、廃電池の回収・処理を通じて鉄や亜鉛の回収と再利用を実現しており、従来“捨てられていたもの”に新たな価値を見出す仕組みが構築されています。
こうした技術は、鉄鋼業の枠を超え、循環型経済の実現に向けた重要なモデルとなり得るものです。

脱炭素は技術だけでは進まない──東京製鐵の本質的な強みとは
東京製鐵のGHG削減への取り組みは、技術革新だけでなく、制度設計、ビジョン、マネジメント、文化のすべてが連動して動いている点に強みがあります。
鉄スクラップを活かした電炉製鉄という「本質的に環境にやさしい製造プロセス」をベースにしながらも、そこで止まらず、より高度な製品領域へ挑戦する姿勢や、徹底したマネジメントによる“確実な実行力”こそが、同社の脱炭素戦略を支える基盤となっています。
脱炭素を「単なるコスト」ではなく「企業価値の源泉」と捉えるこの視点は、今後あらゆる業界で求められる環境経営のあり方を示しています。

まとめ
CO2排出量の削減が目的でありながら、現状把握のプロセスを終えた際にどうするべきなのか明記されているガイダンスもまだまだ少ない状況です。
また企業の規模、業界や色んな要因からそれぞれに最適な削減施策は必ずしも同じではありません。
そして大規模な初期費用が必要な再生可能エネルギーの導入などが真っ先に思い浮かぶのですが実はお金をそこまでかけずにまずはオペレーションを見直すことが遠回りしているようで一番効果的だったりします。
ScopeXでは企業のCO2算定に止まらず、その後の削減施策をどうしていくかなどのご提案も削減パートナーと共にご提案をさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせください。
