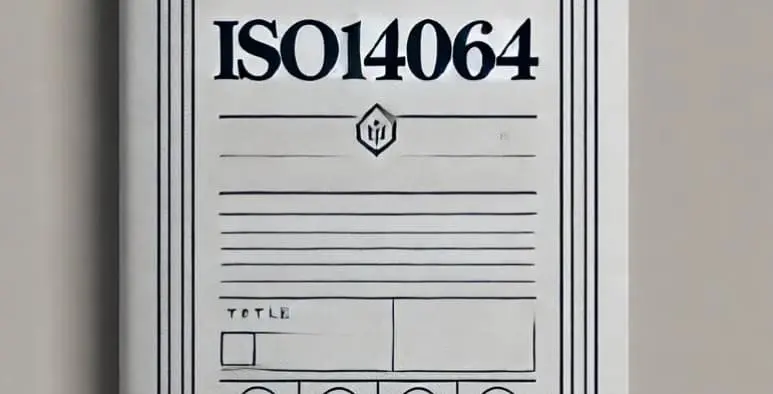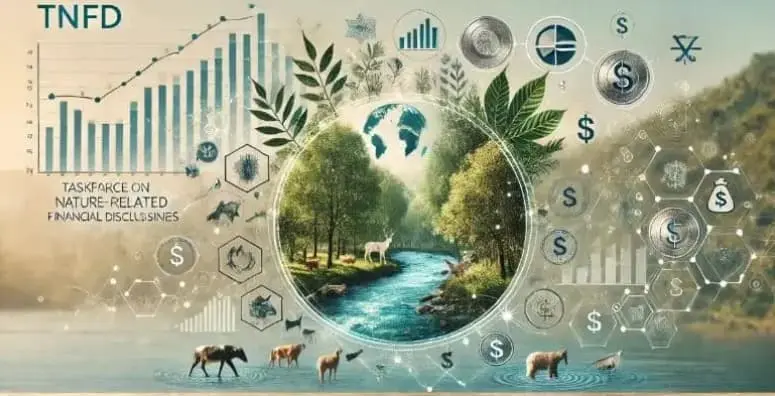環境政策・制度– category –
-

ELV「指令」から「規則」へ ― EU自動車リサイクル新時代に、日本企業が生き残るための必須要件
自動車が役目を終えたとき、その廃棄や再資源化をどのように行うかは、環境負荷と資源循環に直結する重要な課題です。 こうした背景のもと、EUは2000年にELV指令(End-of-Life Vehicles Directive、使用済み自動車指令)を制定し、加盟国に国内法化を義務... -

経済産業省が推進するGX(グリーントランスフォーメーション)とは?政策・支援策を徹底解説
地球温暖化やエネルギー安全保障の課題が深刻化する中で、日本社会において今もっとも注目されているキーワードのひとつが「GX(グリーントランスフォーメーション)」です。 ニュースや企業のプレスリリースでも頻繁に見かけるようになりましたが、実際に... -

2025年最新版 GX経済移行債とは?――仕組み・リスク・投資戦略を専門家が徹底解説
日本政府が打ち出した「GX経済移行債」は、単なる国債の一種ではありません。2050年カーボンニュートラルという国家目標に向けて、産業政策・環境政策・財政政策を金融の力で一体化する、日本独自のアーキテクチャです。 政府は今後10年間で官民150兆円のG... -

【2025年最新版】脱炭素先行地域に選ばれた自治体一覧と注目の事例紹介
地球温暖化の進行が深刻さを増す中、日本政府は「2050年カーボンニュートラル」の実現を目指し、地域単位での脱炭素化を加速させています。その中核を担うのが、環境省が選定する「脱炭素先行地域」制度です。 これは単なる環境対策ではなく、エネルギーの... -

IEAが世界のエネルギー政策に与える影響とは?最新動向と課題も解説
脱炭素社会の実現に向けて、世界各国がエネルギー政策の転換を迫られる中、ますます存在感を高めているのがIEA(国際エネルギー機関)です。 IEAは、1974年の石油危機を契機にエネルギーの安定供給と安全保障を目的として設立された国際機関であり、現在で... -

ネットゼロ・バンキング・アライアンス(NZBA)とは?加盟銀行や金融機関の脱退の動向と今後の課題
金融業界における脱炭素の動きの中で、特に注目を集めてきたのが NZBA(ネットゼロ・バンキング・アライアンス) です。 2021年に国連環境計画・金融イニシアティブ(UNEP FI)が設立したこの枠組みは、2050年までに銀行の融資・投資ポートフォリオをネッ... -

【2025年最新版】SSBJがサステナビリティ開示基準を発表!企業に求められる対応を徹底解説
2025年3月、サステナビリティ基準委員会(SSBJ:Sustainability Standards Board of Japan)が、日本として初めてとなるサステナビリティ開示基準を正式に公表しました。 国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)のIFRS S1・S2を土台としつつ、日本の法制... -

GX2040ビジョンが示す未来 ― 企業が“次に備えるべき”3つの変化
脱炭素社会に向けた日本の新たな道標として、政府は「GX2040ビジョン」を策定しました。単なる環境対策ではなく、エネルギーの安定供給と経済成長の両立を図りつつ、産業構造を次世代型へ刷新するための国家戦略です。 特に、成長志向型カーボンプライシン... -

企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令(CSDDD)とは?—背景・要件・日本企業への影響を徹底解説
グローバルなビジネス環境において、企業の持続可能性が求められる時代となりました。特に、環境破壊や人権侵害に対する国際的な規制が強化される中、EUが新たに導入した「企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令(CSDDD)」は、企業に対し、バリュ... -

ISO14064とは?シリーズの説明とISO14064-1について詳しく解説
ISO14064は、温室効果ガス(GHG)の排出量を透明かつ客観的に算定・報告・検証するための国際規格です。 企業の脱炭素経営が求められる中、GHG排出量の適正な管理と報告の重要性が高まり、各国の規制や投資家の要請に対応するための基準として策定されまし... -

SHK制度とは?GHGプロトコルや省エネ法との違い、改正ポイントまで分かりやすく解説
脱炭素経営が企業の競争力を左右する時代、自社の温室効果ガス(GHG)排出量を正確に把握し、適切に報告することは、もはや最低限の責務となっています。日本国内において、その基盤となるのが温対法に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」、... -

TNFDとは│TCFDやCDPの整合性を最新情報と合わせて解説
近年、世界のサステナビリティ経営において注目を集めているのが、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)です。 これは、気候変動を対象としたTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の枠組みを発展させ、「自然資本」――つまり生物多様性、森林...






とは?加盟銀行や金融機関の脱退の動向と今後の課題.jpg)