Scope3カテゴリ7-雇用者の通勤における温室効果ガスの排出量算定について具体的に解説

企業の温室効果ガス(GHG)排出量を正確に把握するうえで欠かせないのが、Scope3カテゴリ7「従業員の通勤」です。
社員が自宅から職場へ移動する際に発生する排出は、自家用車・鉄道・バスなどの公共交通機関に加え、自転車や徒歩といった幅広い通勤手段を含みます。
特に自家用車通勤は排出量が大きく、管理の重点項目とされています。
近年はテレワークの普及により通勤機会が減少し、従来の算定方法や削減策にも変化が生まれています。
一方で、在宅勤務に伴う家庭での電力使用が新たな課題となるなど、「通勤削減=排出削減」では語れない複雑な側面もあります。
本記事では、Scope3カテゴリ7の概要から具体的な算定方法、そして企業が取り組むべき削減施策までをわかりやすく解説します。
通勤排出の管理は単なる環境対策にとどまらず、働き方改革や従業員満足度の向上にも直結する重要テーマです。持続可能な経営を目指す企業にとって必読の内容となっています。

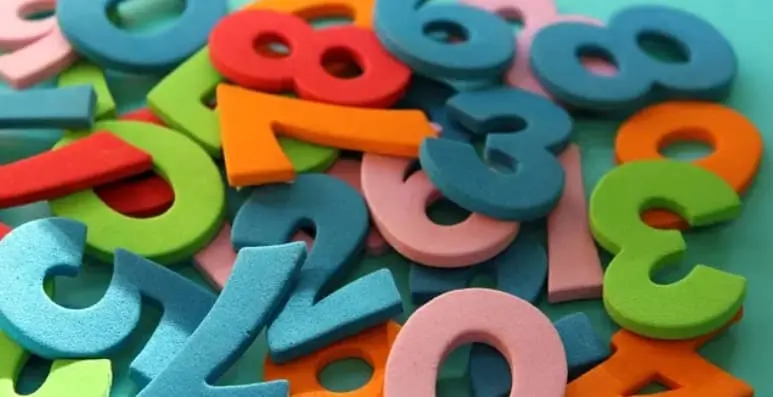

Scope3カテゴリ7の概要|従業員通勤による温室効果ガス排出とは?
Scope3のカテゴリ7「従業員の通勤」は、社員が自宅から職場まで移動する際に発生する温室効果ガス(GHG)排出を対象としています。
対象となる手段は幅広く、自家用車・バス・鉄道などの公共交通機関に加え、自転車や徒歩も含まれます。
それぞれの移動距離や交通手段に応じて排出量を算定する必要があり、特に自家用車通勤は一人あたりの排出量が大きく、重点的な管理が欠かせません。
通勤データ収集の重要性
排出量を正確に把握するには、従業員ごとの通勤距離、利用する交通機関、通勤頻度などのデータ収集が不可欠です。こうした一次データをもとに排出係数を掛け合わせることで、現実に即した算定が可能となります。
人事システムや通勤実態調査と連動させることで、精度の高い管理が実現できます。
テレワーク普及による影響
近年のワークスタイルの変化もカテゴリ7に大きく影響しています。
テレワークの導入により、従来の通勤による排出は減少する一方で、在宅勤務時に自宅で使用する電力や空調による排出が新たに課題となっています。
「通勤減=削減効果」と単純に評価するのではなく、在宅勤務に伴う排出も含めた総合的な視点が求められます。
季節や居住地による変動
通勤排出量は季節要因や居住地によっても変化します。
- 自転車や徒歩は気温・天候の影響を受けやすく、利用率が季節ごとに変動する。
- 冬季は自動車の燃費が低下し、同じ距離でも排出量が増える傾向がある。
- 従業員の居住地が遠方で公共交通機関が限られている場合、車通勤が避けられず排出量が高まる。
こうした点を考慮することで、より現実的な排出量の把握につながります。
管理と削減に向けた取り組み
カテゴリ7は従業員の日常的な行動に深く関わるため、組織の施策だけでなく従業員自身の協力が不可欠です。
通勤データの定期的な更新や、テレワーク・公共交通機関利用の促進などを通じて、働き方改革と連動した効果的な削減策を展開できます。
結果として、従業員のエンゲージメントを高めながら企業全体のサステナビリティを推進することが可能になります。
▼おすすめのお役立ち資料

Scope3カテゴリ7の算定方法|通勤排出量をどう計算するか?
Scope3カテゴリ7「従業員の通勤」による排出量は、いくつかの方法で算定することが可能です。
基本的には、通勤距離・交通手段・人数・費用といったデータをもとに排出係数を掛け合わせて計算しますが、実務上は「費用ベース」での算定が広く使われています。
1. 費用ベースの算定方法
もっとも一般的なのが、従業員の通勤費用に排出原単位を掛ける方法です。たとえば、都市部で鉄道通勤が主流の場合、会社が年間150万円の鉄道通勤費を負担しているとします。
環境省が公表している排出原単位(例:国内線飛行機 0.00000185tCO2/円)を用いると、次のように計算できます。
1,500,000[円]×0.00000185[tCO2eq/円]=2,775 [tCO2eq]
このように、費用ベースの算定はデータ収集が容易で、多くの企業が採用しています。
- 交通費 ÷ ガソリン単価 = 使用燃料量
- 使用燃料量 × 排出係数 = CO2排出量

▼出典:環境省 排出原単位データベース Ver.3.4(EXCEL/6.72MB)<2024年3月リリース>
2. 燃料ベースの算定方法(自家用車通勤)
自動車通勤の場合は、支給した交通費をガソリン価格で割ることで燃料使用量を推計し、それにガソリンや軽油の排出係数を掛け合わせて算定します。
ガソリン価格は経済産業省や資源エネルギー庁の公式データを参照することで、精度の高い計算が可能です。
3. 精緻な算定(車種・燃費ベース)
さらに正確性を追求する企業では、従業員の車種や燃費データをヒアリングし、実際の燃料消費量をベースに排出量を算定するケースもあります。
特に製造業や環境意識の高い企業では、こうした一次データに基づく詳細な算定が行われています。
カテゴリ7も算定方法はいくつかあり難易度が高いものに、出勤で使っている移動サービスで移動した距離や人数で算定するものがありますが、金額で算定することが非常に多いです。
Scope3カテゴリ7の削減施策|企業が取り組むべき通勤由来の排出削減方法
Scope3カテゴリ7「従業員の通勤」による温室効果ガス(GHG)排出は、企業にとって身近でありながら効果的に削減できる領域です。
ここでは、代表的な施策と実践のポイントを整理します。
1. テレワーク・在宅勤務の推進
最も直接的な削減策は、オフィスへの移動を減らすことです。
テレワークの導入により通勤由来の排出を削減できます。
ただし、自宅での電力や空調利用が増える点は注意が必要です。
そのため、在宅勤務時には省エネ行動の促進や効率的な空調利用ガイドの提供など、総合的な対策が求められます。

2. 通勤手段の見直しとモーダルシフト
自家用車通勤は排出量が大きいため、公共交通機関への転換が効果的です。
- 通勤手当制度の改定(鉄道利用者への優遇など)
- 公共交通利用者への補助・インセンティブ
これらの仕組みづくりにより従業員の行動変容を促せます。
3. 自転車・徒歩通勤の支援
比較的近距離に住む従業員には、自転車や徒歩通勤の支援が有効です。
駐輪場やシャワー室の整備、自転車通勤手当の支給など、インフラとインセンティブの両輪が必要です。
4. カーシェアリング・ライドシェアの推進
同じ方向から通勤する従業員同士で相乗りやカーシェアを活用することで、一人あたりの排出を大幅に削減できます。社内マッチングシステムや、参加者へのインセンティブ制度の導入も効果的です。
5. オフィス立地の最適化
長期的な施策として、公共交通機関のアクセスが良い場所への移転や、サテライトオフィス設置が挙げられます。
これにより通勤距離の短縮と低炭素な通勤手段の利用促進が可能になります。
6. 勤務制度の柔軟化
時差出勤やフレックスタイム制を導入することで、
- 通勤時の渋滞を回避し、自動車の燃料消費を抑制
- 公共交通機関の混雑を緩和し、利用転換を後押し
といった間接的な削減効果を期待できます。
7. エコドライブの啓発
自動車通勤が不可避な従業員に対しては、環境配慮型の運転教育が有効です。
急発進・急ブレーキを避ける、適切なタイヤ空気圧を保つなど、日常的な工夫で燃料効率を高められます。
8. 居住地選択への支援
職場近隣への引っ越し支援や、通勤距離を考慮した住宅手当の導入は、長期的に通勤距離そのものを減らす施策となります。
従業員のライフスタイル改善にもつながる点が特徴です。
9. 社内の理解とモニタリング
いずれの施策も、従業員の理解と協力が不可欠です。
- 環境教育や社内啓発
- 削減効果の見える化や優良事例の共有
- 通勤実態調査の定期実施と改善サイクル
これらを通じて組織全体での取り組みを定着させることができます。


Scope3カテゴリ7は、単に排出量を減らすだけでなく、働き方改革・従業員満足度向上・コスト削減といった副次的効果も期待できます。企業にとって取り組む意義の大きい領域といえるでしょう。
まとめ
Scope3カテゴリ7は、従業員の通勤に伴う温室効果ガス(GHG)排出を対象とし、自家用車、鉄道、バス、自転車、徒歩などの交通手段に応じた排出量を算定します。
特に自家用車通勤は排出量が大きく、重点的な管理が必要です。
近年のテレワーク普及により通勤機会が減る一方、在宅勤務に伴う電力消費の増加という新たな課題も発生しています。
削減施策として、テレワークの推進、公共交通機関の利用促進、自転車通勤の支援、カーシェアの活用、オフィスの立地最適化などが有効です。
また、時差出勤やフレックスタイム制の導入により、通勤時の混雑を回避し、排出量の低減につなげることも可能です。
従業員の意識向上や通勤制度の見直しを進めることで、より持続可能な通勤スタイルへの転換を促進し、企業全体の排出量削減につなげることができます。
カテゴリ7の算定で少し難しいケースは、車通勤が多い地域でガソリン補助代として通勤費を支払っているケースや、海外拠点において通勤費が無く給与に含まれているケースなどになります。
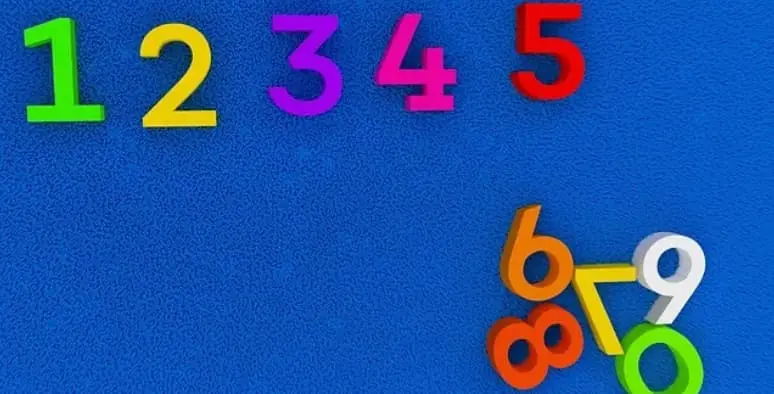
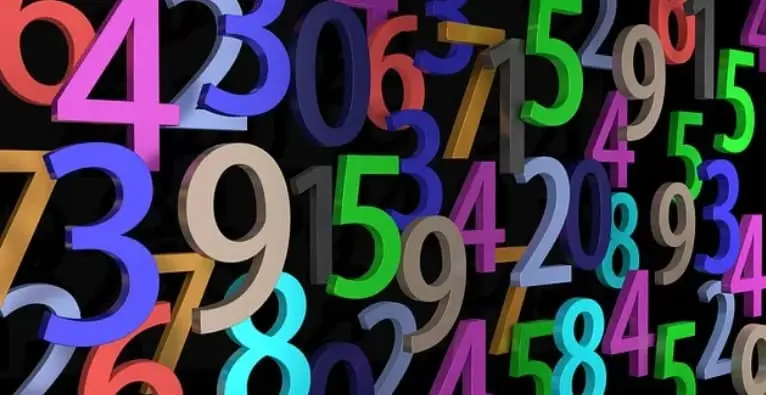
▼おすすめのお役立ち資料


