電気料金はこうして抑える!電力会社の比較ポイントと脱炭素経営への活用法

電気料金の高騰が続く中、企業にとって電力コストの最適化は重要な経営課題となっています。
2016年の「電力全面自由化」により、企業は自社に最適な電力会社を選択できるようになりましたが、現在では500社以上の電力会社が存在し、料金プランも多様化しています。
そのため、単に「電気代が安い会社」を選ぶのではなく、安定供給やサービス内容、契約条件などを総合的に比較し、自社のニーズに合った電力会社を見極めることが求められています。
本記事では、電力会社の種類と特徴、比較のポイント、そして今後の電力業界の展望について詳しく解説します。
特に、「電力自由化のメリットを最大限活かす方法」や「カーボンニュートラルを視野に入れた電力選び」など、企業の持続可能な経営にも役立つ視点を提供します。
さらに、乗り換えを検討する際の注意点や電力会社選びでよくある疑問についても取り上げ、初めて電力会社を見直す企業でも安心して判断できるようサポートします。
電力会社を選ぶことは、単なるコスト削減だけでなく、企業の脱炭素経営やサステナビリティ戦略にも直結します。
これからの時代、どのような視点で電力会社を選び、どのようにコスト最適化を図るべきか。
本記事を通じて、貴社の電力選びをより戦略的なものへと変えていきましょう。

電力会社の種類と選び方
電力コストの最適化を考える際、まず理解しておきたいのが「新電力」と「大手電力会社」の違いです。
2016年の電力全面自由化以前、日本の電力供給は地域ごとに大手電力会社が独占していました。
しかし自由化により、新たな電力事業者が次々と参入し、料金の多様化やサービスの競争が進んでいます。
企業にとっては選択肢が増えた一方で、どの電力会社を選べばよいのか判断が難しくなっているのが現状です。
それぞれの特徴を知り、どのような基準で選ぶべきかを考えていきましょう。

大手電力会社の特徴
日本全国を10エリアに分け、それぞれの地域で長年にわたって電力供給を担ってきたのが大手電力会社です。
東京電力、関西電力、中部電力、東北電力、九州電力、北海道電力、中国電力、四国電力、北陸電力、沖縄電力の10社が該当します。
大手電力会社の強みは、自社で発電所を所有し、安定した供給力を持つことです。それに、地域に根差した運営を続けてきた実績があります。
また、大企業向けの特別料金プランを提供しているケースも多く、電力使用量が多い企業には適した選択肢となります。
一方で、価格競争力にはやや欠ける傾向があります。基本料金が高めに設定されていることが多く、料金の柔軟性も低いため、使用状況によっては新電力のほうがコストメリットを得やすいこともあります。
近年は脱炭素の動きも強まりつつありますが、発電の多くを火力発電に依存しているため、CO₂排出量を大幅に削減するのが難しいという課題も抱えています。

▼出典:資源エネルギー庁「電力の小売全面自由化って何?」
新電力の特徴
新電力は、電力自由化に伴って市場に参入した事業者の総称です。
多くの新電力会社は自社で発電所を持たず、大手電力会社や他の発電事業者から電力を仕入れて販売するビジネスモデルを採用しています。
そのため、設備投資の負担が少なく、価格競争力のある料金プランを提供しやすいのが特徴です。
近年では、再生可能エネルギーを活用した「グリーン電力プラン」を展開する新電力も増えており、カーボンニュートラルを目指す企業にとっては魅力的な選択肢となっています。
太陽光や風力発電を積極的に取り入れ、非化石証書を活用したCO₂排出量ゼロの電力プランを提供している事業者もあります。
電力供給そのものの安定性は大手と変わりませんが、新電力会社自体の経営状況によっては、突然の事業撤退やサービス停止のリスクがあることには注意が必要です。
実際に、電力市場価格の急変動によって経営が立ち行かなくなり、事業継続が困難になった新電力会社も出ています。
▼参考:資源エネルギー庁 登録小売電気事業者一覧
電力会社の選び方と複雑化するメニュー
企業が電力会社を選ぶ際には、コスト削減、供給の安定性、契約の柔軟性、脱炭素経営への対応といった複数の要素を考慮する必要があります。
電力自由化により、電力会社の選択肢は大幅に増えましたが、その分、プランも複雑になっています。
どのプランが最適なのかを判断するためには、電気料金の仕組みや市場価格の影響、契約条件を理解することが重要です。
特に、市場連動型プランを利用する場合は、市場価格の高騰時にコストが大幅に上昇する可能性があるため、慎重な判断が求められます。
1. 料金プランの種類と適用条件を理解する
電力会社の料金プランは、大きく「固定制プラン」「市場連動型プラン」「時間帯別プラン」の3種類に分類されます。
- 固定単価制プラン燃料費調整額がなく、単価が固定されているため、市場の変動に左右されず、安定性を重視する方におすすめのプランです。
ただし、電力市場価格が下がっても料金は固定のため、変動リスクを回避できる一方で、市場価格が安いときの恩恵は受けられません。
- 市場連動型プラン電力市場の価格変動に応じて電気料金が変わるプランです。市場価格が下がれば大幅なコスト削減が可能ですが、価格が高騰した際には電気代が予想以上に上昇するリスクがあります。
燃料価格が上昇すると電気料金も上がるため、原油や天然ガスの価格変動に注意する必要があります。
- 時間帯別プラン昼間と夜間で料金が異なるプランで、深夜帯の電力が割安になるのが特徴です。
夜間稼働の多い企業(工場・データセンターなど)にはコスト削減のメリットが大きい。
昼間の料金が割高になるケースもあるため、電力使用のピーク時間を考慮する必要があります。

2.電気料金を比較する際のポイント
電力会社を選ぶ際には、複数の会社から見積もりを取り比較検討することが重要です。
ここでは、その際に押さえておきたいポイントを解説します。
① 前提条件を揃える
電気料金の見積もりは、過去1年間の契約電力や使用量などの実績値をもとに算出されることが一般的です。
そのため、正確な比較を行うためには、各社で同じ前提条件を揃える必要があります。
② 料金メニューを正しく理解すること
電力会社ごとに、完全定額プランや市場連動型プランなど多様な料金メニューが用意されています。
自社の運営方針や使用状況に最適なプランを選ぶためには、単純に年間電力料金の安さだけで判断するのではなく、各プランのメリットとデメリットを理解して検討することが重要です。
さらに、電気料金に関する窓口となる担当者が、電気料金算定式を理解できるようになることも欠かせません。
算定式を理解していれば、電力会社との協議を同じ目線で進められるため、より有利な条件で契約を結ぶことが可能になります。
3. 電力供給の安定性と経営基盤のチェック
電力会社を選ぶ際には、単に料金の安さだけでなく、供給の安定性や経営の健全性も重要な要素となります。
特に、新電力会社を選ぶ場合には、その会社の経営状況や財務基盤を確認することが不可欠です。
- 突然の市場価格高騰による経営破綻により、電力供給が停止するリスクがあります。
- 事業撤退した場合、企業は新たな電力契約を急遽探さなければならず、最悪の場合、最終保証供給に移行し、一時的に電気料金が上昇する可能性があります。
電力価格が高騰した場合にも安定して電力を供給できるかどうかを確認では、発電所を自社で所有しているか、電力の調達先が信頼できるかなどを事前に確認しましょう。
4. 脱炭素経営視点での電力会社の選び方
現在、多くの企業が脱炭素経営やESG(環境・社会・ガバナンス)投資の観点から、再生可能エネルギーを活用する電力会社を選ぶ動きを強めています。

- 100%再生可能エネルギーを提供するプラン太陽光、風力、水力発電を活用した電力プランが増えており、CO₂排出ゼロの選択肢もあります。
「非化石証書付き電力」や「FIT電気」を選ぶことで、実質的に温室効果ガスの排出をゼロにできます。
- 電力使用量に応じたCO₂クレジットの活用一部の電力会社では、電力使用に応じたカーボンオフセットサービスを提供しており、企業のCO₂削減目標に貢献できます。
- ESG評価への影響企業のサステナビリティ評価は、投資家や消費者からの信頼に直結します。
脱炭素経営を意識した電力選びは、企業ブランドの向上や投資家からの評価向上につながる重要な要素となっています。
特に、欧州では「RE100(企業が100%再生可能エネルギーを使用することを目指す国際イニシアティブ)」を採用する企業が増えており、日本国内でも大企業を中心に導入が進んでいます。
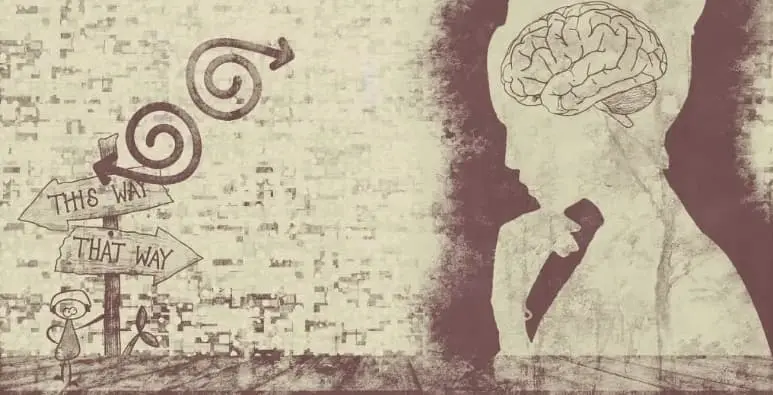

▼出典:環境省 再エネ電気プラン
5. 契約条件と違約金の確認
電力契約は通常、1年単位の契約更新が基本となっていますが、一部の新電力会社では3〜5年の長期契約を求めるケースもあります。
- 契約途中の解約に違約金が発生する場合があるため、契約内容をよく確認することが重要です。
- 市場価格変動と解約金
市場価格に連動することで電力会社側のリスクが軽減され、契約解除のリスクは低いとされています。 - 違約金の有無と条件
重要なのは、個々の契約内容を事前にしっかりと確認することです。中には、契約期間の縛りがなく、いつでも解約できるプランも存在します。 - 電力調達の安定性を確保するためにも、契約期間、解約時の条件、料金調整の仕組みを事前に把握しておくことが求められます。
企業の電力契約は、単なるコスト削減ではなく、供給の安定性、契約条件の透明性、脱炭素経営への貢献といった観点から慎重に選ぶことが求められます。
電力市場の変動を理解し、自社に最適なプランを選ぶことで、持続可能な経営とコスト削減の両立が可能になります。
発送電分離とは?
発電所で作られた電気は送配電設備や送配電網(送配電ネットワーク)を通じて、工場や大型施設、一般家庭といった需用家、つまり消費者に届けられます。
こうした設備や送配電網は、発電設備とともに東京電力や関西電力などの大手電力会社が所有しています。
2016年4月の電力小売の全面自由化後は、それぞれの電力会社の“送配電部門”が移行した一般送配電事業者が送配電を行いますが、実質的にはこれら大手の電力会社が引き続き行っているのと変わりません。
一方で、新しく市場に参入した電力会社には一般家庭に供給する電気はあっても、電気を利用者に届ける設備や送配電網がありません。
新たに自前で電線や電柱を街中に張り巡らせることは、コスト面や景観、限られた空間や土地を利用することを考えても現実的ではありません。
そのため、新たな電力会社は手数料を支払って一般送配電事業者の送配電網を利用することになります。
発電を行い送配電網も持つ大手の電力会社、大手・中小を含めて新規参入した電力会社、こうしたすべての電力会社が同じ土壌で公正な競争を行うには、共通のインフラである送配電網をすべての電力会社が公平かつ自由に利用できなければなりません。
送配電を行う会社が、ライバル電力会社の手数料だけを高くするとか、送配電網を利用させないというようなことはあってはなりませんし、そうした可能性も排除しておく必要があります。
こうして、公正な競争を促すための新たな仕組み作りとして導入されたのが、大手電力会社の発電部門と送配電部門を分ける“発送電分離”なのです。
“発送電分離”を行うことで、どの電力会社がどこへでも送配電網を使って電気を送れる“送配電”の自由化を実現することができ、しっかりとした競争的環境を整えることができるわけです。

電気以外のエネルギー自由化と脱炭素経営の展望
企業が脱炭素経営を進める上で、エネルギーの選択は非常に重要な要素となります。
電力自由化により、企業は自社に適した電力会社を選べるようになりましたが、電気だけでなく、都市ガス、プロパンガス、灯油、重油、自動車燃料などのエネルギーもすでに自由化されています。


これにより、企業はより低コストで環境負荷の少ないエネルギーを選択できるようになり、持続可能な経営へとシフトする機会が広がっています。
また、各エネルギーの算定式やサプライチェーンの仕組みを理解することで、エネルギーコストを適正化し、最適なエネルギー調達が可能になります。
さらに、適正な仕入価格を実現することで、省エネ設備への投資や、CO₂クレジット、非化石証書を活用した実質的な排出量ゼロのエネルギー導入も進めることができ、脱炭素経営の実現にも近づきます。
1. 都市ガスの自由化と低炭素エネルギーの活用
2017年4月、日本のガス市場は全面自由化されました。
それまで、各地域のガス会社が独占的に供給していた都市ガスを、新規事業者も提供できるようになったことで、企業は価格競争によるコスト削減と、環境負荷の少ないエネルギーへの転換を同時に実現できるようになりました。
特に、脱炭素経営を意識する企業にとって、以下のようなガスの選択肢が広がっています。
- カーボンニュートラルLNG(液化天然ガス)の利用:LNG(液化天然ガス)は、石炭や石油よりもCO₂排出量が少なく、温暖化ガス排出削減に貢献します。
さらに、排出されるCO₂を森林保全やCCUS(炭素回収・貯留)技術でオフセットした「カーボンニュートラルLNG」が登場し、企業はより環境負荷の少ないエネルギー調達が可能になっています。
- バイオガスの導入:バイオガスは、食品廃棄物や下水汚泥などから生産される再生可能エネルギーで、都市ガスと同様に利用可能です。
企業や自治体が排出する有機廃棄物を活用することで、エネルギーの地産地消を実現しながら、カーボンニュートラルを推進できます。
- ガス市場の競争による調達コストの最適化:自由化によって、企業は地域独占のガス会社以外からも供給を受けることができるようになりました。
これらの取り組みを活用することで、企業は化石燃料由来のエネルギーから低炭素・再生可能エネルギーへの移行を加速することができます。
2. バイオマス燃料と再生可能燃料の普及
電気やガスだけでなく、ボイラーや工場の熱供給設備、船舶・車両の燃料も、低炭素な代替燃料への移行が進んでいます。
- バイオマス燃料(木質ペレット、廃棄物系燃料)木材チップや食品廃棄物などの有機物を燃焼させることでエネルギーを得る仕組みです。
石炭を使用していた発電所や工場が、木質ペレットやパーム油由来の燃料を混焼することで、CO₂排出量を削減する動きが広がっています。

- 合成燃料(e-Fuel)の導入水素とCO₂を化学的に合成して作られる「e-Fuel(合成燃料)」は、従来の化石燃料を利用していた機械やエンジンにも適用可能で、航空機や船舶、自動車分野での活用が期待されています。

- SAF(持続可能な航空燃料)航空業界では、SAF(Sustainable Aviation Fuel)が普及しつつあり、植物由来の油や廃棄物から生成される燃料が従来のジェット燃料と比較してCO₂排出量を最大80%削減するとされています。

このような再生可能燃料の普及により、工業・輸送業界における脱炭素化が加速しています。
3. 水素エネルギーの普及と実用化
水素は、燃焼時にCO₂を排出しない次世代のエネルギー源として注目されています。政府も「水素社会」の実現を目指し、製造・供給・利用のインフラ整備を進めています。
- グリーン水素とブルー水素再生可能エネルギーを利用して製造される「グリーン水素」、CCUS技術でCO₂を回収する「ブルー水素」があり、企業の選択肢が広がっています。
- 水素燃料電池の活用オフィスや工場では、水素燃料電池を導入することで、発電と熱供給を同時に行うことが可能になっています。
- 水素エネルギー輸送と供給網の拡大日本では海外からの水素輸入を前提としたサプライチェーンの構築が進んでおり、2030年以降の本格的な普及が見込まれています。


まとめ
電力自由化により、企業は最適な電力会社を選択できるようになりましたが、料金プランの多様化や市場の変動により、適切な選択が難しくなっています。
大手電力会社は安定供給が強みですが、価格競争力に欠ける傾向があります。
一方、新電力は低価格や再生可能エネルギープランを提供していますが、経営リスクを伴うため、慎重な比較が必要です。
電力契約は単なるコスト削減だけでなく、脱炭素経営やESG投資の観点からも重要であり、再生可能エネルギーやカーボンオフセットの活用が求められます。
また、電気以外のエネルギー自由化も進んでおり、都市ガス、バイオマス燃料、水素などの低炭素エネルギーへの移行が可能になっています。
企業は、供給の安定性や契約条件、環境負荷の低減を考慮しながら、持続可能なエネルギー戦略を構築することが重要です。

監修:株式会社totoka
最適な料金プランの選択や供給会社の変更を提案。
エネルギーコストを削減するサービスを提供しています
診断は無料で、電気のみならず、ガス、灯油、重油、設備の保守費用などの削減も可能です。
▼電気料金削減をご検討の方はこちら

