企業ガバナンスを強化する様々な委員会の種類について

現代の企業経営は、サステナビリティ、リスク管理、ガバナンス強化など、かつてないほど専門的で複雑な課題に直面しています。
多くの企業では、これらの課題に対応するために様々な「専門委員会」が設置されていますが、それぞれの役割や責任範囲が曖昧であったり、委員会同士の連携が取れていなかったりするケースも少なくありません。
自社の委員会は果たして本当に機能しているのでしょうか。
本記事では、まず専門委員会がなぜ組織運営に不可欠なのか、その基本的なメリットを解説します。
その上で、「ガバナンス」「リスク」「サステナビリティ」「コンプライアンス」「倫理」といった、現代経営を支える主要な委員会を取り上げ、それぞれの具体的な役割と機能を一つひとつ丁寧に紐解いていきます。
自社のガバナンス体制を深く理解し、その実効性を高めるための実践的な指針として、ぜひご活用ください。

専門委員会設置の重要性と利点
専門委員会はなぜ必要?組織を強くする5つのメリットを徹底解説
現代の組織運営は、一人のリーダーや一つの部署だけでは対応しきれないほど、複雑で専門的な課題に満ちています。
このような状況で、より的確な判断を下し、持続的に成長していくために不可欠な仕組みが「専門委員会」です。
専門委員会とは? – 組織の「知恵袋」であり「羅針盤」
専門委員会とは、簡単に言えば「特定のテーマについて、社内外の専門家が集まって議論し、組織の意思決定をサポートするチーム」のことです。
財務、法務、技術、環境、倫理など、様々なテーマに応じて設置され、組織が正しい方向に進むための「知恵袋」や「羅針盤」のような役割を果たします。
専門委員会を設置する5つの大きなメリット
専門委員会を設置することで、組織は以下のような強力なメリットを得ることができます。
メリット①:意思決定の質が格段にアップする
専門家がそれぞれの知見を持ち寄って多角的に議論することで、一つの部署だけでは見過ごしがちな論点にも光が当たり、より質の高い、バランスの取れた意思決定が可能になります。
【例:医療機関の倫理委員会】 医師だけでなく、看護師、法律家、一般市民など、様々な立場の委員が参加することで、患者の人権や医療の質に関するより適切な判断に繋がります。
メリット②:組織の「透明性」と「信頼」が高まる
「なぜその決定が下されたのか」というプロセスが委員会での議論を通じて明確になり、議事録などで文書化されます。
これにより、経営の透明性が高まり、株主や顧客、従業員といったステークホルダー(利害関係者)への説明責任を果たしやすくなり、組織全体の信頼性向上に貢献します。
メリット③:組織全体が「学習」し、成長する
委員会は、部署の垣根を越えた知識共有の場としても機能します。
定期的な活動を通じて、メンバー間で最新の情報やノウハウが交換され、組織全体の専門性や問題解決能力の向上に繋がります。
【例:企業の技術開発委員会】 研究開発部門と製造部門の専門家が知見を共有することで、より実現可能性の高いイノベーションが生まれやすくなります。
メリット④:未来の「リスク」を先回りして防ぐ
各分野の専門家がそれぞれの視点で潜在的なリスクを洗い出すことで、問題が大きくなる前に、早期に特定し対策を打つことができます。
【例:コンプライアンス委員会】 法務、人事、財務などの専門家が法令遵守上の課題を検討し、組織を法的なリスクから守ります。
メリット⑤:会社の「持続的な成長」を支える
目先の利益だけでなく、中長期的な視点から組織の進むべき方向性を検討し、戦略的な提言を行います。これにより、組織の持続可能な成長を力強くサポートします。
【例:環境委員会】 将来の環境規制や社会の要請を見据えた戦略を立てることで、組織の長期的な競争力を強化します。
専門委員会を成功させるための3つの秘訣
これらのメリットを最大限に引き出すためには、ただ委員会を設置するだけでは不十分です。
- 目的と権限をハッキリさせる: 「何のために集まり、どこまでの範囲で意思決定に関与するのか」を明確に定めます。
- 最高のチームメンバーを集める: 必要な専門知識を持つ人を、社内外からバランス良く選びます。
- 定期的に活動を振り返り、改善する: 委員会自体も「これでいいのか?」と常に活動内容を評価し、より効果的な運営を目指して改善を続けることが重要です。
専門委員会は、単なる会議体ではありません。
適切に設計・運営することで、組織をより賢く、強く、そして持続可能なものへと導く、非常にパワフルなツールなのです。
各種専門委員会の役割
ガバナンス委員会とは?経営の「健全性」を守る監督機関の役割を解説
企業の不祥事が後を絶たない中、経営の「暴走」や「独りよがり」を防ぎ、社会からの信頼を得ながら持続的に成長していくためには、経営を客観的にチェックする仕組みが不可欠です。
その中心的な役割を担うのがガバナンス委員会(Governance Committee)です。
ガバナンス委員会は、会社の経営が健全かつ公正に行われているかを監督する、いわば「経営の審判役」。
1. ガバナンス委員会の基本的な役割 – 経営の「審判」であり「コーチ」
ガバナンス委員会の最も基本的な役割は、経営陣の意思決定が適切な手続きに則り、会社全体の利益に繋がっているかを客観的な立場でチェックすることです。
重要な投資や事業再編といった会社の未来を左右する決定が、思いつきや一部の人の利益のためになされていないか、リスクと機会が正しく評価されているかなどを厳しく検証します。
ただチェックするだけでなく、より良い経営になるよう改善を提言することから、時には「コーチ」のような役割も担います。
2. ガバナンス委員会が監督する6つの重要エリア
ガバナンス委員会の監督範囲は多岐にわたります。ここでは、特に重要な6つのエリアをご紹介します。
① 経営のブレイン「取締役会」は機能しているか?
会社の最重要事項を決定する取締役会が、活発な議論の場としてきちんと機能しているかを評価します。
メンバー構成は適切か、社外取締役が独立した立場で意見を言えているか、多様な視点が取り入れられているかなどをチェックし、改善を促します。
② 経営陣への「報酬」は適切か?
経営陣の報酬が、会社の長期的な成長や企業価値の向上ときちんと連動しているかを検証します。
お手盛りにならず、透明性の高いプロセスで決められているかもしっかり監督します。
③ 会社の「ルール」は守られているか?
コンプライアンス(法令遵守)やリスク管理、情報開示といった、会社の土台となる内部統制システムが正しく整備・運用されているかを定期的に評価します。
④ 未来への投資「サステナビリティ」は進んでいるか?
環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)といったESGへの取り組みが、単なるスローガンで終わらず、具体的に実行され、長期的な企業価値向上に貢献しているかを評価します。
⑤ 社会との「対話」はできているか?
株主、従業員、取引先、地域社会といったステークホルダー(利害関係者)とのコミュニケーションが適切に行われ、その声が経営に反映されているかを確認します。
特に、株主との建設的な対話(エンゲージメント)は重要な監督項目です。
⑥ 会社の「重要決定」は妥当か?
冒頭で触れたように、大規模な投資やM&Aといった個別の重要案件の意思決定プロセスが、客観的かつ合理的であるかを監督します。
3. 強いガバナンス委員会をつくるための条件
委員会がその役割を最大限に果たすためには、以下の3つの条件が不可欠です。
- 独立性と専門性 経営陣から独立した立場を保ち、忖度なく意見を述べられることが大前提です。
また、経営、法務、財務など、多様な分野の専門知識を持つメンバーで構成することが重要です。 - 継続的な学びと改善 委員自身が定期的な研修で知識をアップデートしたり、外部の専門家の知見を取り入れたりしながら、常に委員会としての機能を強化していく姿勢が求められます。
- 透明性の確保 委員会の活動内容をきちんと記録し、定期的に取締役会へ報告します。
さらに、その概要を株主総会や統合報告書などで社外に開示することで、経営の透明性を高め、社会からの信頼に繋げます。
ガバナンス委員会は、単なる「お目付け役」ではありません。
会社の健全な成長を促し、社会からの信頼を確保することで、長期的な企業価値を高めるための重要なパートナーなのです。

▼出典:コーポレートガバナンスに関する各種ガイドラインについて
リスク委員会とは?企業の未来を守る「危機管理の司令塔」の役割を解説
現代のビジネス環境は、市場の変動、サイバー攻撃、気候変動、地政学的な緊張など、予測不能なリスクに満ちています。
このような不確実性の高い時代において、企業が持続的に成長していくためには、起こりうる危機を事前に察知し、備えるための「危機管理の司令塔」が不可欠です。
その中心的な役割を担うのが、リスク委員会(Risk Committee)です。
1. リスク委員会の基本的な役割 – 組織の「健康診断」と「防災訓練」
リスク委員会の基本的な役割は、組織全体のリスクを管理する仕組みを整え、運営することです。
これは、人間でいう「健康診断」と「防災訓練」に例えることができます。
- リスクの「健康診断」:特定と評価 まず、組織がどのようなリスクに直面しているかを体系的に洗い出します。
これには、市場の変動や信用問題といった伝統的なリスクだけでなく、近年重要性を増している気候変動リスク、サイバーセキュリティ、企業の評判(レピュテーション)に関わるリスクといった、新しいタイプのリスクも含まれます。 - 有事への「防災訓練」:危機管理体制の整備 自然災害、大規模なシステム障害、不祥事といった重大な危機が現実に発生した際に、組織が混乱なく迅速に行動できるよう、事前に対策を講じます。
具体的には、事業継続計画(BCP)を策定・更新し、定期的な訓練を通じて、いざという時に本当に機能するかを確認します。
2. リスク委員会が担う3つの戦略的ミッション
リスク委員会は、守りだけでなく、企業の成長を支える戦略的なミッションも担っています。
ミッション①:「攻め」と「守り」のバランスを決める
ビジネスにリスクはつきものです。リスク委員会は、ただリスクを避けるだけでなく、「企業の目標達成のために、どこまでリスクを取って挑戦するべきか」という基準(リスクアペタイト)を明確にします。
これにより、無謀な挑戦を避ける「守り」と、成長機会を逃さない「攻め」の最適なバランスを取ることが可能になります。
ミッション②:全社に「リスクのアンテナ」を張り巡らせる
リスクの兆候は、組織の様々な場所に現れます。
- 情報ネットワークの構築: 社内外からリスクに関する情報を効率的に集め、分析し、経営陣が迅速な意思決定を下せるように報告する体制を築きます。
- リスクカルチャーの醸成: 全従業員が「自分たちの仕事にどんなリスクがあるか」を常に意識し、問題があればすぐに報告できるような、オープンな組織文化を育むための教育や研修を行います。
ミッション③:グループ全体を「一つの船」として守る
子会社や海外拠点を持つ企業にとって、グループ全体のリスクを統合的に管理することは非常に重要です。
リスク委員会は、各国の法律やビジネス習慣の違いを考慮しながら、グループ全体としての一貫したリスク管理体制を構築し、船全体の安全を確保します。
3. リスク委員会を最強の「司令塔」にするための条件
委員会がその機能を最大限に発揮するためには、以下の3つの要素が不可欠です。
- 権限と独立性 経営陣から独立した立場で、忖度なくリスクを指摘し、改善を提言できるだけの適切な権限が与えられていること。
- 専門性と多様性 リスク管理に関する高度な専門知識を持つメンバーがいること。
また、客観的な視点を取り入れるために、外部の専門家と連携することも非常に有効です。 - 連携と報告 取締役会や監査委員会といった他の重要な組織と密に連携し、常に情報を共有することで、組織全体のガバナンスを強化します。
リスク委員会は、単に問題が起きた後に対処する部署ではありません。
未来を予測し、潜在的な危機から企業を守り、持続的な成長を可能にするための戦略的な頭脳であり、まさに企業の未来を左右する「危機管理の司令塔」なのです。

▼出典:経済産業省 リスクマネジメントの必要性
サステナビリティ委員会とは?企業の未来を創る「成長エンジン」の役割を解説
現代の企業経営において、「サステナビリティ(持続可能性)」は、もはや単なる社会貢献活動ではありません。
企業の成長と存続に直結する、経営そのものの核心的なテーマとなっています。
この重要な取り組みを全社的に推進し、具体的な形にしていく司令塔がサステナビリティ委員会(Sustainability Committee)です。

1. サステナビリティ委員会のミッション – 未来への羅針盤を描く
サステナビリティ委員会の最も重要なミッションは、企業の持続的な成長と、社会・環境への責任を両立させるための戦略(羅針盤)を描き、その実行をリードすることです。
その際、国際的な目標であるパリ協定(気候変動対策の枠組み)やSDGs(持続可能な開発目標)などを道しるべとしながら、自社ならではの戦略を立てていきます。
具体的には、世界的に重要視されている「ESG」の3つの側面から、目標と実行計画を策定・監督します。
- E (Environment:環境):地球環境への責任
- S (Social:社会):人や社会との関わりにおける責任
- G (Governance:ガバナンス):健全で透明性の高い経営体制

2. サステナビリティ委員会が取り組む主な活動領域
ESGの3つの側面において、委員会は以下のような多岐にわたる活動を推進します。
地球環境(Environment)を守る
- 気候変動対策:2050年カーボンニュートラルに向けたGHG(温室効果ガス)排出削減目標の設定と、その実現に向けたロードマップの作成。
- 再生可能エネルギーの導入: 自社で使う電力を再エネに切り替える計画の推進。
- 資源循環(サーキュラーエコノミー)の促進: 廃棄物を減らし、資源を繰り返し使う仕組みの構築。
- 生物多様性の保全: 事業活動が生態系に与える影響を評価し、保護に取り組む。


人・社会(Social)を豊かにする
- 働きがいのある職場づくり: 従業員の健康と安全の確保、人材育成、多様性(ダイバーシティ&インクルージョン)の推進。
- 人権の尊重: サプライチェーン(製品の原材料調達から消費者に届くまでの一連の流れ)全体で、強制労働や児童労働などの人権侵害がないかを確認・是正する(人権デューデリジェンス)。
- 地域社会との共生: 事業を行う地域社会への貢献活動。
信頼される経営(Governance)を築く
- 透明性の高い情報開示: TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)などの国際的なルールに基づき、サステナビリティへの取り組み状況を投資家や社会に分かりやすく報告する。
- ステークホルダーとの対話: 投資家(特にESG投資家)、従業員、顧客、NGOなど、様々な関係者との対話を通じて、経営戦略に意見を反映させる。

3. 守りから攻めへ – サステナビリティを「競争力」に変える
サステナビリティ委員会は、単にリスクを管理する「守り」の組織ではありません。企業の競争力を高める「攻め」の役割も担います。
- 新たなビジネスチャンスの創出: 環境問題や社会課題を解決するような技術開発や新しいビジネスモデルの創出を支援し、企業の新たな収益源に繋げます。
- サプライチェーン全体の価値向上: 取引先と協力して環境負荷の低減や人権尊重に取り組むことで、サプライチェーン全体の強靭化とブランド価値向上を図ります。
- 気候変動リスクを成長の糧に: 規制強化などの「移行リスク」や、自然災害などの「物理的リスク」を分析し、それに適応できる事業戦略を立てることで、変化に強い企業体質を構築します。
4. サステナビリティ委員会を成功に導く3つの鍵
この重要な委員会が効果的に機能するためには、以下の3つが不可欠です。
- 経営トップの強い意志 経営陣がサステナビリティを最重要課題と位置づけ、委員会に十分な権限とリソース(予算・人員)を与えることが成功の絶対条件です。
- 多様な専門家からなるチーム 環境、社会、ガバナンスなど各分野の社内専門家に加え、客観的な視点を持つ外部有識者をメンバーに迎えることで、議論の質が高まります。
- PDCAの実践 計画(Plan)を立て、実行(Do)し、その進捗を評価(Check)して、改善(Act)するというPDCAサイクルを確実に回し続けることで、目標達成へと繋がります。
サステナビリティ委員会は、企業の目先の利益だけではなく、10年後、50年後の未来を見据えて活動する組織です。
その活動を通じて、企業自身の持続的な成長と、社会全体の持続可能な発展を両立させるという究極の使命を担っているのです。
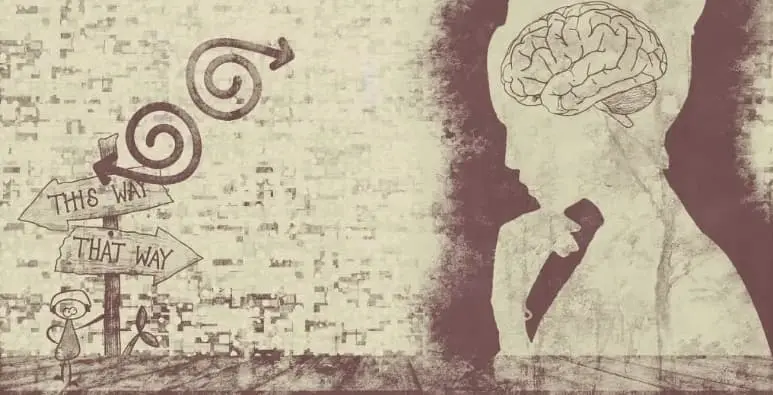

※弊社(株式会社TBM)のサステナビリティ委員会での取り組み
コンプライアンス委員会とは?企業の「信頼」を守る番人の役割を徹底解説
企業活動において、「知らなかった」では済まされない法令違反や不祥事。一つの問題が、長年かけて築き上げた企業の信頼を瞬時に失墜させることもあります。
こうしたリスクから組織を守り、持続的な成長を支えるために不可欠な存在がコンプライアンス委員会(Compliance Committee)です。
コンプライアンス委員会は、単に法律を守るだけでなく、社会の期待や倫理観に応えるための「守りの要」です。
1. コンプライアンス委員会の基本的な仕事 – ルールを守り、育てるサイクル
コンプライアンス委員会の基本的な活動は、以下の3つのサイクルを回し続けることです。
- 体制を「つくる」 法律や社会規範に基づき、全従業員が守るべき行動基準を明確にしたコンプライアンス・マニュアルや行動規範を作成します。また、不正を早期に発見するための内部通報制度を整備・運営することも重要な役割です。
- リスクを「見つける」 事業活動に関わる法規制の変更などを常に監視し、「自社にとって何がリスクになるか」を事前に特定・評価します。特に海外展開する企業にとっては、各国の法律や商習慣の違いを理解した、きめ細やかなリスク評価が求められます。
- 意識を「育てる」 全従業員に対し、コンプライアンスに関する知識と意識向上のための教育・研修を企画・実施します。実際の事例を用いたケーススタディなどを通じて、「自分ごと」として理解を深めてもらうことが重要です。
2. コンプライアンス委員会が担う3つの重要ミッション
基本的な活動に加え、委員会はよりダイナミックなミッションを担います。
ミッション①:不正を「未然に防ぐ」ための仕組み作り
問題が起きてから対処するのではなく、そもそも問題が起きない環境を作ることが最も重要です。
- 定期的なモニタリング: 定期的な監査や点検を通じて、社内のコンプライアンス体制がきちんと機能しているかを確認し、改善します。
- サプライチェーン管理: 自社だけでなく、取引先や委託先のコンプライアンス体制も確認し、サプライチェーン全体でのリスク低減を目指します。
ミッション②:問題発生時に「正しく対処する」危機管理
万が一コンプライアンス違反が発生してしまった場合、組織として迅速かつ適切に対応する司令塔の役割を担います。
- 調査と原因究明: 事実関係を正確に調査し、なぜ問題が起きたのかを徹底的に究明します。
- 是正措置と再発防止: 具体的な改善策を立てて実行し、二度と同じ過ちを繰り返さないための仕組みを構築します。
重大な事案では、経営陣への報告や社会への情報開示の判断も行います。
ミッション③:時代に合わせた「未来への備え」
ビジネス環境の変化に対応し、新たなリスクに備えます。
- 重要分野への対応: 贈収賄防止、独占禁止法などの競争法遵守、個人情報保護(GDPRなど海外の法規制も含む)といった、特にリスクの高い分野について専門的な対策を講じます。
3. コンプライアンス委員会を強くする3つの力
委員会が効果的に機能するためには、以下の3つの力が不可欠です。
- 経営トップの「本気度」 経営陣がコンプライアンスを最重要課題と位置づけ、委員会に適切な権限とリソースを与えることが全ての出発点です。
- 部門間の「連携力」 法務、人事、内部監査といった関連部署と密に連携し、会社全体で取り組む体制を築くことが重要です。
- 外部の「知見」を取り入れる力 自社の常識にとらわれず、外部の専門家の意見を取り入れたり、世界の先進事例(グローバルベストプラクティス)を学んだりしながら、常に活動を評価・改善していく姿勢が求められます。
コンプライアンスは、時にコストや手間のかかる活動と捉えられがちです。
しかし、それは企業の持続的な成長と社会からの信頼を確保するための、最も重要な「投資」と言えるでしょう。
コンプライアンス委員会は、その投資価値を最大化するための中心的な役割を担っているのです。

倫理委員会とは?企業の信頼を支える「倫理の羅針盤」の役割を徹底解説
ビジネスの世界では、利益の追求だけでなく、社会的な「正しさ」も強く求められます。
しかし、技術の進化やグローバル化が進む現代において、何が「倫理的に正しい」のかを判断するのは容易ではありません。
そこで重要な役割を担うのが倫理委員会(Ethics Committee)です。
倫理委員会は、単にルール違反を取り締まるだけでなく、組織が進むべき方向を示す「倫理の羅針盤」として機能します。
1. 倫理委員会の基本的な役割 – 「組織の良心」としての指針作り
倫理委員会の最も中核的な役割は、組織全体が従うべき「倫理的な判断基準」を作り、その運用をサポートすることです。日々の業務で発生するであろう、白黒つけがたい問題に対して、公平で客観的な指針を提供します。
- 複雑な問題への指針提示:利益相反: 社員の個人的な利益と会社の利益が衝突しないか?個人情報保護: 顧客や従業員のプライバシーをどう守るか?研究倫理: 新製品開発における安全性や人道的な配慮は十分か?
特に、人の生命や尊厳に関わる臨床研究や生命倫理の分野では、被験者の権利を守り、研究内容を十分に説明して同意を得る(インフォームド・コンセント)など、極めて厳格な審査が求められます。
2. 倫理委員会が取り組む、現代ならではの重要テーマ
倫理委員会が向き合う課題は、時代と共に変化・拡大しています。
- AI・ビッグデータなど新技術の倫理 技術の急速な発展は、プライバシー侵害やアルゴリズムによる差別といった新たな倫理的課題を生み出します。
倫理委員会は、これらのリスクを事前に特定し、技術を公正に活用するためのガイドラインを策定します。 - グローバルなビジネス倫リ 海外で事業を展開する際には、国や地域によって異なる文化や価値観を尊重しつつ、人権や環境保護といった普遍的な価値観に基づいた一貫した倫理基準を維持する必要があります。
- 組織文化の醸成 ルールを作るだけでなく、研修や具体的な事例研究を通じて、従業員一人ひとりの倫理観を高めることも重要な役割です。
倫理的な行動が当たり前となる組織文化を育むことで、問題の未然防止に繋がります。
3. 倫理委員会を正しく「機能させる」ための仕組み
倫理委員会が形骸化せず、実効性のある組織として機能するためには、いくつかの重要な仕組みが必要です。
- 多様なメンバー構成 判断が偏らないよう、内部の専門家だけでなく、法律家や研究者、市民代表といった外部の有識者を加えることが極めて重要です。
多様な視点を取り入れることで、より客観的で公正な結論を導き出せます。 - 誰もが安心して「声」をあげられる報告体制 従業員が職場で倫理的な懸念を感じた際に、不利益を被る心配なく安心して報告できる内部通報制度のような仕組みが不可欠です。
報告者のプライバシーを厳守し、寄せられた情報に対して迅速かつ公正な調査を行う体制を整えます。 - 社会の変化に対応する「見直し」機能 社会の価値観や法律は常に変化します。
そのため、定期的に倫理監査を行い、組織の活動が倫理基準に適合しているかを確認すると同時に、倫理基準そのものが時代に合っているかを見直し、継続的に改善していく姿勢が求められます。
4. なぜ倫理委員会は企業の「価値」になるのか?
倫理委員会の活動は、コンプライアンス違反を防ぐという「守り」の側面だけではありません。
むしろ、これからの時代においては企業の価値を創造する「攻め」の基盤となります。
倫理的な経営を徹底することは、顧客、取引先、従業員、そして投資家といった、あらゆるステークホルダーからの社会的信頼を獲得することに直結します。
高い倫理観を持つ企業として認知されれば、それは強力なブランド価値となり、優秀な人材の確保や長期的な競争力強化にも繋がります。
単なる「ルール遵守」の部署ではなく、組織の持続的な成長と社会的価値の創造を支える重要な存在として、倫理委員会の役割はますます大きくなっていくでしょう。
まとめ
各種委員会の種類と役割について言及してきましたが、自社にどういった委員会が設置されているかを全て把握できているでしょうか。
サステナビリティ委員会は、新規に設置されるケースが多いですが新規に設置される委員会と既存の委員会と連携が取れていない場合があるという話を聞くことは多くあります。
特にリスクについては、どの委員会でも扱う項目になっていますが、既存の委員会と連携することで業務が重複していないか、効率的な委員運営ができないかという視点を持つことが重要になってきています。
