脱炭素戦略に地熱を:企業が注目すべき地熱発電の最新動向と導入事例

エネルギーの安定供給と気候変動対策が同時に求められる今、地熱発電の存在価値があらためて注目されています。
再生可能エネルギーと聞けば、太陽光発電や風力発電を思い浮かべる方が多いかもしれません。
しかし、これらは天候や時間帯に出力が左右される「変動電源」であることが大きな課題です。
その一方で、天候に依存せず、24時間365日安定して電力を供給できるのが地熱発電の最大の強みです。
特に、製造業やデータセンターといった電力消費の大きな業種では、再エネポートフォリオの一環として地熱電力を導入する動きが加速しています。
日本政府もこうした背景を受け、地熱開発の促進に向けて支援制度を拡充し、温泉資源との共生や中小規模のバイナリー発電導入を後押ししています。
本記事では、地熱発電の仕組みから導入事例、最新技術、環境影響、政策動向について解説します。
企業のサステナビリティ戦略に地熱をどう組み込むべきか、その判断に役立つ情報をお届けします。

地熱発電の基本的な仕組み
地熱発電の原理
地熱発電は、地中深くに存在するマグマの熱エネルギーを利用して電力を生み出す再生可能エネルギーの一種です。
地下に掘削した井戸から高温の蒸気や熱水を取り出し、その蒸気の力でタービンを回転させて発電を行います。
この熱源は、プレート境界付近に集中する「火山性地帯」に多く存在し、日本のような火山国では、比較的浅い地層に数百度の高温資源が存在するという地理的優位性があります。
また、発電に使用した蒸気や熱水は、再び地下へ戻す(リインジェクション)ことで、地熱資源の枯渇や環境影響を防ぐ仕組みが整備されています。
これにより、持続的かつ循環的なエネルギー供給が可能となり、CO₂排出を最小限に抑えるクリーンな電源として機能します。
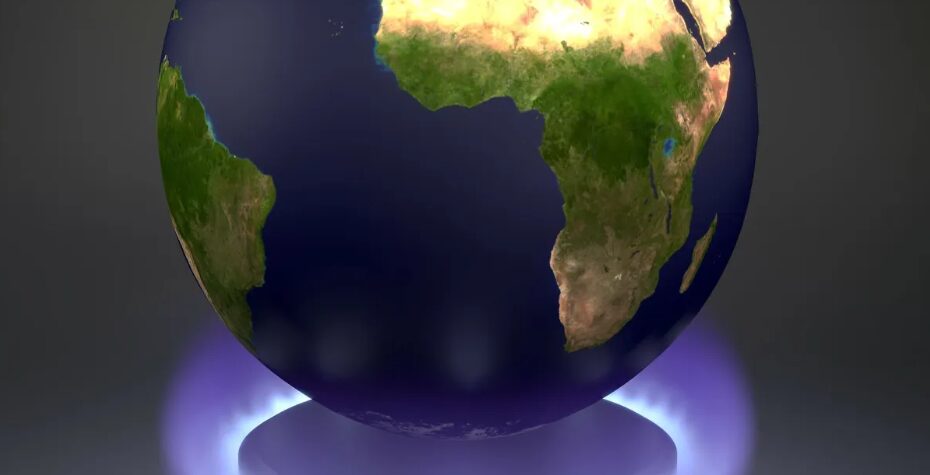

地熱発電の主な方式
地熱発電は、地熱資源の状態や温度帯に応じて、以下の3つの代表的な方式に分類されます:
■ ドライスチーム方式
蒸気が地下から直接噴出する非常に希少な地熱資源に適用されます。
蒸気をそのままタービンに送るためシンプルで効率が高いものの、利用可能な場所が限定されるのが課題です。
■ フラッシュ方式(単純/二重)
高温高圧の熱水を減圧して蒸気を発生させる方式で、日本の大規模地熱発電所でも多く採用されています。
さらに、残った熱水を再度減圧して追加の蒸気を得る「二重フラッシュ方式」により、発電効率を高めることも可能です。
■ バイナリー方式(ORC:有機ランキンサイクル)
80~150℃程度の中低温の熱資源でも発電できる方式です。熱水で沸騰しやすい作動流体(イソブタンなど)を加熱し、その蒸気でタービンを回す仕組みで、環境負荷が小さく、温泉地や小規模事業向けに適した形式です。
国内でも新設プロジェクトの多くがこの方式を採用しています。
注目される次世代技術
従来の地熱発電は「蒸気や熱水が自噴する場所」に限定されていましたが、近年は以下のような新技術の登場により、開発可能地域が飛躍的に広がっています:
- EGS(改良型地熱システム):人工的に地下へ水を注入し、亀裂を形成して熱を回収する手法。地下に熱はあるが水がない地域でも発電可能。
- クローズドループ方式:地下に密閉されたU字管などを設置し、地中の熱で循環流体を加熱して発電する。地下水と接触せず、温泉や環境への影響が少ない。
- 超臨界地熱発電:地下3〜5km以深に存在する超高温流体(約400℃以上)を利用する技術。1本の井戸で従来の数倍の出力を目指す先進分野。
れらの技術革新により、地熱発電はもはや「一部の地域だけのニッチな電源」ではなく、あらゆる地域で安定供給を担う可能性を秘めた主力再エネへと進化を遂げつつあります。

地熱発電のメリット
環境への影響
地熱発電は、温室効果ガス排出が極めて少ないことから、環境に優しい再生可能エネルギーとして高く評価されています。
一般的な火力発電と異なり、化石燃料を燃焼させる工程がなく、発電中のCO₂排出量は太陽光・風力と並んで最小クラスです。
国際的なライフサイクルアセスメント(LCA)の比較によると、地熱発電のCO₂排出量は1kWhあたりおよそ15〜50g程度にとどまり、天然ガスの10分の1以下、石炭火力の50分の1以下と報告されています。

また、多くの地熱プラントでは、使い終わった蒸気や熱水を地下へ再注入する「リインジェクション」方式を採用しており、資源の枯渇や地盤沈下などのリスクを最小限に抑える構造が整っています。
バイナリー方式など密閉循環型のシステムでは、排出ガスが実質ゼロになるケースも珍しくありません。
さらに、地表で必要とする面積が小さいのも利点です。
1TWhの電力を供給するのに必要な土地面積は、太陽光発電の約1/10以下とされ、自然環境や生態系への物理的影響が少ないエネルギーといえます。
ただし、地熱開発に際しては、温泉資源との競合や誘発地震などの課題も存在します。
これらに対しては、地質調査やモニタリングの高度化、ステークホルダーとの協議プロセスを通じてリスク管理が進められており、環境との共生に向けた制度整備も日本を含む各国で進行中です。


▼出典:「CO2排出量」を考える上でおさえておきたい2つの視点
経済的な効果
地熱発電は、長期的に安定した収益性を見込めるエネルギー資源として、経済面でも注目を集めています。
その最大の特徴は、高い設備利用率(70〜90%)と、燃料費ゼロの運用構造にあります。
一度開発が完了すれば、発電にかかる燃料コストはほぼ不要。
さらに、適切に管理された地熱井は30年〜50年以上稼働可能で、長期にわたり安定した電力供給とキャッシュフローが見込めます。
一例として、アメリカ・カリフォルニア州の「The Geysers」では、1960年代に開発された井戸が現在も現役で稼働中です。
加えて、地熱は天候や市場価格の影響を受けにくく、電力価格の変動リスクに対するヘッジ手段にもなります。
これは、長期の電力購入契約(PPA)を締結したい企業にとって極めて魅力的な特性です。
実際、GoogleやMicrosoftなどのグローバル企業は、24/7クリーン電力調達の一環として地熱電力を調達し始めています。
また、地熱発電は発電だけでなく熱の直接利用が可能な点でも経済的な利点があります。
工場のボイラー用熱源、農業温室の暖房、水産養殖など、熱を無駄なく利用できる産業分野での応用が広がっており、コージェネレーション(二重利用)による付加価値創出も期待されます。
初期投資額が大きく、掘削にリスクを伴う点は否めませんが、政府のリスク補償制度や補助金、固定価格買取制度(FIT)の活用により、近年は開発コストの低減も進んでいます。
実際、日本やインドネシアなどでは、探査段階の費用を公的機関が負担するスキームが整備され、民間企業の参入ハードルが下がりつつあります。

地熱発電のデメリット
地震との関係
地熱発電、とくに改良型地熱システム(EGS)や大量の地下水循環を伴うプロジェクトでは、まれに「誘発地震(誘発性地震)」のリスクが指摘されます。
これは、地下深部への注水や熱水の汲み上げによって地圧が変化し、断層が刺激されることで地震が発生する可能性があるものです。
過去には2017年、韓国・浦項のEGS実証事業においてM5.4の地震が発生し、発電所との関連性が科学的に指摘されました。
この件は地熱業界に大きな衝撃を与え、各国での地質調査や運用ガイドラインの見直しが進むきっかけとなりました。
日本でも地震との因果関係を懸念する声が一部ありますが、実際の発電事業において有感地震が頻発している事例は極めて少数です。
特に、従来型のフラッシュ方式やバイナリー方式では、発生するマイクロ地震は地殻変動の範囲内にとどまるとされ、「監視可能で管理できるレベルにある」との専門見解も出ています。
現在では、プロジェクト開始前に断層分布や地圧を3Dで解析する地質リスク評価が義務づけられ、運用中もマイクロ地震のリアルタイム監視が標準化されつつあります。
つまり、技術と管理体制が整えば、誘発地震リスクは適切に抑えられるというのが国際的なコンセンサスです。

▼出典:日本地熱協会とは?
発電効率の課題
地熱発電は「出力が安定している」というメリットがある一方で、発電効率が他の発電方式と比較してやや劣るという指摘もあります。
これは、地下から得られる熱エネルギーの温度に制限があるためです。
たとえば、蒸気タービン方式(フラッシュ型)で利用される蒸気は200℃〜300℃前後のことが多く、これに対し化石燃料を用いる火力発電所では1,000℃を超える高温蒸気が使用されるため、熱効率(熱→電気への変換効率)では火力の方が高くなります。
特に、中低温地熱資源を活用するバイナリー方式では、使用する作動流体の特性上、発電効率が10〜15%程度にとどまる場合もあります。
ただしこれは熱源をムダなく使うという発想に基づく設計であり、熱水の段階的な利用(ダブルフラッシュ・排熱利用)により改善可能です。
また、発電効率は単純な数字だけで比較すべきではありません。
地熱は燃料調達コストがゼロである点、長寿命(30〜50年)で設備を使える点など、ライフサイクル全体で見たエネルギー収支(EROI:Energy Return on Investment)はむしろ高水準とする評価もあります。
設置場所の制約と開発期間の長さ
地熱発電は「24時間安定供給が可能な再生可能エネルギー」という強みを持つ一方で、適切な地質条件を備えた地域が限られているという地理的制約があります。
特に、高温の熱水や蒸気が浅い地盤で得られる火山帯やプレート境界付近に資源が集中しており、利用可能なサイトは一部に限られます。
さらに日本では、貴重な資源の大半が国立・国定公園や温泉地帯に位置しているため、従来は厳しい法規制や景観保護の観点から開発が難航してきました。
たとえば、自然公園法による許認可手続きの複雑さや、温泉業界との調整に要する時間が長く、事業開始までに5年〜10年を要するケースも珍しくありません。
現場調査、掘削調査、地元説明会、環境アセスメントといった各フェーズを経るごとにリードタイムが積み重なり、開発プロジェクト全体が長期化する要因となっています。
近年は、環境省と経済産業省が連携して策定した「温泉と地熱の共生ガイドライン」により、地域合意形成のプロセスを効率化しつつ、観光資源への影響を最小限に抑えるルールづくりが進められています。
また、地方自治体単位で地熱専門官を配置し、許認可手続きのワンストップ化や早期の地元説明会開催を支援する動きも加速中です。
加えて、EGS(改良型地熱システム)やクローズドループ技術といった次世代技術の登場により、かつては適地とされなかった地域でも地熱資源を活かせる可能性が高まっています。
これらの技術は、天然の「蒸気噴出地」だけでなく、熱はあるものの水が乏しい地層や非火山地域でも発電を実現できるため、都市近郊や農山村部などにおいても開発の選択肢が広がる段階にあります。
つまり、設置場所の制約は依然として存在するものの、規制緩和と合意形成の支援制度、さらには革新的な掘削・循環技術が組み合わさることで、プロジェクトの適地選定や着工までの時間を大幅に短縮し、より多様な地域での地熱発電実現が見込まれています。

日本における地熱発電の現状について
地熱発電所の分布
日本は世界第3位の地熱資源国とされ、推定23GW(2,300万kW)超の開発可能資源量を有しています。
これは全国の総電力需要の10%以上を地熱でまかなえるポテンシャルを意味します。
しかし実際に稼働している地熱発電所は、2024年時点で20箇所程度・総出力60万kW弱にとどまっており、開発はごく一部に限られています。
立地は主に東北・九州地方の火山帯周辺に集中しています。たとえば:
- 大分県:八丁原発電所(110MW) … 日本最大の地熱発電所。中部電力・九州電力が共同出資。
- 秋田県:山葵沢発電所(46MW) … 近年開発された新しい地熱施設。
- 岩手県:松川地熱発電所(23MW) … 日本初の商業用地熱発電所(1966年運転開始)。
- 鹿児島県:霧島や姶良地域に小規模バイナリー発電所が複数 … 温泉熱を利用した地域密着型の事例。
また、1〜5MWクラスの小規模バイナリー発電所も、温泉地を中心に全国で導入が進みつつあります。
特に温泉資源と共存できる形での地熱活用が注目されており、自治体と地元企業が共同で運営するモデルも増えてきました。

普及しない理由
地熱発電の技術は確立されており、燃料費がかからない安定電源としての評価も高いにもかかわらず、日本では長年「普及が進まない再エネ」とされてきました。
その背景には、いくつかの構造的・制度的な障壁があります。
■ 温泉との競合と地域対立
日本の地熱適地の多くは、温泉地と重なっているため、地域住民や観光業者との調整が不可欠です。温泉湧出量や水質への影響を懸念する声が根強く、地熱開発に反対する動きが自治体レベルでも続いてきました。
科学的には影響が軽微または共存可能とされるケースも多いですが、「信頼の構築と対話」が不可欠です。

■ 規制と手続きの煩雑さ
地熱資源の多くは国立・国定公園内に位置し、かつては自然公園法などにより厳しく開発が制限されていました。
現在は条件付きで開発が可能となったものの、依然として事前調査・環境アセスメント・許認可手続きが複雑で長期化しやすいことが参入障壁になっています。
実際、商業運転開始までに7〜10年かかることも少なくありません。
■ 初期投資と探査リスク
地熱発電には高額な初期投資と「掘ってみないと分からない」地質リスクが伴います。
1本数億円を超える井戸を複数掘る必要があり、蒸気が得られなければ全額損失となる可能性があります。
この「ドライホール・リスク」の高さが民間投資を妨げてきた大きな要因です。
ただし、これらの課題に対し、近年はJOGMECによる掘削費全額補助や環境省・経産省の共生型ガイドラインの整備など、解決に向けた動きが強化されてきました。
社会的な関心の高まりと制度的な後押しにより、地熱の再評価が本格化しつつある段階にあります。

日本の地熱発電のポテンシャル
前述の通り、日本は火山大国かつ温泉大国であり、豊富な地熱資源を持つ世界有数の地熱大国です。
政府もこの点を踏まえ、2030年度までに地熱発電容量を約2.5倍(150万kW)に拡大する目標を掲げています。

▼出典:もっと知りたい!エネルギー基本計画④ 再生可能エネルギー(4)豊富な資源をもとに開発が加速する地熱発電
また、資源エネルギー庁の2024年8月資料「地熱発電の開発促進に向けて」では、以下のような明確なアクションが示されています:
- 「地熱モデル地区」の設置 … 適地を選定し、地域ぐるみで合意形成を図りやすい環境を整備。
- 掘削費全額支援スキームの導入 … 初期リスクを国が負担することで民間企業の参入を促進。
- 小規模地熱・バイナリー発電の拡充 … 温泉事業者や地元自治体と連携し、地域共生型の地熱利用を加速。
- 熱利用の拡大 … 発電に加え、農業・観光・工業などの地域熱源としても活用。
さらに、新技術であるEGS(改良型地熱)やクローズドループシステムが本格的に導入されれば、地熱資源の未利用エリアが一気に活用可能圏に広がる可能性もあります。
これにより、現在の火山依存から脱却し、非火山地域や都市近郊でも地熱発電が実現する未来が見えてきます。
地熱のポテンシャルは「既にある資源を活かしきれていない」という未開拓性にこそあります。
この潜在力を戦略的に活用できれば、日本のエネルギーミックスの中で地熱はより大きな役割を担うことが可能です。


地熱発電と再生可能エネルギー
再生可能エネルギーとしての地熱発電の位置づけ
地熱発電は、太陽光・風力・水力・バイオマスと並ぶ代表的な再生可能エネルギーの一つです。
その最大の特長は、出力の安定性とベースロード供給能力にあります。
太陽光や風力が「天候や時間帯に依存する変動電源」であるのに対し、地熱は365日24時間、常に一定の電力を供給できる「非変動電源」に分類されます。
これは、電力系統の安定性確保や需要予測精度の向上といった観点から、極めて重要な価値を持ちます。
加えて、地熱は国内資源に依存するクリーンエネルギーであり、化石燃料のように輸入リスクや価格変動の影響を受けないというメリットがあります。
これはエネルギー安全保障の面でも高く評価されており、「再生可能エネルギーの中でも自給率が極めて高い」点が政策的にも注目されています。
国際再生可能エネルギー機関(IRENA)やIEA(国際エネルギー機関)も、地熱を「ベースロード型の再エネとして、系統の安定化に欠かせない存在」と位置づけており、近年ではEUや米国、東南アジア諸国が、脱炭素目標達成の要として地熱を再評価しています。
また、熱供給やコージェネレーション(熱電併給)といった電力以外の活用方法もあるため、地熱は単一用途にとどまらない多用途性を持つ再生可能エネルギーともいえるでしょう。


他の再生可能エネルギーとの比較
地熱発電は、他の再生可能エネルギーと比べて特性や導入条件が大きく異なるため、役割の分担が重要です。
以下は代表的な再エネとの主な比較ポイントです。
■ 太陽光・風力との比較
- 発電安定性:
地熱は天候に左右されず、昼夜問わず出力が安定しています。一方、太陽光や風力は天候・季節・時間帯によって大きく変動し、蓄電やバックアップ電源との組み合わせが必要です。 - 利用可能時間:
太陽光は日中、風力は風がある時のみですが、地熱は24時間稼働可能。このため、企業が目指す24/7カーボンフリー電力調達の実現には、地熱が不可欠な存在になります。 - 設置面積と景観:
地熱は1kWhあたりの土地使用量が非常に小さく、景観影響も比較的抑えられます。太陽光や風力は広大な設置面積を要し、山林伐採や景観への影響が課題となることもあります。 - 導入スピードとコスト:
太陽光・風力は設置期間が短く、コストも年々下がっており、短期的な導入に向くのに対し、地熱は初期調査と掘削に時間とコストがかかるというハードルがあります。ただし、運転後は燃料費ゼロ・長寿命・高稼働率という強みで回収可能です。
■ 水力・バイオマスとの比較
- 水力は大規模開発が一巡し、新規開発の余地が限られます。一方、地熱は未利用資源が膨大に存在し、将来的な伸び代があります。
- バイオマスは燃料調達が必要であるため、地熱のような燃料フリーの構造ではありません。また、排出物や熱効率の点でも地熱が有利な場合があります。
このように、地熱は「発電の安定性」「土地利用効率」「CO₂削減効果」などの点で非常に優れた特性を持ち、他の再生可能エネルギーを補完する存在として注目されています。
特に、再エネ比率が高まるほど求められる“安定型電源”の中核を担えるのが地熱なのです。

▼出典:ISEP 2023年の自然エネルギー電力の割合(暦年・速報)
まとめ
地熱発電は、気候変動対策とエネルギー安定供給の両立を目指す現代において、企業が注目すべき有望な再生可能エネルギーです。
特に、24時間365日稼働可能な安定電源として、他の再エネでは補えないベースロード供給を担える点が大きな特長です。
さらに、CO₂排出量の少なさ、土地利用効率の高さ、長寿命・低運転コストなど、環境・経済両面で優れた特性を持ちます。
日本は世界有数の地熱資源国でありながら、開発の遅れや制度的課題によりそのポテンシャルを活かしきれていない現状がありますが、EGSやクローズドループなどの技術革新と政策支援によって、今後の加速的な普及が期待されています。
再エネ100%や24/7カーボンフリー電力を目指す企業にとって、地熱は極めて有効な戦略要素です。
今こそ、企業は地熱発電をエネルギーポートフォリオに組み込み、その可能性を最大限に引き出すべき時期に来ています。
