環境デュー・ディリジェンスとは?日本企業が今すぐ対応すべき理由と進め方を解説

地球環境の限界が叫ばれるなか、企業にも「責任ある行動」がかつてないほど強く求められています。
特に環境デュー・ディリジェンス(環境DD)は、欧州を中心に法制化が進む中で、今やグローバル企業だけの話ではなくなりました。
実際、EUのCSDDD(企業サステナビリティ・デュー・ディリジェンス指令)は、日本企業にも域外適用される可能性があり、対応を怠れば訴訟リスクや取引停止に直面する恐れもあります。
環境省もこの流れを重く見て、2025年4月に日本企業の環境DD対応促進に向けた議論を公表し、対応の具体的な方向性を提示しました。
にもかかわらず、現時点で実効的な環境DDを導入できている企業は限られているのが実情です。
この記事では、環境DDの基礎知識からプロセス、実際の企業事例、導入方法、そして今後の規制動向までを網羅的に解説します。
日本企業が環境リスクを経営にどう統合すべきか、実務的な視点から読み解きたい方に最適なガイドです。

環境デュー・ディリジェンスとは
定義と目的
環境デュー・ディリジェンス(Environmental Due Diligence:以下、環境DD)とは、企業が自社およびそのバリューチェーン全体にわたる環境への負の影響(汚染、気候変動、生物多様性の損失など)を特定・評価し、予防・軽減する責任ある行動のことを指します。
単なる法令順守を超え、国際的な規範であるOECDガイドラインや国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」などを踏まえた包括的なリスクマネジメントが求められています。
その目的は、「環境リスクを未然に把握・制御すること」にとどまらず、企業の中長期的なサステナビリティと信用の確保にも直結します。
欧州の規制強化や投資家のESG重視の潮流の中で、環境DDの実施はリスク回避策であると同時に、グローバル市場における競争力の前提条件となりつつあります。
環境デュー・ディリジェンスのプロセス
環境DDは、単一の作業ではなく、複数のステップから構成される継続的なプロセスです。
代表的な流れとしては以下のような段階があります。
- 負の影響の特定と評価
バリューチェーン上でどこに環境へのリスクが潜んでいるかを把握し、深刻度と発生可能性を分析します。 - 優先順位の設定と「適切な措置」の実施
すべてのリスクに一律対応するのではなく、深刻な問題から優先的に対応策を講じます。 - ステークホルダーとの「意味ある対話」
現地住民、NGO、従業員など利害関係者との対話を通じて、実効性のあるリスク判断と対応を図ります。 - 情報開示と苦情処理の整備
透明性の確保と被害救済の仕組みを整え、継続的な改善につなげます。
このプロセスは単なる「監査」や「評価」に留まるものではなく、企業の意思決定や戦略そのものを見直す契機でもあります。
従って、部門任せにせず、経営層が主体的に関与する体制が不可欠です。

▼出典:環境デュー・ディリジェンス対応に向けた 取組のポイントについて
環境省の環境デュー・ディリジェンス対応に向けた取組のポイントについて
2025年4月に環境省が公表した「日本企業による環境デュー・ディリジェンス対応促進に向けた懇談会 議論のまとめ」は、日本企業にとっての具体的な対応の方向性を示した重要な文書です。
特に注目すべきポイントは以下の通りです。
- リスクベースのアプローチ:すべての環境リスクに等しく対応するのではなく、重大性と発生可能性に基づいて優先順位を付けること。
- 「適切な措置」の重視:現実的な範囲で可能な行動を選択し、完璧ではなくても誠実に取り組む姿勢が重要視されています。
- 経営層のガバナンス強化:環境DDは経営課題の一部であり、取締役会レベルの議論や方針反映が求められる段階に来ています。

- 環境と人権の統合的対応:気候や汚染の問題が人権に影響を及ぼすケースも多く、部門横断的なリスク対応が必要です。
また、環境省は事例集やツールの整備にも着手しており、企業が独自に取り組むのではなく、政策的支援を受けながら実務に活かせる体制づくりも進めています。
▼出典:環境デュー・ディリジェンス対応に向けた 取組のポイントについて
日本企業における環境デュー・ディリジェンスの現状
燃料転換と持続可能性の観点からの取り組み
日本企業は、気候変動対応の一環としてエネルギー起点の環境リスクへの対策を進めてきました。
特に脱炭素化に向けた燃料転換(例:石炭からLNG・水素・バイオマスへのシフト)は、環境デュー・ディリジェンス(環境DD)の実践的アプローチの一つとして位置づけられます。
これらの燃料転換プロジェクトは、単なる設備投資ではなく、温室効果ガス排出や生態系への影響などのリスク評価と対応策が前提となるため、環境DDのフレームワークが活用されやすい分野です。

たとえば、製造業では自社のボイラー設備の脱炭素化に加え、調達先のエネルギー源を確認するプロセスを組み込みつつあり、サプライチェーン全体での「Scope3」削減の一環として取り組まれています。
ただし、現状では国内外の調達先まで踏み込んでDDを行っている企業は限られており、今後は間接排出源の管理体制を含めた広範な対応が求められます。

環境ビジネスの発展と日本企業の役割
環境DDを受け身の規制対応として捉えるのではなく、新たな事業機会と結びつけて捉える視点が、日本企業の競争力強化に不可欠です。
特に注目されているのが、「クリーン技術」や「循環型素材」、「自然資本保全」などの分野です。
これらは環境負荷を低減する製品・サービスでありながら、その供給・使用過程自体にも環境リスクが伴うため、開発段階から環境DDの導入が望まれます。
実際、再生可能エネルギーや水素インフラ、リユース・リサイクル事業を手がける日本企業の多くが、サプライヤー評価や土地利用に関するリスク評価を導入し始めており、環境DDをビジネスモデルに内包する動きが加速しています。
また、日本はエネルギー・素材・製造の分野で世界有数の技術を有しており、環境リスク管理技術の国際展開(例:アジア諸国への技術供与)も含め、グローバルなESG市場におけるリーダーシップが期待されています。

環境書取りまとめの事例紹介
実際に環境DDを明示的に導入し、その対応を可視化している日本企業の事例は、徐々に増加しています。
例えば、キリンホールディングスでは、気候変動・生物多様性・資源循環の3領域における環境戦略の進捗を、取締役会レベルでレビューする体制を構築。
これにより、経営レベルで環境リスクの把握・対応がなされていることが明確化されています。

さらに、環境報告書や統合報告書において、どの会議体で、誰が、どの課題をどのように議論したのかを開示する企業も登場しています。
これは単なる開示義務を超えて、ガバナンスの透明性を高め、投資家や国際的ステークホルダーとの信頼構築に資する実践です。

とはいえ、こうした先進的な取り組みはまだ一部にとどまり、多くの企業では「環境方針の表明」にとどまっていたり、「自社範囲内での対策」の段階に留まっていることが課題です。
今後は、こうした実例をベンチマークとしながら、社内体制・報告体制の高度化を進めることが求められます。
環境デュー・ディリジェンスの導入方法
ステップバイステップガイド
環境デュー・ディリジェンス(環境DD)を企業内で実装するためには、段階的かつ構造的なアプローチが重要です。
以下は、日本企業が実際に取り入れやすい実行手順の一例です。
- 環境方針とDD方針の策定
最初に、企業全体で共有される環境方針と、それを具体化する形でのDDポリシー(行動原則や優先領域)を明文化します。
経営層の関与を明確にすることで、実効性が高まります。 - 影響リスクの洗い出し(スクリーニング)
業種・製品・地域・調達先などの観点から、自社とバリューチェーン上での環境リスクの所在を特定します。
この段階では、NGOレポートや国際データベースの活用も有効です。 - 負の影響の詳細評価と優先順位付け
「深刻性(規模・範囲・不可逆性)」と「発生可能性」を軸に、重点対応分野を絞り込みます。
評価基準は明文化し、記録に残すことが後工程にも有効です。 - 予防・軽減措置の実施
特定リスクに対して具体的な対応策(設計変更、調達条件の見直し、監査実施など)を講じます。 - ステークホルダーとの対話と開示
リスクが及ぶ対象者やNGOなどと対話を重ね、必要に応じて調整や是正措置を講じます。
外部への情報開示も同時に進め、透明性を高めます。 - モニタリングと改善
一度の対応で終わらせず、進捗の定期的なレビューとプロセス改善を組み込みます。
この一連の流れを、ISO14001や既存の環境マネジメント体制と連携させて設計することが、効率と整合性の面で効果的です。


▼出典:環境省 バリューチェーンにおける 環境デュー・ディリジェンス入門
課題と解決策
環境DDの導入に際しては、国内企業特有の制度的・文化的な壁が存在します。
課題①:サプライチェーン全体に踏み込めない
原因:間接取引先への情報アクセスの難しさや取引慣行上の制約。
解決策:業界横断的な共同調査や、商社・バイヤーとの連携を活用する。政府や業界団体が提供するツール(例:CSR Risk Checker)を組み込むと実効性が高まります。
▼参考:CSR Risk Check
課題②:社内に専門知識が不足している
原因:環境や人権の複雑な法規制に精通する人材が不足。
解決策:短期的には外部専門家を活用し、中長期的には自社で環境DDに関する教育プログラムを内製化する。
環境省のマニュアル類も有用です。
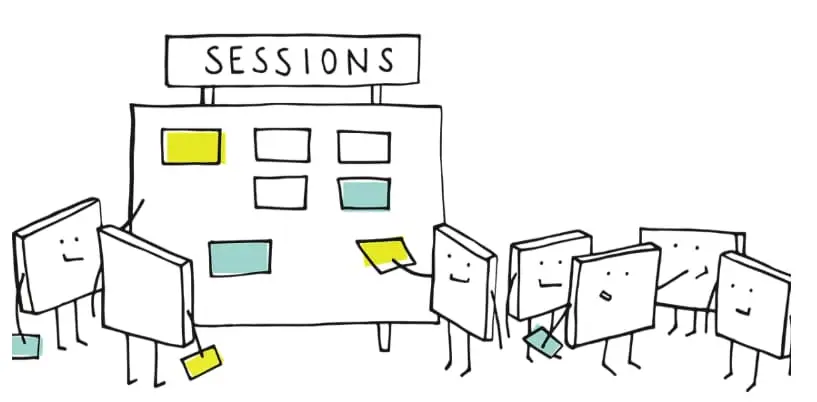
課題③:実施範囲が曖昧で属人的になりがち
原因:明確なルールや役割分担がないため、対応が属人的になり、継続性が担保されにくい。
解決策:DDプロセスを業務フローとして定着させ、社内規程や評価制度に組み込む。
方針→実行→評価→改善のPDCAが回る体制を明文化することが鍵です。

▼出典:サステナビリティ関連データの 効率的な収集及び戦略的活用に関する報告書
外部業者の活用方法と費用感
環境DDの初期段階では、外部の専門コンサルタントや調査会社の支援を受けることが非常に有効です。
活用のタイミングと領域
- 方針策定支援:国際基準との整合性確認、業界ベンチマーク提示
- リスクスクリーニング:調達国・業種ごとの環境リスク分析
- ステークホルダー対話支援:NGO・地域住民との交渉設計
- 苦情処理体制の構築:透明性・公平性を担保する設計
費用感の目安(一般的な中堅企業の場合)
- 初期アセスメント+方針設計:100万〜300万円
- バリューチェーン調査(一次調達先まで):200万〜500万円
- 開示資料の作成支援(CSRD準拠など):100万〜300万円
※プロジェクト規模や調査対象国数に応じて変動します。
一方、全プロセスを丸投げするのではなく、自社内に蓄積すべき知見と外部委託すべき領域を明確に分けることが、費用対効果を最大化するポイントです。
また、複数社に相談して相見積もり・比較検討を行うことも現実的な対策と言えます。
M&A実務における環境DD(Phase I–III)と価格・契約への反映
M&A(企業の買収・合併)では、表に見えない「環境リスク」をどれだけ正確に見極められるかが取引の成否を左右します。
そこで、欠かせないのが環境デュー・ディリジェンスになります。
土地や設備に潜む汚染リスクを調べ、その結果を取引価格や契約条件に反映させる仕組みです。
近年は、欧州の規制強化を背景に、日本企業でも導入が急速に進んでいます。
フェーズI〜III:環境リスクを段階的に“見える化”
環境DDは3つの段階で進められます。
フェーズI(基礎調査)では、土地の履歴や許認可を確認し、汚染の可能性をスクリーニング。
フェーズII(詳細調査)では、土壌や地下水を採取して分析し、汚染の範囲と濃度を数値で把握します。
最終段階のフェーズIII(対策計画)では、除去や浄化の方法を決め、修復コストを確定。
この金額が、そのまま価格調整(PPA)やエスクロー設定の根拠になります環境デュー・ディリジェンスの基礎から応用。

価格と契約にどう反映されるのか
確定した修復費用は、
- ディスカウント方式:あらかじめ価格から差し引く
- エスクロー方式:リスクに備えて一部資金を留保する
といった形で取引条件に反映されます。
一方で、調査しても見つからなかったリスクに備えるため、契約上の保証や補償条項を設けることが一般的です。
最近では、環境保険(PLL/R&W保険)を活用して、将来的な修復費用や訴訟リスクをカバーするケースも増えています。
戦略的に見る環境DD:調査 × 契約の組み合わせが鍵
環境DDは「調査で終わり」ではありません。
フェーズIIIで得たデータをもとに、リスクをどこまで許容するかを明確にし、価格・契約・保険を組み合わせて最適な形に整えることが重要です。
この一連の流れを社内の財務・法務・サステナビリティ部門が連携して進めることで、M&A後のトラブルを防ぎ、企業価値を守ることができます。
環境デュー・ディリジェンスの将来展望
規制強化と企業への影響
今後、環境デュー・ディリジェンス(環境DD)を取り巻く法制度は確実に強化の方向に進むことが予測されます。
特に影響が大きいのが、2024年7月にEUで採択された「企業サステナビリティ・デュー・ディリジェンス指令(CSDDD)」です。
この指令は、EU域内だけでなく、一定規模の非EU企業にも直接適用される域外規制であり、すでにグローバルに事業展開する日本企業の多くがその対象となりつつあります。

さらに注目すべきは、CSDDDの中で「民事責任」が明文化されている点です。
すなわち、環境DDの実施が不十分であった場合、被害を受けた関係者からの損害賠償請求に発展するリスクを抱えることになります。
これは、従来のCSR的な「努力義務」とは一線を画す、法的責任の枠組みへの移行を意味します。
日本企業にとっては、こうした国際規制を「他国の話」として静観するのではなく、法制化が未整備な国内においても事実上の準拠義務が生まれつつあると認識すべき局面に入っています。
特にサプライヤーがEU企業と取引関係を持つ場合、間接的に環境DDの実施を要請されるケースが急増しており、業種・規模を問わず備えが不可欠です。
国際的な動向と日本企業の対応
環境DDをめぐる世界的な潮流は、もはや一過性のトレンドではなく、グローバル・サプライチェーンの新しいルール形成に他なりません。
EUだけでなく、ドイツ・フランス・ノルウェーといった各国が独自にDD関連法を整備しており、米国でも投資家情報開示における環境リスクの透明性が強く求められています。
国連やOECDなどの国際機関も、企業に対し「リスクベースのデュー・ディリジェンスの実施」を義務に近い形で推奨しており、今後、国際規範と国内法のギャップを埋める動きは加速するでしょう。
事実、2025年2月にはEUがCSDDDの簡素化案(オムニバス法案)を提示したものの、方向性としての後退ではなく、より実務的な対応促進が狙いとされています。
日本企業がこれに対応するうえで重要なのは、単に海外の法規制に「引っ張られる」受け身の姿勢ではなく、日本発の先進事例を生み出し、国際的な議論に影響を与える立場に転じることです。
たとえば、環境省が示した懇談会のまとめでは、OECDガイダンスや国連指導原則と整合した形で、環境と人権を統合的に扱うアプローチが提唱されており、これを踏まえた企業戦略が今後の差別化要素になります。
▼参考:責任ある企業行動のための OECDデュー・ディリジェンス・ ガイダンス
特に中長期的には、投資家・顧客・取引先からの評価基準として「環境リスクをどう管理し、開示し、是正しているか」が企業の信用力と結びついていくため、今からの着実な取り組みが競争力の土台を築くことになります。
まとめ
環境デュー・ディリジェンスは、もはや一部の大企業や欧州企業だけの課題ではありません。
グローバルな規制強化とESG要請の高まりの中で、日本企業にも確実にその対応が求められています。
特にCSDDDのような域外規制は、サプライチェーン全体の管理体制と透明性を問うものであり、実務としての対応を怠れば取引停止や法的リスクに直結しかねません。
本記事では、環境DDの定義・プロセスから導入ステップ、実務課題、外部支援の活用法までを解説しました。
今後は単なる規制対応にとどまらず、自社の競争優位性や信頼構築の観点から、環境リスクを経営に統合する視点が不可欠です。
環境省のガイドラインや先進企業の事例も活用しながら、将来を見据えた持続可能な企業経営の一歩を踏み出すことが求められています。
