アフリカの温室効果ガス排出と気候変動の影響 | 初の気候サミットを解説
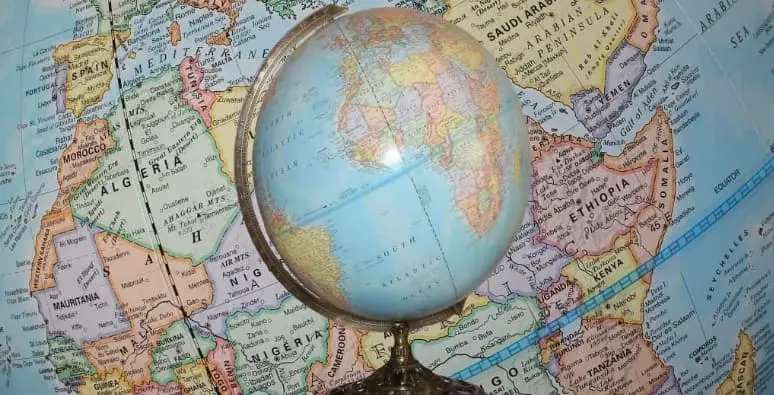
アフリカは現在、世界人口の約14%を占めながら温室効果ガス排出量はわずか4%にとどまっており、1人あたりの排出量でも先進地域に比べ極めて低い水準にあります。
しかしその一方で、アフリカは地球規模の気候変動による影響を最も強く受けやすい地域のひとつです。
干ばつや洪水、砂漠化、生態系の劣化といった深刻な問題は、農業・水資源・住環境に直結し、人々の生活と地域経済に甚大なダメージを与えています。
さらに、熱波や感染症の拡大といった健康リスクも高まっており、社会の安定性そのものが揺らぎつつあります。
こうした現状を踏まえると、アフリカが直面する課題は単なる地域問題ではなく、地球全体の持続可能性に関わる普遍的なテーマであると言えます。
その中でケニアのナイロビで開催された気候サミットは、アフリカの声を国際社会に届け、気候正義を訴える重要な場として大きな意義を持ちます。
本記事では、アフリカにおける温室効果ガス排出の現状と気候変動の影響、さらに気候サミットの果たす役割を解説し、持続可能な未来への道筋を探ります。
▼参考:アフリカの脱炭素化とTICADの役割|再エネ・水素・カーボンクレジットの最前線

アフリカでの温室効果ガスの排出量
現在のアフリカの人口は約9億人(世界の14%)であるが、人口増加率は世界一で、2025年には世界の17%、2050年には20%を占めると推定されています。
一方、温室効果ガスの排出量は世界の4%ほどとなっており、世界の14%を占める人口に対して非常に少ないです。

▼出典:JCCCA HP データで見る温室効果ガス排出量(世界)
1人当たりベースを大陸別で見ると、アフリカは一人当たり年間平均1tのCO2が排出され、北米は10.3t、ヨーロッパは7.1t、日本も所属するアジアでは4.6tとなっており、アフリカでの排出量の少なさが良く分かります。
アフリカの温室効果ガスの主な排出源は、エネルギー、産業、農業、森林伐採、廃棄物処理ですが、アフリカの中での二酸化炭素の排出量の60%以上が、南アフリカ、エジプト、ナイジェリアで排出されていて、コンゴ民主共和国やソマリア、中央アフリカ共和国などほぼ排出していない国もあります。
このように、温室効果ガスの排出量は非常に少なくなっていますが、アフリカは、気候変動の影響を最も受けやすい地域の一つになっていて、深刻な問題が起きています。
アフリカが気候変動で受ける影響
アフリカの気候変動による水資源・農業・生態系への影響
アフリカは世界で最も気候変動の影響を受けやすい地域の一つです。
その背景には、水資源の脆弱性、農業依存度の高さ、生態系の変化という3つの要素が大きく関係しています。
まず水資源について、サヘル地域では降水量の減少が深刻で干ばつが頻発し、農業や牧畜に直接的な打撃を与えています。
一方、東アフリカでは逆に豪雨や洪水が増え、家屋やインフラに甚大な被害をもたらしています。
こうした極端気象は飲料水や農業用水の供給を不安定化させ、時に水資源をめぐる地域紛争の引き金にもなっています。
さらに、農業への影響も深刻です。主要作物であるトウモロコシや小麦の収穫量は減少傾向にあり、特に灌漑設備が整わない農村部では干ばつが作物の生育を直撃しています。
その結果、食料価格の高騰と食料安全保障の不安定化が進み、貧困層を中心に生活が圧迫されています。
加えて、アフリカの多様な生態系も気候変動により急速に変質しています。
サバンナや熱帯雨林では生物多様性の減少が顕著で、アフリカゾウやライオンといった野生動物は生息地の縮小に直面しています。
また、沿岸部では海面上昇がサンゴ礁や漁業資源を脅かし、沿岸住民の生活基盤に大きな影響を及ぼしています。
▼参考:ブルーカーボンとは?| 種類、取り組み、課題を一挙解説
このように、気候変動はアフリカにおける水・農業・自然環境のあらゆる基盤を揺るがし、地域の安定性を大きく損なっているのです。

※AI-CD(Africa Initiative for Combating Desertification)は、2016年に始まったアフリカ15か国による砂漠化対策の国際協力イニシアティブです。
水資源管理・森林保全・農業支援を柱に、気候変動へのレジリエンス強化を目指します。
セネガルとケニアを拠点国に、地域全体で知識共有と住民参加を進めています。
気候変動がアフリカの都市・健康・経済に与える打撃と必要な適応策
急速に都市化が進むアフリカでは、気候変動による都市リスクも顕著です。
未整備のインフラの中で洪水や地滑りが発生すると都市機能が麻痺し、特にラゴス(ナイジェリア)やモンバサ(ケニア)といった沿岸都市は海面上昇による浸水リスクに直面しています。
さらに気温上昇による熱波は住民の健康や生産性を直撃し、エネルギー供給が不安定な都市部では問題が一層深刻化しています。
健康面でも、マラリアやデング熱などの熱帯病は温暖化に伴い流行地域が拡大しています。洪水や干ばつによる衛生環境の悪化はコレラや赤痢といった水系感染症を引き起こし、脆弱な医療体制に大きな負担をかけています。
これらは住民の生活と経済活動に直接的な悪影響を及ぼし、社会全体の安定性を損なっています。
経済的な打撃も深刻です。農業の不作や観光資源の劣化はアフリカ経済を直撃し、野生動物の減少や環境破壊は観光収入の減少につながっています。
加えて、災害復旧や適応策への支出増加は国家財政を圧迫し、経済成長を大きく制約しています。
この状況を乗り越えるためには、再生可能エネルギーの導入、持続可能な農業技術、洪水対策を含む都市インフラ整備が不可欠です。
また、教育や資金支援を通じて地域住民のレジリエンスを高める取り組みも重要です。
アフリカの課題は地域にとどまらず、地球全体の持続可能性と直結しています。したがって、国際社会が一体となって支援と協力を進めることが求められています。
▼参考:バーチャルウォーター(仮想水)とは?:水の見えない負荷を解説

アフリカ大陸での気候サミットの意義
アフリカにおける気候サミットの役割と意義
アフリカで開かれる気候サミットは、気候変動に最も脆弱な地域の現実を国際社会に訴える場です。
干ばつ、洪水、砂漠化、生態系の劣化といった深刻な問題は、農業や水資源、住環境を直撃し、何億人もの生活を脅かしています。
にもかかわらず、アフリカは世界全体の温室効果ガス排出量のわずか3%しか占めていません。
責任は小さいのに被害は甚大――この「不均衡」こそが、サミットで訴えられる気候正義(Climate Justice)の核心です。
サミットを通じ、アフリカ諸国は統一された立場を示し、資金や技術支援を国際社会に求めることができます。
再生可能エネルギーや農業適応策の統一戦略を策定することで、COPなど国際交渉の場で強い発言力を持つことが可能になります。
地域協力と未来への展望
アフリカの気候サミットは、地域全体で共通の目標を設定し協力を深める舞台でもあります。
国境を越えて協力することで、水資源管理や森林保全、再生可能エネルギー導入といった施策が効果的に進みます。
特に太陽光や風力など自然資源を活かした取り組みは、持続可能な未来を築く大きな可能性を秘めています。
また、伝統的な土地管理や水利用の知恵を共有することは、国際社会にとっても価値ある適応策となります。
さらに、サミットには政府、地域社会、若者、民間セクターが参加し、多様な視点での議論が展開されます。
若者が主体的に声を上げ、民間企業が持続可能なビジネスモデルを示すことで、新たな雇用や経済成長を生み出すきっかけにもなります。
最大の意義は、アフリカが「被害者」という立場にとどまらず、気候変動対応のリーダーシップを世界に示す点です。
サミットを通じて、国際社会と共に具体的な解決策を加速させ、持続可能な未来への道筋を描くことが期待されています。
まとめ
アフリカ大陸初の気候サミットは、気候変動の影響を受けるアフリカの国々が、その課題と解決策について共同で取り組むための重要なステップとなります。
このサミットを通じて、アフリカの国々が気候変動に対する取り組みを強化し、その影響を最小限に抑えるための具体的な行動を進めることが期待されます。
