学校法人の脱炭素戦略とは?大学のカーボンニュートラル事例と企業との違いを解説

2020年10月、菅義偉(すがよしひで)前内閣総理大臣による「2050年カーボンニュートラル」宣言以降、日本も大手企業を中心に脱炭素に取り組み始めました。
しかし脱炭素活動は企業だけではなく、教育機関もその一翼を担うことが求められています。
特に学校法人は、未来の世代を育成する場として、教育の中で環境意識を高めるだけでなく、自らが率先して脱炭素活動に取り組むことで、社会全体の持続可能な発展に貢献する重要な役割を果たすと期待されています。
▼参考:【2025年最新】カーボンニュートラルとは?現状と今後のトレンド
本記事では、そんな学校法人の脱炭素活動について、企業との違いや大学の脱炭素活動について共有いたします。

なぜ学校法人も取り組むのか
背景
学校法人が脱炭素に取り組む背景には、気候変動への対応と教育機関としての社会的責任が挙げられます。
学校法人は次世代を育てる場として、環境教育を通じて学生に持続可能な社会の重要性を教える役割があります。
さらに、学校自体がエネルギー消費の大きい施設(特に大学)であるため、その運営を見直し、エネルギー効率化や再生可能エネルギーの導入を進めることが求められます。
メリット
・エネルギーコストの削減
省エネ設備や再生可能エネルギーの導入により、長期的には運営コストの低減が可能です。
・環境教育の強化
実際の取り組みを通じて学生が学ぶことで、環境意識の高い人材を育成できます。
・社会的評価の向上
環境問題に積極的に取り組む姿勢は、地域社会や保護者からの信頼を得ることにつながります。これにより、学校のブランド価値が向上し、学生募集にも好影響を与える可能性があります。
・自治体や企業との連携強化
共同プロジェクトを通じて、地域全体の脱炭素化を推進し、社会全体の持続可能な発展に貢献することができます 。
学校法人が直面する課題
学校法人が脱炭素活動を推進するにあたり、いくつかの重要な課題に直面しています。これらの課題を効果的に克服することで、持続可能な未来を築くための基盤を固めることができます。
・教育施設のエネルギー消費
教育施設には、大規模なエネルギー消費を伴う建物が多く存在します。特に、空調設備、照明、コンピューターなどの情報通信技術(ICT)の利用が増える中で、エネルギー消費量は年々増加しています。
このような状況下のため、エネルギー消費の削減は大きな課題となっています。まずは、現状のエネルギー使用状況を正確に把握し、無駄なエネルギー使用を削減するための具体的な対策が求められます。
・古い建物の改修とエネルギー効率化
多くの学校施設は建設から長い年月が経過しており、エネルギー効率が低いことが多いです。
これらの古い建物をエネルギー効率の高い材料に改修したり、エネルギー効率の高い設備を導入して、エネルギー効率を高めることは、脱炭素活動における重要なステップです。
しかし、建物の改修には多額の費用がかかるため、資金調達が大きな課題となります。
・学校の抜本的な改革
脱炭素活動を成功させるためには、学校全体の意識改革が不可欠です。しかし、環境問題に対する意識の低さや、優先順位を上げにくいというのが現状です。
啓発活動は生徒だけでなく教職員や保護者、地域社会を巻き込む形で行うのが理想です。
しかし、教職員が多忙のため、学校として環境教育プログラムを新たに導入することが困難なケースもあります。
企業と学校法人の脱炭素活動の違い
企業と学校法人の脱炭素活動には、それぞれ異なる目標やアプローチがあります。
それらの違いを理解し、それぞれの強みを活かした取り組みを行うことが、持続可能な未来を築くために重要です。以下に主な違いを記します。
・経済的な目標と教育的な目標の違い
企業の脱炭素活動:
主に経済的な目標に基づいています。企業は利益を追求する組織であり、脱炭素化はコスト削減や企業価値の向上、規制遵守など、経済的な利点を追求する手段として位置づけられています。
例えば、エネルギー効率化によるコスト削減や、再生可能エネルギーの利用による企業イメージの向上がその具体例です。
学校法人の脱炭素活動:
教育的な目標が中心となります。学校法人は、未来を担う学生に対して持続可能な社会の構築に必要な知識と価値観を教育する責任があります。
脱炭素活動を通じて、学生たちに環境問題の重要性や、自らがその解決に貢献できる手段を教えることが目標です。
そのため、学校法人の脱炭素活動は、教育カリキュラムや学内プロジェクトに統合されることが多く、実践的な学びの場として活用されています。
・社会的責任と教育機関の影響力
企業:
社会的責任(CSR)として脱炭素活動に取り組むことが求められています。企業が持つ影響力は大きく、環境に配慮した活動を行うことで、社会全体にポジティブな影響を与えることができます。
また、消費者や投資家からの期待も高まっており、環境に配慮した企業活動は、ブランド価値の向上や市場競争力の強化にも繋がります。

学校法人:
教育機関として、社会的責任を超えて強い影響力を持っています。学校は地域社会や生徒・保護者に対して直接的な影響を与える存在であり、その活動は未来の社会を形作る若者たちに大きな影響を及ぼします。
脱炭素活動を通じて、環境意識を高める教育を行うことで、将来的にはより持続可能な社会の構築に寄与することができます。学校法人の取り組みは、次世代のリーダーを育成するという点で、非常に重要な役割を果たします。
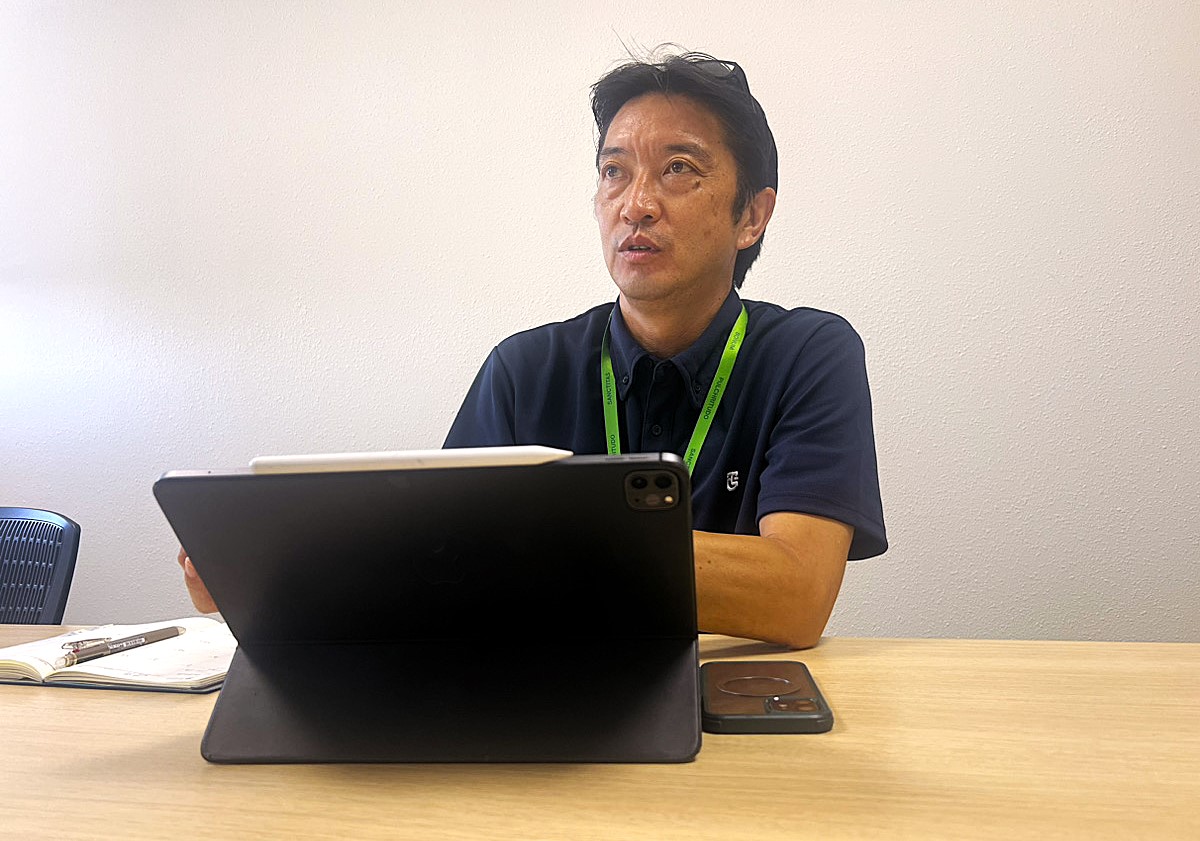
・資金調達と投資のアプローチ
企業:
脱炭素活動の資金を調達する際に、多様なアプローチを取ることができます。例えば、グリーンボンドの発行や、環境関連の補助金、投資家からの資金調達などが挙げられます。
企業は利益を生み出すための資本を活用し、効率的な投資を行うことで、経済的利益と環境保護を両立させることが可能です。
学校法人:
企業とは対照的に資金調達において制約が多い場合があります。公立学校は政府や自治体からの予算に依存しているため、限られた資金で脱炭素活動を進める必要があります。
私立学校は、授業料や寄付金を主要な収入源としていますが、これらの資金も教育活動全体を支えるためのものであり、脱炭素活動に直接投入できる資金は限られています。
そのため、学校法人は補助金や助成金の活用、地域企業との協力、コミュニティからの支援など、多様な資金調達方法を模索する必要があります。
このように、企業と学校法人の脱炭素活動にはそれぞれ異なる目標やアプローチがあります。学校法人は、教育機関としての使命を果たしながら、限られた資源を効果的に活用し、持続可能な社会の構築に貢献することが求められます。
学校法人の種類別活動
学校法人が取り組む脱炭素活動には、学校の種類や規模によって様々な違いがあります。
小学校、中学校、高校、大学の各段階や、私立学校と公立学校の特性を考慮した上で、それぞれに適したアプローチを取ることが重要です。
・小学校・中学校
基礎的な環境教育を中心に、生徒たちの環境意識を高めるプログラムを実施することが重要です。例えば、授業での環境問題に関する学習や、校内でのリサイクル活動、エネルギーの節約を促す取り組みなどが考えられます。
また、小中学校は比較的規模が小さいためエネルギー消費も少ないですが、照明のLED化や、断熱材の導入など、比較的簡単な改善が効果を発揮します。
・高校
より高度な技術や設備を導入し、エネルギー効率化や再生可能エネルギーの利用を積極的に推進することが求められます。
例えば、科学の授業で再生可能エネルギーの研究プロジェクトを行ったり、地域社会と連携して環境保護活動を実施することができます。
・大学
さらに専門的な研究やプロジェクトを通じて、社会全体に影響を与える取り組みが期待されます。
具体的にはキャンパス全体でのエネルギー管理や、持続可能なキャンパス運営のモデル構築、自治体と連携した取り組み、それから他の大学との情報共有や協業も期待されています。
高校や大学では、施設の規模が大きく、エネルギー消費も多くなります。これに対応するためには、包括的なエネルギー管理システムの導入や、大規模な再生可能エネルギー設備の設置が求められます。
また、大学では研究施設や大型の講義棟など、特定の施設が大きなエネルギーを消費するため、個別の対策が必要となります。
私立学校と公立学校の違い
私立学校と公立学校では、財源や運営の柔軟性に大きな違いがあります。
・私立学校
比較的自由に資金を調達しやすく、独自のプロジェクトを立ち上げることが可能です。
例えば、学費だけでなく寄付金や環境関連の補助金、企業スポンサーシップを活用して、最新の省エネ設備を導入することができます
・公立学校
主に政府や自治体からの予算に依存しており、資金の使い道に制約があります。
しかし、公立学校は地域社会との連携が強いため、地域の企業や自治体と協力して、共同でプロジェクトを実施することで、効果的な脱炭素活動を進めることが可能です。
学校法人が参加できる脱炭素コミュニティ
▼日本の団体
カーボン・ニュートラル達成に貢献する大学等コアリション
文部科学省、経済産業省、環境省のもと、大学等による情報共有や発信等の場として、2021年7月29日に設立。大学や高等教育機関が中心となり、地域や国、さらには世界に向けて脱炭素化の活動を展開し、持続可能な社会の実現を目指しています。
登録費用や年会費は無料。1つ以上のワーキンググループに所属するのが条件です。
大学を対象とした脱炭素活動は、今後この組織が牽引していく可能性が高いと思っています。
▼参考:https://uccn2050.jp/
日本サステイナブルキャンパス推進協議会(JSC:Japan Sustainable Campus Initiative)
国内の高等教育機関、行政機関、法人が参加する組織であり、持続可能なキャンパス運営を目指した取り組みを推進しています。
サステイナブルキャンパス構築の推進:エネルギー管理、廃棄物管理、環境教育など、キャンパス運営の様々な側面で持続可能な取り組みを進めています。
諸外国の活動的なネットワークとの連携:国内外の高等教育機関と連携し、グローバルな視点での持続可能な社会の構築を目指しています。
情報共有とベストプラクティスの普及:大学間の情報共有やベストプラクティスの普及を図り、持続可能なキャンパス運営のノウハウを広めています。
持続可能な環境配慮型社会の構築に貢献:キャンパスをモデルとして、日本における持続可能な環境配慮型社会の構築に寄与しています。
一般社団法人 日本環境教育学会 (JSFEE:Japanese Society for Environmental Education)
日本環境教育学会の目的は、環境教育の推進と普及を通じて持続可能な社会の実現を目指すことです。具体的には、以下のような活動を行っています。
・環境教育に関する研究とその成果の発表
・環境教育の実践事例の収集と共有
・環境教育に関する情報提供と啓発活動
・環境教育に携わる人々のネットワーク構築
1990年に任意団体として設立され、2016年に一般社団法人、2017年4月1日には法人へ移行しています。設立以来、環境教育に関する研究発表の場を提供し、最新の研究成果や実践例を共有することを通じて、教育関係者や研究者の支援を行っています 。
▼参考:https://www.jsfee.jp/
▼国際的な団体
国際大学協会(IAU:International Association of Universities)
1950年にユネスコの後援を受けて設立された会員制の組織です。世界中の大学が参加する国際的なネットワークで、持続可能な発展を目指した教育や研究の促進を行っています。
環境問題に関するセミナーやワークショップを通じて、大学間の連携を強化し、持続可能な社会の実現を目指しています。
▼参考:https://www.iau-aiu.net/
国連アカデミック・インパクト(UNAI:United Nations Academic Impact)
国連アカデミック・インパクトは、国連が主導する教育機関の国際的なネットワークで、持続可能な開発目標(SDGs)の達成を目指した活動を行っています。
環境保護や気候変動対策に関するプロジェクトやイベントを通じて、世界中の大学が協力し合うことを促進しています。
▼参考:https://www.academicimpact.jp/
大学の活動事例
慶應義塾大学
2030年に電気使用量の全てを自然エネルギーに転換
大学には6つのキャンパスがあり、大学病院や一貫教育校も含めると、それぞれのエネルギー使用量、使用形態、オンサイト太陽光発電のポテンシャルなどの条件は大きく異なっています。
これらのキャンパスの特徴も勘案して、カーボンニュートラルに向けた具体的な検討をおこなっています。
特に、湘南藤沢キャンパス(SFC)では、カーボンニュートラルのモデルキャンパスとして、自然エネルギー電力への転換を実現するロードマップを作成し、他キャンパスに先行して、太陽光発電システムの設置計画を進めています。
▼参考:https://www.global-sdgs.keio.ac.jp/carbon-neutral/
東京工業大学
「ゼロカーボンエネルギー研究所」を設置
東京工業大学は、本学でこれまで培ってきたエネルギー研究に関わる資源とその成果を本研究所に集約し、ゼロカーボンエネルギーを用いたエネルギーの安定供給と経済性を有した炭素・物質循環社会の実現に取り組みます。
具体的には、ゼロカーボンエネルギーの製造、効率的な利用、貯蔵、物質変換、社会利用、循環利用などの要素技術と、これらを最適化したエネルギーネットワークの構築を包括的に研究します(図)。
さらに、エネルギーを利用する産業、市民、地域などの社会のステークホルダーと連携して、問題解決のための技術ソリューションを提供するとともに、国際社会とも協調してグローバルな環境・エネルギー課題の解決に寄与します。
▼参考:https://www.titech.ac.jp/news/2021/049205
早稲田大学
「WASEDA Carbon Net Zero Challenge 2030s」
早稲田大学はカーボンニュートラル宣言をしており、具体的な活動は脱炭素ロードマップに従って、「最先端研究」「人材育成」「キャンパスのカーボンニュートラル達成」それぞれの分野でカーボンニュートラルの実現に取り組んでいます。
▼参考:https://dpt-netzero.w.waseda.jp/
名古屋大学
未来社会創造機構のもとに脱炭素社会創造センターを設立
このセンターは、二酸化炭素排出削減や吸収促進のための技術開発を行い、政策、社会制度、経済、歴史、文化、自然環境を対象とした研究者が協働しています。
また、地域社会や国際社会と連携し、持続可能な社会の構築を目指しています。センターで培われた知識と技術は、国内外に展開され、カーボンニュートラルの達成を目指しています。
▼参考:https://www.zcs.mirai.nagoya-u.ac.jp/
東北大学
東北大学グリーン未来創造機構(Green Goals Initiative)の設立
東北大学がこれまでに推進してきた東日本大震災からの復興及び日本の新生に寄与するプロジェクトや、東北大学が掲げるSDGsである「社会にインパクトある研究」の30プロジェクト等をさらに発展させ、新たに「Green Technology」、「Recovery & Resilience」、「Social Innovation & Inclusion」の3つの柱のもと大学の総合力を以て全学組織的に社会課題の解決へ挑み、グリーン未来社会の実現に貢献することを目的として、2021年4月に設置。
▼参考:https://www.ggi.tohoku.ac.jp/
九州大学
カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所(I²CNER:アイスナー)の設立
2010年(平成22年)12月1日に文科省「世界トップレベル研究拠点プログラム(WPI))」の採択を受けて、カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所(以下アイスナー)を設置しています。
設立後の10年間で、日本と世界のエネルギー問題の解決に向けて基礎研究に取り組み、国際ネットワークの構築と海外主任研究者を構成メンバーとした国際協働体制を実現し、WPI基準 (“world premier” status) に到達したと評価され、2020年(令和2年)4月、WPIアカデミー拠点に採択されました。
現在は、これまでに築いた国際ネットワークを基に、戦略的パートナー大学(イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校、マサチューセッツ工科大学、インペリアルカレッジ・ロンドン、スイス連邦工科大学、エディンバラ大学)との連携の強化、国際ネットワークの充実、若手・外国人・女性研究者などの多様な研究者の積極的な雇用、国際頭脳循環の加速を通して、カーボンニュートラル・エネルギーに資する最先端の基礎研究を展開しています。
▼参考:https://i2cner.kyushu-u.ac.jp/ja/
千葉商科大学(CUC)
日本初「自然エネルギー100%大学」を目指す
本取り組みは、大学のエネルギー消費を再生可能エネルギーで完全に賄うことを目指すものです。
具体的には、大学が所有するメガソーラー施設などを利用して、再生可能エネルギーの発電と消費のバランスを取る努力を続けています 。
また、地域社会の脱炭素化の拠点としても活動しており、公開講座を通じて地域住民や他の教育機関に対して情報提供と啓発活動を行っています 。CUCはさらに、全国の大学が連携して自然エネルギーの活用と脱炭素化を推進する「自然エネルギー大学リーグ」にも積極的に参加しています 。
カーボン・ニュートラル達成に貢献する大学等コアリションでは、5つのワーキンググループのうち、「ゼロカーボン・キャンパスWG」の幹事大学を務めています。
▼参考:https://www.cuc.ac.jp/about_cuc/activity/environment/index.html
立命館大学
2030年カーボンニュートラル宣言
カーボン・ニュートラル達成に貢献する大学等コアリションで、5つのワーキンググループがあるうち、千葉商科大学と共に「ゼロカーボン・キャンパスWG」の幹事大学として、参画しています。
参考:https://www.ritsumei.ac.jp/sdgs/net-zero/
信州大学
学術研究・産学官連携推進機構(Shinshu University-Innovative Research & Liaison Organization:通称サイロ)の中で、カーボンニュートラルに関する取り組みを実施。
カーボン・ニュートラル達成に貢献する大学等コアリションで、5つのワーキンググループのうち、「地域ゼロカーボンWG」の幹事大学を務めています。
▼参考:https://www.shinshu-u.ac.jp/institution/suirlo/
まとめ
脱炭素と聞くと企業や産業分野をイメージしがちですが、今後は学校法人(特に大学)の取り組みや成功事例も増えてきそうですね。
企業が取り組みづらい環境教育や意識啓発はもちろん、企業や自治体を巻き込んだ雇用機会の創出や地域経済の活性化にも期待したいです。
一方で、地域住民との調整や、活動資金の調達という点では課題もありますので、引き続き学校法人が活動しやすいルールが整備されることを願っています。
