EPD(環境製品宣言)とは?ISO規格・取得方法・活用事例まで徹底解説
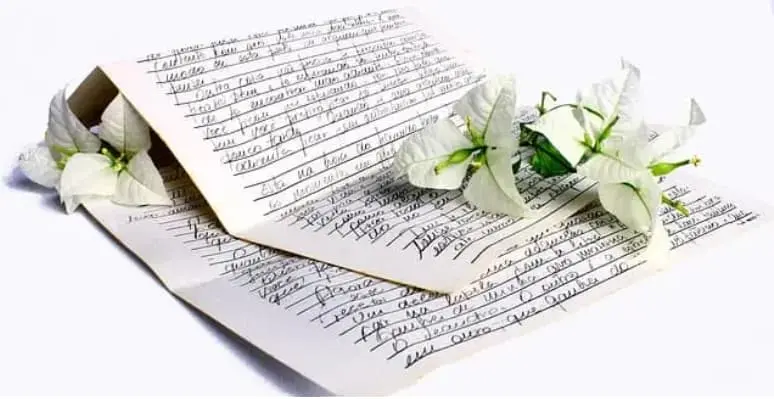
環境配慮やサステナビリティの取り組みが企業価値に直結する時代、製品の環境情報を客観的かつ透明性の高い形で示すことは、国内外の市場で信頼を得るうえで欠かせません。
そんな中で注目されているのが「EPD(Environmental Product Declaration:環境製品宣言)」です。
EPDは、国際規格に準拠し、製品やサービスのライフサイクル全体にわたる複数の環境影響指標を評価・開示する仕組みで、第三者による検証が必須となります。
単なるPR資料ではなく、定量的かつ比較可能な情報を提供できる点が大きな特徴です。
一方で、似た概念として「CFP(カーボンフットプリント)」がありますが、CFPが温室効果ガス排出量に特化しているのに対し、EPDは温室効果ガスに加え、資源消費、水使用量、酸化物排出など幅広い指標を網羅します。
この違いを理解していないと、導入目的や効果を正しく評価できない恐れがあります。
とはいえ、EPDの取得には自社データの収集・算定、PCR(製品カテゴリルール)への準拠、第三者検証、そしてプログラムへの登録といった工程が必要で、初めて取り組む企業にとってはハードルが高く感じられるでしょう。
そこで本記事では、EPDの主な特徴、CFPとの違い、認証取得までの流れをFAQ形式で整理し、企業が導入判断や社内説明に活用できるようわかりやすく解説します。

EPDの基礎知識
環境製品宣言(EPD)とは
環境製品宣言(EPD:Environmental Product Declaration)は、国際規格 ISO 14025 に準拠した「タイプIII環境宣言」と呼ばれる環境情報の開示制度です。
特徴は、製品やサービスの原材料調達から製造、使用、廃棄・リサイクルに至るライフサイクル全体にわたる環境影響を、数値として客観的に示す点にあります。
温室効果ガスの排出量だけでなく、水資源の使用量、大気汚染、資源枯渇など、複数の環境指標を同じ基準で評価できるため、「製品の環境性能パスポート」とも呼ばれます。
この「パスポート」を通じて、事業者は環境負荷の実態を透明に示し、調達担当者や投資家、消費者が比較・選択できるようになります。

▼出典:SuMPO EPD(Environmental Product Declaration)とは
EPDが求められる背景
近年、脱炭素社会の実現に向けた国際的な動きが加速し、企業には単なる環境配慮を超えた説明責任(アカウンタビリティ)が求められています。
ESG投資の拡大や、環境配慮型の公共調達制度、そしてLEEDやCASBEEなどのグリーンビルディング認証では、EPDが重要な評価指標として位置づけられています。
さらに、欧州や北米では建設製品規則(CPR)やBuy Clean政策といった法制度のもと、特定分野ではEPDの提出が事実上の必須条件となりつつあります。
こうした潮流は、日本企業にとっても輸出競争力や国際入札への参加可否を左右する要因となっており、国内外での事業展開を見据えたEPD取得の重要性はますます高まっています。

▼出典:株式会社エックス都市研究所 令和6年度 建設廃棄物の再資源化に関する調査・検討業務
EPDの評価と信頼性を支える仕組み
ライフサイクルアセスメント(LCA)の役割
EPDの基盤となるのが、ライフサイクルアセスメント(LCA)です。これは製品やサービスが環境に与える影響を、「ゆりかごから墓場まで」――つまり原材料の採掘から製造、使用、廃棄やリサイクルに至る全工程で評価する国際的な手法です。
LCAは、単にCO₂排出量(温室効果ガス)だけを測るのではなく、水資源の使用量、資源の枯渇、大気汚染、オゾン層破壊など、複数の環境指標を同時に評価します。

これにより、ある環境負荷を減らすための取り組みが、別の環境問題を悪化させてしまう「バーデンシフト(環境負荷の転嫁)」を防ぐことができます。
この包括的な分析は、企業が真に持続可能な改善策を見極め、グリーンウォッシュ(見せかけの環境配慮)を回避するうえで不可欠です。



第三者検証による信頼性確保
EPDのもう一つの柱は、第三者による検証制度です。
国際規格 ISO 14025 では、EPDの公開前に独立した検証機関がレビューを行うことが義務づけられています。
この検証では、
- LCAの実施内容がISO 14040/14044に適合しているか
- 算定方法や表示内容がPCR(製品カテゴリールール)に準拠しているか
といった点が厳しくチェックされます。

第三者によるレビューを通過することで、EPDは透明性と比較可能性を担保でき、国内外の市場や規制において「信頼できる環境性能データ」として扱われます。
これは単なる社内評価や自己申告とは一線を画す、大きな信頼の裏付けとなります。

▼出典:経済産業省 第2回 サプライチェーン全体でのカーボンニュートラルに向けた カーボンフットプリントの算定・検証等に関する検討会
EPDの国際動向と市場トレンド
欧米市場での普及状況
欧米では、EPDはすでに環境配慮型製品の標準的な評価ツールとして広く活用されています。
特に欧州連合(EU)では、建設製品規則(CPR)が建材の環境影響評価にEPDの使用を推奨し、公共調達指令でもライフサイクル視点での評価が導入されています。
これにより、公共工事の入札条件としてEPDの有無が重要な選定基準になるケースが増えています。
米国では、カリフォルニア州の「Buy Clean」政策が代表的です
。鉄鋼やガラスなど特定の建材について、公共事業での使用にはEPDの提出が義務付けられており、EPDを持たない製品は事実上市場参入が困難になります。
さらに、世界的に採用されている建築物環境認証制度LEEDでも、EPD取得製品の使用が加点対象となるため、建材メーカーにとっては受注競争での重要な武器となっています。
加えて、欧州域内ではECO Platformが各国の建設分野EPDを調和させる取り組みを進めています。
これにより、国境を越えて共通の環境性能基準で製品を比較できる環境が整いつつあり、グリーン建材市場の統合が加速しています。
▼参考:JETRO EU、建物の脱炭素化を目指す指令施行、グリーン・ディール産業関連法の実施段階に注視
アジア市場と日本の展望
アジアでも、環境配慮型建築やサステナブル調達の重要性が高まり、EPDの需要は今後拡大すると見込まれます。
日本では、SuMPO EPDが国内唯一の公式プログラムとして運営されており、建設、電子機器、化学製品など幅広い分野での活用が進んでいます。
注目すべきは、国際EPDシステム(IES)との相互認証に向けた動きです。
これが実現すれば、日本で取得したEPDが欧米市場でも通用するようになり、輸出企業にとって大幅なコスト削減と市場拡大のチャンスとなります。
また、日本国内でも2025年以降、国土交通省が建築物のLCA制度化を本格的に進める予定です。
特に一定規模以上の非住宅建築物では、設計段階から環境影響を評価する仕組みが導入される見込みであり、建材メーカーや関連業界におけるEPD需要は急増すると予測されます。
このように、EPDは欧米だけでなくアジアでも、規制対応と市場競争力の両面で不可欠なツールへと進化しつつあります。

▼出典:NWESCAST 日本グリーン建材市場 2025–2033年:規模、トレンド、予測
EPD取得の流れと企業メリット
取得プロセス
EPDを取得するためには、明確に定められたプロセスを順を追って進める必要があります。大まかな流れは以下の通りです。
- PCR(製品カテゴリールール)の選定・策定
対象製品に適用するルールを選び、必要に応じて策定します。これにより、評価方法や表示項目が統一され、同じ製品カテゴリ内で公平な比較が可能になります。 - LCAデータの収集と算定
製品のライフサイクル全体にわたる環境影響を評価するため、一次データ(自社工場のエネルギー使用量や原材料投入量など)と二次データ(外部データベースから取得する背景データ)を収集します。
日本では、産業技術総合研究所が開発したIDEAデータベースなどのツールが広く活用されています。これらを使って、温室効果ガス排出量や水使用量、資源消費などの影響値を算出します。 - 第三者検証
算定結果や報告書の内容が国際規格やPCRのルールに沿っているかを、独立した第三者機関が検証します。これにより、データの信頼性と透明性が担保されます。 - 公開
検証に合格したEPDは、プログラム運営者の公式サイトなどで一般公開され、誰でも閲覧できる状態になります。これにより、市場や取引先からの信頼を得ることができます。

EPD取得のメリット
EPDの取得は、単なる環境ラベルを得るだけではなく、企業の競争力やブランド価値を大きく高める効果があります。
- 調達競争力の向上
グリーンビルディング認証(LEEDやCASBEE)や公共調達では、EPD取得製品が優先的に選ばれる傾向があります。
また、サプライチェーン全体で環境配慮を求める企業との取引機会が増えます。 - ESG評価・ブランド価値の向上
EPDは第三者検証済みの客観的データであるため、投資家や顧客に対して環境への取り組みを明確に示すことができます。
結果として、ESG評価の改善やブランドの信頼性向上につながります。 - 海外市場参入時の規制対応コスト削減
欧州や北米では、建材や特定製品の輸出条件としてEPD提出を求める制度が増えています。
あらかじめ国際的に通用するEPDを取得しておくことで、複数市場への対応を効率化し、追加の認証コストや時間を削減できます。

以下のような形で専門ページを作りステークスホルダーに対して訴求も行えます。

▼出典:ケイミュー株式会社 窯業系サイディングおよびスレート屋根材では国内初 10製品で環境認証ラベルEPDを取得

EPDに関するよくある質問(FAQ)
EPDの主な特徴は?
最大の特徴は、国際規格に準拠していることです。
ISO 14025の枠組みに基づき、製品やサービスのライフサイクル全体を評価します。
評価対象はCO₂排出量だけではなく、水使用量、資源の枯渇、大気汚染など複数の環境指標に及びます。
さらに、EPDは第三者機関による検証が必須であり、その透明性と信頼性は国際的にも高く評価されています。
EPDとCFP(カーボンフットプリント)の違いは?
両者ともLCA(ライフサイクルアセスメント)の手法を活用しますが、評価範囲が異なります。
- CFP(カーボンフットプリント):製品やサービスが排出する温室効果ガス(GHG)の総量に特化。結果はCO₂換算値(CO₂e)で示されます。
- EPD:温室効果ガス排出量に加えて、水資源利用、大気汚染、資源枯渇など多面的な環境影響を同時に評価します。
つまり、CFPは「気候変動への影響」にフォーカスした指標であり、EPDは製品の総合的な環境性能を可視化するツールです。

EPD認証を受けるには?
EPDを取得するには、次のステップを踏む必要があります。
- 自社データの収集・算定
工場のエネルギー使用量や原材料の投入量などの一次データと、外部データベースの二次データを組み合わせてLCAを実施します。 - PCR(製品カテゴリールール)への準拠
同一製品カテゴリ内で比較可能な評価を行うため、該当するPCRを選択し、そのルールに沿って算定します。 - 第三者検証
ISO規格やPCRに沿っているか、独立した検証機関がチェックします。 - プログラム登録と公開
検証に合格したEPDを、プログラム運営者のウェブサイトなどで公開します。
このプロセスを経ることで、EPDは市場や取引先から「信頼できる環境性能データ」として認知されます。
まとめ
EPD(環境製品宣言)は、ISO 14025に準拠した国際的な環境情報開示制度で、製品のライフサイクル全体における環境影響をCO₂排出量や水使用量、資源枯渇など複数指標で定量評価します。
その基盤となるLCAと第三者検証により、データの透明性と信頼性が確保されます。
欧米ではCPRやBuy Clean政策、LEED認証などでEPDが重要視され、日本でもSuMPO EPDや2025年の建築物LCA制度化を背景に需要が拡大中です。
取得にはPCR準拠の算定・検証・公開プロセスが必要ですが、調達競争力の向上、ESG評価やブランド価値強化、海外規制対応の効率化といったメリットが得られます。
今やEPDは、企業の環境対応を証明し、市場競争で優位に立つための戦略的ツールと言えるでしょう。
