GOSAT-GW(いぶきGW)で何がわかる?CO₂・メタン・NO₂を面で捉える新型衛星の全貌

地球温暖化という言葉は日々のニュースで目にするものの、その原因となる温室効果ガスの正体や、水蒸気を含む大気・海洋の流れがどのように地球を動かしているかまで、理解している人は少ないかもしれません。
今、私たちが直面する気候危機の本質は、「見えにくいものをどう正確に捉えるか」という課題にあります。
こうした課題の解決に挑むのが、日本が世界に誇る革新的な人工衛星「GOSAT-GW(いぶきGW)」です。
2025年6月に打ち上げられたこの衛星は、CO₂やメタンなどの温室効果ガスに加え、排出源の“指紋”ともいえる二酸化窒素(NO₂)を高精度で観測可能にしました。
さらに、水蒸気や降水量など、水循環の中核を担う要素も同時に測定。
これにより、排出量の空間分布や気象災害の予測精度が飛躍的に向上すると期待されています。
本記事では、温室効果ガスの基本とその地球への影響、水循環の科学的な役割、そしてGOSAT-GWがもたらす観測技術の進化と国際的インパクトまでを、丁寧にひも解いていきます。
未来の気候を見通すカギが、すでに宇宙から私たちの地球を見守り始めているのです。

温室効果ガスとは?基本概念とその地球への影響
地球温暖化という言葉を聞くと、まず思い浮かぶのが「温室効果ガス」ではないでしょうか。
しかし、この言葉の本質を正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。
温室効果ガスとは、地球の大気中に存在し、地表から放出された赤外線(熱エネルギー)を吸収・再放射する性質を持つ気体の総称です。
これらの気体は、私たちの暮らしや産業活動とも深く関わっており、地球規模の気候変動と直結しています。
人類の活動によって排出される温室効果ガスが急増している今、これらがどのように地球の気温に影響を与えているのか、そして私たちが直面している課題とは何なのか――その全体像を知ることは、持続可能な未来を考える上で欠かせません。

代表的な温室効果ガスとその役割
温室効果ガスにはいくつかの種類がありますが、特に注目すべきは以下の主要成分です。
- 二酸化炭素(CO₂)
最も多く排出されている温室効果ガスで、主な発生源は化石燃料の燃焼(火力発電・輸送・産業)です。
森林伐採もCO₂の放出を助長します。 - メタン(CH₄)
CO₂と比べて大気中での濃度は低いものの、温室効果は約25倍以上と非常に強力。主な発生源は、家畜の腸内発酵、水田、廃棄物の分解など。

- 一酸化二窒素(N₂O)
農業での肥料使用や工業プロセスで発生。CO₂よりも約300倍強力な温室効果を持ちます。
-温室効果ガスとしての特性と削減策を解説.png)
- フロン類(HFC・PFCなど)
冷媒や工業製品で使用される化学物質で、大気中での寿命が非常に長く、地球温暖化係数(GWP)は数千〜数万倍に及ぶものもあります。
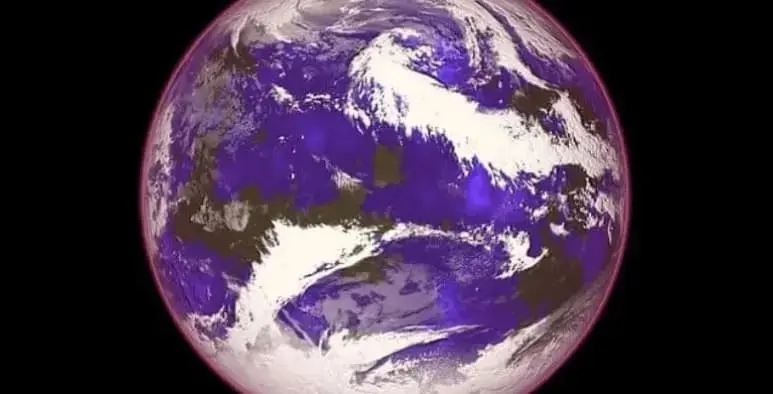
- 水蒸気(H₂O)
自然由来の温室効果ガスであり、大気中の温度に応じて変動します。
直接的な人為起源は少ないものの、他の温室効果ガスによる気温上昇が水蒸気の増加を引き起こし、「増幅効果(フィードバック)」を生み出します。
これらのガスは、それぞれ異なる寿命・温暖化係数(GWP)・発生源を持ち、多層的に気候システムへ影響を与えています。
特にCO₂とCH₄は、衛星による継続的な観測対象としても最も注目されており、政策・科学の両面で監視と削減が求められています。
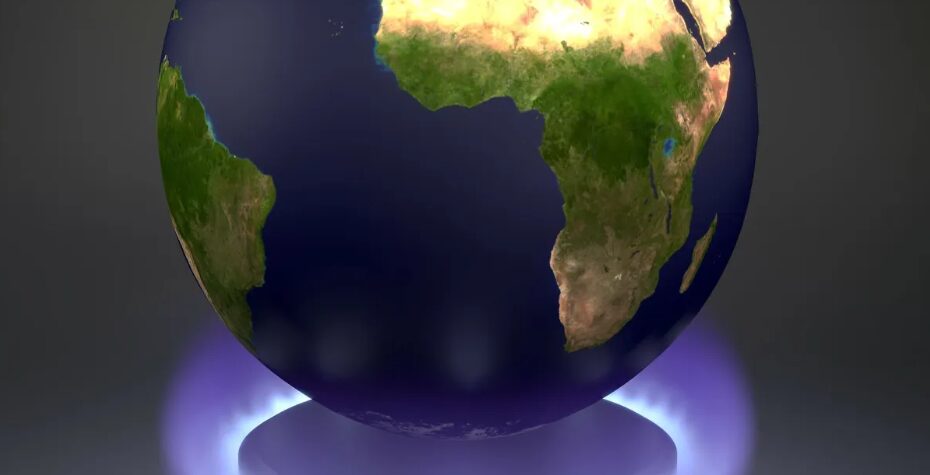

温暖化を引き起こすメカニズムと環境への影響
地球は太陽からのエネルギー(可視光)を受け取り、地表で熱として吸収した後、赤外線として再び宇宙に向けて放出します。
しかし、温室効果ガスはこの赤外線の一部を吸収し、再び地球に向けて放射することで、熱が大気中に閉じ込められる現象を引き起こします。
これがいわゆる「温室効果」です。
本来は生命を維持するために欠かせない自然の仕組みですが、人為起源の排出増加により“温室”の厚みが増しすぎた状態が、現在の地球温暖化の本質です。
この温暖化がもたらす影響は深刻かつ広範囲にわたります。
- 気温上昇による異常気象の増加(猛暑、豪雨、干ばつ、台風の強大化)
- 氷河・永久凍土の融解と海面上昇
- 生態系の崩壊、農業への打撃、食料供給の不安定化
- 人の健康への悪影響(熱中症・感染症リスクの増加など)
- 社会的脆弱性の拡大(気候難民や水資源争奪の懸念)
国連IPCCによる最新の報告書では、温暖化を1.5℃に抑えるには、今後10年が決定的に重要であるとされており、科学的な根拠に基づく排出削減と地球観測の高度化が急務となっています。
GOSAT-GWのような衛星観測技術は、このような課題に対して客観的なデータで真実を可視化する極めて重要な手段となっています。

▼出典:気象庁 ヒートアイランド現象
水循環とは何か?気候と生活を支える“見えない流れ”
私たちが毎日使う水は、どこから来て、どこへ流れていくのでしょうか。
蛇口をひねれば当たり前のように出てくる水も、実は地球全体で絶えず循環している壮大な流れの一部です。
この循環の仕組みこそが「水循環(Hydrological Cycle)」と呼ばれる自然現象であり、気候変動の理解、災害予測、農業・エネルギー政策など、現代社会のあらゆる場面に関係しています。
特に近年では、異常気象や干ばつ、集中豪雨といった極端現象が頻発し、水循環の監視と予測の重要性はこれまでになく高まっています。
その中心的な役割を担い始めているのが、宇宙から地球を観測する気象衛星です。
水循環が果たす地球システムでの役割
水循環とは、海・大気・陸・氷河などの間で水が形を変えながら循環するプロセスを指します。
太陽のエネルギーによって海や陸の水が蒸発し、雲を作り、やがて雨や雪として地上に戻り、川や地下水として再び海へ流れ込む――この一連の動きが地球規模で絶え間なく続いています。
この水の循環は、単なる水の移動にとどまらず、次のような複雑で重要な役割を果たしています。
- 地球のエネルギー分配:水蒸気は熱を運ぶ媒介であり、赤道から極へ熱を運ぶ「熱輸送装置」として機能します。
- 気候システムの調節:降水や蒸発は、地域ごとの気温・湿度・雲量に影響を与え、気候を形作る要因となります。
- 生態系・農業への影響:雨量や土壌の水分量は、生態系の維持や農作物の生育に直結します。
- 人間活動への支援:水資源の管理、飲料水・発電・灌漑への利用など、社会生活と経済の基盤でもあります。
このように、水循環は地球全体をつなぐ“見えないインフラ”であり、そのバランスが崩れることで、気候変動の進行や自然災害の発生リスクが高まるといった深刻な影響が現れます。

衛星観測が変える水循環の可視化技術
これまで、水循環の詳細な挙動を把握するには地上観測網に頼るしかありませんでしたが、地球全体をリアルタイムかつ均等に監視することは不可能という制約がありました。
この課題を打ち破ったのが、宇宙からの衛星観測技術です。
特に注目されているのが、GOSAT-GWに搭載された高性能マイクロ波放射計「AMSR3」です。
AMSR3は、海面水温、降水量、雪氷、土壌水分、上空の水蒸気量など、水に関する主要な物理量を高頻度かつ高精度で観測できる革新的なセンサです。
従来困難だった陸域の降雪量や、集中豪雨の発達に直結する上空の水蒸気の挙動を可視化できる点が、大きなブレークスルーとされています。
また、沿岸域における海面水温の観測精度も向上し、日本の漁業や災害対策への実用的な貢献も期待されています。
さらに、得られたデータは気象庁をはじめとする世界各国の数値天気予報モデルにリアルタイムで同化され、台風の進路や大雨の予測精度を飛躍的に高める役割も果たします。
つまり、AMSR3をはじめとする衛星観測は、水循環を「点」ではなく「面」として捉えることを可能にし、地球規模の水の流れを初めて統合的に理解するツールへと進化しているのです。

GOSAT-GWの全貌|CO₂・メタン・NO₂を“面”で捉える革新衛星
2025年6月、日本が誇る地球観測技術の粋を結集した新型衛星「GOSAT-GW(いぶきGW)」が打ち上げられました。
これは、2009年に打ち上げられたGOSAT(いぶき)、2018年のGOSAT-2に続く「温室効果ガス観測衛星」シリーズの第3世代機であり、地球規模の気候変動対策を支えるデータインフラの中核として世界中から注目を集めています。
特筆すべきは、二酸化炭素(CO₂)・メタン(CH₄)・二酸化窒素(NO₂)という主要な排出ガスを、従来の“点”ではなく“面”で高密度に観測できること。
これにより、都市や発電所、さらには国や企業単位での排出量をより正確に把握できるようになります。
▼参考:環境省 温室効果ガス・水循環観測技術衛星「GOSAT-GW」の 打上げについて

▼出典:環境省ecojin 地球を見守る人工衛星!日本が誇る最新技術GOSAT!
GOSAT-GWの基本仕様とミッション概要
GOSAT-GWは、JAXA(宇宙航空研究開発機構)・環境省・国立環境研究所(NIES)の三者が共同で進める国家的プロジェクトです。
打ち上げはH-IIAロケット50号機によって実施され、種子島宇宙センターから所定の軌道(高度666kmの太陽同期準回帰軌道)に投入されました。
衛星の主なスペックは以下の通りです:
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 質量 | 約2.6トン(燃料含む) |
| 発生電力 | 約5.2〜5.3kW |
| 設計寿命 | 7年以上 |
| 軌道 | 高度666km、3日回帰、13:30地方時通過 |
| プライムコントラクタ | 三菱電機株式会社 |
GOSAT-GWのミッションは、温室効果ガスと水循環の両方を一つの衛星で同時に観測するという、かつてない統合型アプローチを採用している点が最大の特徴です。
これにより、観測効率を飛躍的に高めるだけでなく、異なる観測データを相互補完的に活用する科学的シナジーを生み出すことが可能になっています。
具体的には、以下の二つの先進センサが搭載されています:
- TANSO-3(温室効果ガス観測センサ3型):CO₂、CH₄、NO₂の柱平均濃度を高解像度で面観測。
- AMSR3(高性能マイクロ波放射計3):水蒸気・降水量・海面水温・降雪量などの水循環関連パラメータを観測。
特にTANSO-3は、従来の「サンプリング型」から「イメージング型」へのパラダイム転換を実現し、排出源の“可視化”を大きく前進させています。

▼出典:環境省ecojin 地球を見守る人工衛星!日本が誇る最新技術GOSAT!
GOSAT/GOSAT-2との違いと技術的進化点
GOSAT-GWは、過去のGOSATシリーズの成果と課題を受け継ぎつつ、観測精度・頻度・分解能のすべてにおいて飛躍的な進化を遂げています。
以下に、主要な進化点を示します。
1. 観測方式の進化:点から面へ
- GOSAT/GOSAT-2:フーリエ変換分光計(FTS)による点観測方式(1回に数点のピンポイント観測)
- GOSAT-GW:プッシュブルーム方式の回折格子分光計により、地表を“面”でスキャン可能に
これにより、1回の観測で得られるデータ点数は、従来比で100倍〜1,000倍に拡大。排出源の空間分布や拡散パターンを直接視認できるレベルに達しました。
2. 観測対象の拡張:NO₂の同時観測
GOSAT-GWでは、CO₂・CH₄に加えてNO₂(二酸化窒素)を可視光で同時観測できるのが大きな特長です。
NO₂は化石燃料燃焼と強い相関があり、人為的なCO₂排出の“トレーサー(指紋)”として機能します。
これにより、自然由来の吸収・排出と人為起源排出を区別する分析が可能になります。
3. 観測モードの拡張:ワイドとフォーカスの二段構え
- ワイドモード:911kmの広域観測幅+10kmの空間分解能 → 全球を高頻度カバー(3日で地球一周)
- フォーカスモード:90km幅で最大1kmの超高分解能 → 都市・発電所など特定ターゲットを狙い撃ち
これにより、ホットスポットの特定と精密診断という2つの役割を一台でこなす「戦略+戦術」型の運用が実現されました。
4. データ活用体制の強化:AI・機械学習との連携
NICTやNIESは、GOSAT-GWのデータ解析に機械学習を導入し、NO₂濃度の推定精度や処理速度を大幅に向上させています。
また、逆解析モデル「NISMON」では、観測された濃度データから排出源の分布を数理的に逆算することで、都市や企業レベルの排出推定が可能になっています。

▼出典:環境省ecojin 地球を見守る人工衛星!日本が誇る最新技術GOSAT!
「企業単位」の排出量監視も可能になる可能性
従来の衛星観測では、排出量の監視はあくまで国単位や都市単位の“平均的”な分析にとどまっていました。
GOSAT-GWが注目される最大の理由は、排出源を“個別に”追跡する能力が飛躍的に高まったことにあります。
精密観測モードによる高分解能観測
GOSAT-GWに搭載された「TANSO-3」は、観測手法を根本的に刷新しました。
従来のGOSATシリーズが「点」での観測を行っていたのに対し、TANSO-3は“面”を連続的にスキャンできるイメージング型分光計です。
さらに特筆すべきは、「精密観測モード」と呼ばれる特殊な観測機能。
これは、空間分解能を最大3kmにまで高めることができ、都市部や発電所、製鉄所といった大規模施設を対象にピンポイントで濃度を測定できるモードです。
従来(10km分解能)では、都市全体の平均的な排出濃度はわかっても、個々の施設までは特定できませんでした。
しかし、GOSAT-GWは1〜数kmスケールでの濃度差異を捉え、局所的な排出源の特定に踏み込める次元に到達しています。
NO₂観測という“排出源の指紋”
加えて、GOSAT-GWでは二酸化窒素(NO₂)の観測も新たに可能となりました。
NO₂は化石燃料の燃焼と同時に放出され、大気中での寿命が短いため、排出地点の近くで高濃度となりやすい「トレーサー」として機能します。
CO₂単体では発生源の特定が難しいケースでも、NO₂の局所濃度とセットで解析することで、工場や発電所などの“指紋”を宇宙から捉えることが可能になります。
これはまさに、温室効果ガスの科学的監視における次世代技術の核心です。
もちろん、すべての企業や工場を網羅できるわけではありません。環境省も公式に「現時点で全事業所単位での排出特定が可能なわけではない」と慎重に表現しています。
GOSAT-GWが得意とするのは、発電所・製鉄所・セメント工場など、排出規模の大きい施設です。
中小規模の排出源を個別に識別するには限界があります。
しかし、こうした「大規模排出源」こそが、国全体の排出量の過半を占めているのが現実です。
つまり、GOSAT-GWは国家レベルの目標達成状況を、施設単位の裏付けデータで精密に監視できる手段として、極めて強力な武器となり得るのです。

国際的意義と今後の展望
GOSAT-GWが収集する高密度なデータは、国際的にも多方面で活用が期待されています。
- 国連気候変動枠組条約(UNFCCC)のグローバル・ストックテイクへの科学的貢献
- 各国のNDC(国別貢献)評価における透明性強化
- 国境を越えた排出監視・第三者的検証ツールとしての活用
- 国際排出量取引制度への信頼性ある裏付けデータ提供
すでにGOSAT-GWは、NASAやESAの衛星群と連携した“国際観測ネットワーク”の一翼を担いはじめており、日本発の環境データが、科学的公正性と政策的正当性を担保する基盤として世界的に位置づけられつつあります。

▼出典:環境省ecojin 地球を見守る人工衛星!日本が誇る最新技術GOSAT!
まとめ
地球温暖化の原因とされる温室効果ガス(GHG)は、私たちの暮らしと産業活動に深く関わる気体群です。
特に二酸化炭素(CO₂)やメタン(CH₄)、一酸化二窒素(N₂O)、フロン類は、強い温室効果を持ち、気候変動の主因とされています。
これらの排出が進むことで、異常気象や海面上昇、生態系への影響が顕在化しつつあります。
こうした状況下、2025年に打ち上げられたGOSAT-GWは、温室効果ガスと水循環を同時に観測できる世界初の衛星として注目されています。
CO₂やCH₄に加え、排出源の特定に役立つNO₂も観測対象とし、都市や発電所などの大規模排出源を3kmの高解像度でモニタリング可能です。
さらに、水蒸気や降水量を捉えるセンサ「AMSR3」により、水循環の変化も詳細に把握できるようになりました。
GOSAT-GWが提供する高精度データは、各国の排出量報告の信頼性を高めると同時に、異常気象の予測精度向上や災害対策、国際的な気候合意の履行確認にも大きく寄与しています。
今後の気候政策と科学の橋渡しとして、その役割はますます重要になるでしょう。
