eco検定(環境社会検定試験)®の基礎知識と開催日時について
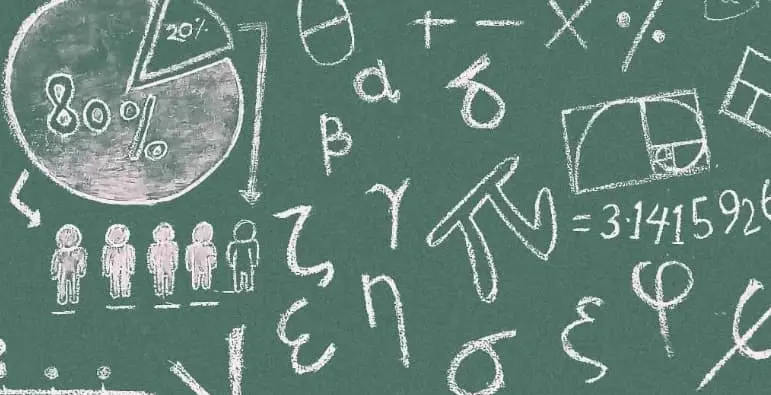
社会や企業の環境意識への高まりを受けて環境関連の資格も注目を受けるようになっており、ビジネスマネージャー検定やカラーコーディネーター検定を運営している東京商工会議所でもeco検定というものを実施しています。
エコ検定(環境社会検定試験)は、日本国内で環境問題に関する幅広い知識を学び、それを実生活や職場で実践できる力を育むための資格試験です。
2006年に東京商工会議所によって創設され、環境意識の向上や持続可能な社会づくりを目指す個人や企業にとって重要な学びの場を提供しています。
この資格は、環境問題に対する基本的な理解を深めるだけでなく、それを具体的な行動に移すことを目的として設計されており、幅広い層に活用されています。

eco検定の意義と目的
エコ検定の大きな意義は、環境に関する「学び」を「行動」に変える点にあります。この資格は、気候変動、エネルギー問題、生物多様性の保護といった地球規模の課題から、家庭や職場で実践できる環境配慮行動まで、幅広い知識を提供します。環境問題の理解を深めるだけでなく、学んだことを行動に活かし、環境負荷の削減や持続可能な社会づくりに貢献することを目指しています。
エコ検定の合格者は「エコピープル」として認定され、日常生活や職場で環境活動のリーダーとなることが期待されています。こうした取り組みは、企業の環境施策やSDGs(持続可能な開発目標)の推進にも寄与し、個人と社会の双方に利益をもたらします。
エコ検定は、環境問題に関心を持つすべての人に適しています。特に以下の層にとって有益な資格です:
- 企業の従業員:CSRや環境管理、サステナビリティ推進に携わる社員
- 学生:環境分野でのキャリアを目指す学生や環境問題に興味を持つ若者
- 一般市民:日常生活で環境負荷を減らす行動を取りたいと考える人
- 自治体職員や教育関係者:地域住民や学生への環境教育に携わる人
エコ検定は専門知識がなくても受験できるため、環境問題に初めて取り組む人にとっても学びやすい入り口となります。
エコ検定のメリット
エコ検定を取得することによるメリットは、個人のスキル向上やキャリア形成にとどまりません。企業や地域社会における環境活動の推進役としても活用できる点が特徴です。
・職場でのスキルアップ
企業では、エコ検定の取得者が環境意識の高い社員として評価されるケースが増えています。CSRやサステナビリティ推進プロジェクトでの活躍や、環境報告書作成などの業務で重要な役割を担うことができます。
・SDGsへの貢献
エコ検定で学ぶ知識は、SDGs(持続可能な開発目標)達成に直結します。特に、気候変動対策(目標13)、エネルギーの確保(目標7)、生物多様性の保全(目標15)など、地球規模の課題への貢献が可能です。
・キャリアの向上と社会的信頼性の確保
環境に関する知識を持つことは、就職や転職時のアピールポイントとなり、企業や地域社会での信頼を得ることにもつながります。
・地域や社会でのリーダーシップ
地域の環境活動や教育において、エコ検定取得者がリーダーとして活躍する場が広がっています。自治体や学校などでの啓発活動に参加する機会が増えることで、社会的な影響力を持つ存在になれます。
eco検定試験について
エコ検定は、地球環境に関する幅広いテーマをカバーしています。公式テキストに基づく出題が中心で、以下の分野が主要な試験範囲となります:
- 地球環境問題:温暖化、気候変動、オゾン層破壊などのグローバルな課題
- エネルギーと資源:再生可能エネルギー、エネルギー効率向上、資源循環型社会
- 自然と生物多様性:生態系保護、生物多様性の重要性、自然資源の持続可能な利用
- 企業活動と環境管理:環境経営、CSR(企業の社会的責任)、環境アセスメント
- 日本の環境政策と法制度:環境基本法、廃棄物処理法、再生可能エネルギー政策
試験は年2回、全国各地で実施されます。形式はマークシート方式で、100問の選択問題が出題され、70点以上(100点満点)で合格となります。公式テキストを中心に学習を進めることで、初学者でも十分合格が可能な試験設計となっています。
受講者と合格率は、
2024年の1回目で、実受験者数:16,487人 合格者9,611人(58.3%)
2023年の2回目で、、実受験者数:18,339人 合格者10,070人(54.9%)
2023年の1回目で、実受験者数:19,023人 合格者10,122人(53.2%)
2022年2回分で、実受験者数:38,300人 合格者24,711人(64.5%)
となっており、毎年着々とeco検定人材が増えています。

自身のパソコン・インターネット環境を利用し自宅・会社で受けられ、受験料も5,500円(税込み)とリーズナブルになっており、合格者の70-%が2ヵ月以内の学習時間というアンケート結果からも比較的受験から合格までのハードルが低い検定かと思われます。(2023年9月現在の情報です)
出典:東京商工会議所 eco検定(環境社会検定試験)®サイト
東京商工会議所のeco検定のサイトでは、合格者や推薦者の声も掲載されておりますので、参考にして皆様も検定受験に挑戦してみるのはいかがでしょうか。
企業や社会での活用
エコ検定は、個人だけでなく、企業や自治体、教育機関においても幅広く活用されています。
企業では、環境活動の推進役として社員にエコ検定を推奨する例が増えており、社内での環境教育プログラムの一環として活用されています。
また、自治体では、地域住民の環境意識を高めるための施策の一環として、エコ検定の受験を推進しています。
教育機関においても、エコ検定の内容を環境教育カリキュラムに組み込む事例があり、次世代の環境リーダーを育成するためのツールとして重要な役割を果たしています。
まとめ
eco検定(環境社会検定試験)は、東京商工会議所が2006年に創設した環境資格で、気候変動や再生可能エネルギー、生物多様性、CSRなど幅広い知識を学べるのが特徴です。
合格者は「エコピープル」として認定され、日常生活や職場で環境配慮行動を実践するリーダーとして期待されています。
受験者数は毎年増加しており、合格率は50~60%と比較的挑戦しやすい水準です。
試験範囲は公式テキストを中心に出題されるため、初学者でも短期間の学習で合格可能です。
企業ではCSRやSDGs推進の一環として社員に取得を推奨するケースが増え、教育機関や自治体でも環境教育のツールとして活用されています。
eco検定は、個人のキャリアアップだけでなく、社会全体の持続可能性向上に直結する実践的な資格として注目されています。
