需要創出の検討が進むグリーン製品とは?政策とバリューチェーン脱炭素化の未来
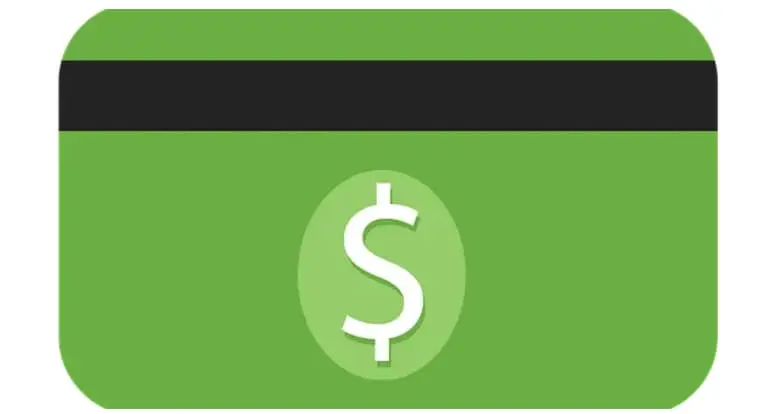
世界中で脱炭素の動きが加速する中、日本でも「グリーン製品」が新たな注目キーワードとなっています。
単なるエコ製品ではなく、製品のライフサイクル全体で排出される温室効果ガスを測定し、数値で示された環境価値を持つことが特徴です。
原材料の調達から製造、流通、使用、廃棄に至るまでの排出量を見える化したカーボンフットプリント(CFP)や、削減貢献量などの指標がその裏付けとなり、科学的根拠をもとに評価される製品として国際的にも注目されています。
こうした製品の普及は、国が掲げる2050年カーボンニュートラル、GX2040ビジョンの実現に不可欠です。
公共調達や表示制度の整備、サプライチェーン全体のデータ連携支援といった政策も動き出し、今まさに市場形成の段階にあります。
さらに、ヨーロッパや中国が進める厳格な環境基準に対応するためにも、グリーン製品は企業の競争力を左右する存在になりつつあります。
本記事では、グリーン製品の定義と重要性、種類や選び方、最新政策や市場動向、そして社会にもたらす効果をわかりやすく解説します。
未来の産業競争力と地球環境の両立を目指す新たな基準、その全体像を一緒に見ていきましょう。

グリーン製品とは何か
グリーン製品の定義と政策上の位置づけ
グリーン製品とは、製品やサービスのライフサイクル全体で発生する温室効果ガス(GHG)の排出量を減らし、その環境価値を明確に示したものを指します。
たとえば、原材料の調達から製造、流通、使用、廃棄までの各段階でどれだけ二酸化炭素を排出したかを数値で示す「カーボンフットプリント(CFP)」や、どの程度の削減効果を生んだかを表す「削減貢献量」といった指標が活用されます。
▼参考:グローバル標準を目指す日本のCO2削減貢献量(Scope4、カーボンハンドプリント)の考え方
こうした評価を受けた製品は、単に「エコな製品」というだけでなく、環境負荷の低さがデータとして裏付けられたものです。
環境省はこの考え方を、「バリューチェーン全体の脱炭素化」を進める上で欠かせない柱と位置づけています。
つまり、製品を選ぶときに環境への影響が“見える”状態をつくり、企業の投資や技術革新がきちんと市場で評価されるようにする仕組みの中で誕生するのがグリーン製品です。

▼出典:グリーン製品の需要創出等による バリューチェーン全体の脱炭素化に向けた検討会 中間とりまとめ(案)
なぜ今、グリーン製品が注目されるのか
グリーン製品への関心が高まっている背景には、日本の長期的な気候変動対策と産業政策があります。
政府は、2050年までに温室効果ガス排出量を実質ゼロにする「ネットゼロ」を掲げ、その中間目標として2030年度には2013年度比46%削減、2035年度に60%削減、2040年度には73%削減という道筋を示しました。
これを実現するために、2025年には「GX2040ビジョン」という新しい産業戦略が打ち出され、2026年度からは排出量取引制度、2028年度からは化石燃料賦課金も導入される予定です。これらの仕組みは、企業の生産活動を環境に優しい方向へシフトさせるための強いインセンティブになります。
▼参考:GX2040ビジョンが企業経営に与える影響とは?カーボンプライシングの動向も解説
同時に、国際競争力という観点からもグリーン製品は不可欠です。
ヨーロッパでは製品の環境性能を求める規制が進み、中国でもカーボンフットプリント表示が急速に標準化されつつあります。
こうした潮流の中で、日本企業が輸出や国際取引で優位性を保つためには、グリーン製品という「新しい基準」を満たすことが求められるのです。
言い換えれば、環境に配慮した製品を選ぶことは、地球環境の保全だけでなく、日本の産業が次の時代に生き残るための鍵にもなっているのです。

▼出典:グリーン製品の需要創出等による バリューチェーン全体の脱炭素化に向けた検討会 中間とりまとめに関する参考資料集
グリーン製品の多様なカテゴリー
素材から生活用品まで広がるグリーン製品
ひとくちに「グリーン製品」といっても、その対象は幅広く、私たちの生活のさまざまな場面に関わっています。
まず、バリューチェーンの最も上流にあたる鉄鋼や化学などの素材分野では、製造工程でのCO₂排出を大幅に削減した「グリーンスチール」や、低炭素型の化学原料が開発されています。
これらは自動車や建築、家電といった後工程の産業で使われるため、最終製品に見えない形で環境負荷を下げる重要な役割を果たします。
▼参考:グリーンスチール導入でCO2削減!今すぐ知るべき5つのポイント
次に、自動車・家電・日用品・飲料などのブランド主導型製品です。
大手メーカーが主導して環境配慮型の製品を市場に投入し、リサイクル素材の利用や再生可能エネルギーによる製造などを積極的に進めています。
消費者が直接手にする機会が多いため、製品の選び方一つがバリューチェーン全体の脱炭素化につながる分野です。
さらに、地域型の地場産業製品も見逃せません。
紙・繊維・食品加工など、地域経済に根ざした中小企業が集まる産業では、自治体や地元金融機関と連携しながら、排出量を測定・削減していく動きが少しずつ広がっています。
こうした取り組みは、地域全体での温暖化対策にもつながります。
このように、グリーン製品は上流の素材から、身近な生活用品まであらゆる産業で広がりを見せています。

▼出典:グリーン製品の需要創出等による バリューチェーン全体の脱炭素化に向けた検討会 中間とりまとめに関する参考資料集
ラベルや認証制度
消費者や企業がグリーン製品を見分けるためには、環境価値を正確に示すラベルや認証制度が重要です。
代表的なものに、製品のライフサイクル全体でのCO₂排出量を数値化するカーボンフットプリント(CFP)表示があります。
これにより、その製品がどの程度環境負荷を減らしているのかが明確になります。
また、エコマークやグリーン購入法適合商品といった認証も、消費者が安心して選べる目印となります。
▼参考:カーボンフットプリント(CFP)とは?CFP表示商品 | 持続可能な選択肢を紹介
さらに今後は、環境省が中心となって「グリーン製品・サービスの評価・表示スキーム」の導入を検討中です。
この仕組みでは、一定の基準を満たした製品を国が登録・公開し、環境に配慮した製品を選びやすくすることを目指しています。
こうしたラベル制度が整備されることで、企業の努力が見える形となり、市場全体でグリーン製品が選ばれやすくなる効果が期待されています。

▼出典:環境省・経済産業省 カーボンフットプリント 表示ガイド
グリーン製品を選ぶメリットと選び方
環境・経済・社会へのメリット
グリーン製品を選ぶことは、環境のためだけではなく、経済や社会全体に広いメリットをもたらします。
第一に、排出削減への直接的な貢献です。
グリーン製品は、原材料の調達から廃棄までのライフサイクル全体で温室効果ガスの排出量を抑えています。
その製品を選ぶという行動そのものが、CO₂削減の一歩になります。
第二に、企業のGX(グリーントランスフォーメーション)投資を後押しできるという点です。
企業が環境に配慮した製品を開発しても、購入されなければ投資は続きません。
消費者がグリーン製品を選ぶことは、「この取り組みを評価する」というメッセージになり、次の技術開発や排出削減設備への投資を促すきっかけになります。
▼参考:経済産業省が推進するGX(グリーントランスフォーメーション)とは?政策・支援策を徹底解説
第三に、市場全体を変える力です。
公共調達や大企業の調達方針がグリーン製品にシフトすると、その影響がサプライチェーン全体に広がります。
消費者の選択は、小さな一歩に見えても、結果的に産業全体の脱炭素化を加速させる要因になります。

▼出典:グリーン製品の需要創出等による バリューチェーン全体の脱炭素化に向けた検討会 中間とりまとめに関する参考資料集
購入のチェックポイント
では、実際にグリーン製品を選ぶときは、どこに注目すればよいのでしょうか。
次の3つの視点を意識すると、信頼できる選択ができます。
ラベル・表示の有無
製品パッケージやウェブサイトに、カーボンフットプリント(CFP)、エコマーク、グリーン購入法適合商品などの認証マークがあるかを確認しましょう。
これらの表示は、第三者の基準で評価されている証拠です。

▼出典:グリーン製品の需要創出等による バリューチェーン全体の脱炭素化に向けた検討会 中間とりまとめに関する参考資料集
ライフサイクルでの排出削減貢献
単に「リサイクル素材を使っている」だけではなく、製造から使用、廃棄までのプロセス全体でどのような工夫がされているかに注目します。
最近では、CO₂削減量やエネルギー効率の高さを具体的に示す製品も増えてきています。
製品の信頼性
企業独自の表現だけでなく、CFP認証や第三者機関の検証を受けているかどうかも判断材料です。
国や公的機関が認めたスキームを活用した製品は、信頼性が高いと言えます。

▼出典:グリーン製品の需要創出等による バリューチェーン全体の脱炭素化に向けた検討会 中間とりまとめに関する参考資料集
日本のグリーン製品市場と政策の最新動向
3つの市場パターンと課題
日本のグリーン製品市場は、産業構造の違いから3つの主要なパターンに分類され、それぞれ異なる課題を抱えています。
- 川上先行型(素材産業)
鉄鋼や化学分野の大手企業が「グリーンスチール」など低炭素素材へのGX投資を進めていますが、中流や下流の企業がそうした素材を採用する需要が不足しています。
結果として、開発された素材の市場化や価格転嫁が進まず、B2B需要が停滞しています。
- 川中先行型(ブランド産業)
自動車メーカーや家電ブランドなどが環境配慮型製品を導入していますが、上流のサプライヤーからの一次データ収集が困難です。
Scope3排出量削減に必要なサプライチェーンの脱炭素化に向けたデータ連携の仕組みが整っておらず、実効性ある進展が難しい状況です。
▼参考:Scope3とは?最新情報と環境への影響と企業の取り組み
- 地域主体型(地場産業) 地域の中小製造業や地場産業は、脱炭素経営に取り組む意識とリソースが不足しています。
大企業からのエンゲージメントも届きにくいため、制度整備や人材支援が不可欠な状態です。
これらの課題は、インプット資料でも繰り返し指摘されたもので、市場創出の鍵として政策的な“自分に最適な戦略的アプローチ”を見極める必要性が強調されています。

▼出典:グリーン製品の需要創出等による バリューチェーン全体の脱炭素化に向けた検討会 中間とりまとめに関する参考資料集
需要創出のための政策
この現状を踏まえ、政府は複数の政策施策を通じてグリーン製品の需要を創出し、市場を活性化しようとしています。
公共調達による初期需要の創出
「グリーン購入法」や「環境配慮契約法」に基づき、国や地方公共団体が環境性能の高い製品を優先的に調達することで、市場に対して強い初期需要を提供しています。
これは、グリーン素材や製品を企業が安心して開発・投入できる環境をつくる上で重要なインセンティブになります
サプライヤー支援・データ基盤整備
Scope3削減や一次データの提供において、中小サプライヤーの負担軽減や体制整備を支援する政策が進められています。
業界ごとの共通基盤や標準フォーマットを整備することで、データ連携の効率化と透明性の高い製品価値評価を実現します。
地域モデル事業の展開
長野市や四国中央市などでは、自治体・地場金融機関・商工会議所が連携し、地域ぐるみで中小企業の脱炭素化支援モデルを構築しています。
こうしたパイロット事業は、成功要因を全国展開するためのケーススタディとして政策に取り込まれています。

▼出典:グリーン製品の需要創出等による バリューチェーン全体の脱炭素化に向けた検討会 中間とりまとめに関する参考資料集
グリーン製品がもたらす環境・経済への効果
バリューチェーン全体の排出削減効果
グリーン製品の普及は、単に個々の製品のCO₂排出量を減らすだけではありません。
サプライチェーン全体での削減効果(Scope3の削減)を生み出す大きな仕組みとなります。
たとえば、鉄鋼メーカーがCO₂排出を大幅に削減した「グリーンスチール」を開発すると、それを材料として自動車メーカーや建設会社が利用します。
その結果、素材の段階での削減努力が、下流企業のScope3(サプライチェーン由来の間接排出)削減につながります。
つまり、上流の努力がバリューチェーン全体に波及して、最終的には製品の利用者である消費者にも環境価値として届くのです。
さらに、こうした連携の広がりは中小企業に新しいビジネスチャンスを生みます。
大手企業が脱炭素型の素材や部品を求めるようになれば、
中小企業も新しい技術やサービスを提供することで、取引拡大や新規参入の機会を得ることができます。
脱炭素化は、単なる負担ではなく、新しい市場を切り開くきっかけにもなるのです。
▼参考:中小企業のための脱炭素経営入門|6つのステップで始める取り組み

▼出典:グリーン製品の需要創出等による バリューチェーン全体の脱炭素化に向けた検討会 中間とりまとめに関する参考資料集
サステナブルな社会と新しい競争力
グリーン製品の価値は、環境負荷の削減だけにとどまりません。
サステナブルな社会を実現しながら、新しい競争力を育てる力があります。
GX(グリーン・トランスフォーメーション)はよく「地球のための守りの施策」と捉えられますが、実際には企業経営において「攻めの戦略」でもあります。
環境に配慮した製品や技術を開発できる企業は、今後ますます高まる国際的なサステナビリティ要求に対応し、海外市場で優位に立てるからです。
EUでは環境規制が強化され、中国でもカーボンフットプリント表示の義務化が急速に進んでいます。
このようなグローバルな潮流の中で、日本企業が国際市場で競争力を維持するには、グリーン製品を通じた「環境価値の可視化」と「技術革新」が欠かせません。
言い換えれば、グリーン製品は未来の市場で生き残るためのパスポートでもあります。
国内の需要喚起だけでなく、世界を見据えた競争戦略としても重要な意味を持っているのです。

▼出典:グリーン製品の需要創出等による バリューチェーン全体の脱炭素化に向けた検討会 中間とりまとめに関する参考資料集
まとめ
グリーン製品は、製品のライフサイクル全体で温室効果ガス排出を抑え、その環境価値を数値で示した新しい基準の製品です。
カーボンフットプリント(CFP)や削減貢献量といった指標を通じて見える化され、企業のGX(グリーントランスフォーメーション)を後押しする役割を担います。
素材から生活用品まで分野は広がり、ラベルや認証制度が選び方の目印になります。
国は公共調達や表示制度、データ基盤整備などで市場形成を支援しており、グリーン製品の普及はバリューチェーン全体の排出削減と中小企業の新たな商機を生みます。
国際競争力を高める攻めの戦略としても重要で、選ぶ一歩が持続可能な社会をつくる力につながります。
